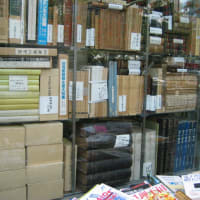「「画餅」といふは、しるべし、父母所生の面目あり、父母未生の面目あり。米麺をもちひて作法せしむる正当恁麼、かならずしも生不生にあらざれども、現成道成の時節なり、去来の見聞に拘牽せらるゝと参学すべからず」(注1)。
正直に白状すると初めてこの文章を読んだとき、理解できたのは「「画餅]といふは、しるべし」までだった。「父母所生の面目」「父母未生の面目」「正当恁麼」といわれたも何のことだかさっぱり判らなかった。現在のわたしはだいたい次のような意味だと思っている。「「画餅」といのは、絵であるから現実の餅としては存在しないという状態であり、また絵としての餅は現実に存在してるという状態であるという二つの側面を持っている。しかしその「画餅」とは米や麦粉を使って作るまさにそのもの(餅一般)であり、生まれるとか生まれないとかではなく、現に手元にあるような言葉(概念)として成立しているわけだ。だから「画餅」は去来(出現したり消え去ったりするもの)についての見たり聞いたりといった感覚的なものに束縛されていると考えてはいけない」。へえ、「画餅」といのは絵の具で描いた餅ではなくて、ちゃんと穀類を使って描くのか。だから道元禅師の論理が成立するのだなあ。「しかあればすなはち、いま道著する画餅といふは、一切の糊餅、菜餅、乳餅、焼餅、茲餅等(茲は米篇で作る)、みなこれ画図より現成するなり」(注2)、つまり「そうであるから、いま話題にしている「画餅」というのは、全ての個々の餅の抽象的概念なのである」。
では「不充飢」とは何なのだろう。「「不充飢」といふは、飢は十二時使にあらざれども、画餅に相見する便宜あらず、画餅を喫茶するにつゐに飢をやむる功なし。飢に相待せらるゝ餅なし、餅に相待せらるゝ餅あらざるがゆへに、活計つたわれず、家風つたはれず」(注3)。これも同じく最初に読んだときは「「不充飢」といふは」までしか判らなかった。早い話、すべてがまったく判らなかった。現在のわたしはおそらくこんな意味なのだろうと思っている。「「不充飢」については、先ずここで言う「飢」とは通常わたしたちが感じる空腹感とは違うものだ。つまり十二時使(現実的な時間のなかで使われているもの)ではなくてもっと抽象的な「希求」といったようなことを意味する。その「希求」が画餅つまり「概念」と相互に出会う都合のよいときがない。ある「概念」を自分のものにしたと思ってもその「概念」への「希求」そのものはけっしてなくなりはしない。その「希求」に待たれる「概念」はなく、更に「概念」に待たれる「概念」(より相応しい概念)がないために、なにも伝えることができないのだ」。ところで「餅に相待せらるゝ餅あらざるがゆへに」の部分だけれども、ここを増谷文雄は「餅に相待せらるゝ飢あらざるがゆへに」と読んでいる(注4)。どちらが正しいかわたしには判らないので一応岩波版テキストの通りに読んでおいた。
煎じ詰めればこういうことか。わたしたちは概念つまり言葉によって他者と交流する。そのためにより相応しい言葉すなわち概念を求めるのだが、それは永久に手に入れることができない。というのもわたしたち自身のはたらきである「希求」にとって、概念とは超越的なものだからだ。まさにこのことを「画餅不充飢」は表している、と道元禅師は言っているのだろうか。しかしわたし自身まだ釈然としない。回を改めてもう一度読みなおしてみよう。それにしても道元禅師がユニックなのは「画餅」と「不充飢」を別々に分析しているところ。そして「画餅」とはなにか、「不充飢」とはなにかという論じ方はこれが漢文だから可能なのだと思う。一般に道元禅師の漢文解釈には独特のものがある。単に中国語に堪能だったというだけでは『正法眼蔵』で展開されるアクロバティックとも見える議論はおそらく出てこなかったのではないだろうか。それにしても難しい。まるで外国語を翻訳しているみたいだ。
(注1)『日本思想体系12 道元(上)』284頁 岩波書店 1970年5月25日第1刷
(注2) 同上
(注3)『日本思想体系12 道元(上)』285頁 岩波書店 1970年5月25日第1刷
(注4)『正法眼蔵』(四)252頁 増谷文雄訳注 講談社学術文庫 2004年10月10日
正直に白状すると初めてこの文章を読んだとき、理解できたのは「「画餅]といふは、しるべし」までだった。「父母所生の面目」「父母未生の面目」「正当恁麼」といわれたも何のことだかさっぱり判らなかった。現在のわたしはだいたい次のような意味だと思っている。「「画餅」といのは、絵であるから現実の餅としては存在しないという状態であり、また絵としての餅は現実に存在してるという状態であるという二つの側面を持っている。しかしその「画餅」とは米や麦粉を使って作るまさにそのもの(餅一般)であり、生まれるとか生まれないとかではなく、現に手元にあるような言葉(概念)として成立しているわけだ。だから「画餅」は去来(出現したり消え去ったりするもの)についての見たり聞いたりといった感覚的なものに束縛されていると考えてはいけない」。へえ、「画餅」といのは絵の具で描いた餅ではなくて、ちゃんと穀類を使って描くのか。だから道元禅師の論理が成立するのだなあ。「しかあればすなはち、いま道著する画餅といふは、一切の糊餅、菜餅、乳餅、焼餅、茲餅等(茲は米篇で作る)、みなこれ画図より現成するなり」(注2)、つまり「そうであるから、いま話題にしている「画餅」というのは、全ての個々の餅の抽象的概念なのである」。
では「不充飢」とは何なのだろう。「「不充飢」といふは、飢は十二時使にあらざれども、画餅に相見する便宜あらず、画餅を喫茶するにつゐに飢をやむる功なし。飢に相待せらるゝ餅なし、餅に相待せらるゝ餅あらざるがゆへに、活計つたわれず、家風つたはれず」(注3)。これも同じく最初に読んだときは「「不充飢」といふは」までしか判らなかった。早い話、すべてがまったく判らなかった。現在のわたしはおそらくこんな意味なのだろうと思っている。「「不充飢」については、先ずここで言う「飢」とは通常わたしたちが感じる空腹感とは違うものだ。つまり十二時使(現実的な時間のなかで使われているもの)ではなくてもっと抽象的な「希求」といったようなことを意味する。その「希求」が画餅つまり「概念」と相互に出会う都合のよいときがない。ある「概念」を自分のものにしたと思ってもその「概念」への「希求」そのものはけっしてなくなりはしない。その「希求」に待たれる「概念」はなく、更に「概念」に待たれる「概念」(より相応しい概念)がないために、なにも伝えることができないのだ」。ところで「餅に相待せらるゝ餅あらざるがゆへに」の部分だけれども、ここを増谷文雄は「餅に相待せらるゝ飢あらざるがゆへに」と読んでいる(注4)。どちらが正しいかわたしには判らないので一応岩波版テキストの通りに読んでおいた。
煎じ詰めればこういうことか。わたしたちは概念つまり言葉によって他者と交流する。そのためにより相応しい言葉すなわち概念を求めるのだが、それは永久に手に入れることができない。というのもわたしたち自身のはたらきである「希求」にとって、概念とは超越的なものだからだ。まさにこのことを「画餅不充飢」は表している、と道元禅師は言っているのだろうか。しかしわたし自身まだ釈然としない。回を改めてもう一度読みなおしてみよう。それにしても道元禅師がユニックなのは「画餅」と「不充飢」を別々に分析しているところ。そして「画餅」とはなにか、「不充飢」とはなにかという論じ方はこれが漢文だから可能なのだと思う。一般に道元禅師の漢文解釈には独特のものがある。単に中国語に堪能だったというだけでは『正法眼蔵』で展開されるアクロバティックとも見える議論はおそらく出てこなかったのではないだろうか。それにしても難しい。まるで外国語を翻訳しているみたいだ。
(注1)『日本思想体系12 道元(上)』284頁 岩波書店 1970年5月25日第1刷
(注2) 同上
(注3)『日本思想体系12 道元(上)』285頁 岩波書店 1970年5月25日第1刷
(注4)『正法眼蔵』(四)252頁 増谷文雄訳注 講談社学術文庫 2004年10月10日