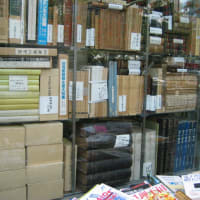『正法眼蔵』の「第十三海印三昧」に不思議な一節がある。曹山禅師に或る修行僧が、「大海死屍を宿せず」の意味を尋ねている。これに答えた曹山禅師の言葉を道元禅師が解説しているのだが、わたしにはどうしても「大海死屍を宿せず」の意味が素直に理解できなかった。望月の佛大辭典によれば「大海の具する十種の徳相の意。舊華嚴經第二十七に「佛子、譬えば大海の十相を以っての故に名づけて大海と爲し、能く壊するものあることなきが如し。何等をか十と爲す、一に漸次に深く、二に死屍を受けず、三に餘水は本名を失し、四に一味なり、五に寶多く、六に極めて深くして入り難く、七に廣大にして量なく、八に大身の衆生多く、九に潮は時を失はず、十に能く一切の大雨を受くるも盈溢あることなし。菩薩地も亦是なり」と云へる是れなり」(注1)とあり更に「又大涅槃經第三十三にも大海に八不思議ありとし、一に漸漸に轉た深く、二に深くして底を得難く、三に同一鹹味、四に潮は限を過まらず、五に種種の寶蔵あり、六に大身の衆生、中に在りて居住し、七に死尸を宿さず、八に一切の萬流大雨之に投ずるもせず滅せずと云へり。今華嚴の大海十相の説は恐らく此等の説を布衍せしものなるべし」(注2)と載っていた。要すれば太平洋みたような大きな海の功徳(この場合は機能というほどの意味)は大涅槃經第三十三では八不思議という形に分類され、華嚴經ではこれが更に敷衍された十種類があげられているということで、つまり大海の機能の一つに死体を海中にいつまでも留め置かないということがあるということだ。簡単にいってしまうと土左衛門は一昼夜すれば岸辺に流れ着く、つまり海中から排除されてしまうということ。『俚諺大辭典』にも「【大海は屍をとどめず】(涅槃經)大海不宿死屍」(注3)と出ているくらいだからかなり有名な一節らしく、したがってこの言葉自体は何等難しいことをいっているわけではないことがわかった。それが道元禅師にかかるととたんに様相が変わってくる。「いはゆる大海は、内海、外海等にはあらず、八海等にはあらざるべし」()(注4)といってこの海がわたしたちの認識している海ではないことを強調する。つまり「海」は菩薩の立場の比喩なのだということ、ここまでは簡単にわかる。しかし不宿死屍というのが「不宿とは明頭来明頭打、暗頭来暗頭打なるべし。死屍は死灰なり、幾度逢春不変心なり。死屍といふは、すべて人々いまだみざるものなり。このゆへにしらざるなり」(注5)となってくると考え込んでしまう。「不宿」というのは「明頭来明頭打、暗頭来暗頭打」であるはずなのだ、といわれてもねえ。道元禅師はこの「明頭来明頭打、暗頭来暗頭打」を『正法眼蔵』のなかで何回か使用している。たぶん宋留学中に覚えたのだろうけれどよっぽど気に入ったのかな。これについては日本思想体系本の頭注に「情況に応じて確執遅滞なくやってのけられること」(注6)とあるのでそのように理解するとしよう。ということはまず菩薩としての大海は死体を情況に応じてすいすいと処理してしまう、ということになる。しかしそれではそのように処理される屍とはいったい何なのだろう。そこで道元禅師は透かさず「死屍は死灰なり」という。「死屍」(シシ)は「死灰」(シハイ)または(シカイ)、つまり生気のないもの。あたりまえだ。そして畳み掛けるように「幾度逢春不変心なり」とくる。恒久的に変わることのない「心」。これは「こころ」ではなく「意味」とか「趣」というくらいに解釈しよう。つまり生気のないものは恒久的に不変であるということか。そして最後に「死屍といふは、すべて人々いまだみざるものなり。このゆへにしらざるなり」とくる。生気のないものを人々はまだ見たことがない、だから知らない。
煎じ詰めれば、大海のような菩薩は恒久的に変わることのない生気ないものを確執遅滞なく処理してしまう。だからそのような生気のないものを人は見たこともないので、したがって知ることもない。ということになるのだろうか、しかしわたしにはまだわからない。不知道正法眼蔵。
(注1)『佛大辭典』第四巻3200頁 望月信亨 佛大辭典發行所 昭和10年3月15日
(注2) 同上
(注3)『俚諺大辭典』528頁 中野吉平 東方書院 昭和8年10月15日
(注4)『日本思想体系12 道元(上)』145頁 岩波書店 1970年5月25日第1刷
(注5) 同上 145頁~146頁
(注6) 同上 137頁
煎じ詰めれば、大海のような菩薩は恒久的に変わることのない生気ないものを確執遅滞なく処理してしまう。だからそのような生気のないものを人は見たこともないので、したがって知ることもない。ということになるのだろうか、しかしわたしにはまだわからない。不知道正法眼蔵。
(注1)『佛大辭典』第四巻3200頁 望月信亨 佛大辭典發行所 昭和10年3月15日
(注2) 同上
(注3)『俚諺大辭典』528頁 中野吉平 東方書院 昭和8年10月15日
(注4)『日本思想体系12 道元(上)』145頁 岩波書店 1970年5月25日第1刷
(注5) 同上 145頁~146頁
(注6) 同上 137頁