今年もこの日が巡ってきた。
何と68年目の12/8である。
私も含めた戦後生まれが,全人口の3/4を越えたのだそうだ。
新聞を見てもネットを繰っても,日米開戦に関する記事は年々少なくなり,今日など殆ど見つけることができなかった(私のスキル不足で見つけられないのもあるだろうが・・・)。
こうして12/8とか8/15は日本人の精神から風化していくのだろうか・・・。
今考えてみると,私が子どもの頃は空前の「軍事ブーム」であった。
漫画週刊誌には,少年サンデーを筆頭に戦争の絵物語や昨日が忌日であった小松崎茂画伯による精細な兵器の図解が掲載されており,不謹慎の誹りを受けようと胸をときめかせて見入ったものだった。
また,さすがに「紫電改のタカ」はリアルで読まなかったが,上記サンデーに掲載されていた「あかつき戦闘機隊」は貪るように読んだ。
さらに,それに拍車をかけるように各ブラモデルメーカーからは,多くの大戦ものが発売された。
小学館の学習雑誌の裏表紙には青島文化教材社の広告が載っており,国際スケールである1/72の大戦中の戦闘機シリーズが発売になっていた。
明灰白色に塗装された零戦21型,コクピットのドアが自動車のようなベルP63キングコブラ,零戦を二回りでかくして表面は直径1mmのリベット仕上げ,しかも艦戦なので主翼が折り畳まれる(可動する)「烈風」,極彩色のど派手なボックスアートが記憶に生々しい「青嵐」,その空冷エンジン版の「瑞雲」なんて名を覚えたのもこの時期だし,今考えるとプロペラプレートの根本を絞りすぎていた日本模型(ニチモ)のスピットファイアMkVbといった往年名機も作った(レヴェルの1/72に填ったのはもう少し後である)。
さらに国産メーカーの雄となりつつあった田宮模型は,1/35で大戦中の戦車を量産。
T34-85やSu100(「ジューコフ」なる元帥の名が付いていた)といったソ連戦車や,M4A3 E8にM36(当時は「バッファロー」なる名が付いていたが,間もなく「ジャクソン」と改められた)といった米戦車も作った(雪の上を走らせたりもした)。
当時大人気だったパンサーとかタイガーといった独戦車に手を出さなかったのは,天の邪鬼たる私の面目である(パンテルとかヤクトパンテル,ティーゲル,ケーニヒスティーゲルとわざと独語読みしていた)。
また,田宮からは1/72で前述青島とは比べものにならない精度の大戦機が発売されており,大東亜決戦機と呼ばれた陸軍四式戦「疾風」を作り(ミニベビーなるモーターを組み込んでプロペラを回転させて悦に入っていた),こいつが零戦並みに量産されてエンジントラブルが無かったら・・・と一人で歯がみしたりもしていた・・・(1/50の三式戦も作った・・)
やがてもう少し年がいくと,メディアによる戦記物にも接するようになる。
学校の図書室から借りて「スターリングラードの戦い」とか「マレー沖海戦」といった子ども向けの総記を読み,さらには松本零士の「戦場漫画シリーズ」(続編はザ・コクピット)とか松本の弟子である新谷かおるの「戦場ロマンシリーズ」といったコミックにものめり込むことになる(特に兵器の考証がしっかりしていた後者は,第一級の模型制作資料となった)。
そうして,戦争の背景を理解することで,何故我が国がに戦争に突入していったのかを知るに至り,それがもたらした国民生活へのあまりに大きな犠牲についても理解することになる。
中世欧州の大航海時代を端緒とする帝国主義がアジア・アフリカの植民地支配を行い,19世紀後半になって遅まきながらそれに参画するに至った我が国の利権がそれらと衝突することで,非情な歴史の潮流に巻き込まれていった経緯については一昨年の今日述べたが,今の我々にすべきこと,そしてできることは戦争の善悪論を超えたところにある正史の理解に他ならない。
戦記物のボックスアートを多く描いた上記小松崎画伯の作品は,好戦的とか戦争賛美といった誹りを受けたという。
しかし,実際に戦争を体験した画伯にとって戦争とは最も忌むべき存在であり,その悲惨さを誰よりも理解していたという。
つまり兵器の造形美を賛美していたのであり,決して戦争を肯定していたのではない。
それすら好戦的と言われるのでは何をか況んやだ(私は言われたが・・・)。
・・・ということで,今宵は私が子どもの頃封切られた(そしてねだったが連れて行ってもらえなかった)「トラトラトラ!」を見て寝る。
愚にも付かぬ駄作「パールハーバー」は一回見て,レンタル代100円と貴重な3時間をどぶに捨てた気分になったので,以来一度も見ていない・・・。

何と68年目の12/8である。
私も含めた戦後生まれが,全人口の3/4を越えたのだそうだ。
新聞を見てもネットを繰っても,日米開戦に関する記事は年々少なくなり,今日など殆ど見つけることができなかった(私のスキル不足で見つけられないのもあるだろうが・・・)。
こうして12/8とか8/15は日本人の精神から風化していくのだろうか・・・。
今考えてみると,私が子どもの頃は空前の「軍事ブーム」であった。
漫画週刊誌には,少年サンデーを筆頭に戦争の絵物語や昨日が忌日であった小松崎茂画伯による精細な兵器の図解が掲載されており,不謹慎の誹りを受けようと胸をときめかせて見入ったものだった。
また,さすがに「紫電改のタカ」はリアルで読まなかったが,上記サンデーに掲載されていた「あかつき戦闘機隊」は貪るように読んだ。
さらに,それに拍車をかけるように各ブラモデルメーカーからは,多くの大戦ものが発売された。
小学館の学習雑誌の裏表紙には青島文化教材社の広告が載っており,国際スケールである1/72の大戦中の戦闘機シリーズが発売になっていた。
明灰白色に塗装された零戦21型,コクピットのドアが自動車のようなベルP63キングコブラ,零戦を二回りでかくして表面は直径1mmのリベット仕上げ,しかも艦戦なので主翼が折り畳まれる(可動する)「烈風」,極彩色のど派手なボックスアートが記憶に生々しい「青嵐」,その空冷エンジン版の「瑞雲」なんて名を覚えたのもこの時期だし,今考えるとプロペラプレートの根本を絞りすぎていた日本模型(ニチモ)のスピットファイアMkVbといった往年名機も作った(レヴェルの1/72に填ったのはもう少し後である)。
さらに国産メーカーの雄となりつつあった田宮模型は,1/35で大戦中の戦車を量産。
T34-85やSu100(「ジューコフ」なる元帥の名が付いていた)といったソ連戦車や,M4A3 E8にM36(当時は「バッファロー」なる名が付いていたが,間もなく「ジャクソン」と改められた)といった米戦車も作った(雪の上を走らせたりもした)。
当時大人気だったパンサーとかタイガーといった独戦車に手を出さなかったのは,天の邪鬼たる私の面目である(パンテルとかヤクトパンテル,ティーゲル,ケーニヒスティーゲルとわざと独語読みしていた)。
また,田宮からは1/72で前述青島とは比べものにならない精度の大戦機が発売されており,大東亜決戦機と呼ばれた陸軍四式戦「疾風」を作り(ミニベビーなるモーターを組み込んでプロペラを回転させて悦に入っていた),こいつが零戦並みに量産されてエンジントラブルが無かったら・・・と一人で歯がみしたりもしていた・・・(1/50の三式戦も作った・・)
やがてもう少し年がいくと,メディアによる戦記物にも接するようになる。
学校の図書室から借りて「スターリングラードの戦い」とか「マレー沖海戦」といった子ども向けの総記を読み,さらには松本零士の「戦場漫画シリーズ」(続編はザ・コクピット)とか松本の弟子である新谷かおるの「戦場ロマンシリーズ」といったコミックにものめり込むことになる(特に兵器の考証がしっかりしていた後者は,第一級の模型制作資料となった)。
そうして,戦争の背景を理解することで,何故我が国がに戦争に突入していったのかを知るに至り,それがもたらした国民生活へのあまりに大きな犠牲についても理解することになる。
中世欧州の大航海時代を端緒とする帝国主義がアジア・アフリカの植民地支配を行い,19世紀後半になって遅まきながらそれに参画するに至った我が国の利権がそれらと衝突することで,非情な歴史の潮流に巻き込まれていった経緯については一昨年の今日述べたが,今の我々にすべきこと,そしてできることは戦争の善悪論を超えたところにある正史の理解に他ならない。
戦記物のボックスアートを多く描いた上記小松崎画伯の作品は,好戦的とか戦争賛美といった誹りを受けたという。
しかし,実際に戦争を体験した画伯にとって戦争とは最も忌むべき存在であり,その悲惨さを誰よりも理解していたという。
つまり兵器の造形美を賛美していたのであり,決して戦争を肯定していたのではない。
それすら好戦的と言われるのでは何をか況んやだ(私は言われたが・・・)。
・・・ということで,今宵は私が子どもの頃封切られた(そしてねだったが連れて行ってもらえなかった)「トラトラトラ!」を見て寝る。
愚にも付かぬ駄作「パールハーバー」は一回見て,レンタル代100円と貴重な3時間をどぶに捨てた気分になったので,以来一度も見ていない・・・。











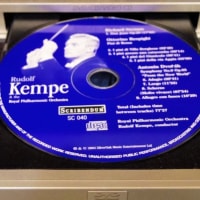
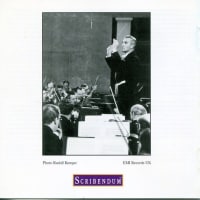
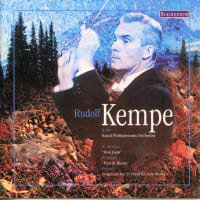







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます