昨年末に入手したCMOSカメラは惑星撮影用途をメインに考えてましたが、木星や土星はオフシーズン入ってしまって、
まだ試せておらず、流星や月の動画撮影しかできてません。一応、このカメラは長時間露光も可能なので、星雲星団の
撮影に使ったらどんなパフォーマンスを示すのかちょっと調べてみたくなり、先日の中越方面への遠征時に試し撮りを
やってみました。
まずはこの季節の深夜に天頂近くまで昇り詰めるこの星団を撮影。

【球状星団 M3(りょうけん座)】
ZWO ASI585MC+タカハシε-180EDC,F2.8,Gain120・240・360・480,STARRY NIGHTフィルター,
総露出時間20分(1分×20フレーム,加算コンポジット),タカハシEM-200Temma2M赤道儀,
口径25mmガイド鏡にて恒星オートガイド,新潟県十日町市にて
りょうけん座にある大型の球状星団で、光度は約6.4等と比較的明るく、口径3cmの双眼鏡で存在確認できる天体です。
使用カメラの撮像センサーは1/1.2型と小さいため写野が狭くて、焦点距離が500mmでも結構な大写しになりました。
球状星団は中心部と周辺部で輝度差が大きいので、4種類のゲイン(カメラ感度)で5フレームずつ撮って所謂HDR合成し、
階調を整えてます。これまでのデジイチ撮影では感度を固定した状態で露出時間を変えて撮ってHDR合成用の元画像を
取得してましたが、それと類似した撮影&画像処理レシピに相当し、今回は露出時間を一定にして感度を変えるという
対応にしました。
で、星団部分を等倍トリミングしてみると・・・

コア部分は白飛び気味になりましたが、この程度であれば許容範囲で、星団外縁部の糠星までしっかり捉えられたんで
ほぼ満足できるレベルです。このカメラにはハード的にノイズを劇的に抑えるための冷却機能は無いんですが、高感度
設定で撮った画像上でもホットピクセルが割と少なくて、普通のダークフレーム(望遠鏡に蓋をして遮光状態で撮った
画像)減算処理をしても、思ったほど画像が荒れたりしませんでした。なお、撮影時の気温は一桁台と低めだったので、
外気による冷却効果が少しだけあったのかもしれません。夏の暑い時期になるとノイズが一気に増えて画像処理で手に
負えなくなったりする可能性もありますが、今回の試写レベルでは意外と使える感触が得られました。
ただ、元画像は色ノリがあまり良くなく、彩度をかなり高めてやらないと鑑賞に堪える画像にならない感じだったんで
メインの惑星撮影で色の出方がどうなるのか気になるところです。
(つづく)










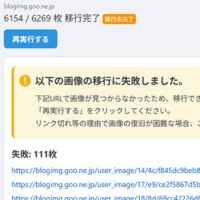









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます