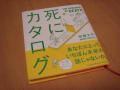『孤独の研究』(木原武一・著、PHP研究所)―再読―
<☆>
「個」と「孤」について考えていたとき、再びこの本を読みたくなった。以下に気なった一節を書き抜こうと思う。 . . . 本文を読む
『いのちの食べかた』(森達也・著、理論社)
見てから読むか、読んでから見るか。むかし何かの映画のキャンペーンで、たしかこんなキャッチコピーがあった。今回は映画『いのちの食べかた』を見てからこの本を読んだ。映画の感想はかなり素直な気持ちを書いたつもりだ。もしこの本を読んでから映画を見ていたら、映画の感想は差別問題のほうに引きずられていたかもしれない。それはそれでよかったのかもしれないが、理屈が先 . . . 本文を読む
『障害・病いと「ふつう」のはざまで』(田垣正晋・編著、明石書店)
主として序章「脱援助と、絶えざる言い換えの努力」(田垣正晋・著)、第1章「社会における障害とは何か」(田垣正晋・著)、第2章「軽度障害というどっちつかずのつらさ」(田垣正晋・著)、第8章「慢性の病気にかかるということ」(今尾真弓・著)を読んだ。
たとえば、階段や坂道を上るのが自分は苦手である。息切れや動悸がするからだ。老化の . . . 本文を読む
『死にカタログ』(寄藤文平・著、大和書房)
比較的世代が近い女性の知人の方から、とてもおもしろかったからと勧められた。実際読んでみると気負わずに読める「死の百科」といった感じだ。いつも自分のこととして死を身近に想ってきたが、それゆえに、逆に死を客観視することが意外とできなかった。本書は楽しいイラストと雑学的知識でそこのところを乗り越えさせてくれる。
生き物は必ず死ぬ。しかし、死に向かって生 . . . 本文を読む
『ファウスト』(手塚治虫・著、朝日文庫)
ゲーテの『ファウスト』といえば、万学を修めたファウスト博士と悪魔のメフィストフェレスとの契約のくだりくらいしか知らないのだが、そのテーマには以前から興味があった。キリスト教的な人間像云々といった思想史的なことよりも、ファウストという老学者が悪魔に魂を渡してまでも求めようとしたものを知りたいと思ったからだ。もちろん、ファウストの人間像はその時代や思想の状 . . . 本文を読む
『老いる準備』(上野千鶴子・著、学陽書房)
ここ数年、老いというものを意識するようになった。とくに昨年あたりからは、その意識が加速してきているように思う。それは生理的な現象や、心理的な面でも衰えをかなりはっきりと自覚し始めているからだろう。たとえば、視力にだけは自信があったのだが、メガネを必要とする場面がめっきり多くなってきた。テレビでよく見ているタレントやアイドルの顔は思い浮かぶのに名前が思 . . . 本文を読む
がんから始まる(岸本葉子・著、晶文社)
もう亡くなってから10年くらいになるだろうか、ある意味で両親以上に世話になった女性がいた。女性というよりは、自分のなかでは血のつながっていないお婆ちゃんのような存在で、とても働き者の人だった。子どもの頃から、その人が自分のことを評して、よく「魂の古い子」だといっていた。いわれた本人は意味もわからず怪訝な感じがしたものだが、あまり悪い気はしなかった。その人の . . . 本文を読む
遊びを育てる(野村寿子・著、協同医書出版社)
いまさらながら遊びとの出会いが少ない幼少期だったと思う。他の子どもと同じ体験ができなかったということもあるが、それ以前に親を含めた周囲の大人の気遣いで遊びとの出会いそのものが少なかった。安全を気遣ってくれたことには感謝しなければならない。けれども、その気遣いが先行して結果的に遊びとの出会いを遠ざけた。そして、自分の「身体性」の発達に何らかの影響を与え . . . 本文を読む