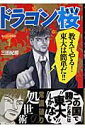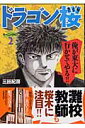今夜フジテレビで「遙かなる約束」というドラマが放映される。このドラマは実話をもとにしており、主人公のモデルであるご夫婦、そしておそらくロシア人の女性もご健在なはず。実はこの話のもとになっている「クラウディア奇蹟の愛」をモチーフに以前舞台も上演されていて、観にいっていたから番宣でピンと来た。その時は今回阿部寛さんが演じる役を佐々木蔵之介さんがやっていた。ちなみに「慣れているからどう?」と言われたわけではないだろうが、今回も脇役で出るようだ。内容はこれからの放送なので何だが、日本人男性のシベリア抑留の話である。他のケースと大きな違いは、いわれないスパイ罪のために負うことになった日本帰国までの果てしない長さで、帰国は1990年代後半ということだったはず。舞台では原作に忠実(多分、原作のタイトルから憶測)に、クラウディアと主人公の関係が中心だったが、おそらくドラマではキャスティングやタイトルから考えて、長年帰国を待っていた久子さん中心に描かれるのだろう。
いずれにしても、壮絶な人生を感じると同時に、一人の人間の崇高な生命力に気づかされる。少し前に歴史の履修が問題になっていたが、まさに一人の人の人生を通した近代史の一端をどういう形であれ、知ることは悪くないと思う。歴史を知ることは、単に世の中や国際社会で恥ずかしくないようにということだけでなく、先人や他者に畏敬の気持ちを持つことや、自分の命そのものの意味を考えることにもつながる。
先週の「東京タワー」も、続編製作が決まった「ALWAYS~三丁目の夕日」も、どちらも名作だとは思うけど、最近メディアが映画、単発、連ドラと、繰り返し製作しブームを作り出している作品は、ちょっと近視眼的すぎるきらいもある。いま、40代の人の半生や昭和30年代に揃いも揃って郷愁を感じるのは早すぎないかなぁ。まあ、別に戦争に関連するものを好んで観る必要はないけれど、よく巷で言われているアメリカと戦争したことを知らない子どもが多い(中国だと思っているらしい。まったくの間違いじゃないが、そういうことじゃなく単なるイメージで勘違いしているのだろう)とか、そもそも日本が戦争をしたことを知らないとか、それが本当だとしたら、それは笑いごとではない。
経済的な格差社会も問題かもしれないけど、心の格差の方が取り返しはつきにくい。
追記:「遙かなる約束」のドラマそのものがそんなに良いものかどうかは、当然ながらまだ観たわけではないのでまったくわかりません。観たのは佐々木蔵之介が特殊メイクなしのサラサラヘアで、80歳くらいまで演じ続ける舞台だけです。