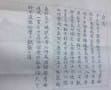平成28年度(第22期) にいがた市民大学入学式兼公開講演会
予てより準備を進めて参りました、標題の入学式・講演会の場に於いて「結いの会」活動状況が下記の日程で実施されま した。
当会に於きましては、会の発足時より、等身大の活動に心がけつつも、顧問始め会員の熱意により、発表資料の通り
「明るく」「楽しく」「元気よく」モットーに活動して参りましたが、六月五日は当会に取まして、記念すべき一日となり ました。発表会終了後の打ち上げは「海老の髭」で行われましたが、今後も当初の目的に沿って活動して行く事を皆で誓い 合いました。
発表された「頼さん」、打ち上げを企画して頂いた「柴さん」お疲れ様でした。
そして、打ち上げの席上で新規にご加入頂きました「やまさん」今後とも宜しくお願い致します。
なお、発表会模様は主催者の了解を得てビデオ撮影致しました。完成しましたら皆様へ記念に贈呈致します。
出来栄えは保証出来ませんが、お楽しみに。
日 程 平成28年6月5日(日) 午後2時から午後4時10分まで(開場:午後1時30分)
会 場 新潟市民プラザ 出席者 470名
対 象 平成28年度 にいがた市民大学 受講生 及び 一般市民
プログラム内容
【第一部:入学式】
■ あいさつ にいがた市民大学学長 荒川 正昭
14:00~14:05( 5分)
■ にいがた市民大学受講生による自主グループ活動報告 ~“学び”の地域還元~
市民大学OBの会「結いの会」活動状況報告
14:05~14:15(10分)
■ 平成28年度(第22期)にいがた市民大学講座紹介
にいがた市民大学運営委員会委員長 中平 浩人
14:15~14:25(10分)
〈休憩 14:25~14:30(5分)〉
【第二部:公開講演会】
■ 基調講演 「戦国武将の学び―何を学び,どう生かしたか」
静岡大学名誉教授・文学博士 小和田 哲男 氏
14:30~16:00(90分)

生涯学習センターからの御礼
下記の通り、生涯学習センターのご担当からお礼のメールが届きました。
「結いの会」
代表 様
お世話になります。
昨日の市民大学入学式では大変お世話になりまして,ありがとうございました。
市民大学の魅力を最大限にお伝えいただきまして,本当にありがとうございました。
発表者の頼様,元気にご挨拶いただきましたメンバーの方にもくれぐれもよろしくお伝えください。
皆様の今後のますますのご活躍を祈念しております。
今後とも,お世話になりますが,よろしくお願いいたします。
予てより準備を進めて参りました、標題の入学式・講演会の場に於いて「結いの会」活動状況が下記の日程で実施されま した。
当会に於きましては、会の発足時より、等身大の活動に心がけつつも、顧問始め会員の熱意により、発表資料の通り
「明るく」「楽しく」「元気よく」モットーに活動して参りましたが、六月五日は当会に取まして、記念すべき一日となり ました。発表会終了後の打ち上げは「海老の髭」で行われましたが、今後も当初の目的に沿って活動して行く事を皆で誓い 合いました。
発表された「頼さん」、打ち上げを企画して頂いた「柴さん」お疲れ様でした。
そして、打ち上げの席上で新規にご加入頂きました「やまさん」今後とも宜しくお願い致します。
なお、発表会模様は主催者の了解を得てビデオ撮影致しました。完成しましたら皆様へ記念に贈呈致します。
出来栄えは保証出来ませんが、お楽しみに。
日 程 平成28年6月5日(日) 午後2時から午後4時10分まで(開場:午後1時30分)
会 場 新潟市民プラザ 出席者 470名
対 象 平成28年度 にいがた市民大学 受講生 及び 一般市民
プログラム内容
【第一部:入学式】
■ あいさつ にいがた市民大学学長 荒川 正昭
14:00~14:05( 5分)
■ にいがた市民大学受講生による自主グループ活動報告 ~“学び”の地域還元~
市民大学OBの会「結いの会」活動状況報告
14:05~14:15(10分)
■ 平成28年度(第22期)にいがた市民大学講座紹介
にいがた市民大学運営委員会委員長 中平 浩人
14:15~14:25(10分)
〈休憩 14:25~14:30(5分)〉
【第二部:公開講演会】
■ 基調講演 「戦国武将の学び―何を学び,どう生かしたか」
静岡大学名誉教授・文学博士 小和田 哲男 氏
14:30~16:00(90分)

生涯学習センターからの御礼
下記の通り、生涯学習センターのご担当からお礼のメールが届きました。
「結いの会」
代表 様
お世話になります。
昨日の市民大学入学式では大変お世話になりまして,ありがとうございました。
市民大学の魅力を最大限にお伝えいただきまして,本当にありがとうございました。
発表者の頼様,元気にご挨拶いただきましたメンバーの方にもくれぐれもよろしくお伝えください。
皆様の今後のますますのご活躍を祈念しております。
今後とも,お世話になりますが,よろしくお願いいたします。