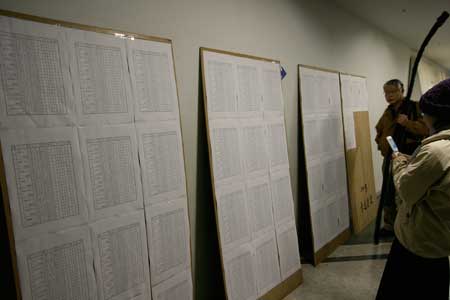行ってきました。都城へ。
まずはちょっと日付を巻き戻して昨日の朝から。
朝6時半に山口のホテルを出発し、高速道を南へ降りていきます。途中で壇ノ浦PAで軽い朝食をとることにしました。

なんて素晴らしい景色!もちろんこういうスポットは今までバス旅行とかで立ち寄ったことはあります。しかし、自分で運転して一人で見るってのは格別です。気分も高揚してきたので引き続きドライブドライブ。
途中で弓のT先生を拾って都城へ。
都城ではただいま全国弓道大会で弓まつりが行われていたのです。もちろん私がわざわざ慣れない高速で長時間ドライブを決行したのは、念願だった自分の弓を購入するため。
この大会は全国から参加者が集まっており、隣町の馴染みの先生達もいました。
「いい弓が出ちょるよ。そして安いっちゃん!」と感激している先生も。
私も期待に胸を膨らませて弓屋さんの展示場へ足を運びます。あるある。弓道具店でよく見かける弓が勢揃いです。
小倉紫峯、横山黎明、永野重次、楠見蔵吉、南崎寿宝…。

「ほぉ~。これはいいね!これいいよ!」とT先生が感激したニベ弓を見たら24万円。しかもそれ、売却済みでした。
最近は合成接着剤を使っている弓が多いらしいのですが、ニベ弓もそこそこ出ており、ほとんどは既に売却済み。やっぱり良い弓は高くても、希少価値のせいか、すぐに売れてるみたいです。
私は以前櫨の勉強会に参加してくれた南崎裕一さんのところに行きました。南崎寿宝四代目である裕一さんの作る弓は、若いながらも冴えた弓を作るとの評判です。
「今は13kgを使ってるけど、希望としては15kgを引きたい。」と伝えて
10kg、11kg、12、13、14と見ていくと…ない!15kgがない!
「あ~。あの、ちょうど今、15kgがなくて…。」と南崎さん。
14kgでもいいかな~?とも思いましたが、竹弓を買う場合は妥協しない方がいいとのT先生のアドバイスもあったので、作ってもらうことにしました。
「煤竹にしますか?」と聞かれるので、違いを聞くと、外観の違いと弓の頑丈さだそうです。自然な色味を持った煤竹は美しく輝いてます。いろいろ迷った挙げ句、煤竹にすることにしました。出来上がるのは半年後だそうです。
「弐段の弓引きがオーダーメイドの煤竹とは贅沢な。」とT先生。
確かに今の私にはまだまだ贅沢ですが、良い弓を使うことで弓から教えられることも多そうです。
小物関係の販売コーナーでは「櫨蝋のワックス」も売られていました。横山黎明さん取り扱いです。
残ったわずかな時間に、決勝戦が行われている試合会場にも行きました。

昨年出場した西日本弓道大会を思い出しました。体育館の中での大会です。この喧噪の中で中てていくのは至難のワザです。男子で優勝したのは大分の方でした。
山口から都城まで400km以上走って疲れた一日でした。でも初めてのmy弓ができると思うと、ついつい頬が緩んでしまう私。これを励みに肝心の稽古もがんばろうと思います。
↓押してくださると励みになります。

人気blogランキングへ
まずはちょっと日付を巻き戻して昨日の朝から。
朝6時半に山口のホテルを出発し、高速道を南へ降りていきます。途中で壇ノ浦PAで軽い朝食をとることにしました。

なんて素晴らしい景色!もちろんこういうスポットは今までバス旅行とかで立ち寄ったことはあります。しかし、自分で運転して一人で見るってのは格別です。気分も高揚してきたので引き続きドライブドライブ。
途中で弓のT先生を拾って都城へ。
都城ではただいま全国弓道大会で弓まつりが行われていたのです。もちろん私がわざわざ慣れない高速で長時間ドライブを決行したのは、念願だった自分の弓を購入するため。
この大会は全国から参加者が集まっており、隣町の馴染みの先生達もいました。
「いい弓が出ちょるよ。そして安いっちゃん!」と感激している先生も。
私も期待に胸を膨らませて弓屋さんの展示場へ足を運びます。あるある。弓道具店でよく見かける弓が勢揃いです。
小倉紫峯、横山黎明、永野重次、楠見蔵吉、南崎寿宝…。

「ほぉ~。これはいいね!これいいよ!」とT先生が感激したニベ弓を見たら24万円。しかもそれ、売却済みでした。
最近は合成接着剤を使っている弓が多いらしいのですが、ニベ弓もそこそこ出ており、ほとんどは既に売却済み。やっぱり良い弓は高くても、希少価値のせいか、すぐに売れてるみたいです。
私は以前櫨の勉強会に参加してくれた南崎裕一さんのところに行きました。南崎寿宝四代目である裕一さんの作る弓は、若いながらも冴えた弓を作るとの評判です。
「今は13kgを使ってるけど、希望としては15kgを引きたい。」と伝えて
10kg、11kg、12、13、14と見ていくと…ない!15kgがない!
「あ~。あの、ちょうど今、15kgがなくて…。」と南崎さん。
14kgでもいいかな~?とも思いましたが、竹弓を買う場合は妥協しない方がいいとのT先生のアドバイスもあったので、作ってもらうことにしました。
「煤竹にしますか?」と聞かれるので、違いを聞くと、外観の違いと弓の頑丈さだそうです。自然な色味を持った煤竹は美しく輝いてます。いろいろ迷った挙げ句、煤竹にすることにしました。出来上がるのは半年後だそうです。
「弐段の弓引きがオーダーメイドの煤竹とは贅沢な。」とT先生。
確かに今の私にはまだまだ贅沢ですが、良い弓を使うことで弓から教えられることも多そうです。
小物関係の販売コーナーでは「櫨蝋のワックス」も売られていました。横山黎明さん取り扱いです。
残ったわずかな時間に、決勝戦が行われている試合会場にも行きました。

昨年出場した西日本弓道大会を思い出しました。体育館の中での大会です。この喧噪の中で中てていくのは至難のワザです。男子で優勝したのは大分の方でした。
山口から都城まで400km以上走って疲れた一日でした。でも初めてのmy弓ができると思うと、ついつい頬が緩んでしまう私。これを励みに肝心の稽古もがんばろうと思います。
↓押してくださると励みになります。

人気blogランキングへ