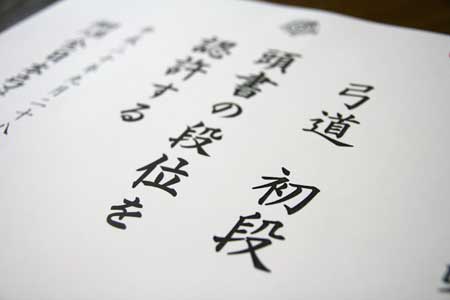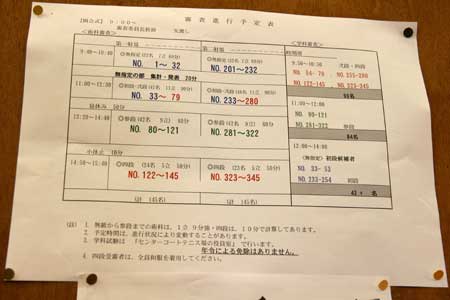今日はずいぶん寒くなってきたし、櫨並木の方もお客さんが少なかったので、夕方四時には片付けて六時前には弓道場の前にいました。いろいろとイベントやらが重なっていたので五日ぶりに弓を引くことになりました。
HookTailのお二人が来られてさっそく三人で自主練習。先生がいないのでイマイチ盛り上がりには欠けていました。しかもそういう時に限って、パンパンと中ったりして…。ま、ともかく久しぶりに引けて満足しました。
HookTailでは、今月末まで「カレンダーにしたい写真展」が開催されています。上の写真みたいに、窓枠を利用したギャラリーでとってもステキです。しかも動物たちのかわいい姿を激写されているではありませんか。はっ!私の櫨の写真も一応展示されているんですが、動物たちに比べるとかなり地味かも。投票でカレンダーにする写真が決まるそうですから、ぜひあなたの一票を櫨におながいします。
また、23日(日)のFBSテレビ「ナイトシャッフル」に2Fの「野の花」が登場するそうですので、そちらもお楽しみに。
それともう一つ。12月19日(金)にはHookTailさんで「はぜねこキャンドル作り」を行います。なぜに「はぜねこ」?それは猫好きが大喜びしそうなキャンドルを櫨蝋で作るからなんです。詳しくは続報をお待ちください。ただいま参加者を募集中です。申込はHookTailさんまで。
↓押してくださると励みになります。

人気blogランキングへ
HookTailのお二人が来られてさっそく三人で自主練習。先生がいないのでイマイチ盛り上がりには欠けていました。しかもそういう時に限って、パンパンと中ったりして…。ま、ともかく久しぶりに引けて満足しました。
HookTailでは、今月末まで「カレンダーにしたい写真展」が開催されています。上の写真みたいに、窓枠を利用したギャラリーでとってもステキです。しかも動物たちのかわいい姿を激写されているではありませんか。はっ!私の櫨の写真も一応展示されているんですが、動物たちに比べるとかなり地味かも。投票でカレンダーにする写真が決まるそうですから、ぜひあなたの一票を櫨におながいします。
また、23日(日)のFBSテレビ「ナイトシャッフル」に2Fの「野の花」が登場するそうですので、そちらもお楽しみに。
それともう一つ。12月19日(金)にはHookTailさんで「はぜねこキャンドル作り」を行います。なぜに「はぜねこ」?それは猫好きが大喜びしそうなキャンドルを櫨蝋で作るからなんです。詳しくは続報をお待ちください。ただいま参加者を募集中です。申込はHookTailさんまで。
↓押してくださると励みになります。

人気blogランキングへ