先のシャスポー銃と順番が前後しますが、
今回はシャスポー銃の元になったドライゼ銃の話。
ドライゼ銃(Dreyse Zündnadelgewehr)は1841年にプロイセン軍に採用された軍用小銃で、
世界初のボルトアクションライフルです。
Shooting Dreyse M.41 chambering m.47 cartridge.avi
ボルトアクションですが、動画にあるようにボルトハンドルは
閉鎖状態で水平もしくはそれより少し下になる後世の銃と異なり、
やや上で固定されます(というかこの動画で初めて知りましたよ…)。
というかコレ、今気づいたんですが、
現在のように定位置でロックされるんでは無くて押し付けるためにボルトを使ってるんですね…。
射手の人が毎回ボルトハンドルを叩くようにしてるのもこのためですね。
ガスシールを良くするために銃身(薬室後部)にはテーパーが設けられ、
逆にボルト前面には逆テーパーとなっており、両者が噛み合うことでガス漏れを防いでいる。
機構的な部分はこちらの動画が秀逸。
Zündnadelgewehr
ドイツ語なので詳細不明ですが、敵が前装銃なので普墺戦争でしょうか。
弾薬は紙巻の弾薬で弾丸・発射薬(黒色火薬)・雷管がひとまとめにされており、
それまでの前装銃と異なり、伏せたままで素早く弾薬を装填する事ができた。
その一方で雷管が弾薬中央にあるため、
発射薬の中を突き抜けていく長い撃針(ニードルガンと呼ばれる所以)を備えており、
この撃針は発射の度に高温に晒されるため焼損し、度々折れた。
閉鎖機構の堅牢さに欠け、弾薬の威力を上げる事ができず、
発射ガスのシールも不完全なドライゼ銃の欠点をフランス軍が改良したのが以前紹介したものがシャスポー銃である。
さて、当時最新鋭だったドライゼ銃(この名称は設計者のフォン・ドライゼに由来する)は日本にも纏まった数が輸入され、
普式ツンナール銃(普式=プロイセン式 ツンナール=針撃ち式を意味するドイツ語らしい)と一般的には呼ばれていた。
しかしシャスポー同様、やはり紙巻薬莢を使うドライゼ銃も
日本では湿気による不発に悩まされたのではないかと想像されます。
今回はシャスポー銃の元になったドライゼ銃の話。
ドライゼ銃(Dreyse Zündnadelgewehr)は1841年にプロイセン軍に採用された軍用小銃で、
世界初のボルトアクションライフルです。
Shooting Dreyse M.41 chambering m.47 cartridge.avi
ボルトアクションですが、動画にあるようにボルトハンドルは
閉鎖状態で水平もしくはそれより少し下になる後世の銃と異なり、
やや上で固定されます(というかこの動画で初めて知りましたよ…)。
というかコレ、今気づいたんですが、
現在のように定位置でロックされるんでは無くて押し付けるためにボルトを使ってるんですね…。
射手の人が毎回ボルトハンドルを叩くようにしてるのもこのためですね。
ガスシールを良くするために銃身(薬室後部)にはテーパーが設けられ、
逆にボルト前面には逆テーパーとなっており、両者が噛み合うことでガス漏れを防いでいる。
機構的な部分はこちらの動画が秀逸。
Zündnadelgewehr
ドイツ語なので詳細不明ですが、敵が前装銃なので普墺戦争でしょうか。
弾薬は紙巻の弾薬で弾丸・発射薬(黒色火薬)・雷管がひとまとめにされており、
それまでの前装銃と異なり、伏せたままで素早く弾薬を装填する事ができた。
その一方で雷管が弾薬中央にあるため、
発射薬の中を突き抜けていく長い撃針(ニードルガンと呼ばれる所以)を備えており、
この撃針は発射の度に高温に晒されるため焼損し、度々折れた。
閉鎖機構の堅牢さに欠け、弾薬の威力を上げる事ができず、
発射ガスのシールも不完全なドライゼ銃の欠点をフランス軍が改良したのが以前紹介したものがシャスポー銃である。
さて、当時最新鋭だったドライゼ銃(この名称は設計者のフォン・ドライゼに由来する)は日本にも纏まった数が輸入され、
普式ツンナール銃(普式=プロイセン式 ツンナール=針撃ち式を意味するドイツ語らしい)と一般的には呼ばれていた。
しかしシャスポー同様、やはり紙巻薬莢を使うドライゼ銃も
日本では湿気による不発に悩まされたのではないかと想像されます。



















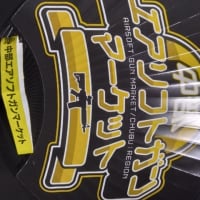
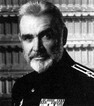





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます