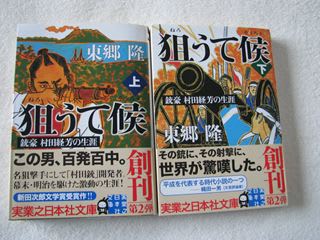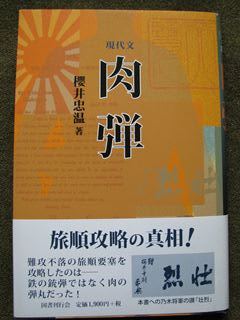決断できない日本
ケビン・メア著
文春新書
ISBN978-4-16-660821-8

「沖縄はゆすりの名人」という問題発言をしたとされ辞任した元米国務省日本部長、
ケビン・メア氏の著書。
氏の姿は最近はテレビでも時々目にしますね。
私はテレビをあまり見ない人なのでどんな事を言っている人なのかよく知らなかったのですが、
アメリカの政府当局者から見た日本の姿というのがどういうものなのか気になったので買ってみました。
冒頭に今回の震災とトモダチ作戦の舞台裏について述べられる。
特に気になるのはやはり福島原発にまつわる部分。
日本政府からもたらされる情報の少なさに苛立つ米政府。
しかしそれは情報を隠しているのではなく日本政府自体が碌に情報を得ていないのだろうという鋭い見方と
有効な対策を打ち出せない当時の政権に対する不信感。
支援品目を送ったら感謝と受け入れの連絡ではなく「破損、汚染したらどうするのか?」といった緊張感に欠ける質問が帰ってきたという信じられない事実。
この件に関してはいち早く支援を提案したものの断られた日航123便事故の際と重ねて書かれている。
何も学んでいないのか…。
また、当時話題となった在日アメリカ人の退避勧告についても触れられている。
自国民(ここではアメリカ人ね)の安全を考えたら最悪の事態を想定して東京から退避させる必要がある。
だが、そんな事をすれば日本人はパニックを起こし、日米同盟が崩壊してしまう。
この本には幾度となく日米同盟について書かれているが、
これを見た際に感心してしまった。
ヨーロッパ各国は早々に東京から自国民を退避させ、
国によっては大使館も大阪に避難させてしまっていたからだ。
2章では「ゆすりの名人」報道について書かれている。
詳しくはここで書かないが、
全て事実としたら濡れ衣以前の報道した側の大きな問題となるだろう。
その他、氏の外交官としての経歴や普天間問題に絡む沖縄の現状、
米国から見た日本の重要性について書かれる。
個人的には米国側から見た各総理大臣・政治家の印象が興味深かったですが、
それよりも興味深かったのはやはり日米同盟について。
アメリカから見て日本はアジアにおけるもっとも重要な国であってこれは今までもこれからも変わらない。
米中関係の改善を図っているが、日本との関係をないがしろにしているわけでは無く、
それはまた別の次元の問題である。
当然、今回の震災が起きた際に即座に助けたのは当たり前の事だと思っている。
などなど、「なるほど」と思って閉まった部分が多数。
逆に「今までなぜ気づかなかったのだろう」と思ったのは日米同盟の不平等さ。
アメリカは日本の憲法を理解しているので今の形になっているという点。
すなわち日本が攻撃を受ければアメリカは日本を支援するが、
アメリカが攻撃を受けても日本は支援をする必要がない(というか憲法でそれを否定している)という点。
我々は日米同盟というものについてあまりにも知らなさすぎる気がしてしまった。
最近も「わたしたちの同盟」というコミックで日米同盟について解説したコミックを在日米軍が公開しましたが、
これは本来、日本側が国民に教えるべき内容なんですよね。
また、国民性の違いというか、物の見方の違いには少々苦笑してしまった。
アジア歴訪で日本より中国に先に行ってもルートの問題でそれ以上の意図はアメリカ側は意識していないのに、
日本側は「我々より中国を優先した」と報道してしまう、っていう…。
あくまでメア氏個人の見方という部分もあるのだろうけど、
日本とアメリカの関係が気になる人は読んでみる価値のある1冊です。