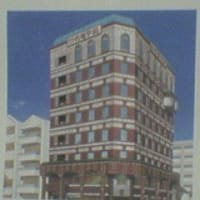(3、青春Ⅰ)
こんにちは。
えー…何だか賑やかになっていますが、それはそれとして講義は進んでいきます。
今回が初めてという人は、最初のオリエンテーションを読んで講義に臨んでください。
それから…もうひとつの連絡は…最後にしましょう。
今日はとっとと講義に入りましょう。
前回は「沖縄戦後史のスタート」についてやったわけですが、今回は青春…ここでは戦後沖縄の青春期を探っていきます。
その前に実際に「沖縄の青春」という映画があるのをご存知でしょうか。
正式には「カメジロー~沖縄の青春~」といい、本土復帰前のアメリカ統治下の那覇市長を務めた、瀬長亀次郎を描いた作品です。
1998年に沖縄で公開されました。
この映画で描かれた彼が市長に就任したのは1956年。
前の時間で話した当てはめで考えると、ちょうど沖縄が戦後の「青春期」にさしかかる時期です。
瀬長が市長に就任したときの沖縄は、米ソ冷戦が本格化し、アメリカにとって軍事的重要度が増した時期でした。
そのような中で、アメリか民政府の下でとはいえ、初の公選制での市長に瀬長は就任したのです。
瀬長は1907年生まれ。戦前から共産主義運動に携わり、戦後は「うるま新報」(「琉球新報」の前身)の社長に就任したものの、政治活動に傾注し、沖縄人民党(現在の日本共産党沖縄県委員会)の結成に参加します。
戦前のみならず、戦後も共産主義者ということで、アメリカ軍に「危険人物」のレッテルを貼られ投獄される経験を持っていました。
そのため、1956年12月、那覇市長に選挙の末に当選を果たしたことはアメリカ民政府、というよりもアメリカ合衆国そのものにとって衝撃でした。
アメリカ本土の新聞に「RED MAJOR」(赤い市長)と露骨に書かれたのは何よりの証であっただろうし、民政府の圧力により就任翌日から沖縄の経済団体、企業、銀行といった資本が、市の財政への援助を取りやめを、県内の新聞で次々に告知するようになります。
那覇市にとってこの援助取りやめは、当時戦災からの復興にまい進していた流れの中で、非常に痛手となる、はずでありました。
なぜなら復興のための公共事業をストップせざるを得ないのですから。
しかしここで予期せぬ出来事が起こります。
この苦境の中、市民がこぞって納税に市役所に押しかけたのです。
少しでも瀬長による市政、市財政の助け、そしてストップした事業の再開を願っての行動でした。
納税のためにやってきた大勢の市民により市役所は混乱します。
だがこの結果、市民の納税率は96%に達し、公共事業は再開されました。
瀬長は言いました「世界中のどこにこのような市民がいるだろうか」と。
困ったのはこの「世界中のどこにもいない市民」により目論見を崩された民政府でありました。
そこで次の手として市会(市議会)の親米派に不信任案を上程させるように命じます。一回目は失敗しましたが、二回目は成功し、瀬長の市長就任の半年後にあたる、1957年の6月、市会は解散し、出直し選挙となります。
結果は人民党などの反米派が「民主主義擁護連絡協議会」(民団)を結成し、多数派の形成に成功し、またしても民政府の「瀬長外し」は阻止されます。
ちなみに民団は後の県知事選挙などに見られる革新共闘の礎となります。
窮地に立った民政府はなりふり構わず、最後の手段に出ます。
法律、ここでは民政府統治下の沖縄に敷かれていた、「市町村会議員及び市町村長選挙法」の改正に乗り出したのです。
瀬長のために「何人も重罪に処せられ、または破廉恥に関わる罪に処せられた者で、その特赦を受けていないものは、市町村長または市町村議員の被選挙権を有しない」という新たな文言を付け加えたのです。
瀬長は前述の通り、共産主義運動や人民党の結成に関わったことで、民政府に逮捕された経験があり、この文言の内容に該当します。
こうして瀬長は1957年11月、市長就任からわずか一年弱でその職を追われることになりました。
しかし瀬長は市長辞職の際、市民に向けて高らかに演説しました。
「私たちは負けたのでしょうか。私たちは勝ったのです。米軍は自分たちの民主的な法を切り崩すことを余儀なくされ、最後の手段を講じた。それは負けを認めたことなのです」
市長の座を辞した瀬長は、1967年にようやく本土への渡航が許されると、各地で沖縄の実情を訴え、本土復帰直前の1970年の国政参加選挙から1990年までの引退まで連続六期、沖縄選出の衆議院議員となります。
またこれと並行して、最後は委員長まで務めた沖縄人民党を本土復帰の際に日本共産党に合流させ、自身は議員引退まで党の副委員長…いわば「沖縄革新の顔」として働きました。
人柄もよく、2001年の死去まで、県内外・党内外から親しまれ続けました。、
…というところで、この続きは次の時間に。
それはそうと…ここへのクリック、本当にお願いします。
ここにきて順位が低迷しています。
これがすべてとは言いませんが…でも低いより高いほうがいいので…本当にお願いします。
…といったところで、次も乞うご期待。
こんにちは。
えー…何だか賑やかになっていますが、それはそれとして講義は進んでいきます。
今回が初めてという人は、最初のオリエンテーションを読んで講義に臨んでください。
それから…もうひとつの連絡は…最後にしましょう。
今日はとっとと講義に入りましょう。
前回は「沖縄戦後史のスタート」についてやったわけですが、今回は青春…ここでは戦後沖縄の青春期を探っていきます。
その前に実際に「沖縄の青春」という映画があるのをご存知でしょうか。
正式には「カメジロー~沖縄の青春~」といい、本土復帰前のアメリカ統治下の那覇市長を務めた、瀬長亀次郎を描いた作品です。
1998年に沖縄で公開されました。
この映画で描かれた彼が市長に就任したのは1956年。
前の時間で話した当てはめで考えると、ちょうど沖縄が戦後の「青春期」にさしかかる時期です。
瀬長が市長に就任したときの沖縄は、米ソ冷戦が本格化し、アメリカにとって軍事的重要度が増した時期でした。
そのような中で、アメリか民政府の下でとはいえ、初の公選制での市長に瀬長は就任したのです。
瀬長は1907年生まれ。戦前から共産主義運動に携わり、戦後は「うるま新報」(「琉球新報」の前身)の社長に就任したものの、政治活動に傾注し、沖縄人民党(現在の日本共産党沖縄県委員会)の結成に参加します。
戦前のみならず、戦後も共産主義者ということで、アメリカ軍に「危険人物」のレッテルを貼られ投獄される経験を持っていました。
そのため、1956年12月、那覇市長に選挙の末に当選を果たしたことはアメリカ民政府、というよりもアメリカ合衆国そのものにとって衝撃でした。
アメリカ本土の新聞に「RED MAJOR」(赤い市長)と露骨に書かれたのは何よりの証であっただろうし、民政府の圧力により就任翌日から沖縄の経済団体、企業、銀行といった資本が、市の財政への援助を取りやめを、県内の新聞で次々に告知するようになります。
那覇市にとってこの援助取りやめは、当時戦災からの復興にまい進していた流れの中で、非常に痛手となる、はずでありました。
なぜなら復興のための公共事業をストップせざるを得ないのですから。
しかしここで予期せぬ出来事が起こります。
この苦境の中、市民がこぞって納税に市役所に押しかけたのです。
少しでも瀬長による市政、市財政の助け、そしてストップした事業の再開を願っての行動でした。
納税のためにやってきた大勢の市民により市役所は混乱します。
だがこの結果、市民の納税率は96%に達し、公共事業は再開されました。
瀬長は言いました「世界中のどこにこのような市民がいるだろうか」と。
困ったのはこの「世界中のどこにもいない市民」により目論見を崩された民政府でありました。
そこで次の手として市会(市議会)の親米派に不信任案を上程させるように命じます。一回目は失敗しましたが、二回目は成功し、瀬長の市長就任の半年後にあたる、1957年の6月、市会は解散し、出直し選挙となります。
結果は人民党などの反米派が「民主主義擁護連絡協議会」(民団)を結成し、多数派の形成に成功し、またしても民政府の「瀬長外し」は阻止されます。
ちなみに民団は後の県知事選挙などに見られる革新共闘の礎となります。
窮地に立った民政府はなりふり構わず、最後の手段に出ます。
法律、ここでは民政府統治下の沖縄に敷かれていた、「市町村会議員及び市町村長選挙法」の改正に乗り出したのです。
瀬長のために「何人も重罪に処せられ、または破廉恥に関わる罪に処せられた者で、その特赦を受けていないものは、市町村長または市町村議員の被選挙権を有しない」という新たな文言を付け加えたのです。
瀬長は前述の通り、共産主義運動や人民党の結成に関わったことで、民政府に逮捕された経験があり、この文言の内容に該当します。
こうして瀬長は1957年11月、市長就任からわずか一年弱でその職を追われることになりました。
しかし瀬長は市長辞職の際、市民に向けて高らかに演説しました。
「私たちは負けたのでしょうか。私たちは勝ったのです。米軍は自分たちの民主的な法を切り崩すことを余儀なくされ、最後の手段を講じた。それは負けを認めたことなのです」
市長の座を辞した瀬長は、1967年にようやく本土への渡航が許されると、各地で沖縄の実情を訴え、本土復帰直前の1970年の国政参加選挙から1990年までの引退まで連続六期、沖縄選出の衆議院議員となります。
またこれと並行して、最後は委員長まで務めた沖縄人民党を本土復帰の際に日本共産党に合流させ、自身は議員引退まで党の副委員長…いわば「沖縄革新の顔」として働きました。
人柄もよく、2001年の死去まで、県内外・党内外から親しまれ続けました。、
…というところで、この続きは次の時間に。
それはそうと…ここへのクリック、本当にお願いします。
ここにきて順位が低迷しています。
これがすべてとは言いませんが…でも低いより高いほうがいいので…本当にお願いします。
…といったところで、次も乞うご期待。