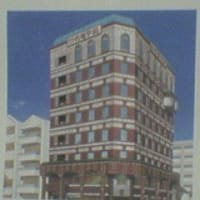(1、プロローグ)
こんにちは。
今日から新しい章に入ります。
まぁほぼ後半戦に入ったと考えてもらって結構です。
改めてよろしくお願いします。
そういうことも含めながら諸連絡を。
今回が初めてという人は、最初のオリエンテーションを読んでから、この講義に臨んでください。
それからここをクリックして、このブログの存在を高めてやってください。
先ほども言いましたが今日から後半戦です。
ビミョーな地位にいるため、佳境を迎えようとしている今、やはり存在を高めておきたいので是非是非お願いします。
2005年の今年、ご存知のように日本は戦後60年の節目を迎えています。
そしてこの講義を発信している北海道であろうと、この講義のテーマとしている沖縄であろうと、その節目への感慨はそれぞれにあるようです。
にもまして、60年というのは、人間で言えば「還暦」にあたります。
ということも含めての感慨もあるようで、テレビの特集などではその絡みで戦後を見つめなおす企画を目にします。
ならばと、私は戦後を人の人生というものに置き換えてみようと思い立ちましたみ。
1945年を出生とするならば、10代から20代とされる1955年から65年にかけて青春期があり、25歳前後の1970年ごろに結婚・就職などの転機で悩み、40歳前後の1985年ごろに不惑と言いながら現実には老いなどによる惑いの年齢を迎え、50歳前後の1995年ごろに還暦・定年を前にして自分を見つめなおし、そして60歳の還暦を2005年に迎える…といったところでしょうか。
そう考えると日本の戦後も、沖縄の戦後もこの置き換えにすんなりあてはまるような気がしてきます。
一方で沖縄の現状を考えるとき、どうしてもそこまでの歴史をたどらなければなりません。
しかしその作業は重く深い作業でもあります。
ここでは半ば乱暴ではありますが、「今」に直結する、沖縄の戦後政治史に的を絞ります。
しかしそれでもなお、重く深い作業にはかわりありません。
沖縄の戦後政治史と、本土のそれと明らかに違うのは、保守・革新の二者択一が極めて明確に存在し続けたということとその狭間で苦悩するリーダーがいたということです。
安易な保守・革新の相乗りで、生温くなった各地の地方行政や、密室政治がはびこってきた国政とは明らかに違うのです。
この章では、青春、苦悩、不惑、還暦直前…それぞれの節目にいたリーダーを取り上げながら、日本では、ともすれば「特異」とされてきた沖縄の戦後政治を見ていこうと思います。
それでは…乞うご期待。
こんにちは。
今日から新しい章に入ります。
まぁほぼ後半戦に入ったと考えてもらって結構です。
改めてよろしくお願いします。
そういうことも含めながら諸連絡を。
今回が初めてという人は、最初のオリエンテーションを読んでから、この講義に臨んでください。
それからここをクリックして、このブログの存在を高めてやってください。
先ほども言いましたが今日から後半戦です。
ビミョーな地位にいるため、佳境を迎えようとしている今、やはり存在を高めておきたいので是非是非お願いします。
2005年の今年、ご存知のように日本は戦後60年の節目を迎えています。
そしてこの講義を発信している北海道であろうと、この講義のテーマとしている沖縄であろうと、その節目への感慨はそれぞれにあるようです。
にもまして、60年というのは、人間で言えば「還暦」にあたります。
ということも含めての感慨もあるようで、テレビの特集などではその絡みで戦後を見つめなおす企画を目にします。
ならばと、私は戦後を人の人生というものに置き換えてみようと思い立ちましたみ。
1945年を出生とするならば、10代から20代とされる1955年から65年にかけて青春期があり、25歳前後の1970年ごろに結婚・就職などの転機で悩み、40歳前後の1985年ごろに不惑と言いながら現実には老いなどによる惑いの年齢を迎え、50歳前後の1995年ごろに還暦・定年を前にして自分を見つめなおし、そして60歳の還暦を2005年に迎える…といったところでしょうか。
そう考えると日本の戦後も、沖縄の戦後もこの置き換えにすんなりあてはまるような気がしてきます。
一方で沖縄の現状を考えるとき、どうしてもそこまでの歴史をたどらなければなりません。
しかしその作業は重く深い作業でもあります。
ここでは半ば乱暴ではありますが、「今」に直結する、沖縄の戦後政治史に的を絞ります。
しかしそれでもなお、重く深い作業にはかわりありません。
沖縄の戦後政治史と、本土のそれと明らかに違うのは、保守・革新の二者択一が極めて明確に存在し続けたということとその狭間で苦悩するリーダーがいたということです。
安易な保守・革新の相乗りで、生温くなった各地の地方行政や、密室政治がはびこってきた国政とは明らかに違うのです。
この章では、青春、苦悩、不惑、還暦直前…それぞれの節目にいたリーダーを取り上げながら、日本では、ともすれば「特異」とされてきた沖縄の戦後政治を見ていこうと思います。
それでは…乞うご期待。