AISの基地局をメーカ製5/8λ2段GPから研究会製8段同軸コリニアに取り替えて到達距離が3倍になった。
何度も書くが表面利得は3.1dBiの差しかない。これで3倍の到達距離はありえない!!
そこで電波伝搬の観点から考察してみる。
前提条件:
●ノイズ等も考慮して受信機の限界感度を-120dBmと仮定する。(ケーブル等の損失は考えない)
●基地局のアンテナは勿論8段同軸コリニア、この利得は解析値9.1dBi、給電点高さ10m。
●船舶側は5/8λ1段GP2.14dBi、給電点高さは5mとする。
●送信出力12.5Wとする。(クラスA)
この理想的な条件での到達距離を計算してみる。
基地局⇔船舶 25km時 受信側電界強度 -91.8dBm(Averageの指し示す距離)
(↑正しい無線機のSメータではRS57だ)
では50km時 受信側電界強度 -101.7dBmと計算される。
(↑正しい無線機のSメータではRS55だ)
更に75kmでは受信側電界強度 -108.8dBmと計算される。
(↑正しい無線機のSメータではRS54だ)
では想定した受信限界の-120dBmの距離は?150kmと計算される。
(↑正しい無線機のSメータではRS52だ。普通の無線機は既にRS51)
ちなみに-128dBmでは200kmとなる。
理想状態での到達距離:
つまり、最大到達距離は150-200k(80海里~107海里)になると考えられる。
では、現実にはどうだったか?AISのレポートを確認してみよう。

アンテナを換えた7-9日までの2日間のMaxは121.9海里、Averageは12海里となっている。
(基地局のロケーション、海抜0m、開けているのは南方向のみ!から考えると最大5000k平方のAriaCoveredを持つので上出来!) 黄色部分変更追記
8段同軸コリニアでの到達距離は計算通りの結果だ。(海上伝搬は計算どおりに飛ぶね)
この解析結果は現実とよく合致している。
この解析ツールは色んな場面で強力なツールとなっている。
(余談になるがプロの解析ツールで計算できなかった事例をこのツールはピタリと予測出来た。)
ではメーカ製5/8λ2段GPの水平線方向への利得計算に応用してみよう。
水平線方向への利得を未知数として、メーカ製GPでの最大到達距離39海里で-120dbmになる時の
アンテナ利得を探ってみた。
すると結果は-4dBiとなった。(表面利得表示は6dBi)
また、Averageでは3倍距離が違うので-10dBi
結論:
メーカ製2段GPの水平線方向利得 最大でも-4dBi、最悪値-10dbiとなった。
8段同軸コリニア 9.1dbi
利得差は最小でも13.1dBi,最大19.1dBiとなる。(設備不具合でこの差になった可能性もあるが)
見かけの利得ではアンテナは語れないものだ
一体真実はどこにあるのだろうか??
これは到達距離3倍になるのは『アンテナの打ち上げ角』が原因と仮定したシミュレーションであり、その仮定が間違っている可能性もあります。
またまた、コメントで論議になるかも??本テーマへ対しご意見を聞かせて下さい。










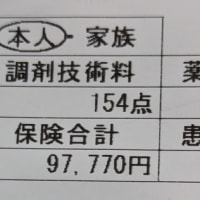








基地局に3エレほどの八木をマイナス仰角を付けて設置し実験してみるのもおもしろいと思います。但しビームなので無指向性アンテナとの違いを考慮する必要があります。
ところで5/8λのアンテナは3dBd、5.12dBi位の利得では?
このブログをご覧になったプロの業務局からコリニアの発注が来た!ので大変でした。勿論断ろうという話もありました。
で事前に予備実験を行いました。勿論、ほぼ同じ設備で。
実はこの時も同様の結果だったのです。つまり2段GP→8段コリニアでRS53がRS59に上昇したのです。
(Sメータの間隔が3dBならば18dB上昇・・と意識してなかったので・・その異常値に気づきませんでした。当時は軽いSメータだと!!)
またAIS装置が無かったので到達距離としては分からなかったわけです。
今思えば事前検証と一致していてアンテナ不良ではないでしょう。
XNFさんの仰る通り3エレで実験をしたいのですが・・業務局は東北なので簡単ではないです。
メーカのカタログ値は自由空間での値で表記されています。
第一電波工業
150MVⅡ:156〜157MHz(送信)、156〜162.5MHz(受信)
(国際VHF用)
●価格:28,000円+税
●全長:2.8m●重量:1,040g
●接栓:M-J●空中線形式:5/8λ2段●インピーダンス:50Ω●VSWR:1.5以下
●利得:6.0dBi●耐風速:50m/s
間違いなくローブだと思いますが、その差少なくとも-13.1dBiと計算されて・・・
これって八木のF/B比並みでしょ??
今朝、コリニアでの最大到達距離を確認したら120海里を越えていました。
最大到達距離も3倍となりました。
そして、現地のロケーションが不明ですが海の反対側に山や崖やビルがある場合はそれらの反射波が合成され海上方向の利得が高くなります。この場合もローブや利得の大きさが効いて来ます。同じ無指向性アンテナでも利得高ければ反射効果が大です。
そんな事も考えられると思うので利得の小さい八木はバックの反射の影響も小さいので実験出来れば色々考察できます。
他の方の意見もお聴きしたいですね。
この場所は大震災の被災地の海岸。まさに津波で根こそぎの場所?
なので高いビルはありません。
北から東に低い山があるのでその方向の飛びは今一です。開けているのは南側100°くらいです。
南の最大到達距離の120海里は水戸沖で、そこの船を捕捉したという事です。
これで場所が分かりましたよね。
本当に実験しようと思っています。スペアナで電界強度を調べて・・
ところで国際VHFが運用できる旧電話通や一級海上特殊無線技士の資格をなぜか持っていたりします。
低い山の反射で伝搬損失13dB~19dBを補償出来る可能性は?ないかも。
144NHzが周波数近いのでメーカ製で段数の多いものとも比較しようと思ったけど・・X700H(4段)でも8段コリニア(段数多いと地平線を這うようなローブになる)の相手にならないか?
あとメーカのGPはエレメントへ有効な給電がされてないので、下段の放射が支配的なんです。なので段数ほどにローブは下がらない。
一方同軸コリニアは全エレメント給電タイプのスタックなので。
これを街中で使うと信号が弱いのは当然!!
理論的にはこうなる。
確かにXNFさんにはそういうお友達がいたのを聞いてましたのでぜひ話を伺いたいですね!!
機会があれば宜しく!
おかしいのでは?単純にS?と書くべきなのでは??
確かに、指摘の通りですね。
ここで議論したいのは利得表記と飛びとの乖離の真相についてですが・・・