今年に入って同軸コリニアの調整会を2度開催したが新たな気付きがあったので書き留めておく。
やはり一番大きな収穫は、スタブをT型に接続に変更したことだ。今回も1.2Gの同軸コリニアで1.5Dを使ったスタブでも調整が難しかった(網線1本単位の調整を強いられた)のがきっかけになった。
実は別の1.2G同軸コリニアアンテナの失敗から段間接続を変更した経験がある。やはり1.2Gアンテナを作ると得るものは多かった。

最新作のこの同軸コリニアも『T型スタブ』を採用した。さらに段間は耐圧強化タイプだ。

で出来上がった430MHz同軸コリニアが下記の写真だ。
完成直前で「最上部位相整合部」「スタブ」の防水処理が残っている。流石に製作品も安定してきた。
段間の強化は塩ビパイプと塩ビ用の接着剤を使って固着してある。
【430MHz8段同軸コリニア】

スタブを変更したおかげで調整時の周波数の動きが素直になっている。私の作った製作マニュアルの430MHzアンテナの235mmと118mmで制作した。
特性は下記の通り
共振点は432.70付近
SWR 1.5以下は428.23~436.28の8MHz
SWR 2.0以下は438.66~423.14MHzの約15MHz
但し給電用の同軸ケーブルを取り付けると長さによっては・・・この特性にはならない。

430MHzの同軸コリニアも8-10段が色んな意味で使いやすい。










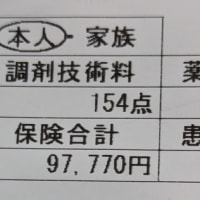








確かに周波数が高いと伝搬は悪化するのは間違いないですね。
144MHzでは届いても430MHzでは届かない!よくあります。
あと、八木では正対方向で普通は伝搬を検討しますが、反射もありますのでその点も考える必要があります。
また八木が全てではありません。
長野県飯田市(盆地)と神津島が144MHz5W同軸コリニアで交信できています。
八木正対方向で伝搬解析を行うとアルプス越えの伝搬ですので電界強度は受信限界値以下の-160dBと計算されます。
ところがS5で交信できています。八木では無いのでXX山反射もありません。
よく島とは交信できているようなので異常伝搬ではなさそうです。
でこの局はかつては元々コーナーリフレクター等の八木を使用されていたのですが今は同軸コリニアを愛用されています。
八木が全てではなく適材適所ですね
コーリニアの仰角を動かすのではなく、むしろ八木を回した方が良いのでは??
http://www.heywhatsthat.com/profiler.html で見ていると、荻窪-木更津は
地形断面に引っ掛かりがありました。
以上のサイトで◎Metricにチェック(これでkm表示)、Parametersのところで
1300MHzあたりを入力してみて下さい。
このところ、1200MHzのD-StarばかりQRVしており、430は通っても1200は通らない
場面によく出会います。
伝搬の解析を行いました。前提430MHz10Wアンテナ高10m(両方)アンテナ利得10dB(両方)の時、荻窪⇔木更津の電界強度は-110dB~115dBです。
430MHzでは常に交信できていると想定してます(あくまで計算値かつ見通しの場合)
これはS2程度で聞こえていることになります。
「430で荻窪と木更津市清見台」の交信が成立した際のSを確認して下さい。
上記よりも上だったか下だったかを確認ください。
●それを基準にすると分かると思います。
出力1W側では-10dBとなり電界強度は-120dB~125dBですので受信限界値以下の可能性があります。
10W側の送信は受信できる可能性はあります。
●しかし32段(これは八木15エレ程度の利得があります)ともなると垂直面は3-4°の幅しかなく僅かな傾きの変化でS9+が聞こえなくなるくらいに変化します。傾きを変えて試してください。これは非常に重要です。木更津10W側に送信してもらいアンテナの角度を変えてみる。
反射だとすると傾ける方向も変わります。
●VU帯の伝搬が延びるのは5月-7月ですのでそこで試して下さい。
●それぞれの場所のロケと標高を頂くともう少し確認できます。できれば正確な位置。←メールで。
まだまだ、考えられることはありますが・・頂いた情報ではこのくらいです。
何かありましたら詳しくはメールでお願いします。