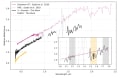軌道長半径 a = 1334 au 離心率 e = 0.98909 軌道系射角 i = 78度 近日点 q = 14.56 au 遠日点 Q = 2654 au 軌道の方向が悪くかなりの部分がヘリオポーズの外に出ているため表面が銀河宇宙線に曝される。以下、機械翻訳。
高傾斜ケンタウロス2012DR30の反射スペクトルで観察された近紫外線赤化https://arxiv.org/abs/2110.13934#
2021年10月26日に提出
高い軌道傾斜角とペリヘリア(i > 60度; q ≧ 15 au)を持つケンタウロスは、内側のオールトの雲から太陽系の巨大惑星領域に入ると予測される、よく理解されていない小惑星の小さなグループです。そのため、現在直接観測できる、比較的変更されていないオールトの雲の数少ないサンプルの1つです。ここでは、色と表面組成を制限するために、これらの天体の最大の1つである2012DR30の2つの新しい反射スペクトルを示します。2012 DR30の光学色が可変であるという報告とは対照的に、0.55〜0.8ミクロンのほとんどの新規および公開されたデータセットからのスペクトル勾配の一貫した測定値は、S≒10 ± 1%/ 0.1ミクロンのスペクトル勾配と一致することがわかります。不確実性。ただし、近紫外線/青および近赤外線波長での2012 DR30のスペクトル変動は、依然として比較的制約がありません。これらの領域のスペクトル変動を特徴づけるには、自己無撞着な回転分解された追跡観測が必要です。2012 DR30の表面での水氷の以前の検出を暫定的に確認し、また、約0.6ミクロンの波長から近紫外線波長に向かってそのスペクトルの勾配の着実な急勾配を一貫して観察します。観察された発赤の原因となるもっともらしい表面材料には、フィロケイ酸塩に含まれる酸化第二鉄、および芳香族耐火有機物が含まれる場合があります。 . . . 本文を読む
ケンタウロス族2013VZ70は土星に捕獲された彗星というよりも衛星同士の衝突事故で分離した衛星の欠片説です。以下、機械翻訳。
ケンタウロス族2013VZ70:土星の不規則衛星のメンバーの残骸? 2021年10月8日に提出
環境。土星には不規則衛星が過剰にあります。これは過去の衝突事件の結果であると考えられています。ホスト惑星の近くでそのようなエピソードの間に生成された破片は、準衛星および/または馬蹄形の共鳴状態に閉じ込められた共軌道に進化する可能性があります。最近発表されたケンタウロス、2013 VZ70は、順行土星の共軌道の軌道と互換性のある軌道をたどっています。
目的。土星との共有軌道関係を確認または拒否するために、2013VZ70の短期的な動的進化の調査を実行します。土星の不規則衛星の人口との可能な関係も調査されます。 . . . 本文を読む
6月下旬に超巨大彗星でニュースになったベルナーディネッリ・バーンスティーン彗星の観測結果 近日点10.97AU 遠日点40,400±260au 軌道傾斜角95度 直径は約150 km 以下、機械翻訳。
C/2014UN271(ベルナーディネッリ・バーンスティーン彗星):ほぼ球形の彗星の牛 2021年9月22日
概要
C / 2014 UN271(ベルナーディネッリ・バーンスティーン彗星)は、オールトの雲からやってくる彗星で、注目に値します。
よく測定された彗星の中で最も明るい(そしておそらく最大の)核を持ち、
オールトの雲のどのメンバーよりも遠い、日心距離rh≈29auで発見されました。で説明します . . . 本文を読む
軌道傾斜角95度と黄道面にほぼ垂直な軌道で接近してくるので探査機を送るにしても土星スイングバイで軌道を95度曲げなきゃいけない。電源も太陽から遠いからRTGに頼るしかないだろう。以下、機械翻訳。
太陽系氷惑星の距離で巨大なオールトの雲彗星が光る
天文学者は、オールトの雲から来たこれまでに記録された最大の彗星を発見しました。そして、天王星の軌道を超えて、地球と太陽の間の距離の20倍(20天文単位)で、それはすでにガスを放出しています。
長周期彗星図すべての長周期彗星は、太陽系を取り巻くオールトの雲から来ていると考えられています。しかし、2014 UN 271は、その雲の中に特に細長い軌道と遠いターンアラウンドポイントを持っているという点で独特です。(この図は概念的なものであり、このオブジェクトの軌道を表すものではありません。)
NAOJ
6月22日にナミビアの0.51メートルのSkyGemsリモート望遠鏡で行われた新しい観測は、「15秒角のコマを伴う明確な彗星活動」を明らかにしています。ルカ・ブッツィは今朝、小惑星メーリングリストで報告しました。 . . . 本文を読む
太陽系内部に降りてきた氷天体がいきなり木星族彗星に成るわけでは無く。ケンタウロス族から木星トロヤ群に移行して潜伏のはずがコマどころか尾まで出して彗星バレバレじゃないか。以下、機械翻訳。
彗星は木星の小惑星の近くでピットストップをします 2021年2月26日
太陽に向かって数十億マイル移動した後、巨大な惑星の間を周回している気まぐれな若い彗星のような物体が途中で一時的な駐車場を見つけました。オブジェクトは、木星と一緒に太陽を周回しているトロヤ群と呼ばれる捕獲された古代の小惑星の家族の近くに落ち着きました。トロヤ群の集団の近くで彗星のような天体が発見されたのはこれが初めてです。 . . . 本文を読む
見たら分かるケンタウロス族から木星族彗星に軌道進化してる奴や。
アクティブケンタウロスP / 2019 LD2(ATLAS)の同時多波長および予備観測 2020年11月19日に提出
Gateway Centaur P / 2019 LD2(ATLAS)(Sarid et al。、2019)の発見は、太陽系小天体のケンタウロス軌道からジュピターファミリー彗星(JFC)への軌道移動を約40年にわたって観測する最初の機会を提供します。これから(Kareta et al。、2020、Hsieh et al。、2020。)ゲートウェイ遷移領域は、水氷が彗星活動に動力を与えることができる場所を超えているため、そこでのコマ生成はすべてのケンタウロスほどよく理解されていません。2020年7月2日から4日までのLD2の同時多波長観測を紹介します:ジェミニノース可視イメージング、NASA IRTF近赤外分光法、およびAROサブミリ波望遠鏡ミリ波長分光法。Precovery DECamイメージは、ニュークリアスの有効半径を\ simに制限します〜1.2 km以下で、カタリナスカイサーベイのアーカイブデータは、明るさの滑らかな変化のみを示しています。LD2のコマの観測された色はg' g′−r′= 0.70 ± 0.07およびr′−私′= 0.26 ± 0.07であり、ダスト生成率は〜10 - 20 kg / sです。LD2のコマ形態を使用して、V 〜、0.6 - 3.3 m / sの間のダストコマの流出速度を推定しました。LD2に対するCOは検出されないため、2020年7月2〜3日の生産率の上限はQ (CO )< 3.8 x 10 27 mol s − 1(3- σ)。近赤外スペクトルは、粒子サイズに応じて1〜10 \%レベルの水氷の証拠を示しています。 . . . 本文を読む
探査機が接近したアロコスやチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星が二葉形状なので小さな氷天体が接触連星のような形状になるのは多数派だと思っていたら、太陽系外縁天体が大体二葉形状なのでは無く太陽に近づくケンタウロス族から木星族彗星に軌道変化する中で、昇華と自転速度加速により引き延ばされて二葉形状になる説です。ふーん。以下、機械翻訳。
昇華トルクによる二葉彗星形状の形成 2020年11月3日に提出
最近の宇宙船とレーダーの観測によると、短周期彗星の核の約70%、主に木星ファミリーの彗星(JFC)は、二葉の形をしています(2つの塊が狭い首でつながっています)。これは、同様のサイズの小惑星の形状とはまったく対照的であり、その約14%が二葉です。これは、彗星に特有のプロセスまたはメカニズムがこれらの形状を生成していることを示唆しています。ここでは、JFC核の二葉形状が、太陽系外縁天体からケンタウロス集団を通って木星ファミリーに動的に移動する際の昇華活動の自然な副産物であることを示します。この動的な移動中に揮発性の昇華から生じるトルクをモデル化し、それらがこれらの核をスピンアップして破壊する傾向があることを発見しました。一度混乱すると、∘)それらを二葉のオブジェクトとして再形成させます。JFCは、木星ファミリーに入る前に回転破壊イベントを経験した可能性が高いことがわかりました。これは、二葉形の有病率を説明する可能性があります。これらの結果は、観測された彗星の二葉形が、太陽系の形成や惑星移動や太陽系外縁天体の居住中の衝突ではなく、その歴史の中で最近(過去1〜10 Myr以内に)発達したことを示唆しています。 . . . 本文を読む
過渡的な木星型トロヤ群のような軌道のP / 2019 LD2(ATLAS)
2020年7月28日に提出
彗星P / 2019 LD2は現在、ジュピタートロイの木馬に似た軌道要素を持っているため、表面的には、この集団のメンバーの揮発性コンテンツとアクティブな行動を初めて研究するユニークな機会を表しています。ただし、数値積分は、2018年7月に現在のジュピタートロイの木馬のような軌道に到達する前はケンタウロスであったことを示しており、2028年2月にケンタウロスに戻り、最終的に2063年2月に木星ファミリーの彗星になると予想されています。P / 2019 LD2の事例は、現在および今後の広視野調査で発見された小さな太陽系の天体を迅速かつ確実に動的に分類するメカニズムの必要性を強調しています。 . . . 本文を読む
太陽系外縁天体を太陽系内部に落とすのも難しいが巨大惑星に当たらない程度に近づいて公転軌道を伸ばしてもらう運の良さはどのケンタウロスに舞い降りてくるのか?以下、機械翻訳。
ケンタウロスと巨大惑星を横断する個体群:起源と分布 2020年6月17日に提出
現在の巨大惑星領域は、海王星以遠天体(TNO)が木星族彗星(JFC)になる途中で交差する移行帯です。それらの動的な振る舞いは、TNOの固有の動的な特徴と、巨大惑星との遭遇によって条件付けられます。Giant Planet Crossing(GPC)集団( auオブジェクト)に対処します5.2< q< 30au)太陽系の現在の構成を考慮して、それらの数とその発生源からの進化を研究する。この主題は、以前の調査から見直され、また、散乱ディスクオブジェクト(SDO)の動的進化の新しい数値シミュレーションによって対処されます。GPCの固有軌道要素分布のモデルを取得します。散乱ディスクは、進行性のGPCとケンタウロスの主な発生源を表していますが、プルティノスからの寄与は、SDからの寄与の1桁と2桁の間です。モデルからGPCの数とサイズの分布を取得し、 のSDから9600 GPCを計算し、を計算しますD > 100km〜10^8 D > 1km現在の人口の。他のソースからの貢献は無視できると考えられます。Centaurゾーンの平均寿命は7.2 Myrですが、GPCゾーンのSDOの平均寿命は68 Myrです。後者は、GPCゾーンで最も長く存続する傾向が高い傾向である初期傾向に依存しています。寿命と近日点距離の相関関係もあり、近日点が長いほど寿命が長くなります。 . . . 本文を読む
太陽系に閉じ込められた星間惑星の証拠はない 2020年6月8日に提出
MNRASで発行された最近の2つの論文で、ナモウニとモライ(2018、2020)は、i)巨大惑星との逆行共軌道運動のオブジェクト、およびii)高い惑星を含む、いくつかの小さな太陽系天体の星間起源の証拠を主張しました傾いたケンタウロス。ここでは、著者の結論を無効にするこれらの論文の欠点について説明します。過去の数値シミュレーションは、実体の過去の進化を表したものではありません。代わりに、これらのシミュレーションは、検討対象のボディの短い動的寿命とその母集団の高速な減衰を定量化する手段としてのみ役立ちます。この急速な崩壊に照らして、観測された物体が初期の太陽系の星間空間から捕獲されたオブジェクトの集団の生存者である場合、これらの集団は信じられないほど大きいはずです(たとえば 木星の逆行性軌道の現在の主な小惑星帯の人口の約10倍)。より可能性が高いのは、観測されたオブジェクトは、遠隔太陽系の親貯水池からのオブジェクトの連続フラックスによって準定常状態に維持されている、人口の一時的なメンバーにすぎません。ハレータイプの彗星とオールトクラウドで、逆行性軌道の最も可能性の高いソースと高度に傾いたケンタウロスを特定します。 . . . 本文を読む