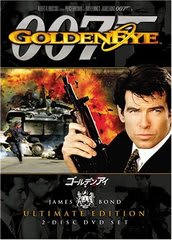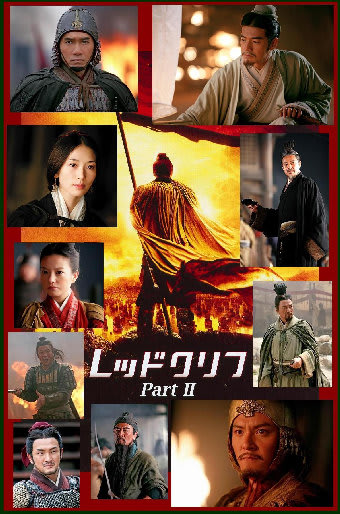この作品は、『バットマン』であって、バットマンでないようにも思いました。バットマン、ジョーカー、ゴッサムシティ、それぞれ架空の存在ですが、今の世の中とも結び付けて描いているようにも感じました。いってみれば”ゴッサムシティ”は架空のどんでもない犯罪の街ですが、それは混沌としている現代社会とリンクしてる。
高潔の正義について、まさに今の世の中に問うテーマだとも思います。ある意味バットマンの世界の中 . . . 本文を読む
久々の007作品のUpです。定期購入してるのですが、みてない作品めちゃたまってます。この『ゴールデン・アイ』は、前作『消されたライセンス』から6年もの間の空白を作ります。007シリーズの配給の権利をめぐって訴訟になっていたのです。本家のシリーズの版権をもつイオン・プロダクション(配給はMGM)と新シリーズをたちあげようとしたコロンビア映画(ソニーが買収)とで007シリーズの争奪戦がおこる . . . 本文を読む
『花より男子』(はなよりだんご)、かなり好きなんです。ドラマ化、映画化やアニメ化がされていますが、原作は、マーガレットに連載された神尾葉子さんによる少女漫画。(今や5800万部発行のNo1の少女漫画だそう)
内容は、学園ものの恋愛ストーリーで、大金持ちの生徒が通う学園を舞台に、それぞれが御曹司のルックスもいい4人組(F4:Flower4、花の4人組)となぜかこのセレブ学園に入学した一般庶民 . . . 本文を読む
栗本薫さんが逝去されて、1ヶ月が過ぎました。ネットでグインサーガの愛読者のみなさんの思いをみましたが、けっこう大半の人が、グインの物語は栗本さんの死とともに終わった・・・という受とめ方。
さてこうしてグインがアニメ化され栗本氏も(病に臥しながらも)テレビで放送を見てたと思ったら、お家にテレビがないそうで、DVDで見るのを楽しみにしていたそうです。こうしてテレビで放送されたら、また新たなファンも . . . 本文を読む
斬新でした。90分くらいの作品なのですが、見終わってなんかむかむかするなと思ったら、画面で酔った事に気づきました。
さて、この作品、いわゆる我々が旅行やイベントなどを撮影するハンディカメラで撮影した映像というのがコンセプトなのです。こういうコンセプトは、かつてはグロ映画『食人族』がありました。行方不明になった探検隊から回収されたビデオテープを再生すると、そこには撮影者が、現地住民に殺さ . . . 本文を読む
さて、前回『レッドクリフ』より三国志談義になってしまいましたが、今回は映画『レッドクリフ』です。前回も書きましたが、この2部作は間をおかずに見るべきです。
Part1を見終わっても、おれこの作品の主人公って誰かよくわかってなかったのですが、周瑜を演じたトニー・レオンだというのがやっとわかりました(アホ)。周瑜って頭脳明晰で容姿端麗の人として描かれており、ルックスはよかったんでしょ . . . 本文を読む
ジョン・ウー監督が三国志の世界を映像化した『レッドクリフ』見ました。もともとは1本の作品みたいですが、長くなったため2部作にしたみたいです。1作目と2作目は間をおいてはいけません。part1(先日民放でしてましたが)をDVDで見て当日か、翌日にすぐに映画館に行ってpart2を見るべきです。5時間くらいに縮めて1本にしたらかなり濃厚な作品だったでしょうね。(やっぱ長いか)
この作品は三国 . . . 本文を読む
原作のコミックは700万部突破なんですね。TVドラマもヒットしたのは知っていましたが、見る時間帯ではないですし。原作を知っている人は、この映画には批判的な感じですね。松下奈緒ちゃんが好きなのと、映画の舞台の場所にひかれて見ました。
まー、一途系純愛作品ですよね。原作では、軸となる主人公のカップルとその幼なじみ2人が深く描かれているみたいです。原作とか見ず、ストレートに映画をみたものにとっ . . . 本文を読む
公式DVDコレクション購入しはじめたので、整理する意味でも感想をUpします。
64年公開の007シリーズの第2弾。シリーズの中でも最上級の評価の作品ということですが、「たしかに」と思いました。エンターテイメント性とストーリーのバランスが素晴らしい作品のひとつだと思います。64年の作品というところがすごいです。今見ても十分楽しめる。
そして、このシリーズ2作目の質の高さと成功で007のシリーズ . . . 本文を読む
WOWOWの連続ドラマ第3弾『空飛ぶタイヤ』。WOWOW独自のカラーを打ち出しています。東京ドラマアワード(これまでと異なる視点で質の高い作品を選ぶ賞だそうです)でも「パンドラ」が大賞を受賞し、WOWOWのドラマ作りの視点が評価されています。「プリズナー」もその独自色を感じました。そして第3弾のこのドラマです。
大企業によるリコール隠しの罪と罰に焦点をあて、“現代社会の闇”に挑んでいます。例 . . . 本文を読む