VI.近年の科学技術動向
ここではロシアにおける近年の科学技術動向について言及する。スコルコボおよびロスナノ、並びに、日露共同研究の好例として味の素ジェネティカ研究所(AGRI)、国際連携の好例として国際科学技術センター(ISTC)の組織について紹介する。
1.スコルコボ
ロシアでは近年、基礎研究の成果を産業化やイノベーションに結び付けることが科学技術の最優先課題となっており、産業化に直結する投資政策の一環として開始されたのがスコルコボ計画である。
スコルコボ計画とは、2009年にメドヴェージェフ大統領(当時)が打ち出したロシアの近代化政策の一丁目一番地とも言える施策であり、経済近代化に向けて取り組むべき5つの方向性(エネルギー効率、原子力、宇宙・通信、医薬、IT)が示された。これは、米国のシリコンバレーと同じような研究開発拠点をモスクワ郊外のスコルコボに創設していく、つまり「ロシア版シリコンバレー」の形成を目指す計画である。計画はプーチンが3期目大統領に就任して以降も引き継がれ、現在進行中の建設工事は2020年に完成予定と言われている。
スコルコボの建設立案に至る背景には、ロシア固有事情として主に以下の3点があったと推測される。
- ●ロシアは基礎研究には強いが産業応用や開発に弱く、有望なシーズを十分活かしきれていないとの認識がロシアの知識層を中心にあった
- ●ソ連時代からの老朽化した研究インフラでは最先端の研究を行うことが難しい
- ●世界クラスの知的産物を生み出すためには、資源依存型の経済からの脱却を目指して早急にイノベーションを起こす必要がある。
ロシアにはスコルコボの建設に先立ち、同様の施策、例えば各種税の免税等の優遇措置が得られる経済特区の指定、特定の分野に特化したテクノパークの設立、ソ連時代の閉鎖都市という位置付けから宇宙・航空機や原子力といった特定の分野に分類されたサイエンス・シティへの指定変更等が実施されており、計画発表当初は、これら地区からはなぜ新たにスコルコボを作る必要があるのかといった疑問の声も囁かれた。
スコルコボ計画では4E(エネルギー効率、環境適合性、人間工学、経済効率)の実現を掲げ、魅力的な居住空間と商業化につながる数多くのイノベーションを起こしうる研究開発空間を一体とする世界最先端の都市環境の創設を目指している。研究開発の中心としてイノベーション・センターを置き、同センターでさまざまな研究開発や教育を実施することとしている。
2020年の完成にむけた主要ミッションは大きく分けて次の3つである。
- ●スタートアップ企業支援
- ●スコルコボの都市建設
- ●教育の充実。
第1の点については、スコルコボの建設が始まった2010年と同時に開始され、現在(2016年3月時点)にいたるまで続いている。その間、スコルコボが支援したスタートアップ企業は、のべ1,400社にのぼり、1万7,700もの新規雇用を創出した。
第2の点に関して、スコルコボの建設当初は、建設予算全てが国家予算によって賄われていたが、現在は30%が国家予算、70%が民間からの出資となっている。民間からの投資を積極的に呼び込みながら、2020年までの完成が目指されている。
第3の点はスコルコボ科学技術大学(スコルテック)に関係している。スコルテックは現在(2016年3月時点)、修士およびPhDを合せて315人、59人の教授を擁し、9つの研究教育イノベーション・センター(Centers for Research, Education and Innovation)を有する。2020年までに、この数をそれぞれ315名から1,200名に、59名から200名に、9から15に増やす予定である。キャンパスはまだ建設中である。

Ⓒスコルコボ側提供資料
スコルコボのテクノパーク(建設中)
ロシア国内外の80以上の企業がスコルコボとパートナー合意を結んでおり、うち63企業が実際に研究開発拠点をスコルコボに置いている。スコルコボでは、国内外の企業と積極的に協力協定を締結し、その誘致を招聘してきた。日本企業としては初めて、パナソニック・ロシアがスコルコボのイノベーション・センターに入居する旨の合意書を締結した。同社は2015年、パートナー企業として初めて日本からスコルコボに進出した企業である。多くの日本企業がスコルコボ進出に足踏みするなか、パナソニック・ロシアはスコルコボから見えるロシアの研究開発のあり方は重要との方針を持ち、積極的に関与していこうとする姿勢を打ち出している。
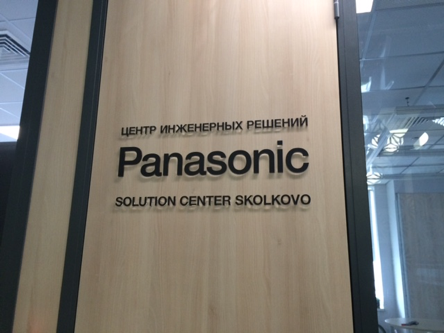
Ⓒ津田
スコルコボのパナソニック・ロシア事務所
ロシア政府が巨額の資金を投じてスコルコボ計画を成功させたいと躍起になる理由は一体何だろうか。それは、スコルコボの完成が、上述の5つの方向性に関する科学都市のモデルケースの成功例を打ち出すことにほかならず、それにより、国内外の民間企業や外国政府がロシアの研究開発拠点に進出・投資することのメリットを生み出すからである。また、行政機関の規制等により新技術の開発が遅れているロシアでは、スコルコボに参加することで得られる各種優遇措置が、産業界が研究開発投資を行うインセンティブを大きくし、規制緩和の重要性を社会や国民に知らしめる好例ともなりうる。
2.ロスナノ
限られた国家予算を重点的に配分することを目的に選定された優先的科学技術分野の一つに「ナノシステムと材料産業」がある。2007年の「ナノ産業発展戦略」の承認を受け、ナノテク重視の方向性が明確に打ち出された。これを受けて、ロシア政府が株式を100%保有する公開株式会社「ロスナノ」が設立されたのは2011年3月のことである。
ロスナノはその設立に際し、ロシア政府から1,300億ルーブルの資金譲渡を受けており、製造業につながるナノテク関連のプロジェクに投資を行っている。ロスナノは投資専門の機関であり、その投資条件の最重要項目は産業化時のインパクトの大きさである。2015年までのロシア国内のナノ産業の市場規模を9,000億ルーブルとし、うち自らが出資した企業による売上高を3,000億ルーブルとするとの計画を打ち出していた。この点については、2015年10月に東京で行われたロシア経済の近代化に関する日露経済諮問会議第5回会合の席上、「70以上の製造企業とナノテク企業の立ち上げに成功し、2015年の売り上げは3,000億ルーブルを達成」との発言がロスナノ側からなされた。
出資対象となるのは製品化直前の段階にある技術である。その出資要件は、代替エネルギー、バイオ医療、新材料、光学機械、金属加工等の分野においてナノテクに関連した技術的実現可能性を有し、2.5億ルーブル以上の売上げが見込め、ロシア国内に製造工場を置くことである。出資の形態は株式購入、債権購入、融資など多岐にわたる。
3.味の素ジェネティカ研究所(AGRI)
ジェネティカ研究所はソ連時代の1968年に設立された国営の企業研究所で、バイオテクノロジー分野、特に産業用微生物の遺伝子学および遺伝子工学の基礎研究では世界を牽引する研究所の一つである。微生物研究をもとに遺伝子組み換えされたタンパク質を用いて、アミノ酸、酵素、ビタミン、抗生物質等を製造するバイオプロセスの研究開発にも携わっており、基礎研究と応用開発を組み合わせた研究所の方針が世界市場における同研究所の成功と競争力の高さを裏付けている。
同研究所は、微生物の品種改良に関する優れた技術(アミノ酸生産におけるスレオニン菌の開発技術等)を有しており、この技術が日本の味の素株式会社の目に留まって、1982年には同研究所のアミノ酸技術の製造に係るライセンス契約が結ばれることとなった。その後、ジェネティカと味の素間で合弁企業設立の交渉が重ねられた結果、1998年に合弁企業「味の素ジェネティカ研究所(AJINOMOTO-GENETIKA Research Institute (AGRI)」が設立された。現在に至るまでAGRIでは、アミノ酸を生産するための微生物を開発する研究等が行われている。当初の出資比率は味の素とジェネティカ研究所が3:1であったが、2003年に味の素がAGRIを完全子会社化した。しかし、AGRI社長はロシア人であり、その他100人程度のロシア人研究者が在籍する。AGRIに所属する日本人は副社長をはじめ数名のみである。AGRIの運営は、ロシア人社長のもと、ロシア人研究者のアイデアや独創性を尊重しつつ、年度ごとの目標設定とその達成を評価するという、日露双方の長所を取り入れたかたちで行われている。AGRIから生み出される多くの研究成果は、味の素が有する世界の工場に輸出され製品化されている。こうした活動の結果として、AGRIはロシアで約120件の特許登録を行うとともに、国際特許も90件ほど取得している。AGRIは、味の素とジェネティカ研究所との双方の信頼関係を基礎として、ロシアの長所と日本の長所をうまく融合した日露研究開発協力の好例として、また、最優良の事例として特筆に価するだろう。
4.国際科学技術センター(ISTC)
国際科学技術センター(International Science and Technology Center:ISTC)は日本・米国・EUなどからの拠出金で成り立っている国際機関である。もともとはソ連崩壊に伴う軍事技術の不拡散のために、当該地域の軍事技術関連研究者に平和目的の研究開発を行わせ、彼らの雇用を創出することを目的に1992年に設立された(発足は1994年)。設立以降、ISTCは、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、グルジア、キルギス、タジキスタンといった旧ソ連諸国をサポートしてきた。ロシアからISTCに対しては、事務所の無償貸与出、資機材の無償提供、免税等の様々な優遇措置があったが、現実にはこれらすべてはロシア側が負担していると言ってもよかった。ところが、メドヴェージェフ大統領(当時)時代にロシアがISTCからの脱退を表明したため、事務所をロシア国外に移転せざるを得なくなり、2015年夏、新事務所がカザフスタンのアスタナに正式に開設された。
設立から20年以上を経て、ISTCの現在の活動は、旧ソ連の軍事技術等の不拡散の分野にとどまらず、研究プロジェクト支援から研究開発マネジメント等の市場経済化支援に至るまで多岐にわたっている。支援プロジェクトの対象分野も、バイオテクノロジー、再生可能エネルギー、ナノテクノロジー、環境回復保護・気候変動、原子力エネルギー、プロバイオティクス、宇宙航空等、広範な範囲に及んでいる。
資金支援を希望する旧ソ連諸国の研究者に研究プロジェクトの提案を出してもらい、採用されれば、拠出国側がその研究に必要な研究費と研究に従事する研究者の給料も支出するという仕組みをとっている。ISTCプロジェクトの実施を通じて、多くの研究者が研究の機会を得るとともに、国際ワークショップ等への参加を通じて、旧西側の研究者や企業とのマッチングも進められた。外国企業がISTCを通じて旧ソ連の研究機関に研究を委託するパートナープロジェクトは、2013年9月までの累計で142社、762件のプロジェクトを実施している。この中には、日立国際電気株式会社のように、高感度監視カメラ開発の分野で社内表彰されるような技術開発成果も生まれた。
VII.極東地域での科学技術活動
ここでは、ロシアの領土の中でも地理的に最も日本に近い地域である極東の科学技術活動を取り上げる。歴代のソ連・ロシアの指導者の中で、プーチン大統領ほどアジアを重視している人物は他にいないだろう。同氏が首相時代を含め、累次にわたり極東地域を視察してきた背景には、アジア太平洋諸国の活力と繁栄を極東開発に導入したいという切実な動機があると考えられる。
1.極東地域の概要
極東はロシア全体の約36%の面積を占めるのに対し、人口は約4.4%にすぎず、他の地域に比べて人口密度が極めて低い地域である。極東地域とは一般的に、アムール州、ユダヤ自治州、カムチャツカ地方、マガダン州、沿海地方、サハ共和国(ヤクーチヤ)、サハリン州、ハバロフスク地方、チュコト自治管区の9つの連邦構成主体からなる地域を指し、これら地域は極東連邦管区を構成している(図表28)。
図表28:極東地域を構成する連邦構成主体

出典:各種資料を元に筆者作成
極東の経済規模は小さく、地域総生産の全国シェアは5.6%にとどまっている。水産業(70.6%)や林業(10.5%)といった一次産業が古くから発達している一方で、二次産業である製造業は1.5%と極めて未発達である。生活必需品である消費財や食料品、自動車などは国内の他地域や近隣諸国からの輸入に依存する構造となっており、自動車の多くは日本製の中古車、市場に並ぶ衣類は中国製、家電機器は中国または韓国製といった状況である。
極東は地域としての一体性や相互の経済関係が薄く、電力不足や輸送システム等のインフラの未整備が深刻な問題として指摘されている。さらに、建設業の比率も高く、公共事業が経済を支える構図となっている。
2.極東開発に向けた施策
プーチン大統領が極東地域を強く意識したのは、2000年に中国黒竜江省と国境を接するアムール州の州都であるブラゴヴェシェンスクを訪問したことが契機だったとされている。連邦特別プログラム「1996-2005年の極東ザバイカル地域経済社会発展計画」が効果的に実施されておらず、極東開発政策を全面的に改める必要性が認識された。
極東開発が本格的に着手され始めたのは、2006年ごろからである。2007年には連邦特別プログラム「2013年までの極東ザバイカル地域経済社会発展計画」が、また2009年には新たに「2025年までの極東・ザバイカル地方社会経済発展戦略」が発表された。前者のプログラムがエネルギーや運輸といった分野に絞って極東地域の発展に不可欠なインフラと良好な投資環境を形成しようとしたのに対し、後者の戦略は極東地域全体の抜本的な発展計画となっている。同戦略では、計画を3段階に分け、第一段階(2009年~2015年)では、投資プロジェクトの始動や雇用の安定、省エネ技術導入等を実現し、続く第二段階(2016年~2020年)では、エネルギー、輸送部門の大規模プロジェクトを実施し、高品質製品の輸出増加を見込んでいる。最終の第三段階(2020年~2025年)では、アジア太平洋地域経済への統合とエネルギー分野の技術革新をもたらすとしている。
この戦略を受けロシア政府は、ロシア連邦国家プログラム「極東ザバイカル地域の社会経済発展計画」を2013年に公表した。本プログラムは、既に決定された連邦特別プログラム「2018年までの極東ザバイカル地域経済社会発展計画」とも連動しており、2014~2025年までの12年間の全期間を通じて、総額約3兆8,000億ルーブルの国家予算を投入することを見込んでいる。
このように、この10年ほどの間で極東地域の発展を支える政策や計画が立て続けに発表されている。これらを迅速かつ効果的に実施する組織として、極東発展省が新しく2012年に設立された。同省の主たる機能は、極東開発に係る連邦特別プログラムの実現に向けて活動調整を行うことにある。
3.科学技術体制とその活動
極東地域では、その気候的・地政学的条件を反映した同地域でしかできない研究分野に重点が置かれている。同地域の学術拠点はウラジオストクである。ウラジオストクを中心とする沿海地方やハバロフスク地方は軍事産業の拠点として広く知られているが、学術都市としての顔も併せ持つのである。ウラジオストクには、RAS極東支部(以下「FEB RAS」と略す)の本部があるだけでなく、極東地域で最大の総合大学である極東連邦大学が置かれている。以下では、FEB RASおよび極東連邦大学の組織概要について言及する。
①FEB RAS
①-1 概要
20世紀初頭から、クラシェニンニコフ(Stepan P. Krasheninnikov)らの探検家の調査により、極東地域の未知なる自然の多くが解明されるなど、同地域は多くの科学者の調査・研究意欲を駆り立ててきた。1932年、ソ連科学アカデミー極東支部が設置され、ソ連科学アカデミーの正会員であったコマロフ(Vladimir L. Komarov)博士が初代総裁を務めた。
ソ連崩壊後はFEB RASと組織名称を改め、2001年よりセルギエンコ(Valentin I. Sergienko)氏が総裁を務めている。FEB RASは6つの研究センターに分かれ、計34の研究所を抱え、また、16の建設会社や病院等を含む社会・学術サービス機関があり、2013年7月時点で、6,493名の研究者(うち、RAS正・準会員47人、ロシア博士37人、PhD1,157人を含む)が研究に従事していた。
しかし先述のとおり、2013年から開始されたRAS改革の一環で、これまでFEB RAS傘下にあった研究所はすべてFASOの所管となった。一方、セルギエンコ総裁をはじめ数十人の職員から成る極東支部はその規模を3分の1程度に縮小したものの、RASの下にとどまった状況にある。
①-2 活動分野
FEB RAS(現在はFASO)傘下の研究所の活動は、自然科学、工学等を中心に様々な分野にわたっているが、最も活な調査研究分野は以下の5つである。
- ●極東および太平洋の鉱物・生物資源の開発
- ●地質学および地球物理学
- ●海洋学(海洋と大気の相互影響や気候変動)
- ●陸地における植物、海洋における生物の生産性・多様性に関する研究、環境モニタリング
- ●自動制御、専門システムの構築。
産学連携の考えが比較的浸透しており、例えば、海洋生物を用いた薬剤やサプリメント等の研究開発では市場での販売を視野に入れている。また、企業との連携を行い製品化につなげていきたいとの意向が明確である。以下では主要な研究所について概説する。
②太平洋地理学研究所
1971年設立。RAS正会員であるバクラノフ(Peter Ya. Baklanov)氏が所長を務め、職員約200人(うち研究者は80人程度)を抱える。19の研究室と3つの研究センターを有する。
主要な研究分野は、1)陸地・海洋における地理的システムの構造および力学に関する研究とその類型化、2)地方ごとの自然利用の発展およびその最適化に関する研究、3)経済および人工分布の地域的構造に関する研究、アジア太平洋地域への統合を考慮した極東地域の発展プログラムの策定などであり、これまでに、極東地域における地質図、植生地図、土壌地図の作成に必要な調査、現場測量、文献調査など幅広く実施してきた。
国際協力について見ると、2003年~2004年科学技術協力プロジェクトとして、「極東における低投入持続型農業の研究」を日本の研究機関と実施している。北海道大学および大阪経済法科大学と研究協力関係を有している。また、後述するアムール・オホーツク・プロジェクトにも参画していた。
バクラノフ所長によれば、ルースキー島のAPEC開催は、同研究所がかつて知事に対し島の観光利用を提案したことに端を発しており、同島の発展・開発に積極的に取り組む姿勢が顕著である。
③太平洋海洋学研究所
1973年設立。ロバノフ(Vyacheslav B. Lobanov)氏が所長を務め、職員約500人(うち研究者は半数程度)を抱える。海洋学、生態学、地質科学、海洋科学の4支部と34の実験研究室を有する。
主要な研究分野は、1)水理物理学、水理化学および水理生物学の研究並びにその実地調査、2)地理学、地理物理学、地理化学に関する研究、3)大気・海洋のための新たなモデルと海洋データベースの構築などであり、近年は地球科学の解明や海洋音響学、海洋観測船による観測等にも力を入れている。
国際協力の分野では、2003年~2004年科学技術協力プロジェクトとして、「オホーツク海及び親潮水域の海洋環境」や「日露による日本海の地球科学的共同研究」等のプロジェクトを日本の研究機関と実施してきた。沿海地方の環境モニタリングについては、九州大学宇宙環境研究センターや東京大学地震研究センターとの共同研究協力がある。
④太平洋生物有機化学研究所
1964年設立。RAS正会員であるストーニク(Valentin A. Stonik)氏が所長を務め、職員約340人(うち研究者は200人程度)を抱える。
同研究所は、極東地域のユニークな海洋生物に関連した生態有機化学、生態科学、分子免疫学、天然生物の有機統合、海洋微生物学、バイオテクノロジー等の研究を行っている。とくに、海中に生存する植物相・動物相の資源を活用した、新規化合物の分離研究が注目されている。例えば、微生物由来の新しい生理活性物質に着目し、再生可能な生物学的な材料をベースに、これらの大量生産技術の確立、新たな治療法、獣医薬、栄養サプリメントの開発に携わっており、モスクワの企業と協定を結んで商品化に係る融資を受けている。
日本との研究協力関係は乏しいが、米国、ベトナム、インド、ニュージーランド等の国々との共同調査実績がある。
⑤海洋生物学研究所
1967年に太平洋海洋学研究所の一部局として設立され、1970年に研究所として独立した。RAS正会員であるアドリアノフ(Andrei V. Adrianov)氏が所長を務め、職員約400人(うち研究者は半数程度)を抱える。研究所は18の研究室と部局から構成される。
主な研究分野は、1)極東の海洋および隣接した太平洋における、植物相、動物相、生態系の生産過程に関する研究、2)生物資源の保護、再生産、効率的利用に関する基礎研究、3)海洋生物の適応能力・発生に関する研究や生物医学研究である。
その研究活動は、極東地域に限定されることなく、他地域からの船舶が排出するバラスト水により極東海域に持ち込まれる有害な外来種調査、潜水および潜水医学にも及んでいる。研究所内には海洋生物博物館が設置されており、天然資源からの製薬サプリメントの開発等にも従事している。
国際協力の分野では、北海道大学水産学部と1992年から無期限の科学技術に関する協力合意協定書を締結しており、サハリンやハバロフスク地方等における共同調査を実施してきた。日本水中映像株式会社、山形大学および熊本大学とも協力合意文書に基づく研究・調査協力を行っている。
⑥自動化・制御プロセス研究所
1971年設立。クリチン(Yuri N. Kulchin)FEB RAS副総裁が所長を務め、職員約260人(うち研究者は半数程度)を抱える。研究所は5部、19の実験研究室、4つの研究センターを有する。
極東地域における制御理論の科学的な基盤や原理に係る基礎研究を中心に、物理学、数学、工学分野の研究が中心である。具体的には、制御問題、情報、機器、レーザー物理、電気光学、表面物理、ナノテク分野におけるモデル構築等に取り組んでいる。また、海洋由来の植物プランクトン等を用いたシリコンベースのナノ光学部品およびナノ電子部品材料開発にも研究ポテンシャルを有している。
日本との国際協力に関しては、大阪大学と長年にわたる研究協力の実績があり、九州大学、東京大学、名古屋大学とも協力交流を有する。リモートセンシング分野においては、太平洋海洋学研究所とも連携して、東北大学と密接な協力関係にある。
②極東連邦大学
①-1 概要
2009年の大統領令により極東連邦大学の創設が決定され、2011年に極東国立大学を拠点校とし、極東国立工科大学、太平洋国立経済大学、ウスリースク国立教育大学の3大学を統合して極東連邦大学が設置された。大学施設は、ウラジオストク市対岸のルースキー島、つまりAPECサミットの会場跡地を利用して建設された。島へのアクセスを改善するため、半島と島の間にある東ボスポラス海峡をまたぐ2本の巨大な連絡橋が建設されている。ルースキー島の大学の敷地は約49ヘクタールで、東京ドームの約10倍にあたり、建設予算は555億ルーブルと言われている。当初から作業の深刻な遅れが懸念されていたが、2012年9月のAPEC 開催までに施設全体の完成を見た。
初代学長はミクルシェフスキー(Vladimir V. Miklushevskii)元教育科学次官が務めたが、現在は、アシモフ(Nikita Yu. Asimov)氏が学長代理というかたちで就任している。
学部生は2万4,000人を超えている。教員は1,598人で、うちロシア博士およびPhDは1,058人を占める。職員数は約5,000人である。2019年までに学生を約3万人受け入れ、うち外国人留学生を全体の4分の1(約7,500人)とする目標が掲げられている。
①-2 教育および研究分野
拠点となった極東国立大学は、47の学部に加え、東洋学研究所や法学研究所といった研究活動のベースとなる研究所を27も抱えており、2006年には、同大学とFEB RASの協力の下、地球物理学、ナノ物理学・ナノテクノロジー、電子工学・IT、医療物理学の4分野にわたる研究・教育センターが設立されていた。それ以外の統合された大学は、典型的なロシアの地方大学であり、活動の中心は教育であった。
極東連邦大学では、優先的発展分野に関連した研究・教育センター(クラスター)が新たに作られつつある。これら優先的発展分野には、海洋資源、エネルギー資源・エネルギー供給技術、ナノシステム・ナノ材料の産業化(製品化)、ロシアとアジア太平洋諸国の協力、バイオ医療等の諸領域が含まれている。
①-3 産学官の連携
極東連邦大学では、基礎研究と応用研究の両方を重視し、産学連携を実現することが重要とされている。2011年全体でみると、研究の成果として60の特許が取得され、ロシアの巨大国営企業との間で協力合意が新たに6つ交わされた。現在、大学自身が37のハイテク関連企業を抱え、そこからの利益は約1,200万ルーブルに上ると言われている。また、資産額2億5,000万ルーブルの大学ベンチャー基金が創設され、既に1,400人以上が運営に関与している。研究活動に対する支出は2011年度で7億2,300万ルーブルに達し、これは前年比で69%の増額である。
極東連邦大学とFEB RASとの関係は密接である。両者の間で、極東の社会経済状況を変革しうる人材育成等に係る協力合意書が締結されている。FEB RASの研究者が、大学において教育プログラムの担当者になっている。ただ、極東連邦大学の教員の80%以上がFEB RASの研究者で占められているため、両者は協力関係にあるというよりも、極東連邦大学がFEB RASの強い影響下にあるとも言える。
VIII.おわりに
本報告書で見てきたように、ロシアの科学技術の発展はソ連時代の影響を強く受け、いまだその影響から抜け切っていない。ロシアは依然として軍事や宇宙、原子力分野では大国である一方、民生分野の科学技術に関しては競争原理が機能せず、停滞したままである。ロシアの政府指導部も資源に依存した経済構造ではいずれロシアは立ち行かなくなることを認識しているとはいえ、効果的な対策を打ち出せないままに至っている。既に幾つかの試みが国家主導で実施されているが、その見通しは決して明るくない。その意味で、科学技術の現状をどのように打破していくかが今後の大きな課題であろう。
将来的にロシアの科学技術が質的な変化を遂げるためには、軍用と民生それぞれの科学技術の発展のバランスを調整し、民間の科学技術投資を増やしていくことが必要である。だが、民間を呼び込むための政府投資も伸ばしていかなくてはならない。こうして、ロシアを先進国並みの産業技術力に変えるためには、上からのアプローチのみならず、下からの突き上げが不可欠となってくると思われる。
また、現在のロシアには、米国のバイドール法に相当する法律がないため、公的資金を投じた研究開発の成果に関して大学や研究者が特許権を取得することが難しい場合がある。研究開発を取り巻く法整備の問題についても今後何らかの対処策を講じていかないと、ブレイクスルー的な技術開発はおろか、科学技術大国への復権の展望は絵に描いた餅に終わってしまうだろう。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます