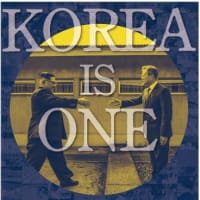韓国映画『1987、ある闘いの真実』は、警察による学生拷問死という一事件から、軍事政権下での民主化運動のうねりを描き出した傑作だ。
観客700万人以上を動員し、社会的議論を呼んだ。だが、ふと考える。
「なぜ日本では、これほど政治的で、かつエンタメ性の高い映画が作られないのだろうか?」
その理由は一つではない。
まず、制作側の制度的な壁。韓国では民主化以降、文化コンテンツ産業に対する国家の支援が充実し、政治を扱う作品でも助成を受けられる。
一方日本では、助成や出資にあたって“政治的中立”が過剰に重視され、政治色が強い企画は通りにくい。さらに、テレビ局や芸能事務所との繋がりが強く、自由な表現が難しい構造もある。
だが最大の違いは、観客側の感受性かもしれない。
日本では、「政治は面倒」「映画は娯楽であるべき」とする意識が根強く、政治映画を観に行くこと自体が“特殊な行動でダサい”として見られる。
これは全共闘運動の挫折以降、政治への冷笑主義が染み込んだ結果でもある。
とはいえ、日本にも可能な政治映画はある。
好きなわけではないが、
是枝裕和の『万引き家族』は、家族の物語を通じて制度の不在を描いた。原一男の『ゆきゆきて、神軍』や『れいわ一揆』(まだ見ていない)も、予算や流通の制限はありながら、現実社会に鋭く切り込んでいる。