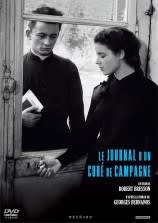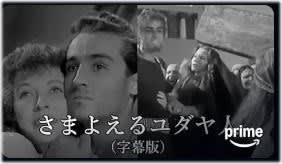1983年の映画『小説吉田学校』を観た。
原作:小説吉田学校(文庫 戦後日本の政治史を知る上で貴重な作品)も読んでいたけれど、本が探し出せない。
良質の社会派ドラマ映画として評価も高い。
森谷司郎監督
脚本を長坂秀佳と森谷司郎
前半はモノクロ映像で占領下の日本を描き、
後半はカラーで独立後の政界の動きを追う
上映時間132分
被占領下の日本。戦後改革を遂行する吉田茂は
対日講和条約の締結に命を賭ける。
映画は、吉田の門下生たちの苦闘、
そして政敵・鳩山一郎と、その盟友三木武吉との宿命の対決を描く。
保守本流:吉田茂(森繁久弥)と鳩山一郎(芦田伸介)の対立を中心に戦後日本の再軍備や憲法改正を巡る対立と、三木武吉(若山富三郎)の根回しなどが中心。
GHQにより公職追放されていた鳩山が復帰する際、吉田は一時的に首相の座を預かるが、再軍備に反対する吉田は、推進派の鳩山に政権を譲ることを拒む。
この対立は、吉田派(官僚出身の政治家)と鳩山派(党人派)との間の権力闘争として描かれています
官僚派 吉田茂、池田勇人、佐藤栄作など 戦前からの高級官僚出身者が多く、行政主導・技術官僚的な政策形成を重視。経済成長志向が強い。
党人派 鳩山一郎、三木武吉、河野一郎など。旧来の政党政治の伝統を重んじ、党の運営や人脈重視。党組織による政治主導を志向。
「官僚的現実主義」と「党人的理想主義」のぶつかり合い
吉田は国を再建するためのリアリストだった。
現在 例
党人派風 安倍晋三、高市早苗
官僚派風 菅義偉、岸田文雄、河野太郎(一部)
この対立は、戦後日本政治の保守本流を形作る「自由民主党」の内部抗争の原型。
そしてこの対立構造は、現在に至るまで日本政治の根本的な力学として続いているということは多くの識者が指摘しているところだ(この対立は単なる歴史的因縁なのではなく、現在の政治のリアルな構造問題として顕在化し続けている)。
登場人物が多いので、当時の政治的背景を理解していないと展開が分かりづらいとの指摘もあるが、この対立構造を押さえてみれば、小説を読んでなくても楽しめる。
吉田茂、池田勇人、佐藤栄作のいずれもが、政界入りする前に国家の要職を担う高級官僚としての経験を持っています。このため、彼らは官僚派」と言えますが、
映画では若いころ吉田を支持する田中角栄役の西郷輝彦の名演が光る。
田中が、(官僚派の)吉田茂を支持したのは、なぜだろうか。
吉田が戦後の日本を主導する保守勢力のトップであり、若き田中が政治家として力をつけるためにその懐に入った、という側面が強いということだ。
「吉田学校」の一員とも見なされた田中角栄だが、彼は官僚派には分類されない。
官僚経験なし:叩き上げの政治家。学歴や経歴から、エリート官僚とは全く異なる「庶民派」。官僚の意見を尊重しつつも最後は自らの判断と強力なリーダーシップで政策を決定し、実行していくスタイル。
幅広い人脈を築き、各界との調整や利害調整に長ける政治主導と実行力。
まさに「党人派」の典型、あるいはその究極の姿とも言える。
映画を見ると、その後の田中角栄の天才ぶりしがばれる。(映画で描かれるあとの時代だ)
たとえば今、世界中が直面している移民・外国人労働者の問題。
経済を回すために現実的に受け入れるべきか?
社会的・文化的統合をどう実現するか?
そもそも「共に生きる」とはどういうことか?
これはまさに、現実)と理想)の対立構造と重なる。70年前の対立が、そのまま今の政治にも響いているといえる。
田中角栄ならどう解決するのだろうか・・・。
映画は感情で伝えてくる。小説で読むと構造が見えてくる。
政治は制度だけじゃ動かない。
人の信念と選択が、社会の未来を決めていく。映画はそれがよく描かれていたと思う
森繁久彌の吉田茂は孤高で寂しげだった。
芦田伸介の鳩山は悔しさと信念をにじませていた。
三木武吉(若山富三郎)はある意味で吉田や鳩山より印象が強いのだが、
若山富三郎のやくざ映画の印象が強すぎるきらいがした。
吉田茂の娘:麻生和子(麻生太郎氏の母 役夏目雅子)の美しさと存在感もポイントのひとつ。
鳩山と三木武吉の人物背景がもう少し描かれてよいと思った。
鳩山には戦争犯罪などの法的な訴追(罪)はない。
あくまでGHQの価値基準による政治的な「思想パージ」であり、「罪」とは言えない。(追放は1951年に解除され、その後に鳩山は首相に就任(1954年〜1956年)。衛文麿内閣の文部大臣(1937年〜1938年)
三木 武吉:鳩山一郎の盟友で、自由民主党結党による保守合同を成し遂げた最大の功労者。「ヤジ将軍」「策士」「政界の大狸」などの異名を取った
過去の話じゃなく、未来を考えるヒントになる。
『小説吉田学校』は、構造と感情をつなぐ“政治の人間ドラマ”だった。