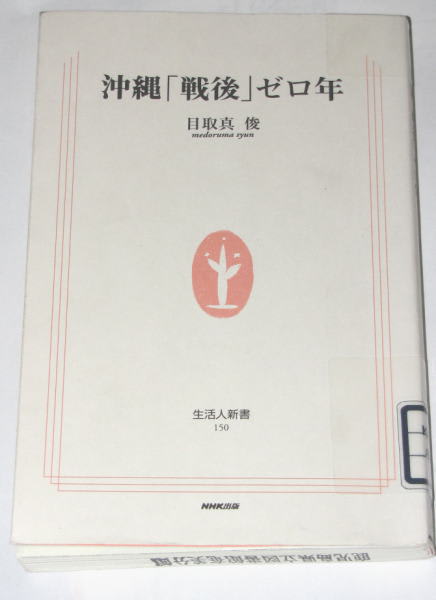 沖縄「戦後」ゼロ年 (生活人新書) [新書]
沖縄「戦後」ゼロ年 (生活人新書) [新書]
目取真 俊 (著) めどるま・しゅん
この本は、2005年出版で、新着図書ではないが、図書館の郷土コーナーにあった。
新着図書コーナーには、沖縄戦関係の本がつぎつぎと並んでいく。沖縄戦関係だけで奄美関連本にひけをとらないのではないか、と思うほどだ。奄美と沖縄の現状と関心の違いを痛感する。
この本は寄贈である旨のシールが貼ってあった。
著者の主張が一気に読める。入門書としてもいいのでは。
第一部 沖縄戦と基地問題を考える。
第二部 <癒しの島>幻想とナショナリズム 戦争・占領・文化
内容(「BOOK」データベースより)
沖縄戦から六十年。戦後日本の「平和」は、戦争では「本土」の「捨て石」に、その後は米軍基地の「要石」にされた沖縄の犠牲があってのもの。この沖縄差別の現実を変えない限り、沖縄の「戦後」は永遠に「ゼロ」のままだ。著者は、家族らの戦争体験をたどり、米軍による占領の歴史を見つめ直す。軍隊は住民を守らない。節目の六十年の日本人に、おびただしい犠牲者の血が証し立てた「真実」を突きつける。登録情報
新書: 189ページ
出版社: 日本放送出版協会 (2005/07)発売日: 2005/07
商品の寸法: 17 x 11 x 1 cm


















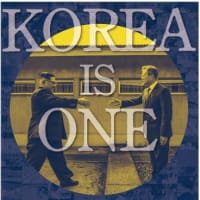

僕、この人の小説、大好きなんですよ。
「水滴」は確か芥川賞を取りました。
彼、小説では、声高に反戦を語るのではなく、
(反戦の要素ももちろんあるのですが)
先祖崇拝、精霊信仰など沖縄の文化をふんだんに取り入れた、ファンタジーとも言える作品が素晴らしいのです。
ぜひ、おじさんのブログでも、取り上げてみてください。
おじさんも、きっと好きになってくれるでしょう!
>「水滴」は確か芥川賞を取りました。
はい、1997年ですね。著者37才になる年ですね。同じ年に同作品で九州芸術祭文学賞も受賞ですね。
あと
wiki 2000年『魂込め(まぶいぐみ)』で川端康成文学賞と木山捷平文学賞を受賞。
2004年には小説「風音」を自ら脚本化し、東陽一監督によって映画化された。同作品はモントリオール世界映画祭でイノベーション賞を受賞した。wiki
ですね。評論には「沖縄/草の声・根の意志」があります。
名瀬の書店では、目取真俊の、まあ、反対の側の作家の作品のほうが多いと思います。
あ、この場合の「側」の意味は本書でいう、「殺される側の視点」の場合の「側」とは違うと思います。
重要ですが、論じれば複雑なので省略します(笑)
それと関連して、次元はことなりますが、ジョオジakechi氏の小説は、(その手法においても)あらゆる「側」からの超越(拒否)を試みているという点で、まあ、そおですね、あえて申しますと、方向性において著者との親和性が認められなくもないといったところでしょうか。
目取真俊 ブログ 海鳴りの島から は、お気に入りにいれて今日まで、著者のブログと気づかずに読んでいました。
僕と彼以外の誰が読んでもワカンナイのです。
相当に僕の家の歴史に詳しい人ではないとワカンナイことが、説明もなしに猛スピードで執筆されていく。
・・・、そこがいいんですよ。
僕も、友人の結婚式のために創った、ごく個人的なる曲を、数十人の前で歌ったりします。
客はその友人の事を、かけらも知らないのですが、それでも盛り上がるのです。
そういうことです。
ジョオジakechi氏の小説の解説、的を射た解説だと思います。
ジョオジakechi氏の小説における「ワカンナイ」はOMOROの本質論へ導く重要なキーワードですね。スルドイ。深い。面白い。「どうもありがとう」キヨシロウ