(1967/アーサー・ペン監督/ウォーレン・ベイティ、フェイ・ダナウェイ、ジーン・ハックマン、マイケル・J・ポラード、エステル・パーソンズ、ダブ・テイラー、デンヴァー・パイル、ジーン・ワイルダー、エヴァンス・エヴァンス /112分)
 舞台の演出家出身で、自身の舞台と同じ配役の映画「奇跡の人(1962)」でオスカー候補になったアーサー・ペンの、「逃亡地帯(1966)」に続く4本目の作品。アメリカン・ニューシネマの先駆けといわれた記念碑的な映画でもある。
舞台の演出家出身で、自身の舞台と同じ配役の映画「奇跡の人(1962)」でオスカー候補になったアーサー・ペンの、「逃亡地帯(1966)」に続く4本目の作品。アメリカン・ニューシネマの先駆けといわれた記念碑的な映画でもある。
アメリカン・ニューシネマにはこれといった定義はないらしいが、個人的にはこう思っています。
主人公が(少なくともその思考が)反体制的な人物であること。赤裸々な性表現がみられること。それまでのハリウッド的なハッピーエンドではないこと。そして、音楽の使い方や映像が新しい感覚であること。
同じくニューシネマの先駆けといわれた「卒業(1967)」と共に封切りでは観てなくて、リバイバルもしくはレンタル・ビデオで観た映画です(どっちだったか忘れました^^)。今回、BS2放送にて数十年ぶりに再会です。
プロデューサーが主演も兼ねたウォーレン・ベイティ。昔は“ビーティ”って言ってましたが、いつの頃からかベイティが当たり前のようになっていますね。お若い人の為に申し上げますと、名女優シャーリー・マクレーンの実弟であります。
脚本に惚れたベイティの初プロデュース作品とのことで、その脚本を書いたのが、デヴィッド・ニューマンと、後に監督にも進出するロバート・ベントン(「クレイマー、クレイマー」、「プレイス・イン・ザ・ハート」etc)。
「チャイナタウン (1974)」などの脚本家ロバート・タウンも、スペシャル・コンサルタントとしてクレジットされていました。
原題は【BONNIE AND CLYDE】。
ご存じ、大不況まっただ中のアメリカ、中西部の複数の州にまたがって銀行強盗を繰り返したギャング“ボニーとクライド”の出会いと悲惨な最期を描いた映画です。彼らはテキサス州出身の実在した人物で、『ウィキペディア(Wikipedia)』によると、次のように書かれています。
<ボニーとクライド(Bonnie and Clyde)は、1930年代前半にアメリカ中西部で銀行強盗や殺人を繰り返した、ボニー・パーカー(Bonnie Parker、1910年10月1日 - 1934年5月23日)とクライド・バロウ(Clyde Barrow、1909年3月24日 - 1934年5月23日)からなるカップルである。
ルイジアナ州で警官隊によって射殺されるまで、沢山の殺人に関与し、数え切れないほど多くの強盗を犯した。当時のアメリカは禁酒法と世界恐慌の下にあり、その憂さを晴らすように犯罪を繰り返す彼等の事を凶悪な犯罪者であるにも拘らず、新聞も含めて英雄視する者も多かった。後にボニーとクライドの犯罪は何度か映画化された。>
映画のオープニング・ショットは、自宅の2階の部屋で全裸でイライラしているボニーのセクシーな赤い唇。先行き不透明な時代の空気を感じてなのか、それとも自身の退屈な人生を恨んでか、ベッドの枠を叩いたり大きくため息をついたりしている。そんな彼女がふと窓辺に寄り外を見下ろすと、若い男が彼女の母親の車に乗り込み、今にも盗もうとしている。盗られてたまるかと声をかけると、男は悪びれた様子もなく落ち着いて微笑み返す。ハンサムだし、洒落た格好をしている。退屈していたボニーは男にソコで待つように言って、洋服を着て外へ飛び出す。
『年寄りの車を盗もうなんて酷いじゃないの』
『売ってもらおうかと思ってネ』。その男こそ、刑務所を出てきたばかりのクライド・バロウだった。
こうして二人は知り合い、ビビビと惹かれあい、アッという間に最初の強盗に手を染めるのだ。
原題通りコレは二人の物語なのですが、冒頭のシーンでも分かるように、起承転結の軸はボニーにあります。終盤、バックもブランシュも居なくなり、モスの実家に居候することになった時に、彼女がクライドに言います。
『強盗を始めた頃は、どこかにたどり着けると思ってた。でも、違った』
『ただ、進むだけなのね』
無軌道な若者を描いた青春映画のようにも見えるのは、二人の間には愛情があったからで、死の前日に初めて二人が結ばれるという設定も影響していますね。
BGMにバンジョーを使って中西部の雰囲気を出し、あわせて冒険活劇のような軽快さも出す。ジョン・フォードの「怒りの葡萄」を思い起こすような大恐慌で家を追われた人々を点描し、彼らの『銀行に家をとられた』と言う言葉に銀行強盗を思いつく。この辺にも脚本のギャング寄りの視点がみられます。
数十年前に観た時には軽さだけが目立っていたのですが、今回は銃撃シーンも迫力あったし、強盗シーンなどの編集の巧さも感じました。ただ、たまに舞台をみているような平面的なショットもあるんですよね。
例えば、序盤で知り合った二人がそのまま町まで歩いて行き、通りを歩いているシーンで、通りを遠近法をいかしたアングルではなく、セット撮影がモロ感じられるようなミドルショットの移動撮影を使っている。その後に、同じ通りを屋外のロングショットで捕らえたショットが入るので、繋ぎに違和感があったりする。ま、それらはほんの数カットのことなので、全体には全然影響無しですがね。
それと、時の流れの表現が曖昧でした。数時間の話だったりとか、数日、数週間の物語なら話の展開だけで時間の経過は気にならないのですが、この映画は数ヶ月以上かかった話であるはずなのに台詞だとか、服装だとか、風景だとかにそういう変化に関する描写が殆どない。
二人の出会いが1931年で、死んだのが34年。映画は3年も経ったようには描かれてなく、暫く観ている分は気にならないが、中盤辺りから?マークが点灯しました。
映画の出来は★半分おまけして★★★★★ですが、お薦め度も五つ★にすると、この2年後に作られた「明日に向って撃て!」を超すことになるので、★★★★にしました。だって、「明日に向かって撃て!」の方が好きなんだもん。
1967年のアカデミー賞で、作品賞、主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞( ハックマン、ポラード)、監督賞、脚本賞、衣装デザイン賞にノミネートされ、助演女優賞(パーソンズ)、撮影賞(バーネット・ガフィ)を受賞したそうです。
ジーン・ハックマンはクライドの兄バック・バロウ役。エステル・パーソンズはバックの妻ブランシュ、マイケル・J・ポラードはギャング仲間のC・W・モス役。ボニーとクライドを警察に売るCWの父アイヴァン・モスを演じたのがダブ・テイラーで、二人を追いつめるテキサスレンジャーに扮したのがデンヴァー・パイルでした。
尚、中盤に車を盗まれるカップルというのが出てきますが、男の方がジーン・ワイルダー(ユージン・グリザード役)、女はエヴァンス・エヴァンス(ヴェルマ・デイヴィス役)でした。
 舞台の演出家出身で、自身の舞台と同じ配役の映画「奇跡の人(1962)」でオスカー候補になったアーサー・ペンの、「逃亡地帯(1966)」に続く4本目の作品。アメリカン・ニューシネマの先駆けといわれた記念碑的な映画でもある。
舞台の演出家出身で、自身の舞台と同じ配役の映画「奇跡の人(1962)」でオスカー候補になったアーサー・ペンの、「逃亡地帯(1966)」に続く4本目の作品。アメリカン・ニューシネマの先駆けといわれた記念碑的な映画でもある。アメリカン・ニューシネマにはこれといった定義はないらしいが、個人的にはこう思っています。
主人公が(少なくともその思考が)反体制的な人物であること。赤裸々な性表現がみられること。それまでのハリウッド的なハッピーエンドではないこと。そして、音楽の使い方や映像が新しい感覚であること。
同じくニューシネマの先駆けといわれた「卒業(1967)」と共に封切りでは観てなくて、リバイバルもしくはレンタル・ビデオで観た映画です(どっちだったか忘れました^^)。今回、BS2放送にて数十年ぶりに再会です。
プロデューサーが主演も兼ねたウォーレン・ベイティ。昔は“ビーティ”って言ってましたが、いつの頃からかベイティが当たり前のようになっていますね。お若い人の為に申し上げますと、名女優シャーリー・マクレーンの実弟であります。
脚本に惚れたベイティの初プロデュース作品とのことで、その脚本を書いたのが、デヴィッド・ニューマンと、後に監督にも進出するロバート・ベントン(「クレイマー、クレイマー」、「プレイス・イン・ザ・ハート」etc)。
「チャイナタウン (1974)」などの脚本家ロバート・タウンも、スペシャル・コンサルタントとしてクレジットされていました。
原題は【BONNIE AND CLYDE】。
ご存じ、大不況まっただ中のアメリカ、中西部の複数の州にまたがって銀行強盗を繰り返したギャング“ボニーとクライド”の出会いと悲惨な最期を描いた映画です。彼らはテキサス州出身の実在した人物で、『ウィキペディア(Wikipedia)』によると、次のように書かれています。
<ボニーとクライド(Bonnie and Clyde)は、1930年代前半にアメリカ中西部で銀行強盗や殺人を繰り返した、ボニー・パーカー(Bonnie Parker、1910年10月1日 - 1934年5月23日)とクライド・バロウ(Clyde Barrow、1909年3月24日 - 1934年5月23日)からなるカップルである。
ルイジアナ州で警官隊によって射殺されるまで、沢山の殺人に関与し、数え切れないほど多くの強盗を犯した。当時のアメリカは禁酒法と世界恐慌の下にあり、その憂さを晴らすように犯罪を繰り返す彼等の事を凶悪な犯罪者であるにも拘らず、新聞も含めて英雄視する者も多かった。後にボニーとクライドの犯罪は何度か映画化された。>
映画のオープニング・ショットは、自宅の2階の部屋で全裸でイライラしているボニーのセクシーな赤い唇。先行き不透明な時代の空気を感じてなのか、それとも自身の退屈な人生を恨んでか、ベッドの枠を叩いたり大きくため息をついたりしている。そんな彼女がふと窓辺に寄り外を見下ろすと、若い男が彼女の母親の車に乗り込み、今にも盗もうとしている。盗られてたまるかと声をかけると、男は悪びれた様子もなく落ち着いて微笑み返す。ハンサムだし、洒落た格好をしている。退屈していたボニーは男にソコで待つように言って、洋服を着て外へ飛び出す。
『年寄りの車を盗もうなんて酷いじゃないの』
『売ってもらおうかと思ってネ』。その男こそ、刑務所を出てきたばかりのクライド・バロウだった。
こうして二人は知り合い、ビビビと惹かれあい、アッという間に最初の強盗に手を染めるのだ。
原題通りコレは二人の物語なのですが、冒頭のシーンでも分かるように、起承転結の軸はボニーにあります。終盤、バックもブランシュも居なくなり、モスの実家に居候することになった時に、彼女がクライドに言います。
『強盗を始めた頃は、どこかにたどり着けると思ってた。でも、違った』
『ただ、進むだけなのね』
無軌道な若者を描いた青春映画のようにも見えるのは、二人の間には愛情があったからで、死の前日に初めて二人が結ばれるという設定も影響していますね。
BGMにバンジョーを使って中西部の雰囲気を出し、あわせて冒険活劇のような軽快さも出す。ジョン・フォードの「怒りの葡萄」を思い起こすような大恐慌で家を追われた人々を点描し、彼らの『銀行に家をとられた』と言う言葉に銀行強盗を思いつく。この辺にも脚本のギャング寄りの視点がみられます。
数十年前に観た時には軽さだけが目立っていたのですが、今回は銃撃シーンも迫力あったし、強盗シーンなどの編集の巧さも感じました。ただ、たまに舞台をみているような平面的なショットもあるんですよね。
例えば、序盤で知り合った二人がそのまま町まで歩いて行き、通りを歩いているシーンで、通りを遠近法をいかしたアングルではなく、セット撮影がモロ感じられるようなミドルショットの移動撮影を使っている。その後に、同じ通りを屋外のロングショットで捕らえたショットが入るので、繋ぎに違和感があったりする。ま、それらはほんの数カットのことなので、全体には全然影響無しですがね。
それと、時の流れの表現が曖昧でした。数時間の話だったりとか、数日、数週間の物語なら話の展開だけで時間の経過は気にならないのですが、この映画は数ヶ月以上かかった話であるはずなのに台詞だとか、服装だとか、風景だとかにそういう変化に関する描写が殆どない。
二人の出会いが1931年で、死んだのが34年。映画は3年も経ったようには描かれてなく、暫く観ている分は気にならないが、中盤辺りから?マークが点灯しました。
映画の出来は★半分おまけして★★★★★ですが、お薦め度も五つ★にすると、この2年後に作られた「明日に向って撃て!」を超すことになるので、★★★★にしました。だって、「明日に向かって撃て!」の方が好きなんだもん。
1967年のアカデミー賞で、作品賞、主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞( ハックマン、ポラード)、監督賞、脚本賞、衣装デザイン賞にノミネートされ、助演女優賞(パーソンズ)、撮影賞(バーネット・ガフィ)を受賞したそうです。
ジーン・ハックマンはクライドの兄バック・バロウ役。エステル・パーソンズはバックの妻ブランシュ、マイケル・J・ポラードはギャング仲間のC・W・モス役。ボニーとクライドを警察に売るCWの父アイヴァン・モスを演じたのがダブ・テイラーで、二人を追いつめるテキサスレンジャーに扮したのがデンヴァー・パイルでした。
尚、中盤に車を盗まれるカップルというのが出てきますが、男の方がジーン・ワイルダー(ユージン・グリザード役)、女はエヴァンス・エヴァンス(ヴェルマ・デイヴィス役)でした。
・お薦め度【★★★★=友達にも薦めて】 






















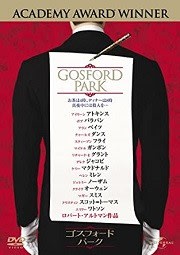












ただ、初めて観た時は、ジーン・ハックマンが出ていたなんて知らなかったし、ジーン・ワイルダーが出ているのを知ったのは3度目に観た時だったと思います。
そういう意味でも、何度観ても楽しめる映画の1本ですね(ラストが哀しいので、積極的に観たいとは思わないんですが^^;)。
ラストシーンは、最初に観た時は事前情報が入っていたし、確か「明日に向かって撃て!」を先に観ていたので、『なるほどね』という感じだったと思います。今回じっくり観てみると、その後のストンという幕切れがなんともドライで、その後の映画に与えた影響が想像できましたネ。
やはり男性の好む映画と女性のそれとは
違うのはよくわかりますが
同じ映画を観ても感じるところがこれも違う。
面白いです。(^ ^)
3年ほど前の拙記事・・・
コメント欄を今読み返しましたら
みなさん、ほんとに映画好きで元気のいいこと!!
ベストメンバーがこぞってお話していって
くれてます。勿論、十瑠さんも。(^ ^)
ナニが影響しているのか分からないんですが?イイことです。
>同じ映画を観ても感じるところがこれも違う。
どこ、何処、ドコ?
違ってたってどこ?
優一郎さんが“赤星”さん!
ブログは開いたままだけど、どうしてるんだろう・・・?
モスもそういった意味での仲間だったようです。
最初に登場する全裸のフェイ・ダナウェイ・・そのやせて肋骨も少しでている背中のシルエットが印象的だな~
クライドは農家出身らしい雰囲気のまんまですが、ボニーは角度によってはいい女でした。
バイではややこしい映画になるのでイン○○ンツにしちまッたってことですか。
ベレー帽のフェイさんが好きです
展開でしたね。
これが日本だと、
北への逃避行=やがて雪景色
というような展開になるのでしょうか。
(^_^)
でもコレって基本的なことですよねぇ。
最近コメントが多く、出張のほうまでなかなか手が回らない状態です。嬉しい悲鳴ですね。
>アメリカン・ニューシネマの定義
>反体制的な人物
これが肝要ですね。
最近よく投稿されるモカさんが“反体制”という言葉に異議を唱えていましたので、少し考えました。
“体制”を政府や政治体制とのみ考えるのは、定義としては狭く、子供から見た大人(「卒業」)といった概念なども含め、権威や安定(への反感)という言葉で補完する必要があるかもしれません。
「ダーティハリー」はニュー・シネマのグループには入れられないのかもしれませんが、紛れもなくニュー・シネマの精神がいっぱいでしたね。官憲による警察に対する反感・・・
記事の中で書いておいて何なのですが、ボニーとクライドをヒーローのように捉えるのは何だか違うような気がします。
僕は途中から二人が可哀想で仕方がなかった。ドライなタッチの中に悲しさを感じてならなかったですね。多分二人の最期を知っているからなのでしょうが。
昨今の我が国のTVドラマだって、反体制的な主人公が多いです。
アメリカン・ニューシネマが面白かったのはそれだけじゃない。それまでに描かれなかった人間の側面があぶり出されたからです。