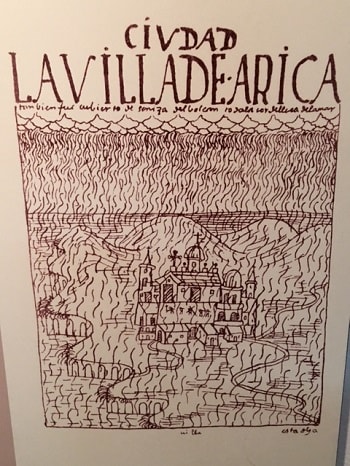ホテルオークラ
秘蔵の名品 アートコレクション展「旅への憧れ、愛しの風景 マルケ、魁夷、広重の見た世界」
2016.7.27~8.18
毎年楽しみにしている夏の一日。
展示の最初には、川端康成の直筆の色紙が。シュピタール古城の門に刻まれた言葉だという。「歩み入るものにやすらぎを。去りゆく人に幸せを。」
今回は「旅」がテーマ。外国の要人も利用するオークラ東京を訪れるだけでも、ちょっとした旅気分。ここの書店も、洋書比率が高い品揃えなので、外国人旅行者目線も体験したり。裏からの小さな入口への小径が、ちょっと安らぎでもある。

◆今回は、マルケ(1875~1947)が18点集まっている。マルケを観るのは初めて。(もともと無知なので今さらだけど)知識も先入観もなく白紙で出会えるのが、うれしい。最初の一回は一回しかないのでね。
順番に観ていくと、「水面」ってものに魅せられた。そして雲を見比べるのが楽しくなっていく。曇りの日もいいものだなと知らされる。
観た順に、「ノートルダム 曇天」1924 (以下画像は絵ハガキと図録から)

後ろの雲を背負ったようなノートルダム寺院。寺院より雲と河岸に目がいく。コンクリの河岸壁の灰色が、数年前にパリに行った時の印象と似ている。気が付くと、雨上がりの道路が濡れていて、影がうつりこんでいる。マルケの水面、面白い。
「サン・ジャン・ド・リュズの港」1927 バスク国境。雲がかかってきたけれど、水面は静かに反射している。マルケはどんなに長いあいだ水面をみていたんだろう。
「コンフラン・サント・オノリースの川船」1911 一番気に入った一枚。鏡みたいに静かな水面。空高く秋の空のような。水と空と、広やかで静かで気持ちいいー。水面も千差万別、同じものはないようだ。昼下がりくらいかな。

「エルブレイ・ セーヌ河畔」1919 この絵に至っては、画面のほとんどが水面。雲が映って水面が白く。黄色い花、少しこちらに向かって川が流れてくる。時間は、4時頃か、パリなら5時か6時でもこれくらいの明るさかな。マルケの絵は、時間と季節を推測すると、なんだかゆったり、和む。
フランスだけでなく、アルジェの絵が数点。マルケは妻と出会ったアルジェを何度も訪れている。
「アルジェの港」1942

「アルジェの港、ル・シャンポリオン」1944

アルジェでは特に港を多く描いている。埋立地、工場、人影はほぼなく、タンカーが停泊したり出港したり。どちらかといえば無機質に近い人工的な港。わずかに鈍みのある色。特段美しい風景ではないと思う。でもマルケは魅了されたそうだ。
とにかくも、たっぷりと水面。水平線と空を見渡せる。雲や空や水面の移り変わりは、フランスとどんなふうに違っていたんだろう。朝に昼に夜に、上階のホテルの窓から見降ろしていたような時間の流れ。一日の変化。出る船、入る船の繰り返しを見飽きなかったのかもしれない。私も、港に面したホテルの窓から、知床やコタキナバル、高松港の船の出入りを眺めるのは見飽きなかった。
ポンヌフの三枚が並んでいたのは、うれしい。年代には開きがあるけれど、同じアパートの窓からの眺め。定点観測のよう。
「ポンヌフ夜景」1938

きらきらときれい。映画を見てミーハーにも行ってみたのがちょうど夜だったので、親しみを感じる。絵の依頼主のサンマテリーヌ百貨店のシルエットも丸く夜景でかたどられている。
「ポンヌフとサマリテーヌ」1935頃

わりに明瞭に見渡せるけれど、気づくと少し橋の欄干に雪が積もっている。空を覆うのは雪雲だった。
「冬のパリ」1947頃

あ、と声が出そうになる。マルケが生涯描き続けてきた雲が、ついに降りてきて街を包んでいる。雪が積もった日の情景。雲のせいだけでなく、橋も建物も車も、形は失われつつあいまいになっている。
これは没年の絵。他にこんなにも雲につつまれた絵はあったかなと戻ってみると、初期1918年の「霧のリーヴ・ヌ―ヴ、マルセイユ」はこんなふうに霞んでいた。これも形はあいまい。亡くなる時は、昔に戻るのかな?。それともこういうあいまいな筆致の作品は他の時期を通してあるのかな?
もっと見てみたいものです。
◆大好きな三岸節子が見られたのが、思いがけずうれしかった。何年振りかだし、二点とはいえ複数展示されているのを観るのは、2005年の回顧展と、いつだったか愛知の一宮市三岸節子記念館に行った以来かも。
先日来フリーダカーロの画集などを見ていたので、改めて節子の人生も少し似ていると思い返す。先天性股関節脱ということで、節子はこのことがその後の自分の生涯の指向を決定付けたと。そして19歳で結婚した天才肌の画家の夫は、とっかえひっかえの浮気者。節子は3人の子供と姑の面倒を見ながら、極貧生活。
フリーダと違うのは、すくなくとも節子は若いうちに、夫の苦しみからは解放されたこと。三岸好太郎は結婚10年で突然他の女性との旅中に亡くなり、再婚(別居婚)した画家の菅野圭介も、彼の浮気がスクープされ5年で離婚。好太郎の訃報を受けたとき節子は、「助かった、これで自殺しなくてすむ」と思ったという。息子の回想では、「ああ、これで自分も絵が描けると真っ先に思った」と言っていたと。節子は、それから亡くなる94歳まで描き続けた。
節子は反骨反逆のひとであり、闘うひとだと改めて思う。そして「俺は桜の花のようにパッと咲いてパッと散る」と言った光太郎に対し、節子は「画家は長く生きて成熟した絵を描くことこそ本領である」と。
その言葉通り、二枚の絵を見ると、節子の長い人生が重なっているよう。薄くない絵。長い時間の中で対峙し続けたかのような色彩。
「細い運河」1974(69歳)

マルケじゃないけどこの水面もすごい。「ベネチアの次にパリが好き」(80歳談)と。
「アルカディアの赤い屋根 ガヂスにて」1988(83歳)
ヴェロンに住んでいる間、82歳の時にはアンダルシアにも滞在した。

花だけなく屋根も、この人の赤い色はなんて深いんだろう。見ただけじゃない色。周りの色も空気も湿度も取り込んでいるような色。漆喰の白壁もそう、手触りまで。目に染みるような青い空も。スペインだー!って、この広がりにリュック放り投げてしまいたくなる(妄想)。
旅の風景、ということでこの場に展示されたのだと思うので、画集と「三岸節子画文集―未完の花」から、旅のことに絞って少し抜き書き。
菅野圭介と別れた後、節子は49歳で初めてフランスに渡り、1年3か月滞在。63歳で南仏カーニュに移住。69歳でブルゴーニュの(陸の孤島)ヴェロンの農家に引っ越し。84歳まで途中帰国をはさみながらも滞在。その途中で、イタリアやスペインにも滞在。
「新しい環境がどんな影響を与えるか、女性特有の、あふれるような豊かな、感覚だけは持って生まれてきたのだから、新しい世界に水のように浸して、心が謳いだすままに、仕事をしてみたいと思っているまでである。」(49歳記)と。
改めて画集を開いて通して見かえしてみると、ヨーロッパの色彩に出会ってからの節子の色彩は、より克明になっている。出口をつき破った水が、色の中にあふれだしたような。
そしてフランス、アンダルシア、ヴェニス、軽井沢、大磯と、住んだところによって色彩がはっきり異なって特徴的。場所の色彩が彼女の中に染み込んでいるよう。感受性が強い人なんだろうと思う。手の先で描くなんてことはできなくて、全身全霊で風景に入って描いている。
夫からは解放されたけれど、今回彼女の日記や手記を読み返してみると、絵を描くことは彼女にとって苦行ともいえることだったよう。70歳でも「絵の世界は業であり修羅であり歓喜でもあるが・・。」と。
30代の時は、後々の絵は重すぎて初期のボナール風の室内の明るい絵のほうが好きだったけれど、今は、なんというか、すべてが好き。そして年々見入ってしまう。本当に好きになっったのは自分が40代になったかもしれない。年を重ねるにつれて、また違う思いで見られるだろうか。
・・・・・・・・・・・・・・
上記以外で、心に残った絵を。
前田青邨(1885~1977)「春富士」1971
以前から気になる青邨、ここで出会えるとは。布か紙を押し付け摺ったような。日本通運の所蔵品。日通さんの美術品専門の輸送部門は、テレビなどで見るたびに深く尊敬するけれど、今回は5点出品、いいなあと思う作品ばかりだった。
赤松麟作(1878~1953)「夜汽車」1901

明治5年に初めて新橋横浜に鉄道が開通し、この作品は30年後。日本の昔の市井を描いた油絵は、なぜか個人的に好き。高橋由一のお豆腐絵の絵とか。
レトロな(当時の最先端かな)木の車内、床に落とされたみかんの皮。母親の膝で丸くなって眠る子供と赤い鼻緒の草履。珍しげに外をのぞくおじいさん。今じゃありえない車内タバコ。ひしめき合った車内のひといきれ。でも本当に旅気分なのは、これを眺めた赤松のまなざし。こんな濃いい車内は、昔中国の三等列車でイヤってほど味わったぞ。
小杉放菴(1881~1964)「金太郎遊行図」1942泉屋博古館分館から
大好きなこの絵と再会できるとは♪。出光美術館の回顧展でも似た構図の絵に出会ったけれど、こちらのほうが顔がかわいいのです。お孫さんをモデルにしただけあって、元気いっぱい、むっちりとした手や足に孫への慈しみがあふれてる。実物というよりはイメージで描いたくまや鳥。公差した構図。
放菴も不同舎で学び、ヨーロッパを巡った。が、海外で東洋の美に目覚め、日本画へ。その契機となったのが、1915年に大観や観山と旅した東海道だと解説に。この道中の風景を皆で交換日記のように繋げた絵巻物は、東博で少しずつ展示されている。行くたび続きを楽しみにしているけれど、放菴も参加していたとは。
曾宮一念(1893~1994)「平野夕映え」1965
赤い雲が胸に迫ってくる。夕日に焼けて湖に映っている。地平線も見えそうなくらい遠くはるかな彼方も描いているせいか、郷愁と旅愁が一度に漂う。101歳まで生きたイチネンさんの72歳の作。6年後には失明し、その後は随筆を書いていたそうだけど、この雲の赤色を見ていると、この時すでに目の不調を予感していたのかと思うほど。
牛島憲之(1900~1997)「岬の道」1989
アイヌ語で「向こうの島」を意味する利尻島イクシュシシリを訪れて、19年後に描いた。こんなに急な坂は、本当にこうなのか、ひとり上る人影は影のよう。断崖の海の上に浮かぶ雲は、抜け出た魂が浮遊しているみたい。心の中のイクシュシシリの残像に、19年分の歩いた道が織りなされた心象のように。
堀文子(1918~ )「紫の雨」1965

藤の花を描いたと解説にあった。クリムトを思いだした。金地にピンクって組み合わせに感嘆。あでやかにしんしんと。タイトルが「紫の雨」って素敵な。花と雨が重なって脳裏に入ってくる感じ。2007年の横浜高島屋での回顧展の画集を開いてみると、ここまで抽象化された絵は、あまりないようだけれど。
77歳でアマゾン、マヤの遺跡、80歳でマチュピチュ、81歳でヒマラヤと。確かヒマラヤには青いけしの花を探しに行ったとか。 三岸節子もそうだけど、年齢をものともしない女性の話を聞くと、元気出るわ。
山本丘人(1900~1986)「曇れる火山」1958
一瞬「暴れる」に見えてしまった。でも一触即発、膨張して今にも噴火しそうに見える。今の日本じゃ、この絵は怖い感じ。このころどこかで噴火があったのかと調べると、1953年阿蘇山、1955年桜島、1957年伊豆大島三原山、1958年阿蘇山。いずれも死傷者がでる大災害。丘人も怖いと感じていたのだろうか。
東山魁夷は11点。北欧の絵が3点。魁夷は、「戦争が終わった時が大きなはっきりとした分岐であるとすれば、北欧のたびは戦後の私の芸術の歩みの中で重要な意味をもつ。」と。
「フレデリク城を望む」1963、描かれていない空は、湖面に広く映っている。
今回はスケッチが心に残った。
「布留の森」1973ー85は、小さな面のパーツが集合して色を構成している過程を見るような。

「酒造りの家」1973-85
軒先のこれ杉玉っていうんだっけ。全体に茶色い絵という第一印象だったけれど、先日拝読した方のレビューにあった赤いポストが目に入り、「あ、そういえばこれか。実家のもこれだったわ」と思った瞬間、ポストが生き生きしてきた。そうすると一気に重さが消え、壁の板張りの色は質感に代わり、そこに自分も立ってるような感じに。ポストが鍵を開けたような、面白い体験でした。
「山峡朝霧」1983は6曲の屏風。

魁夷が描くと黒も、丸みが。色彩あふれる絵もいいけれど、たまに「色いらない」って思える絵に出会う。たちこめた霧、もっとたち込めて何も見えなくなってしまうのではと、思わず待ってしまう。
***
「海外との出会い」の章には、海外留学した洋画家の作品が並ぶ。
その街のあたりまえの景色が特別なものにみえる、旅人の眼。自分が旅行した感覚と重なる。
牧野義男(1870ー1956)「テームス河畔」は23歳で渡米し、27歳でロンドンに。The Color of Londonと、現地で人気画家にだったそう。最初はロンドンの霧を怖れてマスクをしていたというのが笑ってしまうけれど。
佐伯祐三(1898~1928)が4点、すべて、あの有名な一言を放ったヴラマンクから離れていったん帰国し、1924年から二年間再びパリに滞在した時のもの。ユトリロに影響を受けた時期とのこと。裏通りや小さな小路。「エッフェル塔の見える街角」1925は、角にある店のひさしにひかれる。
「広告と蝋燭立」1925が好きな一枚。ひとりで夜のホテルにぽつっといる感覚が思い起こされる。

デュフィ(1877~1953)「ベルサイユ城風景」1930ー35
置かれた彫刻や湖に映る姿もフォーブな。ピンクがゴールドに見えてくる。
*****
第三章は日本画。
上村松園「菊の香」1945頃は、松園の中でも好きな「菊寿」1939年にそっくり。それは、落ち込んだ時に見ると元気出る画。菊の位置が違うけど、これも同じく好きな絵になった。

改めて、松園の着物は本当にハイセンス。しみったれた組み合わせなんてしない。たとえあの怨念渦巻く「焔」だって、ものすごくおしゃれ。
細部までこんなに近づいて見られて、アスコットホールにも感謝。改めて、菊一輪の美しさときたら。菊の花は、はなびら一枚一枚まで楚々と瑞々しく、葉っぱまでかわいらしいことに気付いた。
どうしてこの絵を見ると元気が出るのか?なぜだか自分でもその全容はわかりませんが。
伊東深水(1898~1072)「鏡獅子」1962(部分)

今にも声が漏れてしまいそうな口もとを、きっと閉じている。激しい女の刹那の思いのようにも見えるし、凛とした生きざまのようにも見えるし。深水は64歳、かなりの数の女性を見てきたさすがのとらえ方だなあ、と若輩ながらそれだけは感じたり。
最後は歌川広重の「保永堂版東海道五十三次」。ここで時間があまりなくなってしまったけれど、21:名物とろろ汁まで、結構芸が細かい。
22:宇津の山は酒井抱一などでも描かれたあの場面。広重の印象も知ることができてよかった。つまり木はおどろおどろしく、やはり険しく難所のイメージどおりだった。38:待っている犬。46の百雨などなど。
最後は急ぎ足。時々自分が旅行した時の気持ちを思い出したり、いい絵もたくさん見られて、冒頭の色紙の「去りゆくものにしあわせを」の通り、小さな幸せ気分で帰りました。