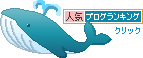さあて、深見真先生の、ヤングガンカルナバル最新刊、「前夜祭・標的は木暮塵八」(トクマノベルズEdge)をついに読みました。
さあ、いよいよ、盛り上がってきましたよ。
ついにクライマックス突入か? って感じです。
まず、冒頭で弓華の愛しの伶ちゃんが誘拐されちまいます。誘拐したのは弓華の腹違いの弟、ギャウザル。
そして伶ちゃんは、哀れ素っ裸にひんむかれ、ガラス張りの檻の中に。
その外側には、人間性を失った男「人間ブタ」たち。
うっひゃああ。ラノベレーベルでは書けない、ノベルズならではのヤバい描写。
弓華の母親、志摩麗華こと聖火は、「伶を助けたかったら、仲間のヤングガンをひとり殺せ」とせまるのであった(くぅ~っ、サディスト母ちゃんだぜ)。
弓華は「人間ブタ」たちを蹴散らしつつ、「必ず助けるから」とガラス越しのキス。そしてしばしのお別れ。
そんな爆弾を抱えつつ、ついにカルナバル開幕。
これによって、ハイブリッド、鳳凰連合、豊平重工、飛龍会、ヴェルシーナなど、これまで出てきた殺し屋軍団に、新顔のホンチーバン、翼心会のメンバーによるメキシコ市街での殺し合いバトルロイヤル開始。
我らがハイブリッドの面子は、塵八、弓華、毒島、ソニア、そして……。
ハイブリッドのボス、白猫さんはカルナバル開催のために人質に。
弓華らが負ければ、白猫さん、弓華の母ちゃんの玩具になること必至。
なに、このハイテンション?
カルナバル、ファーストバトルはメンバーがメキシコに着くや否や始まった。
ハイブリッドの友軍、飛龍会が襲われた。相手はホンチーバン、中国の黒社会組織。
相手は中国拳法の達人じじいだ!(ついに出たよ、拳法の達人、わくわく)
平等院将一、いきなりの大ピ~ンチ。
わはははは、と笑ってしまいそうになるこの展開。
ヤングガン・カルナバル。さらに激しく、濃く、エロくなること必至。
そして次巻では、弓華の因縁の相手たち(母ちゃんに弟に琴刃)が襲いかかってくる(だよね?)。弓華は愛しの伶ちゃんを救えるのか?
ええっと、それで第一主人公の……塵八は、なにするの?
ブログランキングに一票お願いします
↓

さあ、いよいよ、盛り上がってきましたよ。
ついにクライマックス突入か? って感じです。
まず、冒頭で弓華の愛しの伶ちゃんが誘拐されちまいます。誘拐したのは弓華の腹違いの弟、ギャウザル。
そして伶ちゃんは、哀れ素っ裸にひんむかれ、ガラス張りの檻の中に。
その外側には、人間性を失った男「人間ブタ」たち。
うっひゃああ。ラノベレーベルでは書けない、ノベルズならではのヤバい描写。
弓華の母親、志摩麗華こと聖火は、「伶を助けたかったら、仲間のヤングガンをひとり殺せ」とせまるのであった(くぅ~っ、サディスト母ちゃんだぜ)。
弓華は「人間ブタ」たちを蹴散らしつつ、「必ず助けるから」とガラス越しのキス。そしてしばしのお別れ。
そんな爆弾を抱えつつ、ついにカルナバル開幕。
これによって、ハイブリッド、鳳凰連合、豊平重工、飛龍会、ヴェルシーナなど、これまで出てきた殺し屋軍団に、新顔のホンチーバン、翼心会のメンバーによるメキシコ市街での殺し合いバトルロイヤル開始。
我らがハイブリッドの面子は、塵八、弓華、毒島、ソニア、そして……。
ハイブリッドのボス、白猫さんはカルナバル開催のために人質に。
弓華らが負ければ、白猫さん、弓華の母ちゃんの玩具になること必至。
なに、このハイテンション?
カルナバル、ファーストバトルはメンバーがメキシコに着くや否や始まった。
ハイブリッドの友軍、飛龍会が襲われた。相手はホンチーバン、中国の黒社会組織。
相手は中国拳法の達人じじいだ!(ついに出たよ、拳法の達人、わくわく)
平等院将一、いきなりの大ピ~ンチ。
わはははは、と笑ってしまいそうになるこの展開。
ヤングガン・カルナバル。さらに激しく、濃く、エロくなること必至。
そして次巻では、弓華の因縁の相手たち(母ちゃんに弟に琴刃)が襲いかかってくる(だよね?)。弓華は愛しの伶ちゃんを救えるのか?
ええっと、それで第一主人公の……塵八は、なにするの?
 | ヤングガン・カルナバル前夜祭・標的は木暮塵八徳間書店このアイテムの詳細を見る |
ブログランキングに一票お願いします
↓