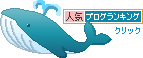米澤穂信さんの新作「インシテミル」読みました。
角川や東京創元社で出しているのとはがらりと雰囲気を変えてます。新潮の「ボトルネック」ともまたちがう。
今まででもっともミステリーらしいミステリーです。
それにしてもこの人、スニーカー文庫からデビューしたかと思ってたら、いつのまにか新潮や文春で書いてますよ。しかもハードカバー。
まあ、もともとあんまりラノベっぽくない作品を書いてる人だったんですが……。
スニーカーで人気でなくて切られるかと思ってたら、いつのまにか売れっ子作家に。
内容は、クローズドサークルもの。とうぜん連続殺人事件発生。
ここからしていつもの米澤じゃない。
ものすごい時給のモニターのバイト(一週間、外界から遮断される)に応募した主人公の結城。彼ら十二人は地下にある暗鬼館に幽閉されます。そこには十二体のインディアン人形が。
このへんのノリから、これは文春じゃなくて講談社だろう? と思ってしまいます。
もっとも彼らは変なあだ名で呼び合ったりしませんし、放送に過去の罪を暴露されることもありません。
ただ、この作品がふつうのクローズドサークルものと違う点は、この中での生活にルールが強要される点です。
夜の間は自室にいなければならない(鍵は掛からないけど)とかそういうことです。
破った場合はガードというロボットが制裁をくわえるようになってます。
さらにただいるだけで手に入る高額なバイト料の他に、さまざまボーナスがあり、その説明がされます。
つまり、人を殺した場合、殺された場合、探偵をして犯人を暴いた場合と特典が付くのです。
そして、各自の部屋には殺人のための凶器が用意されています。みな別々の。
このへんのノリはまさに「バトルロワイヤル」であり、あるいは「カイジ」であり、「扉の外」です。
要するに「インシテミル」とは「そして誰もいなくなった」に、デスゲームの要素をぶち込んだものなのです。
「そして誰もいなくなった」の場合、集められたものたちは、その気になれば自室で鍵をかけて閉じこもることも、逆に夜はみなで集まってやり過ごすこともできましたが、「インシテミル」ではどちらも禁止されています。それを強制的に守らせようとするもの(ガード)が存在します。
その結果、物語は「そして誰もいなくなった」や「十角館の殺人」とどう変わってくるのか?
それは読んでのお楽しみってことですか?
それにしても、この米澤穂信っていう人、今まで書いてきた作品から、あまりマニアックなミステリー読みじゃないのかと思ってましたが、かんちがいだったようです。
全編からミステリーマニアの匂いがぷんぷんします。
ブログランキングに一票お願いします
↓

角川や東京創元社で出しているのとはがらりと雰囲気を変えてます。新潮の「ボトルネック」ともまたちがう。
今まででもっともミステリーらしいミステリーです。
それにしてもこの人、スニーカー文庫からデビューしたかと思ってたら、いつのまにか新潮や文春で書いてますよ。しかもハードカバー。
まあ、もともとあんまりラノベっぽくない作品を書いてる人だったんですが……。
スニーカーで人気でなくて切られるかと思ってたら、いつのまにか売れっ子作家に。
内容は、クローズドサークルもの。とうぜん連続殺人事件発生。
ここからしていつもの米澤じゃない。
ものすごい時給のモニターのバイト(一週間、外界から遮断される)に応募した主人公の結城。彼ら十二人は地下にある暗鬼館に幽閉されます。そこには十二体のインディアン人形が。
このへんのノリから、これは文春じゃなくて講談社だろう? と思ってしまいます。
もっとも彼らは変なあだ名で呼び合ったりしませんし、放送に過去の罪を暴露されることもありません。
ただ、この作品がふつうのクローズドサークルものと違う点は、この中での生活にルールが強要される点です。
夜の間は自室にいなければならない(鍵は掛からないけど)とかそういうことです。
破った場合はガードというロボットが制裁をくわえるようになってます。
さらにただいるだけで手に入る高額なバイト料の他に、さまざまボーナスがあり、その説明がされます。
つまり、人を殺した場合、殺された場合、探偵をして犯人を暴いた場合と特典が付くのです。
そして、各自の部屋には殺人のための凶器が用意されています。みな別々の。
このへんのノリはまさに「バトルロワイヤル」であり、あるいは「カイジ」であり、「扉の外」です。
要するに「インシテミル」とは「そして誰もいなくなった」に、デスゲームの要素をぶち込んだものなのです。
「そして誰もいなくなった」の場合、集められたものたちは、その気になれば自室で鍵をかけて閉じこもることも、逆に夜はみなで集まってやり過ごすこともできましたが、「インシテミル」ではどちらも禁止されています。それを強制的に守らせようとするもの(ガード)が存在します。
その結果、物語は「そして誰もいなくなった」や「十角館の殺人」とどう変わってくるのか?
それは読んでのお楽しみってことですか?
それにしても、この米澤穂信っていう人、今まで書いてきた作品から、あまりマニアックなミステリー読みじゃないのかと思ってましたが、かんちがいだったようです。
全編からミステリーマニアの匂いがぷんぷんします。
 | インシテミル米澤 穂信文藝春秋このアイテムの詳細を見る |
ブログランキングに一票お願いします
↓