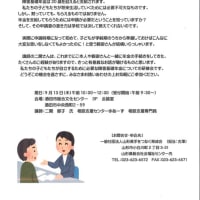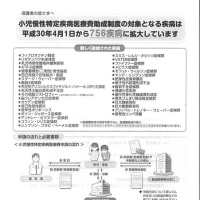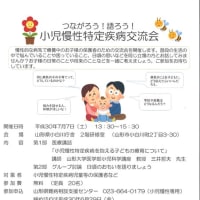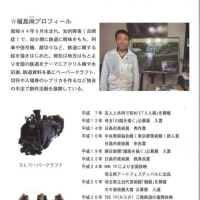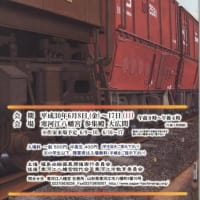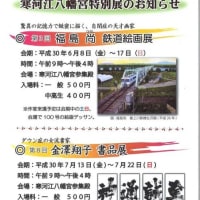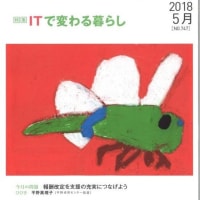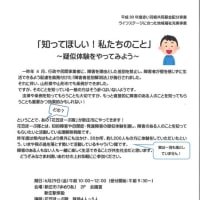一見関係のなさそうな
三題噺http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%A1%8C%E5%99%BA
をする。
立命館大学、望月昭氏ブログ「対人援助学のすすめ(別名:日々是新鮮)」
http://d.hatena.ne.jp/marumo55/
に次のような記述がある。
---------------------------------------
【引用始め】
1 八百長の証拠になった携帯メイル
大相撲の八百長が問題になってますけど、今回ついに本場所中止にまでなった文字通りの「決め手」は、携帯メイルという証拠ですよね。
これまでも八百長の問題は何度も何度も取りざたされてきたのに、いつもうやむやで終わってしまったのは、結局、八百長の「交渉」が、生身の人が走り回って耳打ちしていたという「揮発モード」だったのに対して、今回は「残存性」こそが命の、メイルという不揮発なモードでそのプロセスが残っていたからですよね。
2 情報の可視化・保存の重要性
「不揮発な何かに残す」ということの重大な意味は、相撲の八百長の当事者にはさぞかし「残すんじゃなかった」という後悔先に立たずの話ですが、「個別の支援教育プラン」などに代表されるような、生徒の「できる」記録も、なぜにそれを他の人にも読める・見えるかたちで保存するのが重要なのか、ということも、今回の事件の表現モードの特質からも知れようというものです。
八百長という例えは悪いのですが、「暗黙知からナレッジ(知識)に」という情報を公共的に可視化・保存することの重要性が、事の重大性という点では全く共通の問題です。
厚労省に依頼されて、「連携」や「情報移行」の現状やシステムの実例を全国調査しているのですが、「ケース会議を開いてます」「随時、先生が集まって相談します」っていうやりかたの連携や情報共有では、揮発モードで終わっちゃう場合があるんですよね。その人たちが一生連携していけばよいかも知れませんが、異動しちゃったら、もうそこで揮発(消滅)しちゃうわけです。
3 記録保存されないと、当事者のキャリアアップできない
なるほどそれじゃ次の担当者や移行先の支援者は困るよね、だから記録が大切だな、ってそのあたりで納得しちゃうこともあるんですが、それだけじゃないんですよね。
もうちょっと本質的なことは、不揮発なもの(記録)として残されないと、障がい者という当事者がその時点でも将来的にもキャリアアップのためにそれに自身が関わりハンドル(自発的利用が)できる「ポートフォリオ」(記録集)として使えない、ということがもっとも問題なわけすよね。
今回の大相撲では不揮発モードで八百長の「てだて」まで残っちゃった力士は、キャリアアップどころか廃業でしょうけどね。ま、それほどまでに不揮発モードは個人のキャリアに大きく影響を及ぼすというお話ですね。
【引用終わり】
-----------------------------------------------
以上、大相撲の八百長が携帯メイルに残っていたため大騒ぎになっている。
記録を残すことは事ほどさように大変なことである。
障がい者の事業所では、個別の支援計画を作成することが義務化されている。
それは、一人一人の障がい者が「最善の利益を得る」ため、その記録を積み上げていくというねらいがある。
学校においては、個別の指導計画の作成が義務付けられていて、かなり緻密な内容のものが毎学期、毎年度、本人により適合するように修整しながら作成されている。
また、中長期的な個別の教育支援計画も同様に作成されている。
そして、各地域の育成会では、保護者の手によって「生活支援ノート」〈山形市手をつなぐ育成会でも独自のものを作成〉のフォーマットが作成されている。
知的障がい者の生育歴はじめ、地域生活を送る上で必要とする関連情報を書き込めるようになっている。
しかし、こうしたノートの活用は十分広まっていない。
必要性を感じても実行するまで面倒で、続かないのが実情である。
ある程度の時間と分量が蓄積されないと、役立っている実感が生じないからである。
「生活支援ノート」に保護者が少しずつ書きためていくことで、時間の経過と共にかつての子どもの様子を振り返ると、確実に子どもの変化が見えてくる。
それがまた「生活支援ノート」の活用を一層促すといったことにつながってくる。
障がいのある本人にとって、日常生活で必要とすることが見えるようにするためにも、「生活支援ノート」に記録していくことは重要である。
携帯メイルといった不揮発性の機能によって、消去(揮発性)できない記録を残すことの現代的意義を上記の望月昭氏は評価している。
そう考えると、障がいのある本人たちが「最善の利益を得る」生活ができるようにするには、一つの手立てとして「生活支援ノート」の普及・活用を、もっと訴えていく必要がある。(ケー)
三題噺http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%A1%8C%E5%99%BA
をする。
立命館大学、望月昭氏ブログ「対人援助学のすすめ(別名:日々是新鮮)」
http://d.hatena.ne.jp/marumo55/
に次のような記述がある。
---------------------------------------
【引用始め】
1 八百長の証拠になった携帯メイル
大相撲の八百長が問題になってますけど、今回ついに本場所中止にまでなった文字通りの「決め手」は、携帯メイルという証拠ですよね。
これまでも八百長の問題は何度も何度も取りざたされてきたのに、いつもうやむやで終わってしまったのは、結局、八百長の「交渉」が、生身の人が走り回って耳打ちしていたという「揮発モード」だったのに対して、今回は「残存性」こそが命の、メイルという不揮発なモードでそのプロセスが残っていたからですよね。
2 情報の可視化・保存の重要性
「不揮発な何かに残す」ということの重大な意味は、相撲の八百長の当事者にはさぞかし「残すんじゃなかった」という後悔先に立たずの話ですが、「個別の支援教育プラン」などに代表されるような、生徒の「できる」記録も、なぜにそれを他の人にも読める・見えるかたちで保存するのが重要なのか、ということも、今回の事件の表現モードの特質からも知れようというものです。
八百長という例えは悪いのですが、「暗黙知からナレッジ(知識)に」という情報を公共的に可視化・保存することの重要性が、事の重大性という点では全く共通の問題です。
厚労省に依頼されて、「連携」や「情報移行」の現状やシステムの実例を全国調査しているのですが、「ケース会議を開いてます」「随時、先生が集まって相談します」っていうやりかたの連携や情報共有では、揮発モードで終わっちゃう場合があるんですよね。その人たちが一生連携していけばよいかも知れませんが、異動しちゃったら、もうそこで揮発(消滅)しちゃうわけです。
3 記録保存されないと、当事者のキャリアアップできない
なるほどそれじゃ次の担当者や移行先の支援者は困るよね、だから記録が大切だな、ってそのあたりで納得しちゃうこともあるんですが、それだけじゃないんですよね。
もうちょっと本質的なことは、不揮発なもの(記録)として残されないと、障がい者という当事者がその時点でも将来的にもキャリアアップのためにそれに自身が関わりハンドル(自発的利用が)できる「ポートフォリオ」(記録集)として使えない、ということがもっとも問題なわけすよね。
今回の大相撲では不揮発モードで八百長の「てだて」まで残っちゃった力士は、キャリアアップどころか廃業でしょうけどね。ま、それほどまでに不揮発モードは個人のキャリアに大きく影響を及ぼすというお話ですね。
【引用終わり】
-----------------------------------------------
以上、大相撲の八百長が携帯メイルに残っていたため大騒ぎになっている。
記録を残すことは事ほどさように大変なことである。
障がい者の事業所では、個別の支援計画を作成することが義務化されている。
それは、一人一人の障がい者が「最善の利益を得る」ため、その記録を積み上げていくというねらいがある。
学校においては、個別の指導計画の作成が義務付けられていて、かなり緻密な内容のものが毎学期、毎年度、本人により適合するように修整しながら作成されている。
また、中長期的な個別の教育支援計画も同様に作成されている。
そして、各地域の育成会では、保護者の手によって「生活支援ノート」〈山形市手をつなぐ育成会でも独自のものを作成〉のフォーマットが作成されている。
知的障がい者の生育歴はじめ、地域生活を送る上で必要とする関連情報を書き込めるようになっている。
しかし、こうしたノートの活用は十分広まっていない。
必要性を感じても実行するまで面倒で、続かないのが実情である。
ある程度の時間と分量が蓄積されないと、役立っている実感が生じないからである。
「生活支援ノート」に保護者が少しずつ書きためていくことで、時間の経過と共にかつての子どもの様子を振り返ると、確実に子どもの変化が見えてくる。
それがまた「生活支援ノート」の活用を一層促すといったことにつながってくる。
障がいのある本人にとって、日常生活で必要とすることが見えるようにするためにも、「生活支援ノート」に記録していくことは重要である。
携帯メイルといった不揮発性の機能によって、消去(揮発性)できない記録を残すことの現代的意義を上記の望月昭氏は評価している。
そう考えると、障がいのある本人たちが「最善の利益を得る」生活ができるようにするには、一つの手立てとして「生活支援ノート」の普及・活用を、もっと訴えていく必要がある。(ケー)