法務省が,共謀罪に関する条約の立法ガイドの記述に関する翻訳について,保坂議員らの指摘(←クリック)に対して,反論をしてきた。ここ(←クリック)のtopicsの「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念について(2006/6/22) をクリックし,出てきたページの下の方の「国際組織犯罪防止条約の『立法ガイド』における記述について(外務省ホームページへのリンク)」をクリックする。
この問題は,
「立法ガイド」(←クリック)のうち、パラグラフ51(43/543)にある「The options allow for effective action against organized criminal groups, without requiring the introduction of either notion - conspiracy or criminal association - in States that do not have the relevant legal concept.」を
「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀又は犯罪の結社の概念のいずれかについてはその概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置をとることを可能とするものです」
と翻訳するか
「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀又は犯罪の結社の概念のいずれについてもその概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置をとることを可能とするものです」
と翻訳するかという問題だ。
外務省は,上の翻訳が正しいとし,「念のため、『立法ガイド』を作成した国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)に対してご指摘のパラグラフの趣旨につき確認したところ、UNODCから、同パラグラフは共謀罪及び参加罪の双方とも必要でないことを意味するものではないとの回答を得ています」とし,法務省もこの部分をリンクする以上,同様の見解なのだろう。
しかし,共謀罪の問題は,実はここから先が問題だ。つまり,ここでいう参加罪とは何か?ということだ。参加罪というのは厳密には,犯罪組織に参加する行為そのものを犯罪化することだが,国際組織犯罪防止条約の参加罪は,犯罪組織に参加する行為そのものではなく,犯罪組織の犯罪行為などの一定の行為に参加する行為を犯罪とするものとなっているのだ。
したがって,いまの日本にある共謀共同正犯理論や予備罪などで十分,参加罪は日本には既に存在しているといえるのではないだろうか?
◆以上,詳しくは,
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/e2ec293558815aa740deb16e9b2cb9a3
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/7a9e57a24925d9121e02622af77e0508
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/9fb1f7f3d353392cce15a991e91181bb
などをご参照下さい。
法務省には,ぜひ,この点についても明確なご回答をいただきたいところだ…。
日本は,準空気銃の所持さえ,禁止されるような国ですから(ここ←クリック),テロ対策は十分でしょう…。あっ,スイスアーミーナイフも持ってると逮捕(?!)されちゃいますよ(ここ←クリック)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。
この問題は,
「立法ガイド」(←クリック)のうち、パラグラフ51(43/543)にある「The options allow for effective action against organized criminal groups, without requiring the introduction of either notion - conspiracy or criminal association - in States that do not have the relevant legal concept.」を
「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀又は犯罪の結社の概念のいずれかについてはその概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置をとることを可能とするものです」
と翻訳するか
「これらのオプションは、関連する法的概念を有していない国において、共謀又は犯罪の結社の概念のいずれについてもその概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置をとることを可能とするものです」
と翻訳するかという問題だ。
外務省は,上の翻訳が正しいとし,「念のため、『立法ガイド』を作成した国際連合薬物犯罪事務所(UNODC)に対してご指摘のパラグラフの趣旨につき確認したところ、UNODCから、同パラグラフは共謀罪及び参加罪の双方とも必要でないことを意味するものではないとの回答を得ています」とし,法務省もこの部分をリンクする以上,同様の見解なのだろう。
しかし,共謀罪の問題は,実はここから先が問題だ。つまり,ここでいう参加罪とは何か?ということだ。参加罪というのは厳密には,犯罪組織に参加する行為そのものを犯罪化することだが,国際組織犯罪防止条約の参加罪は,犯罪組織に参加する行為そのものではなく,犯罪組織の犯罪行為などの一定の行為に参加する行為を犯罪とするものとなっているのだ。
したがって,いまの日本にある共謀共同正犯理論や予備罪などで十分,参加罪は日本には既に存在しているといえるのではないだろうか?
◆以上,詳しくは,
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/e2ec293558815aa740deb16e9b2cb9a3
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/7a9e57a24925d9121e02622af77e0508
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/9fb1f7f3d353392cce15a991e91181bb
などをご参照下さい。
法務省には,ぜひ,この点についても明確なご回答をいただきたいところだ…。
日本は,準空気銃の所持さえ,禁止されるような国ですから(ここ←クリック),テロ対策は十分でしょう…。あっ,スイスアーミーナイフも持ってると逮捕(?!)されちゃいますよ(ここ←クリック)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。










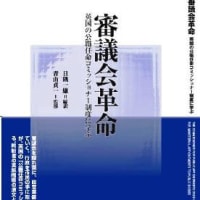
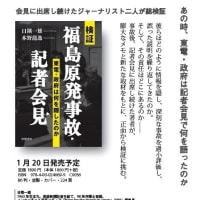
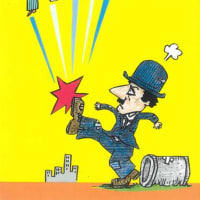
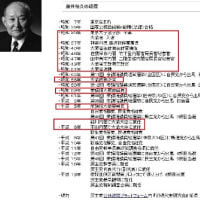
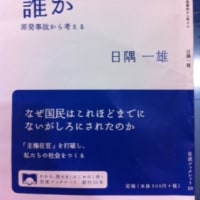
されている語法にも論理学の定理 (ド・モルガンの法則) にも反している
と言わざるを得ません。
従って問題は、どの解釈が正しいのかということではなく、なぜこれら
の団体が異常な解釈を与えたり、外務省がそれを「反論」と称すること
がまかり通るのかということです。
まず、"without"は"with"の否定に他ならず (OALD英英辞典でも"not"を
用いて定義されている)、かつ、英和辞典を見れば、原文のように"either"が単数名詞の前に来る形容詞の場合、否定文中ではその名詞が
指し示すどちらもが否定される全否定と明記されています。
(大修館のジーニアス大英和辞典と小学館プログレッシブ英和中辞典で
確認)
接続詞の"either A or B"という形の場合は、手元の辞書では否定文中で
全否定になるという記述や用例はありませんが、もし全否定でないと、
形容詞"either"で修飾される名詞が指し示す両者を具体的に表現して、
意味を変えずに"either A or B"という形に書き換えたときの整合性が
とれなくなります。
また、この否定文中での"either A or B"の意味は、下のトラックバック
(http://niphonese.jugem.jp/?eid=82) にあるコメントでも述べられて
いるように、"either A or B"を、"A"と"B"の論理和と考えたときの
ド・モルガンの法則
¬(A ∨ B) = ¬A ∧ ¬B
(ただし、"¬"は"not"、"∨"は"or"、"∧"は"and"を表す)
に合致します。
このようなことは、わざわざくどくどと述べるまでもなく、(少なくとも
理科系の教育を受けた者にとっては) 自明に近いのですが、下の数学科
出身の弁護士の経験によると、法曹界では正真正銘のド・モルガンの法則
が成り立っていないらしく、底知れぬ不安にかられます。
http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/column/ozaki/29.html
いずれにせよ,今回の条約及び立法ガイドについては,全体を読むとけっして共謀罪を設けるよう求めているものではないというのが最大のポイントだと思っています。一文の翻訳の仕方の問題ではなく…。
なく確定するはずの箇所を、なぜUNODCや外務省・法務省が勝手に
異なる解釈ができるのか、という疑問でした。(論理式を用いたのは
構造をわかりやすくするつもりでした。)
条約や立法ガイドの全体の趣旨が大問題だというのは仰る通りです。
あくまで法律の素人なもので、感謝しつついろいろ勉強させていただ
いております。