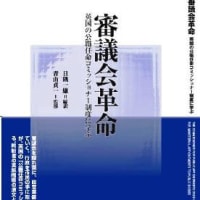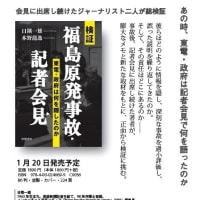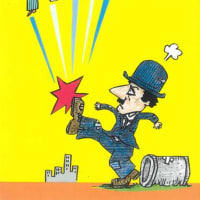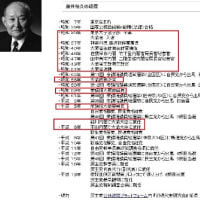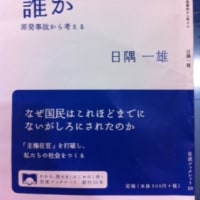北海道新聞で、北海道警察裏金疑惑キャンペーンを仕切った高田昌幸さんが、そのブログ「ニュースの現場で考えること」で強烈なメッセージを送っている。きれい事をいうだけでなく、それを実現するように職場で実践することが重要だ、というメッセージだ。もしかしたら、先日の道警幹部による敗訴について、きちんと伝えることのなかったメディア全体に対する怒りがにじみ出たのかもしれない(違っていたらごめんなさい)。
いずれにせよ、事件報道を売り物とする新聞社内で、事件報道のネタ元である警察を徹底的に敵に回す記事を書くことが歓迎されていたとは思えず、実際に、社内でけんかし続けてきたであろう高田さんでなければ、書けないようなメッセージだ。
高田さんは言う。
【日本で一番言論が不自由なのは、会社組織の内部において、である。そして、一番、モノを云うのが難しい場所は、会社組織の内部である。新聞社やテレビ局はかなり緩やかだとは思うが、それも比較級の問題でしかないように思う。過去、例えば、新聞労連は、何度も何度も、記者クラブ問題を取り上げてきた。そして、その是正を訴えてきた。しかし、その主張をリードしていたはずの新聞労連幹部は、組織に戻り、職場の中において、記者クラブの開放をどう主張、実践してきたのだろうか。堂々と、モノを言いつけたのだろうか。その主張を組織内部で貫こうとすれば、時には、すさまじいばかりのケンカも起きようが、それを恐れず、堂々と主張を続けただろうか。
一番難しいのは、足元、すなわち、日々の仕事の場で、堂々と意見を言い続けること、日々の自分の現場で闘うことなのだ、と思う。誤解を恐れずに云えば、例えば、労連委員長としてシンポジウムなどに出席し、そこで「あるべき姿」を語るのは容易い。内部の人が、匿名でメディア批判を行うのも容易い。
「言論の自由」は、対権力との関係において語られるが、しかし、言論の自由を実践する場所は、「対権力=メディア企業の外側」ではなく、メディア企業の内部にこそある。メディア企業内部の日常的場面にこそ存在するのだと思う。われわれが「権力のポチ」であるならば、それは、まず第一に、「会社の・組織のポチ」となって体現されているはずなのだ。】
私自身、耳が痛くなるが、果たして、この強烈な檄文だけでよいのだろうか。
孤高の虎は、この檄文に応えることができよう。しかし、この世の中、虎ばかりじゃぁない。ウサギもいれば、猫もいるし、それこそ犬もいよう。それらの人に、虎になれといっても難しい。
これは、マスメディアの世界だけのことではない。普通の会社でも、会社の不正などを質すことを虎だけに期待してはいけない。だからこそ、労働組合があるのだと思う。団結することで、自らの待遇を守るとともに、社内の不正に対峙する。マスメディアであれば、不当な圧力に対し、立ち上がるということだ。団結すれば、比較的ハードルが低くなる。
そう、私は、高田さんに、ただ、檄文を書くだけでなく、マスメディアが世の中の労働組合を守り切れなかったことを反省するとともに、今後労働組合を強化し、あるいは、別の方法で団結を強化し、マスメディアでも編集部が社内的に少しづつ独立を獲得できるようにすることも呼びかけてほしいと願っているのだ。
先日、BPOの放送倫理検証委員会が発表したNHK番組改編事件に対する意見書(http://www.bpo.gr.jp/kensyo/decision/001-010/005_nhk.pdf)の末尾に付されたフランスにおける内部的自由の制度は一つの検討材料のはずだ。
雇用者に対して、団結することができれば、ポチでなくなることだってできるかもしれない…。
先の意見書には、次のような一節が書かれている。
【NHKの「放送倫理の確立に向けて」(1999年)は、次のように述べている。
「放送は、ジャーナリズムの一つとして、表現の自由のもとに、国民に多様な情報を提供するという民主主義にとって欠かせない役割を担っている。このため、制度的に番組編集の自由が保障されている。この番組編集の自由を実質的に支えるのは、番組編集に関する放送事業者の自律であり、その自律の根底にあるのが、取材・制作に携わる者一人ひとりの『放送倫理』である。なかでも公共放送であるNHKは、国民の受信料によって成り立っていることから、その存立には視聴者との信頼関係が不可欠であり、とりわけ高い放送倫理が求められる」。
ここでは、放送事業者の自律、取材・制作者の放送倫理、視聴者の信頼が三位一体であることの自覚が語られている。しかし、取材・制作者一人ひとりの放送倫理が、放送事業者の自律を根底から支えているとすれば、これと業務命令との関係はどういうことになるのだろうか。放送倫理を根拠に、業務命令を拒否することができる、ということか。それとも、それとこれとは話が別、ということか。
NHK内で、あるいは放送界やマスメディア全体でも、放送倫理と業務命令との関係をどう考えるか、という問題はまだ十分には議論されていない。通例、事業体の最終的な意志決定の権限は経営者や上司に属すとされているが、果たして言論・報道・表現活動に関わる組織において、それをそのまま当てはめることができるのか。
私たちはここに、ひとつのアイロニーを見ないわけにはいかない。『ETV2001シリーズ戦争をどう裁くか』が問題視したのは、まさにこのような問いであった。
20世紀の戦争や紛争の世界を支配した命令の絶対性とそれへの服従が、世界各地で、無数の非人間的な行為を生んだ、21世紀はそれを克服するためにある、とシリーズ全体が説いていたのではなかったか。命令と倫理の関係はいまもアクチュアルな問題として、身近に存在しつづけている。】
★キャンペーン中「私は、民主党が導入しようとしている政治家の相続税脱税防止規定(世襲防止強力対策)に賛同します。民主党がこの規定を実効的なものにすることを期待します」
【PR】

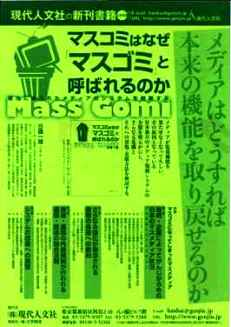
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。なお、多忙につき、試行的に、コメントの反映はしないようにします。コメント内容の名誉毀損性、プライバシー侵害性についての確認をすることが難しいためです。情報提供、提案、誤りの指摘などは、コメント欄を通じて、今後ともよろしくお願いします。転載、引用はこれまでどおり大歓迎です。
いずれにせよ、事件報道を売り物とする新聞社内で、事件報道のネタ元である警察を徹底的に敵に回す記事を書くことが歓迎されていたとは思えず、実際に、社内でけんかし続けてきたであろう高田さんでなければ、書けないようなメッセージだ。
高田さんは言う。
【日本で一番言論が不自由なのは、会社組織の内部において、である。そして、一番、モノを云うのが難しい場所は、会社組織の内部である。新聞社やテレビ局はかなり緩やかだとは思うが、それも比較級の問題でしかないように思う。過去、例えば、新聞労連は、何度も何度も、記者クラブ問題を取り上げてきた。そして、その是正を訴えてきた。しかし、その主張をリードしていたはずの新聞労連幹部は、組織に戻り、職場の中において、記者クラブの開放をどう主張、実践してきたのだろうか。堂々と、モノを言いつけたのだろうか。その主張を組織内部で貫こうとすれば、時には、すさまじいばかりのケンカも起きようが、それを恐れず、堂々と主張を続けただろうか。
一番難しいのは、足元、すなわち、日々の仕事の場で、堂々と意見を言い続けること、日々の自分の現場で闘うことなのだ、と思う。誤解を恐れずに云えば、例えば、労連委員長としてシンポジウムなどに出席し、そこで「あるべき姿」を語るのは容易い。内部の人が、匿名でメディア批判を行うのも容易い。
「言論の自由」は、対権力との関係において語られるが、しかし、言論の自由を実践する場所は、「対権力=メディア企業の外側」ではなく、メディア企業の内部にこそある。メディア企業内部の日常的場面にこそ存在するのだと思う。われわれが「権力のポチ」であるならば、それは、まず第一に、「会社の・組織のポチ」となって体現されているはずなのだ。】
私自身、耳が痛くなるが、果たして、この強烈な檄文だけでよいのだろうか。
孤高の虎は、この檄文に応えることができよう。しかし、この世の中、虎ばかりじゃぁない。ウサギもいれば、猫もいるし、それこそ犬もいよう。それらの人に、虎になれといっても難しい。
これは、マスメディアの世界だけのことではない。普通の会社でも、会社の不正などを質すことを虎だけに期待してはいけない。だからこそ、労働組合があるのだと思う。団結することで、自らの待遇を守るとともに、社内の不正に対峙する。マスメディアであれば、不当な圧力に対し、立ち上がるということだ。団結すれば、比較的ハードルが低くなる。
そう、私は、高田さんに、ただ、檄文を書くだけでなく、マスメディアが世の中の労働組合を守り切れなかったことを反省するとともに、今後労働組合を強化し、あるいは、別の方法で団結を強化し、マスメディアでも編集部が社内的に少しづつ独立を獲得できるようにすることも呼びかけてほしいと願っているのだ。
先日、BPOの放送倫理検証委員会が発表したNHK番組改編事件に対する意見書(http://www.bpo.gr.jp/kensyo/decision/001-010/005_nhk.pdf)の末尾に付されたフランスにおける内部的自由の制度は一つの検討材料のはずだ。
雇用者に対して、団結することができれば、ポチでなくなることだってできるかもしれない…。
先の意見書には、次のような一節が書かれている。
【NHKの「放送倫理の確立に向けて」(1999年)は、次のように述べている。
「放送は、ジャーナリズムの一つとして、表現の自由のもとに、国民に多様な情報を提供するという民主主義にとって欠かせない役割を担っている。このため、制度的に番組編集の自由が保障されている。この番組編集の自由を実質的に支えるのは、番組編集に関する放送事業者の自律であり、その自律の根底にあるのが、取材・制作に携わる者一人ひとりの『放送倫理』である。なかでも公共放送であるNHKは、国民の受信料によって成り立っていることから、その存立には視聴者との信頼関係が不可欠であり、とりわけ高い放送倫理が求められる」。
ここでは、放送事業者の自律、取材・制作者の放送倫理、視聴者の信頼が三位一体であることの自覚が語られている。しかし、取材・制作者一人ひとりの放送倫理が、放送事業者の自律を根底から支えているとすれば、これと業務命令との関係はどういうことになるのだろうか。放送倫理を根拠に、業務命令を拒否することができる、ということか。それとも、それとこれとは話が別、ということか。
NHK内で、あるいは放送界やマスメディア全体でも、放送倫理と業務命令との関係をどう考えるか、という問題はまだ十分には議論されていない。通例、事業体の最終的な意志決定の権限は経営者や上司に属すとされているが、果たして言論・報道・表現活動に関わる組織において、それをそのまま当てはめることができるのか。
私たちはここに、ひとつのアイロニーを見ないわけにはいかない。『ETV2001シリーズ戦争をどう裁くか』が問題視したのは、まさにこのような問いであった。
20世紀の戦争や紛争の世界を支配した命令の絶対性とそれへの服従が、世界各地で、無数の非人間的な行為を生んだ、21世紀はそれを克服するためにある、とシリーズ全体が説いていたのではなかったか。命令と倫理の関係はいまもアクチュアルな問題として、身近に存在しつづけている。】
★キャンペーン中「私は、民主党が導入しようとしている政治家の相続税脱税防止規定(世襲防止強力対策)に賛同します。民主党がこの規定を実効的なものにすることを期待します」
【PR】

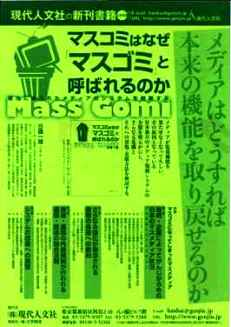
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。なお、多忙につき、試行的に、コメントの反映はしないようにします。コメント内容の名誉毀損性、プライバシー侵害性についての確認をすることが難しいためです。情報提供、提案、誤りの指摘などは、コメント欄を通じて、今後ともよろしくお願いします。転載、引用はこれまでどおり大歓迎です。