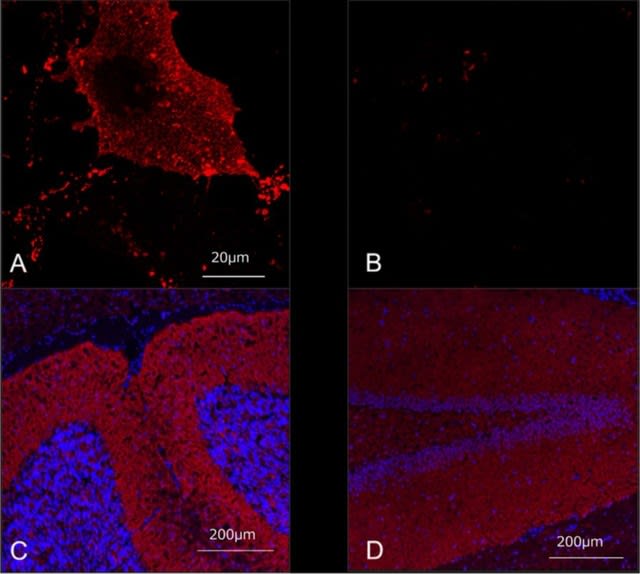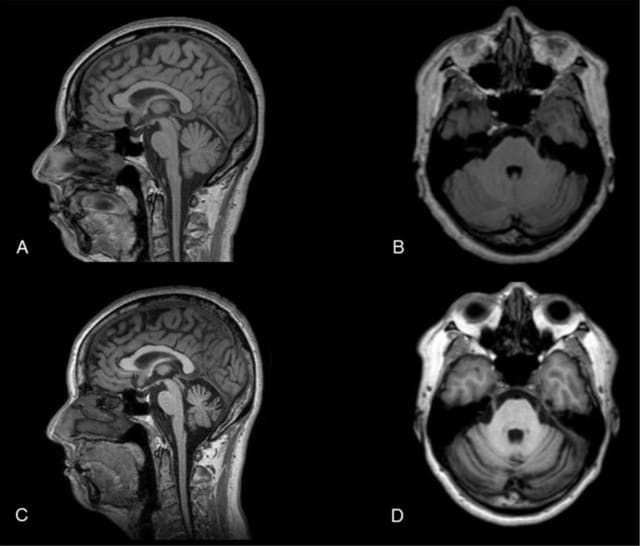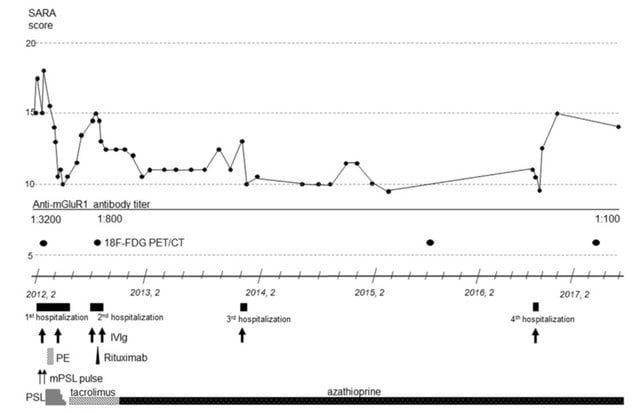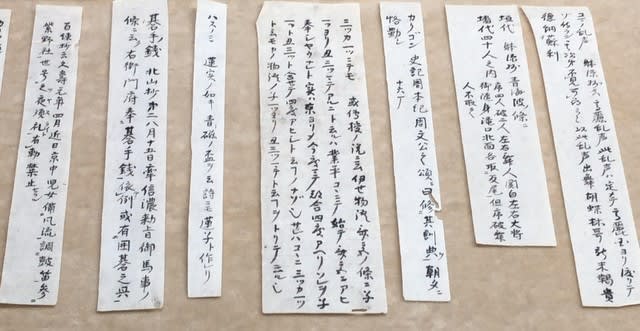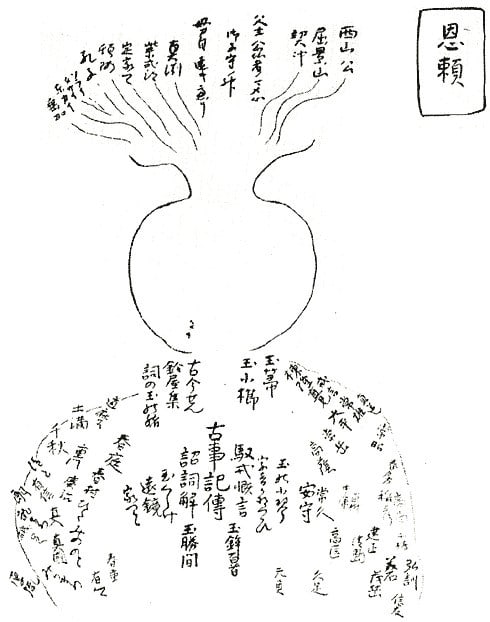【会長講演は神経内科医の直面する問題を示す】
米国神経学会年会(AAN)に参加している.私が一番楽しみにしているのは会長主催の全体講義(plenary session)である.その理由は,その時代においてまさに神経内科医が直面している問題を取り上げるためである.2014年にJames Bernat教授は<「現代の神経内科医が直面する倫理とプロフェッショナリズムをめぐる課題」と題する講演を行った.神経内科医を取り巻く環境は大きく変化しており,それは倫理観やプロフェッショナリズムといった医師としての根幹を脅かしかねない状況となっていること,そしてそれらが神経内科医を追い詰め,燃え尽き症候群という問題を引き起こしていることを警告するものであった.
また昨年のTerrence Cascino会長による「燃え尽き症候群に対する学会の取り組み」に関する講演は感動的であった.実際に学会内容は大きく変わり,以前のような口演とポスター発表主体から,教育を重視し,個人がさまざまなストレスから身を守るためのレジリエンスを鍛える催し物や,燃え尽き症候群の危険因子である上司のリーダーシップ不足の解消のための教育講座が開始された.それらのプログラムは本年はExperimental learningおよびLeadership Universityと名付けられ,数も内容も充実し,取り組みが軌道に乗っている印象を強く受けた.

【充実する学会の活動】
本年度のRalph L. Sacco会長による講演はどのような話になるのか非常に関心を持っていた.結論から言うと,米国神経学会の活動はさまざまな面で成功しているという内容で,これまでの悲壮感はなく,自信に満ち溢れた内容であった.まず示されたのが学会のミッションである.それは患者さんを中心にした神経疾患の治療・ケアの質の向上,および学会員のキャリア形成の満足度の向上を促進するというものであった.このミッションのためのさまざまな取り組みは成果を挙げ始め,学会員数は国内外を問わず順調に増加し,またダイバーシティ・マネジメントにも成功した.強調されていたのは政治への働きかけで,神経疾患に対する国家からの研究費は前年と比べ9%増加し,脳卒中に対する法案が可決するなど勝利宣言をした.

さらに医療格差や男女間格差,適正薬価,ビジネスへの取り組みを行っている.研究に関する取り組みの目玉はPrecision Medicineの神経内科学への導入である.患者の個人レベルで遺伝子を分析し,最適な治療方法を選択する新しい医学であるが,NIHのディレクターであるFrancis Collinsによる講演から非常に強烈な印象を受けた.会長の意図は,医学的発見を単に学術的成果に留めるのではなく,患者さんの健康につなげるという必要性を示すことであった.
【20数年前の感動を伝えたい】
今回,岐阜大学からは私と,神経内科医1年生の2人が参加した.まだ自分で発表するわけではなく,多くの発表についても意味が分からないかもしれない.英語もあまり聞き取れないかもしれない.しかしそれでも2人を連れてきたいと思ったのは自分の経験からである.私は神経内科医1年目の最後に,勤務先の信楽園病院の堀川楊部長から頑張ったご褒美にと航空券をいただき,ボルチモアで開かれた米国人類遺伝学会(ASHG)に参加させていただいた.さまざまな人種の研究者が一堂に会して,熱気のある議論をしていたことをいまでも覚えている.研究内容はほとんど理解できなかったものの,その熱気に興奮し,早く自分も研究者の仲間入りをしたいとその後の研究のモチベーションにつながった.事実,その2年後には,同じ学会において口演の機会を得ることができた.ただし質問の英語がほとんど聞き取れず立ちん坊になり,ボスの辻省次教授に答えていただいたのだが,本気で英語の勉強をしなければという気持ちを持った.おそらく今回初参加した2人も,この学会から私が20数年前に感じたものと同じものを感じてくれたのではないかと思う.どんどん世界を目指してほしいと思う.
【米国神経学会に参加しよう】
近年,米国神経学会に参加する日本人神経内科医は激減した.おそらく海外学会に参加するための研究費が獲得しにくくなったことや,より細分化された領域の学会への参加を優先していることが理由だと思う.しかし本学会は,近年,上述の大きな変化を遂げ,学ぶところが非常に大きい.若手医師にとっては多くのプログラムが用意され,幅広い知識の習得の場としては最適であり,また我々の年代のような指導者的立場にある医師にとっても,患者さんや医師にとって大切なことを改めて認識する機会を提供してくれる.翻って新専門医制度のような患者さんや医師にとって本当に意味があるのか分からないことに多くの議論や労力を割かねばならない日本の状況は不幸であり,なぜこのような大きな差が生じたのか恨めしく思えてくる.いろいろな疾患をそれぞれ1例でも経験し登録すれば,それで専門医になり,医療が良くなると考える日本と,積極的な教育の機会を提供し,変化する環境に対するレジリエンスを鍛えようとする米国とでは考え方がまったく違う.いずれにしても,来年,多くの日本人神経内科医がフィラデルフィアで,この学会の新しい雰囲気を味わっていただきたいと思う.
米国神経学会年会(AAN)に参加している.私が一番楽しみにしているのは会長主催の全体講義(plenary session)である.その理由は,その時代においてまさに神経内科医が直面している問題を取り上げるためである.2014年にJames Bernat教授は<「現代の神経内科医が直面する倫理とプロフェッショナリズムをめぐる課題」と題する講演を行った.神経内科医を取り巻く環境は大きく変化しており,それは倫理観やプロフェッショナリズムといった医師としての根幹を脅かしかねない状況となっていること,そしてそれらが神経内科医を追い詰め,燃え尽き症候群という問題を引き起こしていることを警告するものであった.
また昨年のTerrence Cascino会長による「燃え尽き症候群に対する学会の取り組み」に関する講演は感動的であった.実際に学会内容は大きく変わり,以前のような口演とポスター発表主体から,教育を重視し,個人がさまざまなストレスから身を守るためのレジリエンスを鍛える催し物や,燃え尽き症候群の危険因子である上司のリーダーシップ不足の解消のための教育講座が開始された.それらのプログラムは本年はExperimental learningおよびLeadership Universityと名付けられ,数も内容も充実し,取り組みが軌道に乗っている印象を強く受けた.


【充実する学会の活動】
本年度のRalph L. Sacco会長による講演はどのような話になるのか非常に関心を持っていた.結論から言うと,米国神経学会の活動はさまざまな面で成功しているという内容で,これまでの悲壮感はなく,自信に満ち溢れた内容であった.まず示されたのが学会のミッションである.それは患者さんを中心にした神経疾患の治療・ケアの質の向上,および学会員のキャリア形成の満足度の向上を促進するというものであった.このミッションのためのさまざまな取り組みは成果を挙げ始め,学会員数は国内外を問わず順調に増加し,またダイバーシティ・マネジメントにも成功した.強調されていたのは政治への働きかけで,神経疾患に対する国家からの研究費は前年と比べ9%増加し,脳卒中に対する法案が可決するなど勝利宣言をした.

さらに医療格差や男女間格差,適正薬価,ビジネスへの取り組みを行っている.研究に関する取り組みの目玉はPrecision Medicineの神経内科学への導入である.患者の個人レベルで遺伝子を分析し,最適な治療方法を選択する新しい医学であるが,NIHのディレクターであるFrancis Collinsによる講演から非常に強烈な印象を受けた.会長の意図は,医学的発見を単に学術的成果に留めるのではなく,患者さんの健康につなげるという必要性を示すことであった.
【20数年前の感動を伝えたい】
今回,岐阜大学からは私と,神経内科医1年生の2人が参加した.まだ自分で発表するわけではなく,多くの発表についても意味が分からないかもしれない.英語もあまり聞き取れないかもしれない.しかしそれでも2人を連れてきたいと思ったのは自分の経験からである.私は神経内科医1年目の最後に,勤務先の信楽園病院の堀川楊部長から頑張ったご褒美にと航空券をいただき,ボルチモアで開かれた米国人類遺伝学会(ASHG)に参加させていただいた.さまざまな人種の研究者が一堂に会して,熱気のある議論をしていたことをいまでも覚えている.研究内容はほとんど理解できなかったものの,その熱気に興奮し,早く自分も研究者の仲間入りをしたいとその後の研究のモチベーションにつながった.事実,その2年後には,同じ学会において口演の機会を得ることができた.ただし質問の英語がほとんど聞き取れず立ちん坊になり,ボスの辻省次教授に答えていただいたのだが,本気で英語の勉強をしなければという気持ちを持った.おそらく今回初参加した2人も,この学会から私が20数年前に感じたものと同じものを感じてくれたのではないかと思う.どんどん世界を目指してほしいと思う.
【米国神経学会に参加しよう】
近年,米国神経学会に参加する日本人神経内科医は激減した.おそらく海外学会に参加するための研究費が獲得しにくくなったことや,より細分化された領域の学会への参加を優先していることが理由だと思う.しかし本学会は,近年,上述の大きな変化を遂げ,学ぶところが非常に大きい.若手医師にとっては多くのプログラムが用意され,幅広い知識の習得の場としては最適であり,また我々の年代のような指導者的立場にある医師にとっても,患者さんや医師にとって大切なことを改めて認識する機会を提供してくれる.翻って新専門医制度のような患者さんや医師にとって本当に意味があるのか分からないことに多くの議論や労力を割かねばならない日本の状況は不幸であり,なぜこのような大きな差が生じたのか恨めしく思えてくる.いろいろな疾患をそれぞれ1例でも経験し登録すれば,それで専門医になり,医療が良くなると考える日本と,積極的な教育の機会を提供し,変化する環境に対するレジリエンスを鍛えようとする米国とでは考え方がまったく違う.いずれにしても,来年,多くの日本人神経内科医がフィラデルフィアで,この学会の新しい雰囲気を味わっていただきたいと思う.