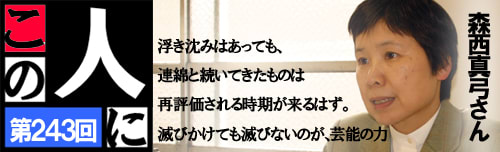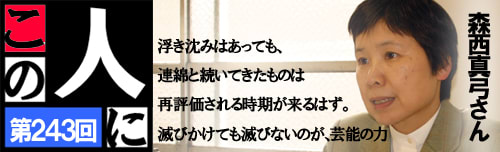
森西 真弓さん(『上方芸能』編集代表)
1968年4月26日に創刊された雑誌『上方芸能』は今年、40周年を迎えた。当初は「上方落語をきく会」の会報という位置づけだったが、徐々に上方(京阪神)の芸能全般を取り上げる雑誌へと進化し、現在では能・狂言、歌舞伎、文楽、日本舞踊、上方舞、邦楽、現代演劇、歌劇、落語、漫才など、幅広いジャンルを取り扱っている。ウォロと同じ市民メディアとして歩み続けてきた『上方芸能』の編集代表・森西真弓さんにお話を伺った。
もともと伝統芸能に興味はおありだったんですか。
中学生の頃から歌舞伎に興味をもち始め、テレビの劇場中継を見ていました。京都に住んでいたので、高校生のときは南座で年に2、3回ある公演をほとんど観に行ってました。スクラップ帳に貼ってある入場券を見ると、最初は一等席で観てるんです。親に買ってもらったのかどうか、はっきり覚えてないんですけど。
大学生になって歌舞伎研究会に入りました。1974年入学ですが、その頃の活動は下火で部員は4~5人だったかな。3・4回生の部員はいたけど、2回生はゼロ。それで私が2回生になったときは3回生がいなかったので、部長になったんです。高校の頃から「大学生になれば歌舞伎研究会の部長になりたい」という夢をもっていて、わりとあっさり実現してしまいましたね(笑)。でも、部長とは名ばかりで、雑用を一手に引き受けていた感じです。年に1回、機関紙を発行していて、その編集も手がけました。考えれば、今とやっていることは変わりません。
卒業したのは78年で、オイルショック直後ですから就職先がまったくありませんでした。市役所や警察、一般企業の入社試験も受けましたが次々に落ちて、卒業目前になったある日、たまたま本屋で『上方芸能』を立ち読みしていたら、スタッフ募集の記事が載ってたんです。たった1人いた専任の編集部員が辞めるというのでね。
その頃、すでに『上方芸能』を定期購読されていたんですか?
いえいえ、歌舞伎の専門誌は購読してましたが『上方芸能』はいつも立ち読み(笑)。でも、その記事を見つけたので、56号を初めて買って、書類を整えて応募したんです。試験は面接と課題作文で、めでたく合格。あとで発行人の木津川計(きづがわけい)に受かった理由を聞くと、「他の受験者は編集の経験者や芸能ファンだったが、新卒は君だけだった。新卒だと、思うように教育できるだろうと考えて」と話してくれました。
その頃の『上方芸能』は、今と同じスタイルでしたか?
そうですね。今とほぼ同じで、頁数も164頁ぐらいですね。専従の編集スタッフは私1人でしたが、ボランティアの人が5~6人手伝ってくれていました。うちの編集会議はいつも夜に開催するんですよ。みんな、仕事が終わってから会議に駆けつけてくるので。
ウォロと同じですね。当時の苦労話は何かあります?
パソコンもなければワープロもまだなかったので、原稿はほとんど手書き。達筆すぎて読めないのもありましたね。メールもないし、原稿を執筆者のところまで取りに行くということもしょっちゅうでした。でも、みなさんからいろいろ親切に教えてもらいながらやってました。入ってすぐに編集教室に通わせてもらったんですが、結局は実地で、失敗しながら覚えるのが一番だと思いました。それに、もともと芸能が好きですから、新たに触れた浪曲や落語などにも、それぞれに味わいがあるのがわかって楽しかったですね。
しばらくしてから編集次長になられたんですね。そのきっかけは?
平凡社が出している『別冊太陽』が83年に、大阪築城400年を記念して「浪華繁盛(なにはのにぎはひ)」という特集を組んだんです。そのとき私も原稿を書かせていただいたんですが、木津川が「社会では肩書きも大事」と言って、「今日から君は編集次長だ」と。突然でびっくりしましたけど。部下なし、上から2番目、下から一番目の編集次長になりました。
編集長になられたのは??
今から10年前、『上方芸能』が30周年を迎えたときです。その翌年に池坊短期大学で講義を担当しないかというお話もいただいてたので、これまた突然、編集長に任命されました。もともと木津川は、「編集長というのは若い人がやるもんだ。60歳になった人間がやるものではない」という持論があるので……実は私、今年の4月から編集代表になりまして、編集長は後輩の広瀬依子が務めることになりました。彼女も今年から大学で教えることになりました。
スタッフが順調に育っているということですよね。『上方芸能』を40年間発行し続けてきた、そのパワーの源は?
スタッフの力だけではなく、上方芸能を復興させたいという多くの方々の願いの集積です。戦後、東京一極集中が進み、演劇も芸能も関西は衰退しましたから。芸術の質という面では今もけっして劣っているとは思いませんが、公演回数など量の面で考えると格段の差があります。この差があるからこそ私たちの雑誌は必要とされているし、人間国宝の方々も応援してくださっています。でも、もともと文化はすべて上方発祥なんですよ。今言うと、なんか負け惜しみみたいですけど(笑)。
伝統芸能の世界では後継者のいない分野があると言われています。伝統芸能そのものの将来をどうお考えですか。
浪曲の世界では今、3人の演者(浪曲師)と2人の曲師(三味線伴奏者)が「新宣組」というユニットを結成して、自主公演や普及活動に取り組んでいます。全員30代ですが、みなさん魅力的で確実にファンを増やしてます。
それぞれに浮き沈みはあっても、これまで連綿と続いてきたものは、いつかきっと再評価される時期が来るはずです。滅びかけても滅びないというのが、その芸能のもっている力でしょうし、私はわりと楽観的に考えてるんですよ。
ただ、伝統をそのまま忠実に受け継いでいるだけではダメで、芸を革新しつつ次の世代に引き継いでいく努力も必要でしょう。
06年に亡くなられた文楽人形遣いで人間国宝の吉田玉男さんは、「曽根崎心中」の徳兵衛役に抜擢されたとき、心中を決意する場面で「恋人のお初の足を自分ののどにあててうなずく」という演出を考案されました。それまで文楽人形の女形に足はなかったので、初めての試みだったそうです。他にもさまざまな工夫や研究を積み重ねて役を創り上げられたのですが、若手には「何もその通り真似ることはない。独自に役を解釈して変えてもらっていい」とおっしゃっていました。きっぱりと、品格のある素敵な方でしたね。
玉男さんのお話を聞き書きでまとめられたのが、『吉田玉男 文楽藝話』ですね。
はい。もともとは国立劇場から、東京公演のときに発行する『上演資料集』に師匠の芸談を連載したいので、その聞き手を務めてほしいという依頼を受けたんです。それで年4回、ご自宅へ伺ってお話を聞くという幸せな時間を6年間過ごさせていただきました。
文楽の人形は今、かしらと右手を操る主遣い(おもづかい)、左手を操る左遣い、両足を操る足遣いの3人がいますが、もともとは1人で人形を遣ってました。それが約300年前、江戸時代に吉田文三郎が3人遣いの芸を築き、玉男さんにまで受け継がれ、そこからまたお弟子さんに受け継がれている。すごく奥深さを感じますね。
文楽は主遣いになるまでかなりの年数をかけるので、玉男さんが座頭役(ざがしらやく)になられたのは50歳を過ぎてからだそうです。でも、それだけの年数を経ているから、主遣いになっても、あれだけ見事にやれるんだなと思います。
同じ伝統芸能でも、歌舞伎は若いスターに大きな役を与えます。未熟な部分もありますが、少しずつうまくなっていく過程を見ることができる。たとえば、市川海老蔵は04年に十一代目を襲名して、いろいろ大役を務めてますよね。今はまだ荒削りなところもあるけれど、スケールが大きく、きらりと光る部分があってファンが多い。
なるほど、文楽と歌舞伎では育て方が違うんですね。
違うといえば、昔はそれぞれの都市に合わせて作品の内容も違ってたんですよ。『曽根崎心中』はわかりやすいほうですが、3回観ても筋のわからないような複雑な作品が文楽にはあります。理由は、江戸時代の大阪の人は理屈を好んだからだそうです。そのことはちゃんと『戯
け ざいろく財録』という文献に残ってるんですよ。享和年間の頃に歌舞伎の作者が、江戸と大阪、京都では観客の反応が違うのでその理由を調べたんです。今でいう三都比較ですね。それを読むと、大阪の人は理屈が好きだから複雑なストーリーを好む。江戸はパワー、力で勝負。京都は着だおれのまちだから見栄えで勝負すると。これはいわばマーケティング・リサーチのはしりでしょうし、伝統芸能であっても、その時代や都市の雰囲気に合わせて作品を変化させていくからこそ、人々に受け入れられ伝わっていくのだと思います。
「伝統は革新の連続である」という言葉を思い出しました。ありがとうございました。
インタビュー・執筆 編集委員
川井田 祥子
プロフィール
1955年京都生まれ。大学卒業後、『上方芸能』編集部に入社。83年より同誌編集次長、99年より編集長、08年より編集代表を務める。また、立命館大学産業社会学部教授、文化庁文化審議会文化財分科会伝統芸能専門委員、独立行政法人日本芸術文化振興会評議員なども兼務。主著に『上方芸能の魅惑――鴈治郎・玉男・千作・米朝の至芸』(2003年・NHK出版)、『吉田玉男 文楽藝話』(2007年・日本芸術文化振興会)、『上方芸能事典』(2008年・岩波書店、編纂)がある。
◎『上方芸能』購読のお申し込みは……
発行は年4回(2・5・8・11月)。1冊1,500円。全国の主要書店でも扱っているが、定期購読も申し込み受付中。年間購読料7,000円(税・送料込)。
『上方芸能』編集部
〒550-0003 大阪市西区京町堀1-12-14-607
電話:06-6441-3337 ファックス:06-6447-0900
kamigata@d6.dion.ne.jp