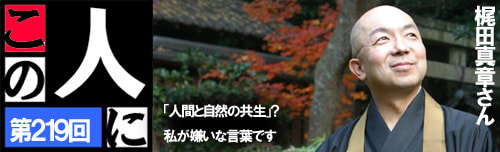
梶田真章さん(
法然院 貫主)
インタビュアー・執筆
編集委員 村岡正司
観光客の往来が絶えない京都市左京区の「哲学の道」。ここより少し山手に入った鹿ケ谷の閑静な森に建つ浄土宗の古刹法然院には、参拝、観光はもとより四季を通じて開かれる催しを目当てに多彩な人びとが集い、語らう。これらの仕掛け人は、”法然院ファンのゆるやかなネットワーク“である「法然院サンガ(註1)」を20年来主宰してきた貫主、梶田真章さんだ。宗教者として、一市民として、次世代へ伝えたい人と人とのつながりの意味を、「寺」を舞台に具現化し続ける。
■市民への環境学習の場としてお寺を開放した最初の試みが、1985年からの「法然院森の教室」ですね。これをスタートさせるについては何かきっかけがあったのですか。
先代である父の後を継ぎ、貫主として寺を預かるようになったのは84年3月のことですが、それ以前から環境問題には関心がありました。高度成長期を過ぎバブル期に向かう途上、京都にも開発の波が押し寄せてきていた頃です。大文字山のゴルフ場建設計画など、私の住んでいる地域でもそういう動きがありましたし…。また当時、寺を訪れる方たちから「いい場所ですね」という感想を聞くことが多く、最初は単に喜んでいたのですが、後で考えると「他の地域はだんだん悪くなっていることの表れではないか、今のうちによい環境を取り戻さなければ…」と思い至るようになりました。また時を同じくして境内で野鳥の観察をしていた久山さんという方と出会い、話をするうちに、市中に近い場所ながらムササビやフクロウ、モリアオガエルなど、野生の生き物が数多く生息する豊かなこの森を生かし、市民向けに一緒に何かを発信していけないかということになったのです。
■いわばお寺と市民の協働プロジェクトですね。今でこそ環境を考える催しは各地で開かれるようになりましたが、それらの草分け的存在ともいうべきでしょうか。
いえ、身構えて何かをやってやろう、という先駆者的な自負は全くなく、今でもそれは変わりません。私の普段からの思い、久山さんとの出会い、76年からこの法然院の森に居を移したこと…すべての偶然が積み重なって始まったのです。森の生き物たちと出会う境内のフィールドワークや写真展、アマゾンの熱帯雨林を保護する方の講演まで、子どももおとなも楽しめるさまざまな催しを久山さんたちと考え、実践してきました。現在は2〜3か月に一度の開催ですが、環境学習という言葉さえまだ耳新しかった最初の10年くらいは月例で行っていましたね。
今のようにインターネットがない頃はDMを送ったりクチコミに頼って広報していましたが、じわじわとリピーターが増え、89年には「森の教室」を母体とした子ども向けの環境学習サークル「森の子クラブ」が誕生しました。また93年、情報発信と学びの場を兼ねた施設「法然院森のセンター(共生き堂)」を山門の下に作り、同時に久山さんたちは「フィールドソサイエティー」というNPOを発足させました。以来、「森のセンター」の委託運営をお願いし、生き物の観察会や体験プログラムなど、環境学習の輪を広げていっていただいています。
■法然院は市民活動だけではなく、音楽、演劇、美術などさまざまなアーティストたちの表現の場としても開放され、人気を呼んでいます。利用されるみなさんはどこに魅力を感じているのでしょう。
境内を開放し「森の教室」をスタートさせたことは、「法然院はこういう形で寺を運営していきたい」という看板を上げ、お披露目をしているとみなさまに映ったようです。そういうわけでコンサートなり環境保全のシンポジウムなり、ここで何かやりたいと思っていらっしゃる方からの求めがあれば誰彼問わず場を提供するようになりました。お寺を訪れる方々との出会いを重ねる中で始まったものですが、歳月を経てひとつのスタイルになっていきました。
今日のように紅葉を見に来る観光客のほとんどは2、30分程度ここに留まり、あわただしく次の目的地へと去って行きますね。でも紅葉の美しい色合いを見るだけならテレビや写真の方がいい場合もあります。せっかく法然院にお越しになったのですから、肉眼では見えないものに心の眼を向けていただきたい。見た目のきれいさだけでなく紅葉のいのちの内面を見つめてほしいと思います。観光とは文字通り「光を心に観る」ということですから。
ここで開かれるさまざまな催しに参加する方々は、鳥の声、葉のそよぐ音などを聴きながらおよそ1、2時間をゆっくりと過ごすことになります。日常とは違った時間が流れるこの場で、多様な「いのち」の営みの存在を感じ取り、生きていることは絶えず他の「いのち」に支えられているのだという思いを抱く。この法然院という場を大事に思ってくださる方は、そこに何らかの安らぎを求めておられるのではないでしょうか。何百年もの間、数限りない人のいろいろな思いが積もり積もったこの場にこそ、人と人との、そして人と周りの生き物との出会いをなし、信仰、学び、安らぎを見出せる拠りどころがあるのかも知れません。
■お寺にゆっくり滞在する時間を提供することには、人と自然との関係についての梶田さんの「思い」を伝えるという仕掛けがなされているわけですか。
そうですね。でもよく言われる「人間と自然の共生」などは、私が嫌いな言葉です。ヨーロッパ人の思想が明治以降に伝わって以来、そう思わされてきた影響もあるのでしょうが「人間」と「自然」とを区別する限り、「自然は人間の外、周囲にあるもの」、つまり人は自然とは別物だと言っていることになります。私の考えでは「自然」とは眼に見える対象ではなく、「生き物同士が生かしあうしくみ」という「心」の部分だと思っています。先ほどの例でいえば、「紅葉自体」が自然ではなく、「それぞれの『いのち』を預かる、紅葉と自分との関係」が自然であるわけです。しかしながら人それぞれイメージするものは違うわけですから、事あるごとに「あなたの言っている『自然』とは何ですか」と問い、具体的に意味を説明してもらわなければなりません。「森の教室」を始めた頃はそんなに気にならなかったのですが、最近はなるべく自然という言葉を使わないようにしています。
■貫主としての大変ご多忙な毎日のなかにありながら、「法然院サンガ」でお寺を利用する方のスケジュール調整などもほとんどお一人でされているとお聞きしましたが…。
あまりそれらを大変だとは思ったことがありません。もともと人と出会って話をするのが好きですし、この法然院を使っていただいた方が喜んで下さるのを見るのはもっと好きですから…。寺を預かる私がみなさまとお話をすることで、寺に何を求めておられるのかが分かりますし、またかかわっている各市民団体の会合などにも努めて顔を出し、お話をする機会をもつなど、できるだけ外にも出ていくようにしています。
一方で600ほどある檀家との付き合いは、寺として一番大事なものです。すなわち法事や葬式を行い、できるだけ檀家とのつながりを密接にすることで、寺を維持する基盤も強固なものになっていくわけです。うちでは春秋の特別拝観以外は無料で境内を開放し、また「法然院サンガ」についても運営組織を別個につくっているわけではありませんので、いろいろな経費などは寺の収入のなかから支出しています。これらは檀家からの応援や相互の信頼関係がなければ成り立たないでしょう。
もとより多くの日本の寺は、核家族化が進み、親・子・孫がバラバラに住むようになった高度成長期までの長い時代、お盆や墓参りに象徴されるように先祖とのつながりに関する儀式をとりおこなう場として檀家との関係を維持しながら、かつ寺を訪れる方々との出会い、すなわち「縁」をも培ってきたのです。さまざまな方が訪れ、またさまざまな方に開かれた場が寺であったわけです。
法然院はその考えを継ぎ、かつ現代に合った寺のあり方を目指してきた結果、今の姿になりました。
人間は生かされている存在に過ぎなく、むしろ与えられた環境のなかでどう生きるべきかを考える場、周りの「いのち」と私たち人間とのつきあいを学ぶ場になればいいと思っています。それが寺本来の機能といえるのかも知れません。
●プロフィール●
1956年京都市生まれ。大阪外国語大学卒業。84年より京都市左京区の法然院(註2)第31代貫主(註3)に就任、現在に至る。アーティストの発表の場やシンポジウムの会場として寺を開放するなど、現代における寺の可能性を追求。一方で環境問題に強い関心を持ち多くの市民団体に参加する。現在、フィールドソサイエティー顧問、京都芸術センター運営委員、京都市景観・まちづくりセンター評議員、きょうとNPOセンター副理事長などを兼任。
(註1)サンガ サンスクリット語で「共同体」を意味する言葉。漢字では「僧伽」と書き、これを略したのが「僧」。僧とは元来、出家者個人を表わす言葉ではなく、仏教を信じる人々の集団を意味した。「法然院サンガ」という名称は、「寺は開かれた共同体でなければならない」という梶田氏の考えをもとに名づけられている。
(註2)法然院 正しくは善気山法然院萬無教寺。江戸時代初期に開かれた念佛道場が基となる浄土宗内の独立した一本山であったが、1953年に浄土宗より独立し、単立宗教法人となり現在に至っている。(参考:法然院パンフレット)
(註3)貫主 寺院における僧職の長に対する呼称。宗派によって異なるが一般的には「住職」ということが多い。











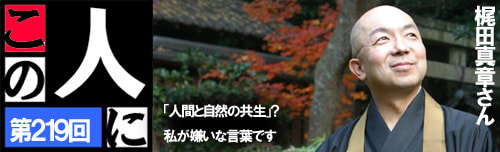
 第1章「協会創設のあとさき」
第1章「協会創設のあとさき」