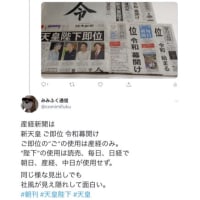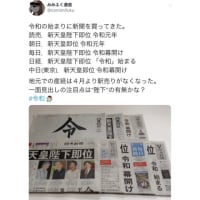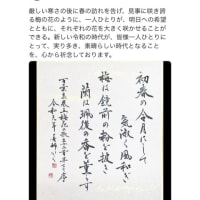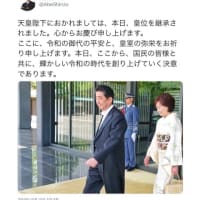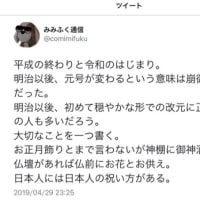2009年2月14日土曜日・午後3時45分から1時間番組として、
NHK総合テレビで放送される『100年インタビュー・宮崎駿』の録画DVDを
ブログ記事更新のため見直しました。
また、祝日(2月11日)を利用して、
現在BS2で特集放送されている手塚治虫さんの番組。
『手塚治虫のすべて』
『手塚治虫・現代への問いかけ』
をまとめて見ました。
その番組の中で、
1979年に制作された、『わたしの自叙伝~こども漫画33年~』。
安藤忠雄さんが出演された、『夢と未来・アトムからのメッセージ』。
に込められた強いメッセージを紹介します。
特に、
<子供時代の経験が、その後の人生にどのように影響しているか!>
について、3者共通の認識をお持ちのようで興味深い内容になっています。
*手塚治虫さんが番組『わたしの自叙伝』で語られた言葉。
「小学校3年生の頃に友人がボクに昆虫図鑑(あまりに美しい)を貸してくれた事が人生を変えました。それ以来昆虫に夢中になり、子供の頃の昆虫手帳(精密に描かれた)を10冊くらい描きましたし、天文学や様々なものに興味を持つきっかけになりました。」
「小学校の先生が作文を書く時、<丁寧な文字で枚数を1枚でも多く>と指導されたことが、ボクの漫画家人生の基礎になっています。」
「親爺が漫画好きで家には漫画本が多く、噂を聞いた友人達が家に遊びに来ました。」
「子供時代に刺激を受け自発的にのめり込んだものは、その後の一生を支配するような力があるのではないか?と思います。」
「子供の頃、よく両親に外国映画に連れて行ってもらい、ドイツ映画のSF(1926年制作:メトロポリスと思われる)に強い影響を受けました。」
「子供の頃から体力がなく、大きなコンプレックスを持っていました。しかし、何か別の方法(飛び抜けた特技)を持って見返してやろうと考え、漫画(ハングリー・アート)を選ぶことになっていきます。」
「いつまでも子供(の気持ち)でいたいと考えています。そのためには漫画を書き続けるしか手段がありませんでした。」
「自分が持つ漫画へのテーマは、<生きる>と言うことであり、その中に風刺と告発は欠かせません。」
「荒唐無稽な物の中に生み出される夢。そのことが(漫画において)最も重要な要素です。」
「日本映画『桃太郎の海鷲』を見たことで、漫画映画制作への強い願望を抱きました。」
「何かに迷った時、<自分がやらなければ誰がやるんだと言う使命感>が生じてきます。」
「ハングリーアートとしての漫画は、反発・批判が次へのステップに繋がります。ですから、(大人からの)漫画批判が、漫画家にとっての肥やしになりますし、批判されることで考える機会が与えられます。」
<子供達への3つのメッセージ>
~手塚治虫:ラスト・メッセージより~
・皆さんは、(事あるごとに)野次馬になってください。
とにかく、何でもかんでも好きなことを全部かじってください。
・皆さんが、今まで受けた(あるいはこれから受けるであろう)、
一番大きなショックな出来事を一生大事に、
忘れることなく持っていてください。
それは、将来きっと役に立ちます。
・皆様には、(何よりも)命を大事にしてください。
*安藤忠雄さんが番組『夢と未来(第弐夜)』で語られた言葉。
「(鉄腕アトムについて)子供の頃のワクワクした気持ちが、今読むと入り込めない。少年時代の夢の世界は、子供の頃だけに感じられる特別な感情。」
「子供心にある<遊び心を刺激してくれた未来図>に夢を持つことが、科学への興味や人生への興味につながる。」
「当時の日本(少年期を過ごした大阪)の町並みと手塚漫画に描かれる未来都市を比較し、開かれた未来に夢を描いた。」
「大人もまた国の復興を語り希望を語った前向きな時代変化の中で、子供心に漫画を通して未来像をイメージした。」
「今の時代、高いイマジネーションを描く人がいないことが現代の不幸であり、<経済ありき>の都市建設思考の中にあって、本当の豊かな世界があるのか疑問を持つ。」
「僕が作った(クリエートした)建築を見て、後世の若人達が何か感じてくれればいい。」
「今の若い人は未来を語らない。しかし、夢を語らないことで未来をクリエートすることはできない。1950年代~60年代の人々は夢を語ったし、夢を現実化ようと一生懸命に格闘した。私にしても手塚さんにしてもそうした時代の中で生きた。」
また、『手塚治虫・現代への問いかけ』第一夜、
<手塚治虫・ラストに込められたメッセージ>
の番組に出演された、
・マンガ家の萩尾望都さん。
・作家の高橋源一郎さん。
・精神科医の香山リカさん。
・俳優の船越英一郎さん。
のいずれも興味深いコメントを残されました。
特に漫画界のカリスマ・萩尾望都さんの出演は衝撃的でした。
「なんとなく漫画家になりたいと思っていたけれど、高校3年生の時に読んだ手塚漫画『新撰組』との出会いは、私にとって決定的な出来事だった。」
また、香山リカさんも
「小学生時代に読んだ手塚漫画『赤の他人』の衝撃が、その後の私の人生の大きな転機になっている。」
と告白しています。
いずれも10代の読書経験が、
その後の人生に強い影響を与えたことを読み取れます。
また、お2人とも現在の世界同時不況下において、
お勧めの一冊として『ブッダ』を上げていました。
さらに作家の高橋源一郎さんは、
「手塚漫画は悲劇的結末で終わることが多い。しかしその悲劇は英雄的な死(自己犠牲)を迎える事で読者の共感を得ている。」
「漫画『罪と罰』のラストの群像表現に見られる主人公の位置付けは、多くの人間の中での、些細な1つの行動でしかないことを物語っている。」
と分析。
『罪と罰』の群像表現の解釈に萩尾望都さんが感心していたことが印象に残りましたし、萩尾さんが子供のように色々と他の出演者に質問をしていたことで、最上のクリエーターの資質である好奇心の旺盛さを感じました。
船越英一郎さんが、
番組最後に漫画『火の鳥・太陽編』の中の言葉として紹介された、
「人間が作った宗教は、どれもが(信者にとって)正しい。だから、正しいもの同士の争いを止めることは誰にもできない。」
は、現在のパレスチナ情勢やイスラム情勢とリンクし、心打たれました。
また、出演された方々の共通意識として、
<困難な時代は、考えることのできる貴重な時間。>
と前向きに考えることで、前進できるのではないか?
と語っていました。
もし、考えることのできる時間を手にしたなら、
現実逃避ではない空想社会(未来像)をイメージし、
理想(目標)に向かって努力する時間に充てよう。
<困難な時代は、考えることのできる貴重な時間。>
は、そんな言葉にも聞こえます。
安藤さんの語る、
<高いイマジネーションを描くことのできる人材の不足。>
は、クリエーター(創造性=想像性=子供心)不足の証明。
切羽詰った時代の中で、有効な時間の使い道を考えて見ましょう。
<いつもとは違った視線。>
この記事で紹介するクリエーター達が、実践した生き方だと感じます。
<生きることは、クリエートすること。>
そんなことを感じさせる番組群でした。
『手塚治虫・現代への問いかけ』第参夜、
<いのちとヒーロー・ブラックジャックからのメッセージ。>
では、 医師・作家の海堂尊さんがゲスト。
・黒澤映画「赤ひげ」と、ブラックジャックを比較しながら<医療報酬の現場>。
・ドクター・キリコとブラックジャックの対立、<安楽死の是非>。
など、思いテーマにも触れながら、持論を紹介されました。
『手塚治虫・現代への問いかけ』第四夜、
<生と死を超えて・火の鳥からのメッセージ。>
では、劇作家の野田秀樹さんが出演され、空間・時間・シナリオ・キャラクターの役回り等、独自の視点から手塚漫画を語っています。
「ボクは特に鳳凰編が好きで、舞台化しようとしたが(火の鳥は)別の契約が入っていて断られた。手塚さんから恐縮されて、すべての漫画本が贈られてきて、<火の鳥以外は、すべてOKですよ。>と言われたが別の作品(坂口安吾)を選んだ。」
と貴重な思い出話をされていました。
最後に、
<宮崎駿さんの言葉>
を自分なりの言葉に置き換え読者の皆様に紹介します。
「幼児期の1日は、大人にとっての1年に値するんですよ。大人はある程度の常識を身に付けると、それで世界が解ったような気になって新しいことの興味を示さない。でも、子供は、一瞬一瞬が未知への挑戦であり、大人にとって他愛もない事に達成感を覚える。子供とは、無垢で価値判断がニュートラルな状態なことを指すんです。その子供の個性をのばす教育と言いながら、その実、時代にあった大人の価値基準を子供に押し付けて、つまらない大人を生産している。本来の子供の成長は、そんなものではないんです。」
「職人としての仕事の中で経験していく技術の追求とともに、本来養われるはずの精神の向上や洞察力が、工業製品で大量消費される単純でマニュアル化された世界の中で埋没していく。そのことが社会を薄っぺらで手応えのないものに変えてしまったし、製作(職人としての技術向上)する中で養われるはずのモノを見る目を曇らせてしまった。どんなに心を込めてモノづくりをしても、気付いてすらもらえない高い技術が、経済効率の下で、どんどん失われていく。」
今週放送される(た)一連の特集番組は、
漫画・アニメファンにとって、
伝説的な一週間(2009年2月第2週)として、
記憶されるのではないかと感じます。
<関連記事リンク>
*「手塚治虫の大特集 in NHK2009」。
http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/d/20090128
*100年インタビュー「宮崎駿」番組。
http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/e/f7269eed6cdca3175ecf6ee435823a58