
尾形光琳生誕350周年記念
特別展「大琳派展 ~継承と変奏~」(会期終了)
~東京国立博物館(平成館):2008年10月7日(火)~11月16日(日)開催。
→ http://www.tnm.jp/jp/exhibition/special/200810dairinpa_list.html
『風神雷神図屏風』
~展示日の日程~
国宝『風神雷神図屏風 』:俵屋宗達筆(京都・建仁寺蔵) 10/28 ~
重文『風神雷神図屏風』:尾形光琳筆(東京国立博物館蔵) 10/7 ~11/16
『風神雷神図屏風』:酒井抱一筆(東京・出光美術館蔵) 10/21~
『風神雷神図襖』:鈴木其一筆(東京・富士美術館蔵) 10/7 ~11/16
(注)4作品すべてを観覧する場合は10月28日~11月16日の期間限定になります。
<mimifukuから、一言。>
先日の記事中で紹介しました、
東京・上野の東京国立博物館で開かれていた「対決―巨匠たちの日本美術」。
琳派の2大巨頭、宗達と光琳の描いた「風神、雷神図屏風が展示されました。
~2008年8月11日⇔17日までの1週間。
そして2008年10月7日からの、
特別展<大琳派展>において琳派史上最も重要な4人の画聖による、
『風神雷神図』が公開されます。
宗達の国宝『風神雷神図屏風』は、
京都東山の建仁寺が所蔵するもので日本美術史上の傑作のひとつとされ、
その独創性は類を見ないものと言われています。
ただし京都に住んでいた宗達は、
三十三間堂の国宝彫刻『風神雷神像』や、
同じく、
国宝『北野天神縁起絵巻』の中での“雷神図”などをヒントとして、
描いているのではないかと考えられています。
以前に当ブログ内でも書いていますが、
私は宗達の「風神雷神図屏風」を30分位の時間、
京都国立博物館の2階平常展示室で、
一人きりで鑑賞したことがあります。
金地の中に浮かぶ 『雷神』が、なぜ白色なのか?
『北野天神縁起絵巻』での<雷神>は“赤色”で描かれています。
この<赤>は清涼殿での落雷の場面として画中に描かれていることから、
火を表現していると考えることができるでしょう。
しかし宗達はなぜ<雷神>を白で描いたのでしょうか?
想像ですが、雷神の白は目が眩むような光の表現ではないか?
すべての色は、強い光があたると白に近づくことは知られています。
(逆に光が不足するに従って、すべての色は黒に近づきます。)
一瞬の閃光は、目の前を真っ白にします。
金よりも強い色としての白は、光の象徴。
金地(金箔)の明るさと強さにも負けない輝きの色は?
そのことから、
~宗達の描いた雷神の<白>は、光の神。
では『風神』はどうでしょうか?
なぜ風神の色を緑なのか?
緑色で着色された風(象徴としての)は山から吹き降ろします。
想像ですが当時の山とは今とは違って“神隠し”などが横行する、
神秘的な場所であったと思われます。
石川県では毎年12月9日に、
材木を職業の生業とされている方々(大工さんや建具屋さん等)のお祭りで、
「山祭り」という風習があります。
商売の「恵比寿講」のようなお祭りでその日は仕事をお休みして、
山の神に感謝し酒盛りの宴会をします。
その日は、
必ず風が吹く(山が荒れる)との伝承もあるようです。
調べてみると京都ではそのような風習はないようですが、
宗達は加賀の国に長く滞在したとの言い伝えもあり(確証はない)、
何かの関係があるのかも知れません。
科学的(気象学)にみると風は気圧の変化と大きな関係があります。
山の湿潤な空気は雲を齎し雨を降らせます。
湧き上がる雲と気圧の変化は風を起こします。
プロ野球の阪神ファンにはお馴染の<六甲おろし>は、
山からの風であり盆地地形である当時の京都人の感覚としては、
風は海から吹き込むのではなく山から吹き下ろされるものだったとも考えられます。
また、
現在の科学でも森(木々)の空気が風を呼び込むことは認知されており、
日陰の中の清涼感を求めて多くの人が、夏の暑い日に緑を求めます。
そのことから、
~宗達が選んだ風神の<緑>は、山(森)の神。
宗達の『風神雷神図』の素晴らしさは雲の流れにもあります。
雷神図の天井から落ちてくるかのように描かれた雲はスピード感があり、
国宝『阿弥陀二十五菩薩来迎図』の速度感同様の優れた絵画表現を感じます。
また風神図の雲は画面端から雷神に向かい真っ直ぐ横に伸びていきます。
この作品は、「夕立ち」を表しているとも解釈されています。
今年(2008年)の夏は全国的に突発的な豪雨が多く、
この絵を
<雷の接近>
と、
<突風の接近>
と感じられれば違った見方ができるはずです。
宗達と光琳の絵画を比較すると似て非なるものとお分かりできると思います。
注目は“雲の表現(形態と雲の動きと色合い)と両者が描く目(眼球)の位置”です。
特に両者(今回展示される4作品を含め)の目の位置に注目してください。
宗達の場合空間の上から下界を見下ろすように目(眼球)の位置を書き込んでいます。
この宗達の手による眼球の書き込みで、
雷神は遠く空高くから地上に目を向けていることが感じられ、
本物を前にしそのことに気付いた瞬間、
“雷神はあっという間に空高く”へ舞い上がります。
と同時に、
眼球は雷光を生み出すと見える左手の先(太鼓を叩くバチを握り締める拳)をも見つめ、
雲の流れと眼球の焦点と左手の角度の統一性は、
一本の雷光を下界に向け放射する一瞬を見事に捕らえています。
この瞬間表現の素晴らしさは架空の偶像に対して実像としてリアル感を求めた、
宗達の考える緻密な構図計算の導入が如実であり、
絵師としての技量の高さを感じさせます。
風神の眼球はほぼ中央に位置し一見すると敵意のないひょうきんな表情にも見えますが、
その実、
無表情な中にも残忍性が感じられ雲の流れは真っ直ぐに横に流れることで、
強い風の到来を表現しているのではないか?
“風雲急を告げる”風神の表現は、
ユーモラスな顔の表情とは別に自然の驚異を示しているのかも知れません。
また風神の不自然に蹴り上げられた左足は、
国宝『信貴山縁起絵巻』の護法童子の“後ろ足表現”との類似性も見られ、
空間を駆け抜ける一瞬を見事に表しており生物としての実像に対する、
デフォルメを何の不自然さもなく画面に描き込まれていることへの驚きは、
20世紀絵画と比較しても何の遜色のない高いデザイン性を知ることになります。
比較して光琳の作品は私の目には残念ながらあくまでも写し(不完全な模写)であって、
宗達が表現した「空間の物語」も「絵画に対する思想」も稀薄だと言わざる得ません。
ただ、
光琳の表現の中で最も注目すべき点は雲を描く黒墨の濃さ。
黒墨のたらし込みを強調することで“暗雲立ち込める”雰囲気を表し、
嵐への予感を感じることもできます。
この尾形光琳作の『風神雷神図屏風』と同時公開される、
酒井抱一作の『夏秋草図屏風』(上記作品:裏面)には、
<雷神の裏面には夏草>
<風神の裏面には秋草>
が描かれて(貼り付けられて?)います。
~ただし近代に分離されており、展覧会では別の展示室に展示されています。
抱一もまた、
この作品から季節を感じ自分の思いを描いています。
裏面の蔦紅葉の蔦が風に吹かれる様は野分(のわき)を表していると言われ、
抱一が抱くこの屏風へのイメージは、
夏の積乱雲の発達と秋の台風(野分)への畏怖の念かも知れません。
なぜ宗達が画面からはみ出すように絵を描いているのか?
特に雷神図の画面からのはみ出しは、
突然おとずれる稲光や雷鳴の音が遠くから急速にやってくる様を表していると考えられ、
光琳の行儀良く画面内に収まる雷神図は、
雲の動きも感じられず光の速度を感じることができません。
宇宙のあらゆる物質の中で最も早く移動する光の速度を宗達は、
あらゆる技法で挑戦しようとしたのではないか?
そんなことを比較しながら鑑賞すれば、また違った見方ができるはずです。
お時間が許せば、
ぜひ日本人を古くから魅了して止まない、
この作品(題材)をご覧ください。
絵画との対話は想像力に働きかけます。
自分の持つすべての知識を総動員して、
絵の前に対峙し“ひととき空想”にふける。
空想を自分の言葉に変換しながら絵画を記憶していく。
モノの見方はひとつではない。
モノの見方を学ぶことは応用力の向上につながり、
応用力の向上はその時々の答えの出し方に変化を与える。
そして、
それぞれの答えが次の創造へのヒントとなるのです。
1つの答えを求める教育と同時に複数の答えを絞出す教育。
複数の答えを絞出すための多くの知識と経験の収得。
教育の形はデータ(既に確定しているとされる事項)の記憶に焦点を向けるだけでなく、
複数のデータを自分達で創造する。
この絵に限らず絵画鑑賞を含めて、“芸術鑑賞が持つ、
人への導きは無限の形を有する”ことを知る学習能力が高まれば、
人生は少しだけ豊かになると感じます。
余談になりますが同じ琳派の巨人、
酒井抱一の「風神雷神図屏風」は出光美術館(東京)
鈴木其一の「風神雷神図襖」は富士美術館(東京)
が所蔵しておりこの展覧会で展示されます。
また、
『風神雷神図扇』 酒井抱一筆(東京・太田記念美術館蔵)
が10/7 ~10/26に展示されます。
<文中紹介した作品の所蔵先>
*国宝 「信貴山縁起絵巻」(和歌山・朝護孫子寺所蔵)
→ http://www.town.heguri.nara.jp/gazou/sigiengi_4L.jp
*国宝『北野天神縁起絵巻(承久本)』(京都・北野天満宮所蔵)
→ http://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/exp2/w/143.html
*国宝「阿弥陀二十五菩薩来迎図」(京都・知恩院所蔵)
*夏秋草図屏風:酒井抱一筆(東京国立博物館所蔵)
<ブログ内:関連記事>
*特別展「対決-巨匠たちの日本美術」
→ http://blog.goo.ne.jp/mimifuku_act08/e/8815dfff64fe63023e1408be5ceeec65










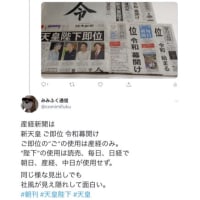

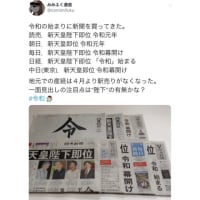

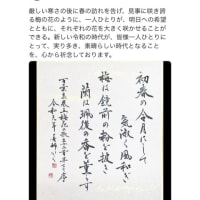
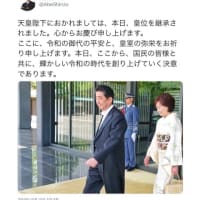



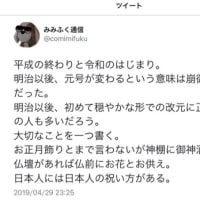






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます