暑かった日がウソのように肌寒い朝。
急ぎ足で秋がやってきたような気がします。
澄んだ空気の気配を感じて外に出ると、
スイフヨウが咲いていました。


今年のスイフヨウは、高さが3メートルほど、
つぼみは100個位ついています。
時間が経つと、お酒に酔ったようにピンクから赤に色を変える
スイフヨウの花の色変わりが楽しみです。



左から、紫蘇、ジンジャー、琉球朝顔の花。
応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
昨年秋から、毎日新聞で連載していた「境界を生きる」のシリーズ、
「学校現場で」が二日続きで、上下で掲載されました。
最後まで読んでくださってありがとう
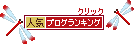
 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

急ぎ足で秋がやってきたような気がします。
澄んだ空気の気配を感じて外に出ると、
スイフヨウが咲いていました。


今年のスイフヨウは、高さが3メートルほど、
つぼみは100個位ついています。
時間が経つと、お酒に酔ったようにピンクから赤に色を変える
スイフヨウの花の色変わりが楽しみです。



左から、紫蘇、ジンジャー、琉球朝顔の花。
応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
昨年秋から、毎日新聞で連載していた「境界を生きる」のシリーズ、
「学校現場で」が二日続きで、上下で掲載されました。
 境界を生きる:学校現場で/上 性同一性障害「私の個性」 境界を生きる:学校現場で/上 性同一性障害「私の個性」 心と体の性別が一致しない性同一性障害(GID)の児童・生徒は、男女別の生活を求められる学校でさまざまな悩みや苦しみを抱えている。一方で、自ら一歩踏みだし、道を切り開く生徒も現れ始めた。思いを受け止め、周囲の教諭や生徒たちも変わろうとしている。【五味香織】 ◇校内で公表、理解得た経験 市の弁論大会で訴え 8日夜、川崎市で市内の定時制高校の弁論大会が開かれた。弁士は7校の代表14人。離婚家庭で築いた家族のきずなの話や、デートDV被害の告白。年配の生徒は社会人経験を踏まえてこれからの生き方を語った。 3番目で演台に立ったのは、県立川崎高1年の小林空雅(たかまさ)さん(15)。「みなさんは、個性をどのように考えていますか」。集まった約700人の生徒たちに問いかけた後、手元の原稿から目を上げて一呼吸置いた。 「私は男ですが、体の作りは女性として生まれてきました」 GIDであることを告白し、自分の抱えてきた苦しみを「眠っている間さえも、本当の性別と異なる性の体と生活している違和感から逃れることができません」という言葉で表した。 □ 小さいころから女の子の体であることに違和感があり、市立中学2年の冬、専門医にGIDと診断された。中学側は小林さんの希望を受け、男子生徒としての通学を認めた。 今春入学した現在の高校も、小林さんの合格が決まった時点で出身中学にトイレや更衣室などの対応を聞き、入学に備えた。同高の定時制課程にはさまざまな事情のある生徒が通うが、GIDであることを明らかにした生徒が入学したケースは初めてだったという。 既に戸籍を男性名に改名していた小林さんは入学に際し、校内で同級生たちにも公表したいと学校側に伝えた。専門医に「公表するなら早い方がいいのでは」と助言を受け、「何かがあって困った時に『実は……』と打ち明けるより、初めから知ってもらった方がいい」と考えたという。学校側はクラスの自己紹介や全校集会で、公表する機会を設けた。 西原秀夫副校長は「生徒にとって何が一番いいのかを考え、対応した」と話す。 □ 弁論大会で小林さんが繰り返し語ったのは、学校生活の楽しさだ。「すばらしい友達や先生方に恵まれました。校内でカミングアウトしても、以前と変わりなく接してくれています。自分がコンプレックスだと思うことは、他の人からすれば気に留めることはないのかもしれません。自分(の体)が嫌なことに変わりはありませんが、それがあなたの個性だと言われると、少し気持ちが軽くなります」 そして「自分に自信を持って、一人一人が一生懸命に輝いていける社会になるといいですね」と締めくくった。 すべての弁論が終わり、優勝者が発表された。小林さんだった。客席の同級生たちから「やったー!」と歓声が上がった。 同学年の女子生徒(15)は「私の友達にも同じような子がいる。他人に話すだけでもプレッシャーがあるはずなのに、大勢の前ですごい」。GIDのことを初めて知ったという市立橘高2年、斉藤美穂さん(16)は「重い内容で、話すには勇気がいると思った」と話した。 大会終了後、会場の外で「おれも(GID)なんだ」と打ち明け、連絡先の交換を求めてきた生徒もいた。トロフィーと賞状を手にした小林さんは「優勝できて、もっと自信を持とうと思えた」と笑顔を見せた。 毎日新聞 2010年9月15日 東京朝刊 |
 境界を生きる:学校現場で/下 性別悩む生徒、支えよう 境界を生きる:学校現場で/下 性別悩む生徒、支えよう ◇差別、偏見なくしたい…教諭ら、講習で対応考え 性同一性障害(GID)や同性愛など性的少数者(セクシュアル・マイノリティー)の子どもたちを理解し、差別や偏見のない学校作りを目指そう。そんな動きがようやく、教育関係者の間で活発になってきた。 「ひょっとして、この子は性別のことで悩んでいるのではないか。そう感じたら、まず何をすべきですか」 8月下旬、JR大阪駅近くの大学サテライトキャンパス。日本性教育協会が主催した夏季セミナーの会場は、参加申し込みを事前に打ち切ったにもかかわらず、定員を超す100人以上で埋まった。テーマは「児童・生徒と性同一性障害」。小中高の教職員や各地の教育委員会関係者の姿が目立った。 埼玉県の小学校がGIDと診断された児童に学校生活上の性別変更を認めたことを受け、文部科学省は4月、「児童・生徒の心情に十分配慮した対応を」と全国に通知した。しかし、現場の教員らには「どうすればいいのか」との戸惑いもある。講師を務めたGID学会理事長の中塚幹也・岡山大大学院教授は「対応に決まりはない。まずは子どもに『親身になって聴いてくれる人だ』と思ってもらうことが大切」と、基本的な心掛けをアドバイスした。 また、文科省の通知は学校に医療機関との連携を求めているが、この日のセミナーで専門的なジェンダークリニックがある地域として紹介されたのは10都道府県にも満たず、会場からは「実態に即さない通知だ」との声が漏れた。 中塚教授が岡山県内の人権担当教諭約500人を対象に実施した調査では、教諭の4人に1人が性別への違和感に苦しむ児童・生徒に接した経験があった。この日受講した50代の女性小学校教諭も「性別のことで悩んでいる児童がいたが、自分からはなかなか明かそうとせず、対応に苦慮した」と話す。「『プールに入りたくない』とだけ言われた場合、わがままとの見極めが難しい。特別扱いはいじめを引き起こしかねないというジレンマもある」 セミナーを企画した東優子・大阪府立大准教授(ジェンダー研究)は「対応の実例を知りたい教諭が多いようだ。専門家の講演を1時間聴くような形ばかりの知識教育ではなく、子どもたちの現実の悩みに沿って学校環境をどう整えられるか、考え合う取り組みが広がってほしい」と話す。 □ 性のあり方に関する悩みはいじめや不登校、自殺などの要因とも指摘されている。子どもたちが一人で抱え込まないように、教育関係者の理解促進に積極的に取り組む自治体や民間団体も現れた。 大分県は今月中にも中学校などの教職員を対象に「セクシュアル・マイノリティの人権」と題した出前講座を始める。性暴力被害者の相談事業などに取り組むNPO法人「えばの会(女性と子どもの性と人権を考える市民ネット)」との連携事業で、同会スタッフが講師を務める。県人権・同和対策課の長尾政昭課長補佐は「正直に言って、行政としては対策が手薄になりがちな分野。専門知識を持つNPOの力を借りて、まずは教職員に正確な情報を行き渡らせ、ゆくゆくは保護者や一般市民にも広げたい」と話す。 奈良教職員組合は2月、人権意識が高い学校作りに役立ててもらおうと、用語解説や学校での支援、家族への支援の方法などを紹介した「教職員のためのセクシュアル・マイノリティサポートブック」(A4判、19ページ)を作製。基本的な考え方として(1)本人の気持ちを尊重する(2)自分の性のありようが認識できない人、揺れている人、変わる人もいる(3)周囲が勝手に決め付けない(4)周囲との「違い」を否定しない--を挙げている。柴田俊和書記次長は「全国の学校などから注文が相次ぎ、1000部増刷した。当事者の高校生から『先生たちが自ら考えてくれたことが、泣きたいほどうれしい』という手紙も届いた」と反響の大きさに驚く。サポートブックはホームページ(http://www1.ocn.ne.jp/~jtu‐nara/)からダウンロードできる。 また、「“共生社会をつくる”セクシュアル・マイノリティ支援全国ネットワーク」(http://kyoseinet.blog25.fc2.com/)も3月、当事者が学校時代に何がつらかったかを振り返るインタビューを中心に構成したDVD「セクシュアル・マイノリティ理解のために~子どもたちの学校生活とこころを守る」(送料別1500円)を作製。事務局長の杉浦郁子さんは「GID以上に理解が進まない同性愛にも力を入れて作った」と話す。【丹野恒一】 ============== ■セクシュアル・マイノリティーと学校生活に関するQ&A Q:同性愛と性同一性障害はどう違う? A:同性愛は性的指向(興味や恋愛の対象)が同性に向かうこと。性同一性障害は自己の性別認識が体の性別と食い違うこと。性的指向が異性と同性のどちらに向かうかは関係ない。 Q:性別のことで生徒が悩んでいるようだ。本人には確かめていないが、どう対応すればよい? A:まず話しかけてみる。次にそういったテーマの本を教室や図書室や保健室に置いたり、授業中に何気なく話題に挙げ相談しやすいきっかけを作る。大事なのは知識があると見せることではなく、知ろうとする姿勢を見せること。教諭が笑いのネタとして「オカマ」「ホモ」などの言葉を使うと、本人はますます学校での居場所をなくす。 Q:性別に違和感のある子の精神的苦痛を和らげる環境整備の例は? A:制服を男女で分けず、例えばスカートかズボンか選べるようにする。トイレは男女兼用の場所を設けたり、職員用を使えるようにする。更衣室は別室を使わせたり周囲から遮断されたコーナーを作る。水泳授業はリポート提出などの代替措置を検討。宿泊行事の部屋割りや風呂は本人の意向を確かめる。 ※大阪府立学校人権教育研究会のリーフレットなどを基に作成 毎日新聞 2010年9月16日 東京朝刊 |
最後まで読んでくださってありがとう

 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね




























