待ちに待った、源平花桃が咲きました。
うれしくて、うきうきと心が弾みます。

4月4日の朝日新聞「くらし考」に、医学書院の≪シリーズ ケアをひらく≫の編集者をしている
白石正明さんのインタビュー記事「ケアをどう考えますか?」が紹介されていました。
 ≪シリーズ ケアをひらく≫は、
≪シリーズ ケアをひらく≫は、
上野千鶴子さんの『ニーズ中心の福祉社会へ 当事者主権の次世代福祉戦略 』や、
『べてるの家の「当事者研究」 』、『ALS 不動の身体と息する機械」などなど、とってもよい本が多い。
「最近手がけた本」と書かれている二冊の本。
先日、わが家に滞在されたあいさんがコーディネートされてる
4月14日夜のジェンダーコロキアムで、
テーマ本になっている最新刊の『リハビリの夜』と
『逝かない身体――ALS的日常を生きる』は、読みたいと思っていて、ちょうど取り寄せて読んだところ。
≪シリーズ ケアをひらく≫リハビリの夜
著:熊谷 晋一郎/2009年12月 /定価2,100円


『逝かない身体 ALS的日常を生きる』
著:川口 有美子/2009年12月 /定価2,100円
よみごたえがある、というより、ずしんと響く"衝撃"の二冊の本。
14日のジェンダーコロキアムで、熊谷さんの話しを聴けるのが楽しみです。
「百聞は一見にしかず」
以下に書評を紹介しますので、ぜひあなたも手にとって読んでみてください。
応援クリック してね
してね 


本文中の写真をクリックすると拡大します。
新聞記事
最後まで読んでくださってありがとう
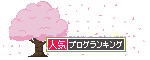
 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね

うれしくて、うきうきと心が弾みます。

4月4日の朝日新聞「くらし考」に、医学書院の≪シリーズ ケアをひらく≫の編集者をしている
白石正明さんのインタビュー記事「ケアをどう考えますか?」が紹介されていました。
 ≪シリーズ ケアをひらく≫は、
≪シリーズ ケアをひらく≫は、上野千鶴子さんの『ニーズ中心の福祉社会へ 当事者主権の次世代福祉戦略 』や、
『べてるの家の「当事者研究」 』、『ALS 不動の身体と息する機械」などなど、とってもよい本が多い。
「最近手がけた本」と書かれている二冊の本。
先日、わが家に滞在されたあいさんがコーディネートされてる
4月14日夜のジェンダーコロキアムで、
テーマ本になっている最新刊の『リハビリの夜』と
『逝かない身体――ALS的日常を生きる』は、読みたいと思っていて、ちょうど取り寄せて読んだところ。
≪シリーズ ケアをひらく≫リハビリの夜
著:熊谷 晋一郎/2009年12月 /定価2,100円


『逝かない身体 ALS的日常を生きる』
著:川口 有美子/2009年12月 /定価2,100円
よみごたえがある、というより、ずしんと響く"衝撃"の二冊の本。
14日のジェンダーコロキアムで、熊谷さんの話しを聴けるのが楽しみです。
「百聞は一見にしかず」
以下に書評を紹介しますので、ぜひあなたも手にとって読んでみてください。
応援クリック



本文中の写真をクリックすると拡大します。
| 今週の本棚:養老孟司・評 『リハビリの夜』=熊谷晋一郎・著 (医学書院・2100円) ◇脳性麻痺の医師が身をもって示す身体論 とても興味深い本である。著者は三十二歳の脳性麻痺(まひ)の医師。幼少の頃(ころ)は、もっぱら自分のリハビリに明け暮れていた。普通の基準からすれば、身体の動きがなにしろ不自由で、歩くことすらできない。だから、人生のほとんどが動くことの修練に費やされたことになる。むしろそういう人の人生論といってもいい。 こういう本というと、根性もの、精神力ものになりやすい。それはまったく違う。著者の自分を見る目は、よい意味できわめて客観性が高い。客観的な記述に、これほど共感できたのは、長い間生きてきたつもりだが、はじめてだといってもいい。なんだか著者と自分が一体化した感じがする。すぐれた身体論の特徴がそこにある。身体はむしろ共感するものであり、現代人が暗黙の常識としているような、個々別々の、「客観的事物」としての物質的存在ではない。 普通の人はこうした「障害」のある人を目にしたとき、どこか「目をそむけたくなる」気持ちが起こるはずである。それは右の共感に関係している。著者はその基礎にあるものを「規範化」された動き、規範化された身体と表現する。規範に外れたものを排除する。それは社会的にはごく当然の心情であろう。身体についてなら、普通は規範自体を意識していない。まさか「普通の」動きに適応できない人がいるとは、考えないからである。でもリハビリの専門家なら、そんなことは知っているだろうが。 そうはいかない。専門家であろうがなかろうが、現代人に変わりはない。どの社会にもそれなりの「規範」があって、そのなかでも身体は無意識の規範をいちばん強く帯びてしまう。現代はそうした規範性がじつはきわめて強い。現代社会は昔に比べて自由だと思っているのは意識で、だから無意識つまり身体はより強く束縛されているのかもしれない。服装はある程度自由だが、これは無意識ではない。では服の中にある身体はどうか。現代人が昔に比べてどれだけ多くの人に出会うか、それを考えてもわかるであろう。服で身体を隠しても、その「動き」はつねに「他人目(ひとめ)にさらされている」のである。 著者はそれを直接に論じているのではない。自分が現代社会にどのように適応していったか、それを詳細に論じる。著者の目的はこうである。「随意運動を手にするためには、既存の運動イメージに沿うような体の動かし方を練習するしかない、というのは間違いだ。それとは逆に、運動イメージのほうを体に合うようなものに書きかえるというやり方もある。私はこのような自分の経験を通して、規範的な運動イメージを押し付けられ、それを習得し切れなかった一人として、リハビリの現場のみならず、広く社会全体において暗黙のうちに前提とされている『規範的な体の動かし方』というものを、問いなおしていきたいと思っている」 著者ははじめに現代の脳科学でわかってきた運動に関する常識を解説する。さらにリハビリの簡単な歴史、思想の流れを紹介する。その次にまさに自分史が書かれる。両親から離れて、はじめて一人立ちして、アパートに住んだとき、トイレに行ってどうなったか。読者としての私は思わずそれに釣り込まれてしまう。まるで自分が転んで動けなくなったように感じる。 研修医として採血をする。いわゆる健常な人だって、初めは緊張する。著者の場合はどうなるんだろう。こちらがドキドキしてしまう。緊張して体がこわばる。これは著者の表現を使えば、「身体内協応構造」のためである。体のなかのたくさんの筋肉は、いちいち脳に指図されて動くわけではない。自前で適当に動くようになっている。それが場合によってはこわばりを生んでしまう。著者ははじめからその傾向が強いから、そのことがよくわかっている。 それを助けてくれるのは、周囲の人たちである。その手助けを「身体外協応構造」と著者は名づける。たしかにそうだなあ。読者である私はそう思う。自分の動きと他人の動きが上手にかみ合って、採血という動きが完了する。かといって、あらかじめこうして、次にこうしてと、プログラムが組まれるわけではない。 いろいろな立場の人に、本気で読んでほしい。しみじみそう思う。読みながらまず武道のことを思った。武道はもともとたがいに命がけで、動きのやり取りをする。そこに身体内外の協応構造がまさに表れる。その極(きわみ)の一つが合気道であろう。「気を合わせる」というのは、みごとな表現ではないか。 現代教育の大問題はじつは知育ではない。体育である。おりからオリンピックで盛り上がっているが、普通の人の体育はどうなっているのか。オリンピックの成績が問題なのではない。あなたの日常の体の動きが、じつは最大の問題ではないのか。他人が動き回るのを、ただテレビで見てりゃあ済むんだろうかしらネ。 毎日新聞 2010年3月7日 東京朝刊 |
| 「リハビリの夜」 熊谷晋一郎さん 車いすの医師が問う身体 脳性まひで自由が利かない体ながら、小児科医として働く。自身の身体感覚を手がかりに、リハビリにとどまらず、体の「動き」の本質を問い直した。 夏休みのリハビリキャンプで味わった苦痛や、挫折に伴う「官能的」な体のざわめき。電動車いすに初めて乗ったときの、空間のとらえ方の変化。言葉にしにくい体感が表現される。 「物心つく前から、リハビリは生活の一部だった」という。だが、「健常者の動きに近づけようとするリハビリ」には違和感を覚えてきた。目標を達成しようと焦るほど、体はこわばっていく。一方で、身の回りのことはすべて親が手伝ってくれていた。自分に何ができて、何ができないのかさえわからない。 そんな状況を変えたのは、東大入学と同時に始めた一人暮らしだった。トイレで用を足すこともできず、失敗を繰り返す。コップの持ち方から、研修医時代の採血の仕方まで、物や人との新たなつながり方を探る生活の中で、リハビリで押し付けられた体に合わない動きとは違う「自分の動き」を見いだした。 診療の一方で、昨年11月からは母校の特任講師としてバリアフリーの研究にも取り組む。「いろいろな障害や依存症、性的マイノリティーなどの当事者とやりとりする機会を増やし、医学の分野でやってきたことともつなげていきたい」(医学書院、2000円)(堀内佑二) (2010年3月16日 読売新聞) |
新聞記事
| 【特別寄稿】 川口有美子著『逝かない身体――ALS的日常を生きる』を読む 沈黙の身体が語る存在の重み 介護で見いだした逆転の生命観 柳田邦男(ノンフィクション作家・評論家) 《凄い記録だ》――私はこの本を読み進めるうちに率直にそう感じ,「生と死」をめぐる著者・川口有美子さんの思索の展開と,次々に登場する既成概念を打ち砕く数々の言葉に,ぐいぐいと引きこまれていった。 難病ALSの母を介護した12年間の記録だ。症状の進行がはやく,大半は言語表現力を失った沈黙の状態に陥っていた。 ALSは随意筋を司る神経細胞が死滅していく病気だ。手足が動かなくなるだけでなく,呼吸する肺の筋肉も動かなくなるので,人工呼吸器をつけないと生きられない。唇も動かなくなるから,発語ができなくなる。最近は技術の発達により,頬などに残されたわずかに動かせる場所にセンサーを取りつけて,YESかNOかの意思表示ができるようになった。 例えば介護者が50音表の文字盤を示し,「あかさたな……」と発音しながら指でたどっていく。「あ」と言った時に,患者が頬の筋肉を動かすと,センサーがピッと鳴る。次は「あいうえお」と1語ずつ読んでいく。「う」のところでピッと鳴ると,患者が言おうとする言葉の第1語が「う」であることがわかり,パソコンに記録させる。同じようにして,次の1語を探すと,「た」であることがわかり,患者は「うた(歌)を聴きたい」と言っているのだと汲み取り,好きな歌をCDでかけてあげる。患者とのコミュニケーションは,こうやって時間をかけて可能になったのだ。 ALSが他の病気と違う最も大きな特質は,五感と脳は生きているという点だ。ALSが進行すると,頬かどこかに最後まで残っていた筋のわずかな動きも消えてしまう。そうなると,センサーは何も感知できないから,患者は意思表示の手段を失う。目蓋も動かせなくなる。たいていは乾き目を避けて,閉じたままにする。患者は光もなく何の意思表示もできない中で生き続けるのだが,聴覚も思考力もあるのだから,ただひたすら耐えるだけという過酷な日々を送ることになる。そういう状態をTLS(Totally Locked-in State)と言う。 私は30年以上にわたって,がんが進行した人々の生き方と死の迎え方について学びを重ね,人間が「生きる」意味と「尊厳ある死」とは何かについて,自分なりにたどり着いた考えを持てたつもりでいた。しかし,最近,何人もの進行したALSの患者・家族にお会いして,その「生と死」への様々な向き合い方を見るにつれて,ALSの場合,「生きる意味」や「尊厳ある生」の問題は,がんの場合とかなり異質な面があり,もっともっと思索を深めなければ本質に迫れないなと,立ちすくむ状態になっていた。 そのさなかに,川口さんの『逝かない身体』に出会ったのだ。 この手記は,個人的な介護のドキュメントなのだが,母の言葉,心理,身体の様子などについてのとらえ方が実にきめ細かく,それらの一つひとつを通して,「生きる意味」や「生きるのを支える条件」についてどんどん思索を深め,自分を変えていく。しかも,医学の用語や既製の概念などにとらわれない平易な言葉と文章で表現している。それらは,一般的に考えられている難病患者の「いのち」をめぐる通念を180度逆転させるような,極めてドラマティックな気づきを含むので,私は川口さんが到達したそうした気づきの文章に出会う度に,心を揺さぶられ,「目から鱗」の気持ちになった。それらは,「生きる意味」「生きることを支える条件」の新たな発見と言ってもよいものだ。 特に注目すべき気づきを紹介したい。 * 川口さんは,はじめのうちは,死よりほかに母を楽にする方法はないだろうと考えていた。慈悲殺の考えだ。しかし,ある日,母が早めに書いてあった遺書をこっそり読むと,そこには家族に対し,「いっぱいお世話かけてごめんね でもうれしかった ありがとう」と書かれていた。そして,続く文章からは,最後まで娘たちに介護されて,自分も娘たちもハッピーエンドを迎えたいという意思が伝わってきて,ハッとなった。安楽死は,そういう母の最後の人生計画と言うべきものを台無しにするものではないか。川口さんが母の寝顔を見ると,母は娘に否定されそうになっている命を全身全霊で守ろうとしているかのように,すやすやと眠っている。他者が手を出すのを拒否する安らかさ! 究極のオーラと言おうか。 川口さんのいのちを見る眼が,突然逆転する。コペルニクス的転回だ。 《「閉じこめる」(=ロックトイン:筆者註)という言葉も患者の実態をうまく表現できていない。むしろ草木の精霊のごとく魂は軽やかに放たれて,私たちと共に存在することだけにその本能が集中しているというふうに考えることだってできるのだ。すると,美しい一輪のカサブランカになった母のイメージが私の脳裏に像を結ぶようになり,母の命は身体に留まりながらも,すでにあらゆる煩悩から自由になっていると信じられたのである。(中略)患者を一方的に哀れむのはやめて,ただ一緒にいられることを尊び,その魂の器である身体を温室に見立てて,蘭の花を育てるように大事に守ればよいのである。》(『逝かない身体――ALS的日常を生きる』200ページより引用) 川口さんは,母がロックトインの状態になってからも,顔色などから母の心情を読み取っていた。顔の肌がさらっと涼しげな時は,リラックスしているのだとわかるし,発汗にしても,汗や肌の微妙な違いを見分ければ,身体のどこかに痛みがあるためか,焦りやストレスのためかの区別がついたという。身体は硬直したままであっても,皮膚の下の毛細血管は母の心情を反映して,恥ずかしければ顔が赤くなるし,具合が悪ければ青白くなり緑色っぽくもなる。 そして,川口さんは母の身体から,「あなたたちといたいから,別れたくないから生きている」という声を聞く。 言葉は発しなくても,全身全霊で向き合っていた母と娘との間には,密度の濃いコミュニケーションが成立していたのだ。私は25歳だった息子が脳死状態に陥った時,ベッドサイドで同じことを経験したので,そういう「瞬間々々の真実」を信じることができる。 そうした魂レベルの会話は,受け手の側の感受性が問われるものであることに,川口さんは気づく。 こうして川口さんは,「ただ寝かされているだけ」と言う医療者がいようが,重病人を辛いままに「生かしている」と批判する人がいようが,そうした言葉に動かされることなく,母を生の側に引き留めるだけ引き留めて,12年間の介護を全うしたのだ。 「生きる意味」は,病者が自らは見いだせなくなっても,「他者」によって見いだされうるものであろうという川口さんの気づきも重要だ。社会的な理解も支援も遅れているがゆえに,自己肯定感を持てない患者が多いこの国において,刺激的な命題と言えるだろう。 死と生に関する表面的なスピリチュアリティ論でなく,いのちを支えるリアリティに満ちた鮮烈な言葉が連打される問題提起の手記だ。 『逝かない身体』が大宅壮一ノンフィクション賞候補に 第41回大宅壮一ノンフィクション賞の候補作品が3月23日に発表となり,川口有美子著『逝かない身体』(医学書院)が選出された。同賞は,大宅壮一氏の半世紀にわたるマスコミ活動を記念して制定されたもので,過去には柳田邦男著『マッハの恐怖』,沢木耕太郎著『テロルの決算』,猪瀬直樹著『ミカドの肖像』などが受賞している。選考会は4月5日に開催予定。 --------------------------------------------------------------------------- 柳田邦男氏 NHK記者時代の1972年に『マッハの恐怖』で第3回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。その後作家活動に入り,戦争,災害,事故,公害,病気などのドキュメント作品や評論を書き続けている。1979年『ガン回廊の朝』(講談社)で第1回講談社ノンフィクション賞,1995年『犠牲(サクリファイス)わが息子・脳死の11日』(文藝春秋)で第43回菊池寛賞を受賞。新著に『新・がん50人の勇気』(文藝春秋),『生きなおす力』(新潮社)などがある。 |
最後まで読んでくださってありがとう

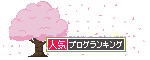
 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね





























