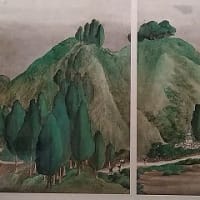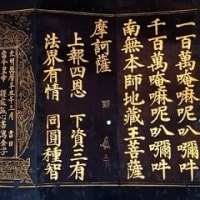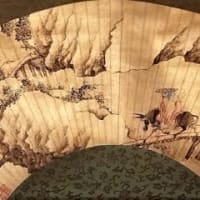○イアン・ブルマ『近代日本の誕生』(クロノス選書) ランダムハウス講談社 2006.10
たまたま寄った神田の三省堂で、新創刊らしい叢書を見つけた。知らない名前の著者だったが、装丁がきれいだったので買ってしまった。そして、4ページほどの「日本語版への序文」を読んで、これはいい見つけものだ、と直感した。
著者は語る。日本人は、自分の国の文化や歴史を特異なものと考えたがる傾向がある。しかし、事実は逆で、日本近代史の面白さは、世界中の至るところで起きた(または、今も起きている)出来事と共通点が多いことにある。強力な外国文明が迫ってきて、文化的伝統が破壊され、国家存亡の危機が高まる中で、自己変革に挑戦する国家が、どんな挫折を味わい、大惨事を経験し、勝利をつかむのか。その全てが「日本近代史にはドラマチックな形で非常によく現れている」。日本という国は「完全無欠な国ではない」が、挫折や困難を乗り越え、比較的自由な経済大国となり、豊かな文化や活発な知的活動を楽しめる国になった。だから、日本近代史は、全体として「一種のサクセスストーリー」である、と著者は言う。
本書は、原題『Inventing Japan: 1853-1964』のとおり、ペリー来航の1853年から、東京オリンピックの1964年までを一気に通観したものだが、著者の叙述態度には、つねに「オプティミスティックな批判精神」が感じられる。著者は、日本の犯した過ちを、逃れられない原罪のように、ペシミスティックに断罪することはしない。しかし、本書が、保守派知識人の喜ぶ「日本のサクセス」礼讃に満ちているかといえば、とんでもない。いつ、どうして、日本は進むべき道を間違ったのか(どうして、間違い続けているのか)、著者の批判は、明晰で怜悧で、容赦がない。
だが、その批判の鋭さにもかかわらず、日本近代史を「純粋に物語として読んでも非常に面白い」と言ってはばからない明朗快活さが、本書の後味を楽しいものにしている。これは、原文がいいのか翻訳の技なのか分からないが、文章全体に気持ちのいい力がみなぎっている。たぶん日本人の歴史学者なら、往々にして、従来の学説に右顧左眄して曖昧な物言いになるところ、ハッとするような指摘を惜しげもなく投げ出して、前へ前へキビキビと進んでいく文体が、さわやかである。日本人に、歴史を学ぶ醍醐味と、正しい意味での勇気と活力を与えてくれる良書であると思う。
以上、本日は京都駅前のネットカフェにて。
たまたま寄った神田の三省堂で、新創刊らしい叢書を見つけた。知らない名前の著者だったが、装丁がきれいだったので買ってしまった。そして、4ページほどの「日本語版への序文」を読んで、これはいい見つけものだ、と直感した。
著者は語る。日本人は、自分の国の文化や歴史を特異なものと考えたがる傾向がある。しかし、事実は逆で、日本近代史の面白さは、世界中の至るところで起きた(または、今も起きている)出来事と共通点が多いことにある。強力な外国文明が迫ってきて、文化的伝統が破壊され、国家存亡の危機が高まる中で、自己変革に挑戦する国家が、どんな挫折を味わい、大惨事を経験し、勝利をつかむのか。その全てが「日本近代史にはドラマチックな形で非常によく現れている」。日本という国は「完全無欠な国ではない」が、挫折や困難を乗り越え、比較的自由な経済大国となり、豊かな文化や活発な知的活動を楽しめる国になった。だから、日本近代史は、全体として「一種のサクセスストーリー」である、と著者は言う。
本書は、原題『Inventing Japan: 1853-1964』のとおり、ペリー来航の1853年から、東京オリンピックの1964年までを一気に通観したものだが、著者の叙述態度には、つねに「オプティミスティックな批判精神」が感じられる。著者は、日本の犯した過ちを、逃れられない原罪のように、ペシミスティックに断罪することはしない。しかし、本書が、保守派知識人の喜ぶ「日本のサクセス」礼讃に満ちているかといえば、とんでもない。いつ、どうして、日本は進むべき道を間違ったのか(どうして、間違い続けているのか)、著者の批判は、明晰で怜悧で、容赦がない。
だが、その批判の鋭さにもかかわらず、日本近代史を「純粋に物語として読んでも非常に面白い」と言ってはばからない明朗快活さが、本書の後味を楽しいものにしている。これは、原文がいいのか翻訳の技なのか分からないが、文章全体に気持ちのいい力がみなぎっている。たぶん日本人の歴史学者なら、往々にして、従来の学説に右顧左眄して曖昧な物言いになるところ、ハッとするような指摘を惜しげもなく投げ出して、前へ前へキビキビと進んでいく文体が、さわやかである。日本人に、歴史を学ぶ醍醐味と、正しい意味での勇気と活力を与えてくれる良書であると思う。
以上、本日は京都駅前のネットカフェにて。