A.憎悪の生みだす幻影について
「マイ・ブラザー」(ジム・シェリダン監督2009)という映画がある。デンマークの女性監督が撮った映画を、ハリウッドでリメイクしたものだというが、それを現代の米軍帰還兵の兄とその弟の物語に焼き直した渋い映画である。戦争に行った夫が戦死と伝えられ、子を抱えた妻は夫の弟と親密になったところで夫が生還して帰ってくる、という世界中で昔から戦争をした国ではよくあった事例のドラマである。しかし、この「マイ・ブラザー」は何よりアフガニスタンでの戦場場面の過酷さを描いて、本国で平和な日常を生きている人間の想像を超えたものを映像化する。物語はだいたいこんな筋である。
海兵隊大尉のサム(トビー・マグワイア)は、よき夫でよき父だった。落ちこぼれの厄介者の弟トミー(ジェイク・ギレンホール)が犯罪で入っていた刑務所を出所するのと入れ替わりに、妻のグレース(ナタリー・ポートマン)と二人の娘を残し、サムはアフガニスタンに出征する。しばらくしてグレースのもとにサムの訃報が届く。悲しみに沈むグレースたちを慰めたのはトミーだった。彼は兄嫁や姪たちを支える中で次第に更生していくが、ある日、死んだはずのサムが別人のようになって生還する。死んだと思ったサムは、敵に捕らわれ恐ろしい体験の中から奇跡的に生還したのだ。米軍兵士として囚われた捕虜体験のために心が壊れた兄・サムは、妻の不貞をしつこく疑い、しまいには拳銃を取り出してキレる。監督の意図は、戦争のPTSDを家族の絆が癒すことが出来るのかを問うというのが基本線だが、それとは別にぼくには気になったことがある。
それは戦争での敵の残虐さの描写である。アフガニスタンで敵に捕らわれたサムは、銃を突きつけられて仲間のアメリカ兵士を虐待しろと言われ、自分の命かわいさに仲間を殺してしまう。結局、部隊で彼だけが生き残って帰国する。敵であるタリバーンは、人間性のかけらもない冷酷で野蛮な人間たちであり、捕虜の心を弄び嘲笑って仲間同士の殺し合いをさせては喜んでいる。これは実際にあったことだろうか?戦場での出来事は、平和な世界では想像もつかない悲惨・残酷・異常なことが起るだろう。映画は虚構の作りものだとはいうものの、この映画を見たアメリカの観客は、悪魔のごときタリバーンを憎むだろう。でも、イスラーム原理主義を信奉する過激なテロリストは、人間ではない悪逆非道な怪物が集まっているのだろうか?暴力と残酷を喜んで遊んでいるような、そんな人間たちが、組織や集団を維持できるのだろうか?
ヴェトナム戦争の従軍兵士を主人公にした映画に、「ディア・ハンター」(マイケル・チミノ監督1987)というのもあった。ロバート・デニーロ、メリル・ストリープ、それにクリストファー・ウォーケンの感動を呼ぶ演技でイイ映画だったが、あれを見たときにも思った。これはアメリカ人が自分たちのリアルな日常という視点からだけ、戦争・戦場を見ているドラマで、家族や友人についてはあれほど繊細で優しい感情を紡いでいるのに、敵であるヴェトコン、ヴェトナム人たちはまったく同じ人間だとは思っていない。敵はロシアン・ルーレットで遊んでいる残忍で野蛮な鬼でしかない。ぶち殺して当然な連中であり、同情の余地などない。
戦場の兵士は、敵を同じ人間と思ったら戦えない。ただ無関係な他人・外人というだけ(それでも人間だから)ではなく、人間ではない悪魔、鬼だと思うことで敵を狙撃し殺戮し爆撃する心理が完成する。それはたぶん正義の問題や、イデオロギーの問題ではない。憎悪が行為を駆動する。映画は、敵を悪魔・鬼として描くことで、観客を同じ感情に導く。
もうひとつ、「紅いコーリャン」(チャン・イーモウ張藝謀監督1987、ベルリン映画祭金獅子賞)という中国映画がある。昨年のノーベル文学賞を受賞した獏言の「紅高粱」「高粱酒」が原作の、チャン監督の処女作である。この主演女優コン・リ鞏俐はその後大女優になったが、主演男優の姜文は後に「鬼が来た 鬼子來了」という映画を製作監督している。日中戦争時代の中国が舞台で、登場する日本軍は、畑をつぶして道路を建設するため村の人々を強制労働させ、人々へのみせしめに、抗日運動家の男を吊るし、村の肉屋に彼の生皮を剥ぐよう命じる。その夜、主人公は男たちに酒をふるまい日本軍への抵抗を誓う。ところが日本軍を待ち伏せるコーリャン畑にでたヒロインは無惨に撃ち殺され、男たちは怒りの声をあげて日本軍に襲いかかるが、全滅して血の海と化す。たった二人生き残った親子はコーリャン畑に立ちつくす。
この映画の日本軍は残酷な鬼。いきなりやってきて人の皮を剥け、と銃を突きつけて殺す。村上春樹の「ねじまき鳥クロニクル」にも、ノモンハンで、生きた人間の皮を剥いて殺す場面があったが、あれはロシア軍人がやる。でもこれは日本軍がやる。中国の反日教育というのも、日本軍がいかに残酷であったかを語り、このような物語が単なるホラー映画ではなく、現実にあったこととして人々に語り継がれている。日本軍はそんなひどい事はしていない、といくら主張しても歴史認識は簡単には改まらない。実証的に事実を確認しようとしても当事者は死んでいて、資料も乏しく闇の中であるから、何があったのかを議論しても決着は難しい。これは実証科学の問題にはならず、敵と味方の根深い感情の齟齬なのだ。戦争が生み出した憎悪は、やった方はすぐ忘れてもやられた方は百年二百年語り継ぐからだ。でも、これはどこの国でもやっていることだとすれば、日本ではどうだったのか?
戦争中、日本では中国の国民党蒋介石は卑怯で根性の曲がった悪役だと宣伝し、日米戦争が始まると鬼畜米英、出て来いニミッツ、マッカーサー、出てくりゃ地獄へ逆落とし♪、という歌まで歌わせて、国民に敵への憎悪を煽っていたが、直接日本人民が、悪辣な敵に虐殺されたり、日本の兵士が米軍や八路軍(中国共産党軍)などに非人道的な虐待や虐殺をされた物語を映画や小説にしたものがあっただろうか。ちゃんと調べたわけではないが、今まで見たことがない。日本人は敵に優しいのか?本物の悲惨を見るのが怖いのか?戦争が終わって、鬼畜米英が占領にやって来たとき、日本政府の男たちがまず考えたことは、日本の女が敵に片っ端から強姦されないように、プロの娼婦を用意することだった。慰安所の発想と同じ。敵にへりくだり女を差し出そうという卑屈。それが実際はあっという間にアメリカ大好き、日米友好に切り替えてしまった。アメリカ人もびっくり!日本人はほんとは敵を憎んだりしないやさしい国民だった!
日中国交回復を田中角栄が実現したとき、相手の周恩來はアジア百年の未来をにらんで、侵略戦争は日本の一部の軍国主義者がやったことで、日本人民大衆が望んだことではない、われわれは日本人を許そう、と言った。それは苦渋を含む寛容だったと思う。でも、日本人はさっさと過去はなかったことにして、手放しでこれからは日中友好、パンダ大歓迎!に走った。実に軽薄で、状況次第で謝ったり、大歓迎したりするかと思えば、今度は、一転してあいつらは卑劣だ傲慢だといい出して、敵視しはじめる。まともで冷静な賢さとは、相手を敵視しないだけでは不十分で、相手の憎悪や敵視を受け止めて、それでも私はあんたと同じように喜んだり悲しんだりする同じ人間だと言うためには、やっぱり歴史を知らないといけない。

B.イスラーム原理主義って?
御存じのように21世紀が始まったところで、アメリカを狙った同時多発テロが起り、世界の秩序破壊を企て、危険で卑劣なテロによって多くの罪もない人間を殺す「現代の悪魔」とみなされたのが、「イスラーム原理主義者」のテロリストである。その思想的根拠はイスラーム教にあり、現代社会の基本原理であり国際秩序の合意であるはずの、民主主義政治、政教分離原則、自由主義的経済、基本的人権、内政不干渉などを根本から否定する過激な非合法集団が、世界中で危険な陰謀を企んでいるとされる。具体的には、アル・カイーダでありターリバーンであり、パレスチナやパキスタンやイランなどに隠れ潜むハマース、ヒズボラ、ムスリム同胞団といった秘密組織である、とされる。いわば現代の最大の悪役であり、これを殲滅するためにアメリカ海兵隊やCIAは、必死で追いかけまわしている。9.11直後は、アメリカ国内ではイスラーム教徒というだけで危険視され、テロリストと関係があると見られたら拘束されたりした。今はさすがにそんなことはないし、イスラーム教徒・イスラム教国といっても、アメリカの政策に協力的なサウジアラビアのような国は敵視されないし、イスラーム教一般と原理主義とは別のものだということにはなっている。
そもそも「イスラム原理主義」という言葉自体は、アメリカ製である。宗教的ファンダメンタリズムという言葉は、本来1920年代のアメリカ合衆国で、聖書の近代的な文献解釈に反対する保守的なキリスト教徒たちが自分たちをファンダメンタリストと自称したことによる。キリスト教内部の原理主義は、神学的立場から神の創造を否定するダーウィンの進化論を認めず、これを学校教育で扱うことに反対したような人々の主張であり、大方の近代主義者からは時代遅れの頑固者の呼称として定着した。
それが、1979年のイラン・イスラム革命でアメリカ合衆国の傀儡政権だったパフラヴィー国王が打倒され、シャリーア(イスラーム法)に基づいて国家を統治する革命政権が樹立された時に、アメリカではホメイニ師に象徴される思想と運動をイスラーム原理主義と呼んだ。革命政権を敵視したアメリカは、イランは狂信的なファンダメンタリズム、教典の原典を無謬と信じ、著しく極端な教義を主張し追求する運動や思想という意味に一般名詞化した。ここから Islamic Fundamentalism という表現に、イスラームへの敵対や侮蔑の感情を込めて使用されるようになった。日本もそれに倣って「イスラーム原理主義」なる用語がメディアに登場した。
アメリカに敵対する邪悪な者どもに対して、「イスラーム原理主義」が使われているのだが、第二次世界大戦時の交戦相手である日本軍・日本人に対する「ジャップ」や、ベトナム戦争時の南ベトナム解放民族戦線や北ベトナム軍に対する「べトコン」などと同じ一種の蔑称である。ただ「イスラーム原理主義」は、言葉としては人種や民族への蔑称ではなく、イスラーム教という宗教の過激派、イスラーム教徒の中でも他宗教への不寛容な立場を意味する色合いが強い。イスラーム教徒の側からすれば、世俗化に抗して社会活動や政治活動を通じてイスラームの復興やイスラームによる統治を求める「イスラーム復興運動」や「イスラーム主義」は、『コーラン』の教えに忠実であろうとする正当なもので、これを暴力テロと結びつけて「原理主義」などと呼ぶのはまったく不当な表現だと言うだろう。アラビア語ではイスラーム主義者はイスラーミー、原理主義者はウスーリーユーンとなるという。
最近では、聖戦を唱えるジハード主義(Jihadism)、ジハード主義者(Jihadist)という言葉がメディアの一部で使用されているが、要するに反アメリカ、反シオニズムをスローガンにしているイスラーム教徒の過激派を指すと考えられる。この「過激派」という言葉についても、恣意的な用法でしかなく、必ずしも暴力テロや武器をもつ戦闘を行うものが「過激派」、行わないものが「穏健派」との区別はあいまいである。日本の一部の有力紙はパレスチナのハマースを「過激派」、ファタハを「穏健派」と表現しているが、これは「イスラエルを和平交渉相手として認めるか否か」の違いに過ぎない。どちらも武器や民兵組織で暴力を行使している。
Fundamentalであることとは、宗教をその基本精神、核となる教えにあくまで忠実に生きようとすることだ、という本来の意味で考えるなら、キリスト教徒にはキリスト教原理主義、ユダヤ教徒にはユダヤ原理主義、仏教徒には仏教原理主義が成立するはずである。キリスト教徒によって建設されたアメリカ合衆国にとって、イスラーム教という宗教は仏教や儒教などと違って、歴史的思想的にそのルーツを共にするものだから、「イスラーム原理主義」の思考法と行動原理はある意味で理解可能であり、それゆえにリアルな恐怖と憎悪も抱くと思う。
でも、日本という土壌では、キリスト教もユダヤ教もさして根がなく、ましてイスラーム教については根どころか葉っぱの先ほどの縁もない。だから「イスラーム原理主義」という言葉は、見たこともない幽霊、ターバンを被って銃をもって爆弾を巻いた恐ろしい人たち、という根も葉もないイメージだけになる。9.11のテロリストはもちろん許しがたいことをしたのだが、彼らが何を信じ、何を意図してあんなことをしたのかファンタジーみたいで理解できない。ただ怯えたり怖れたり憎んだりするのは、無知で軽薄のそしりを免れないと思う。
「マイ・ブラザー」(ジム・シェリダン監督2009)という映画がある。デンマークの女性監督が撮った映画を、ハリウッドでリメイクしたものだというが、それを現代の米軍帰還兵の兄とその弟の物語に焼き直した渋い映画である。戦争に行った夫が戦死と伝えられ、子を抱えた妻は夫の弟と親密になったところで夫が生還して帰ってくる、という世界中で昔から戦争をした国ではよくあった事例のドラマである。しかし、この「マイ・ブラザー」は何よりアフガニスタンでの戦場場面の過酷さを描いて、本国で平和な日常を生きている人間の想像を超えたものを映像化する。物語はだいたいこんな筋である。
海兵隊大尉のサム(トビー・マグワイア)は、よき夫でよき父だった。落ちこぼれの厄介者の弟トミー(ジェイク・ギレンホール)が犯罪で入っていた刑務所を出所するのと入れ替わりに、妻のグレース(ナタリー・ポートマン)と二人の娘を残し、サムはアフガニスタンに出征する。しばらくしてグレースのもとにサムの訃報が届く。悲しみに沈むグレースたちを慰めたのはトミーだった。彼は兄嫁や姪たちを支える中で次第に更生していくが、ある日、死んだはずのサムが別人のようになって生還する。死んだと思ったサムは、敵に捕らわれ恐ろしい体験の中から奇跡的に生還したのだ。米軍兵士として囚われた捕虜体験のために心が壊れた兄・サムは、妻の不貞をしつこく疑い、しまいには拳銃を取り出してキレる。監督の意図は、戦争のPTSDを家族の絆が癒すことが出来るのかを問うというのが基本線だが、それとは別にぼくには気になったことがある。
それは戦争での敵の残虐さの描写である。アフガニスタンで敵に捕らわれたサムは、銃を突きつけられて仲間のアメリカ兵士を虐待しろと言われ、自分の命かわいさに仲間を殺してしまう。結局、部隊で彼だけが生き残って帰国する。敵であるタリバーンは、人間性のかけらもない冷酷で野蛮な人間たちであり、捕虜の心を弄び嘲笑って仲間同士の殺し合いをさせては喜んでいる。これは実際にあったことだろうか?戦場での出来事は、平和な世界では想像もつかない悲惨・残酷・異常なことが起るだろう。映画は虚構の作りものだとはいうものの、この映画を見たアメリカの観客は、悪魔のごときタリバーンを憎むだろう。でも、イスラーム原理主義を信奉する過激なテロリストは、人間ではない悪逆非道な怪物が集まっているのだろうか?暴力と残酷を喜んで遊んでいるような、そんな人間たちが、組織や集団を維持できるのだろうか?
ヴェトナム戦争の従軍兵士を主人公にした映画に、「ディア・ハンター」(マイケル・チミノ監督1987)というのもあった。ロバート・デニーロ、メリル・ストリープ、それにクリストファー・ウォーケンの感動を呼ぶ演技でイイ映画だったが、あれを見たときにも思った。これはアメリカ人が自分たちのリアルな日常という視点からだけ、戦争・戦場を見ているドラマで、家族や友人についてはあれほど繊細で優しい感情を紡いでいるのに、敵であるヴェトコン、ヴェトナム人たちはまったく同じ人間だとは思っていない。敵はロシアン・ルーレットで遊んでいる残忍で野蛮な鬼でしかない。ぶち殺して当然な連中であり、同情の余地などない。
戦場の兵士は、敵を同じ人間と思ったら戦えない。ただ無関係な他人・外人というだけ(それでも人間だから)ではなく、人間ではない悪魔、鬼だと思うことで敵を狙撃し殺戮し爆撃する心理が完成する。それはたぶん正義の問題や、イデオロギーの問題ではない。憎悪が行為を駆動する。映画は、敵を悪魔・鬼として描くことで、観客を同じ感情に導く。
もうひとつ、「紅いコーリャン」(チャン・イーモウ張藝謀監督1987、ベルリン映画祭金獅子賞)という中国映画がある。昨年のノーベル文学賞を受賞した獏言の「紅高粱」「高粱酒」が原作の、チャン監督の処女作である。この主演女優コン・リ鞏俐はその後大女優になったが、主演男優の姜文は後に「鬼が来た 鬼子來了」という映画を製作監督している。日中戦争時代の中国が舞台で、登場する日本軍は、畑をつぶして道路を建設するため村の人々を強制労働させ、人々へのみせしめに、抗日運動家の男を吊るし、村の肉屋に彼の生皮を剥ぐよう命じる。その夜、主人公は男たちに酒をふるまい日本軍への抵抗を誓う。ところが日本軍を待ち伏せるコーリャン畑にでたヒロインは無惨に撃ち殺され、男たちは怒りの声をあげて日本軍に襲いかかるが、全滅して血の海と化す。たった二人生き残った親子はコーリャン畑に立ちつくす。
この映画の日本軍は残酷な鬼。いきなりやってきて人の皮を剥け、と銃を突きつけて殺す。村上春樹の「ねじまき鳥クロニクル」にも、ノモンハンで、生きた人間の皮を剥いて殺す場面があったが、あれはロシア軍人がやる。でもこれは日本軍がやる。中国の反日教育というのも、日本軍がいかに残酷であったかを語り、このような物語が単なるホラー映画ではなく、現実にあったこととして人々に語り継がれている。日本軍はそんなひどい事はしていない、といくら主張しても歴史認識は簡単には改まらない。実証的に事実を確認しようとしても当事者は死んでいて、資料も乏しく闇の中であるから、何があったのかを議論しても決着は難しい。これは実証科学の問題にはならず、敵と味方の根深い感情の齟齬なのだ。戦争が生み出した憎悪は、やった方はすぐ忘れてもやられた方は百年二百年語り継ぐからだ。でも、これはどこの国でもやっていることだとすれば、日本ではどうだったのか?
戦争中、日本では中国の国民党蒋介石は卑怯で根性の曲がった悪役だと宣伝し、日米戦争が始まると鬼畜米英、出て来いニミッツ、マッカーサー、出てくりゃ地獄へ逆落とし♪、という歌まで歌わせて、国民に敵への憎悪を煽っていたが、直接日本人民が、悪辣な敵に虐殺されたり、日本の兵士が米軍や八路軍(中国共産党軍)などに非人道的な虐待や虐殺をされた物語を映画や小説にしたものがあっただろうか。ちゃんと調べたわけではないが、今まで見たことがない。日本人は敵に優しいのか?本物の悲惨を見るのが怖いのか?戦争が終わって、鬼畜米英が占領にやって来たとき、日本政府の男たちがまず考えたことは、日本の女が敵に片っ端から強姦されないように、プロの娼婦を用意することだった。慰安所の発想と同じ。敵にへりくだり女を差し出そうという卑屈。それが実際はあっという間にアメリカ大好き、日米友好に切り替えてしまった。アメリカ人もびっくり!日本人はほんとは敵を憎んだりしないやさしい国民だった!
日中国交回復を田中角栄が実現したとき、相手の周恩來はアジア百年の未来をにらんで、侵略戦争は日本の一部の軍国主義者がやったことで、日本人民大衆が望んだことではない、われわれは日本人を許そう、と言った。それは苦渋を含む寛容だったと思う。でも、日本人はさっさと過去はなかったことにして、手放しでこれからは日中友好、パンダ大歓迎!に走った。実に軽薄で、状況次第で謝ったり、大歓迎したりするかと思えば、今度は、一転してあいつらは卑劣だ傲慢だといい出して、敵視しはじめる。まともで冷静な賢さとは、相手を敵視しないだけでは不十分で、相手の憎悪や敵視を受け止めて、それでも私はあんたと同じように喜んだり悲しんだりする同じ人間だと言うためには、やっぱり歴史を知らないといけない。

B.イスラーム原理主義って?
御存じのように21世紀が始まったところで、アメリカを狙った同時多発テロが起り、世界の秩序破壊を企て、危険で卑劣なテロによって多くの罪もない人間を殺す「現代の悪魔」とみなされたのが、「イスラーム原理主義者」のテロリストである。その思想的根拠はイスラーム教にあり、現代社会の基本原理であり国際秩序の合意であるはずの、民主主義政治、政教分離原則、自由主義的経済、基本的人権、内政不干渉などを根本から否定する過激な非合法集団が、世界中で危険な陰謀を企んでいるとされる。具体的には、アル・カイーダでありターリバーンであり、パレスチナやパキスタンやイランなどに隠れ潜むハマース、ヒズボラ、ムスリム同胞団といった秘密組織である、とされる。いわば現代の最大の悪役であり、これを殲滅するためにアメリカ海兵隊やCIAは、必死で追いかけまわしている。9.11直後は、アメリカ国内ではイスラーム教徒というだけで危険視され、テロリストと関係があると見られたら拘束されたりした。今はさすがにそんなことはないし、イスラーム教徒・イスラム教国といっても、アメリカの政策に協力的なサウジアラビアのような国は敵視されないし、イスラーム教一般と原理主義とは別のものだということにはなっている。
そもそも「イスラム原理主義」という言葉自体は、アメリカ製である。宗教的ファンダメンタリズムという言葉は、本来1920年代のアメリカ合衆国で、聖書の近代的な文献解釈に反対する保守的なキリスト教徒たちが自分たちをファンダメンタリストと自称したことによる。キリスト教内部の原理主義は、神学的立場から神の創造を否定するダーウィンの進化論を認めず、これを学校教育で扱うことに反対したような人々の主張であり、大方の近代主義者からは時代遅れの頑固者の呼称として定着した。
それが、1979年のイラン・イスラム革命でアメリカ合衆国の傀儡政権だったパフラヴィー国王が打倒され、シャリーア(イスラーム法)に基づいて国家を統治する革命政権が樹立された時に、アメリカではホメイニ師に象徴される思想と運動をイスラーム原理主義と呼んだ。革命政権を敵視したアメリカは、イランは狂信的なファンダメンタリズム、教典の原典を無謬と信じ、著しく極端な教義を主張し追求する運動や思想という意味に一般名詞化した。ここから Islamic Fundamentalism という表現に、イスラームへの敵対や侮蔑の感情を込めて使用されるようになった。日本もそれに倣って「イスラーム原理主義」なる用語がメディアに登場した。
アメリカに敵対する邪悪な者どもに対して、「イスラーム原理主義」が使われているのだが、第二次世界大戦時の交戦相手である日本軍・日本人に対する「ジャップ」や、ベトナム戦争時の南ベトナム解放民族戦線や北ベトナム軍に対する「べトコン」などと同じ一種の蔑称である。ただ「イスラーム原理主義」は、言葉としては人種や民族への蔑称ではなく、イスラーム教という宗教の過激派、イスラーム教徒の中でも他宗教への不寛容な立場を意味する色合いが強い。イスラーム教徒の側からすれば、世俗化に抗して社会活動や政治活動を通じてイスラームの復興やイスラームによる統治を求める「イスラーム復興運動」や「イスラーム主義」は、『コーラン』の教えに忠実であろうとする正当なもので、これを暴力テロと結びつけて「原理主義」などと呼ぶのはまったく不当な表現だと言うだろう。アラビア語ではイスラーム主義者はイスラーミー、原理主義者はウスーリーユーンとなるという。
最近では、聖戦を唱えるジハード主義(Jihadism)、ジハード主義者(Jihadist)という言葉がメディアの一部で使用されているが、要するに反アメリカ、反シオニズムをスローガンにしているイスラーム教徒の過激派を指すと考えられる。この「過激派」という言葉についても、恣意的な用法でしかなく、必ずしも暴力テロや武器をもつ戦闘を行うものが「過激派」、行わないものが「穏健派」との区別はあいまいである。日本の一部の有力紙はパレスチナのハマースを「過激派」、ファタハを「穏健派」と表現しているが、これは「イスラエルを和平交渉相手として認めるか否か」の違いに過ぎない。どちらも武器や民兵組織で暴力を行使している。
Fundamentalであることとは、宗教をその基本精神、核となる教えにあくまで忠実に生きようとすることだ、という本来の意味で考えるなら、キリスト教徒にはキリスト教原理主義、ユダヤ教徒にはユダヤ原理主義、仏教徒には仏教原理主義が成立するはずである。キリスト教徒によって建設されたアメリカ合衆国にとって、イスラーム教という宗教は仏教や儒教などと違って、歴史的思想的にそのルーツを共にするものだから、「イスラーム原理主義」の思考法と行動原理はある意味で理解可能であり、それゆえにリアルな恐怖と憎悪も抱くと思う。
でも、日本という土壌では、キリスト教もユダヤ教もさして根がなく、ましてイスラーム教については根どころか葉っぱの先ほどの縁もない。だから「イスラーム原理主義」という言葉は、見たこともない幽霊、ターバンを被って銃をもって爆弾を巻いた恐ろしい人たち、という根も葉もないイメージだけになる。9.11のテロリストはもちろん許しがたいことをしたのだが、彼らが何を信じ、何を意図してあんなことをしたのかファンタジーみたいで理解できない。ただ怯えたり怖れたり憎んだりするのは、無知で軽薄のそしりを免れないと思う。
















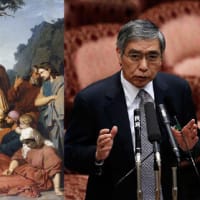









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます