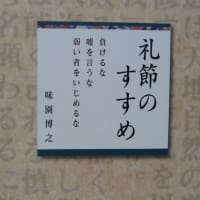第4156号 02.06.05(金)
貞観十六年、太宗、侍臣に謂ひて曰く、古人云ふ、鳥、林に棲むも、猶ほ其の高からざらんことを恐れ、復た木末に巢ふ。魚、泉にかくるるも、猶ほ其の深からざらんことを恐れ、復た其の下に窟穴す。然れども人の獲る所と為る者は、皆、餌を貪るに由るが故なり、と。『貞観政要』546
貞観十六年に、太宗が左右の侍臣たちに語って言われた、「古人の言に『鳥は林に棲んでいるが、それでもなお、その木の高くないことを恐れて、さらに木の高い梢に巣を造る。魚は水中に隠れているが、それでもなお、その水の深くないことを恐れて、さらにまた水底の洞穴に住んでいる。それにもかかわらず、人間に捕らえられるのは、皆、餌をむさぼり食うからである』とある。
【コメント】鳥も魚も生きるために一所賢明なのですが、それでも生を諦めざるを得ないのは天が与えた宿命なのでしょうか。
そこに行くと人間程我儘勝手な生き物はいないのではないでしょうか。大量殺戮をしても、共産圏諸国なのだという勝手な理由でしのいでいるのです。
--------------------------
◎今日のひと言「楽しく生きる」
人生を楽しく生きるためには、立派な習慣を身につけるよう気配りをするのが、一番賢明な習慣ではないでしょうか。
それはちょっとした心がけから来ることだと思います。幸福でありたいと思えば、ものごとの明るい面を見ようとすることが大事でしょう。
それと併せて、読書をする、筆写をすることも楽しみに加わると思います。
--------------------------
古典のおしえ 二--2
『易経』は、<労謙す、君子終わりあり、吉なり>と教えています。「一生けんめいたらいても謙遜して誇らない。それが君子の徳であり、長く地位を保って全うすることがしあわせをえる道である」というのです。こういう控え目な態度は、自立と前向きな考え方であるとおもいます。
※人と話すときは、良いことばをつかいましょう。心が美しくなる秘訣です。
-----------------------------
百人一首 61
いにしへの 奈良の都の 八重桜
けふ九重に にほひぬるかな【伊勢太輔】
その昔の都、奈良で咲いた八重桜が、今日は、九重、すなわちこの宮中で、美しくかがやいていることよ。
--------------------------
『善の研究』第501回
たとえば我々が充分に熟達した事柄においては少しも選択的意志を入るるの余地がない、選択的意志は疑惑、矛盾、衝突の場合に必要となるのである。勿論誰もいう如く知るという中には已に自由ということを含んでおる、知は即ち可能を意味しているのである。
-----------------------
貞観十六年、太宗、侍臣に謂ひて曰く、古人云ふ、鳥、林に棲むも、猶ほ其の高からざらんことを恐れ、復た木末に巢ふ。魚、泉にかくるるも、猶ほ其の深からざらんことを恐れ、復た其の下に窟穴す。然れども人の獲る所と為る者は、皆、餌を貪るに由るが故なり、と。『貞観政要』546
貞観十六年に、太宗が左右の侍臣たちに語って言われた、「古人の言に『鳥は林に棲んでいるが、それでもなお、その木の高くないことを恐れて、さらに木の高い梢に巣を造る。魚は水中に隠れているが、それでもなお、その水の深くないことを恐れて、さらにまた水底の洞穴に住んでいる。それにもかかわらず、人間に捕らえられるのは、皆、餌をむさぼり食うからである』とある。
【コメント】鳥も魚も生きるために一所賢明なのですが、それでも生を諦めざるを得ないのは天が与えた宿命なのでしょうか。
そこに行くと人間程我儘勝手な生き物はいないのではないでしょうか。大量殺戮をしても、共産圏諸国なのだという勝手な理由でしのいでいるのです。
--------------------------
◎今日のひと言「楽しく生きる」
人生を楽しく生きるためには、立派な習慣を身につけるよう気配りをするのが、一番賢明な習慣ではないでしょうか。
それはちょっとした心がけから来ることだと思います。幸福でありたいと思えば、ものごとの明るい面を見ようとすることが大事でしょう。
それと併せて、読書をする、筆写をすることも楽しみに加わると思います。
--------------------------
古典のおしえ 二--2
『易経』は、<労謙す、君子終わりあり、吉なり>と教えています。「一生けんめいたらいても謙遜して誇らない。それが君子の徳であり、長く地位を保って全うすることがしあわせをえる道である」というのです。こういう控え目な態度は、自立と前向きな考え方であるとおもいます。
※人と話すときは、良いことばをつかいましょう。心が美しくなる秘訣です。
-----------------------------
百人一首 61
いにしへの 奈良の都の 八重桜
けふ九重に にほひぬるかな【伊勢太輔】
その昔の都、奈良で咲いた八重桜が、今日は、九重、すなわちこの宮中で、美しくかがやいていることよ。
--------------------------
『善の研究』第501回
たとえば我々が充分に熟達した事柄においては少しも選択的意志を入るるの余地がない、選択的意志は疑惑、矛盾、衝突の場合に必要となるのである。勿論誰もいう如く知るという中には已に自由ということを含んでおる、知は即ち可能を意味しているのである。
-----------------------