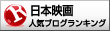溝口にしては内容に乏しいと言われる作品だが、大群衆シーンが再三出てきて、様々な人間が交錯するドラマはすごい。
言ってみれば、蜷川幸雄の劇のような迫力である。
こう言うのは正しくない。むしろ蜷川が、溝口の影響を受け、大群集シーンによる劇を作っているのだと。
溝口は映画のみならず劇にも大きな影響を与えていると思う。
市川雷蔵の平清盛の義弟になる林成年が、比叡山の僧侶と争う祇園祭のシーンは、「一体どのようにクレーン撮影をつないだのか」と、ゴダールが映写室に行きフィルムを調べたというほどのもの。
最後、比叡山の僧兵の強訴シーンのエキストラの大行列、また大行列。
神輿に矢を射込む雷蔵の演技のリアリティ。
人件費高騰の現在では出来ない大群衆シーンである。
最後、都の野原で公家と戯れている、白拍子から女御になり、また白拍子に戻ったの清盛の母・木暮実千代。
それを見て言う清盛。
「母君には、あれが一番幸福なのだ」
人生の流転を感じさせる名シーンである。
その野原は、中村錦之助の『宮本武蔵』の第2作『般若坂の決闘』の最後、槍の宝蔵院流と戦ったのと同じロケ地。
確か奈良にあったはずだ。
言ってみれば、蜷川幸雄の劇のような迫力である。
こう言うのは正しくない。むしろ蜷川が、溝口の影響を受け、大群集シーンによる劇を作っているのだと。
溝口は映画のみならず劇にも大きな影響を与えていると思う。
市川雷蔵の平清盛の義弟になる林成年が、比叡山の僧侶と争う祇園祭のシーンは、「一体どのようにクレーン撮影をつないだのか」と、ゴダールが映写室に行きフィルムを調べたというほどのもの。
最後、比叡山の僧兵の強訴シーンのエキストラの大行列、また大行列。
神輿に矢を射込む雷蔵の演技のリアリティ。
人件費高騰の現在では出来ない大群衆シーンである。
最後、都の野原で公家と戯れている、白拍子から女御になり、また白拍子に戻ったの清盛の母・木暮実千代。
それを見て言う清盛。
「母君には、あれが一番幸福なのだ」
人生の流転を感じさせる名シーンである。
その野原は、中村錦之助の『宮本武蔵』の第2作『般若坂の決闘』の最後、槍の宝蔵院流と戦ったのと同じロケ地。
確か奈良にあったはずだ。