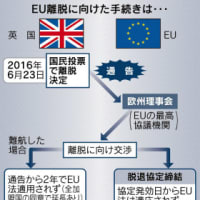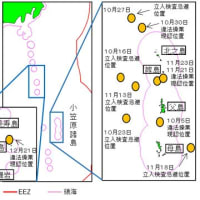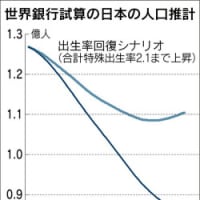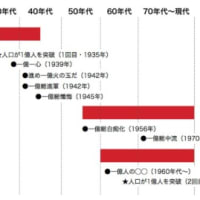エコノミスト・室田康弘『経済学は現実を捉えられるか』(中央公論1975/4月号)の先の記事に続いて、経済学批判に対する専門的な知見によるコメントの続きだ。
『評論「経済学の現実把握」室田康弘1975年140815』
そこで、室田は経済学が採用しているアプローチに問題があり、本質に迫っていないとの考え方を示し、永井に共感を寄せ、古典物理学的アプローチを以下の三点から批判する。
1)社会構造の非定常性(構造は常に変化する)
2)パレート分布の存在(非対称分布の存在)
3)時間の非可逆性(歴史過程の存在)
1)社会構造の非定常性(構造は常に変化する)
「最も予測が必要なときに、有用な予測を出すことが出来ず、最も予測を必要としない平穏なときに予測が花盛りになるのは何故だろうか」と室田は提起する。
“予測←計量モデル←過去モデル”になるから、過去の構造が続いたときにしか、結果は出せない。
これは永井が提起した「真理であって、しかも自明の理ではない」命題を社会科学は一般法則としてほとんど見出し得ない、即ち、「真理は、自明の理だ」と云うことになる。このことの別表現になる。
構造変化が生じたとき、構造変化を前提としないモデルによっては、予測が不可能なのだ。むしろ構造変化のもつ意味を読み解く、例外的な事象を予兆として把握することが重要になる。ここで室田説が永井説と重なることになる。
そこで室田の現代経済学批判(1975年当時)になる。
計量経済学の泰斗、クライン教授の予測の定義「標本観測値から決定される関係式に基づいた、標本に含まれない状態について科学的な叙述を試み」。これを捉えて、「この定義の暗黙の前提として安定した母集団が存在し、そこからランダムにとられた標本が経済データということ」と指摘する。
続けて、「しかし、歴史を通じて社会現象に安定的な構造が存在し得たか」「構造変化という母集団の変化こそが日常的であり、その変化を正しく認識することが予測の役割ではないか」と反問する。
これが若き日の室田流か!と拍手を送りたい処だ。
この問題は、3)時間の非可逆性(歴史過程の存在)と結びつく。筆者の専門の言葉で云えば、不可逆過程の問題となる。人間もまた、生を受けてから死に至るまで、一つの過程を辿る。その集積が社会であれば、歴史過程を組み込むことが社会科学の重要な要素であることは論をまたない。
2)パレート分布の存在(非対称分布の存在)についても、計量経済学はこれを無私してきたことを室田は批判する。
では、どの様な方法を用いるか、との問いに、室田は「段階的接近法」を提案する。
「ある仮設値から出発…訂正判断を加えながら、問題点を発掘しつつ、志向錯誤を繰り返し、或る一定の整合的な姿に収束させ、それを予測する」という方法だ。
この方法では、主役は予測作業に参加した人間の問題発掘能力と論理力になる。また、」この方法での予測はかなり高い精度を有してきたと云う。しかし、予測への主観因子の混入と再現性の問題で批判されてきたと云う。
これに対する室田の指摘は次の様だ。
「再現性」のみが科学の要件ではない、「先見性」を無視して良いのか。局面ごとに変わる法則を見つけることが、超歴史的は法則を見つけるよりも、先見性に富むのではないか。
永井が指摘した成熟過程の変化は、母集団そのものの変化に他ならない。その意味で、室田の云う先見性は、40年後の現在、ますます重要性を帯びている。ここで指摘された点は、現在、どのように議論されているのだろうか。
『評論「経済学の現実把握」室田康弘1975年140815』
そこで、室田は経済学が採用しているアプローチに問題があり、本質に迫っていないとの考え方を示し、永井に共感を寄せ、古典物理学的アプローチを以下の三点から批判する。
1)社会構造の非定常性(構造は常に変化する)
2)パレート分布の存在(非対称分布の存在)
3)時間の非可逆性(歴史過程の存在)
1)社会構造の非定常性(構造は常に変化する)
「最も予測が必要なときに、有用な予測を出すことが出来ず、最も予測を必要としない平穏なときに予測が花盛りになるのは何故だろうか」と室田は提起する。
“予測←計量モデル←過去モデル”になるから、過去の構造が続いたときにしか、結果は出せない。
これは永井が提起した「真理であって、しかも自明の理ではない」命題を社会科学は一般法則としてほとんど見出し得ない、即ち、「真理は、自明の理だ」と云うことになる。このことの別表現になる。
構造変化が生じたとき、構造変化を前提としないモデルによっては、予測が不可能なのだ。むしろ構造変化のもつ意味を読み解く、例外的な事象を予兆として把握することが重要になる。ここで室田説が永井説と重なることになる。
そこで室田の現代経済学批判(1975年当時)になる。
計量経済学の泰斗、クライン教授の予測の定義「標本観測値から決定される関係式に基づいた、標本に含まれない状態について科学的な叙述を試み」。これを捉えて、「この定義の暗黙の前提として安定した母集団が存在し、そこからランダムにとられた標本が経済データということ」と指摘する。
続けて、「しかし、歴史を通じて社会現象に安定的な構造が存在し得たか」「構造変化という母集団の変化こそが日常的であり、その変化を正しく認識することが予測の役割ではないか」と反問する。
これが若き日の室田流か!と拍手を送りたい処だ。
この問題は、3)時間の非可逆性(歴史過程の存在)と結びつく。筆者の専門の言葉で云えば、不可逆過程の問題となる。人間もまた、生を受けてから死に至るまで、一つの過程を辿る。その集積が社会であれば、歴史過程を組み込むことが社会科学の重要な要素であることは論をまたない。
2)パレート分布の存在(非対称分布の存在)についても、計量経済学はこれを無私してきたことを室田は批判する。
では、どの様な方法を用いるか、との問いに、室田は「段階的接近法」を提案する。
「ある仮設値から出発…訂正判断を加えながら、問題点を発掘しつつ、志向錯誤を繰り返し、或る一定の整合的な姿に収束させ、それを予測する」という方法だ。
この方法では、主役は予測作業に参加した人間の問題発掘能力と論理力になる。また、」この方法での予測はかなり高い精度を有してきたと云う。しかし、予測への主観因子の混入と再現性の問題で批判されてきたと云う。
これに対する室田の指摘は次の様だ。
「再現性」のみが科学の要件ではない、「先見性」を無視して良いのか。局面ごとに変わる法則を見つけることが、超歴史的は法則を見つけるよりも、先見性に富むのではないか。
永井が指摘した成熟過程の変化は、母集団そのものの変化に他ならない。その意味で、室田の云う先見性は、40年後の現在、ますます重要性を帯びている。ここで指摘された点は、現在、どのように議論されているのだろうか。