
「平川医院」。建物入口の意匠が卓抜。
宿場らしく細長い土地も。
「寺町通り」。
行徳の町は、かつて「戸数千軒、寺百軒」といわれたように、寺が多く集まっている町です。旧行徳街道沿いには古い家並みも残り、落ち着いた雰囲気があります。この街道をまがった通りが「寺町通り」と呼ばれる道です。
かつての成田参詣道で、徳願寺のほか、長松禅寺、妙頂寺、妙応寺などがあります。また、法善寺、妙堂寺、円頓寺、浄閑寺などもあります。
さらに旧行徳街道を南下すると、源心寺や了善寺など多くの寺院が軒を連らねています。
(この項、「 」HPより)
」HPより)
ところで、「市川」「行徳」「妙典」などの地名のいわれは?
「市川(いちかわ)」の地名は、江戸川が坂東一の大きな川であったことから「一の川(いちのかわ)」と呼ばれた、また川の下流沿岸で荷を積んだ川舟が集まって市が開かれ「市川」と呼ばれた、などに由来する。一の川に続く川を二川(ふたがわ)、三河(みかわ)といった。
南北朝時代は「市河村」が記録されているが、室町・戦国時代には渡船場がある宿駅になっていた。その後江戸時代は市川村と呼ばれ、幕府と旗本大久保家の領地で石高915石余あったという。
・・・
市川は古代から「市川の洲」と呼ばれた砂州上にあった。「大洲(おおす)」は川中にできた砂質の大きな洲で江戸川の自然堤防上にあった。また「大和田(おおわだ)」のワダは川の曲流部など広い丸みのある平地をいい、江戸川の大きな曲流部にある土地を指した。
「関ヶ島(せきがしま)」は室町時代に佐原・香取神宮の行徳関が置かれた所で、大小の河流と沼・沢地に囲まれた島状だったことから関所のある島を意味した。「伊勢宿(いせじゅく)」は伊勢参りの船が出た所というが、近くには伊勢外宮の豊受大神を祭った豊受神社がありまた宿場でもあった名残という。
「押切(おしきり)」は江戸川がこの地を押し切って流れを変えた所、また対岸の村人達が隣村の妨害を押し切って開拓し移住した土地ともいう。「湊(みなと)」は地形が港向きで船の往来があった所といい、その村人達が開拓して村になった所が「湊新田(みなとしんでん)」である。
「欠真間(かけまま)」は大津波で真間村の一部が欠けて流された時、その土砂でできた下流の新しい土地を指す。
「行徳(ぎょうとく)」は室町時代、この地で徳のあった修験者が村人から「行徳さま」と呼ばれていたのが地名になった。行徳千軒寺百軒といわれるほど民衆は信仰心が厚く、「徳を行う」ために寺々を巡って参拝し功徳(くどく)をつんだ。江戸時代の行徳領は浦安から市川南部、船橋西部にわたる33ヵ村でその中心が「本行徳(ほんぎょうとく)」であった。
「妙典(みょうでん)」は法華経が妙なる経典という意味で地名にした。彼らが開発した船橋市法典の地名も同様の意味がある。
・・・
(この項、「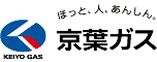 」HPより)
」HPより)
※「妙典」=読みは「みょうでん」。武蔵野線「船橋法典」は「ほうてん」。
 「下新宿」バス停。
「下新宿」バス停。
 市川市マンホール。市の木クロマツと魚のデザイン。小型の蓋。
市川市マンホール。市の木クロマツと魚のデザイン。小型の蓋。
ちょっと脇道へ。旧道らしい雰囲気ですが。かつては江戸川の河原の縁だった?


ようやく「江戸川」べりへ。
江戸川は昔、太日河(ふといがわ)とよばれ、 渡良瀬川の水が流れていた。
江戸幕府は、江戸時代の初期に利根川水系の改修を行い、寛永年間(1624~1644)には、洪水の防止と新田開発のための用水確保とともに、安定した水上輸送路を確保するために、関宿(せきやど)から金杉(現在の野田市)のあいだに新たな流路を開削し、金杉で太日河につなげた。それ以来、利根川からの水が流れ、現在の江戸川の原型ができあがった。その後、江戸へつながる川として「江戸川」とよばれるようになった 。江戸川から江戸へは、江戸川(現在の旧江戸川)→新川(塩の道)→小名木川→隅田川というルートである。当時は、北関東や東北から江戸へ物資を運ぶ重要な運河となっていたのである。
天明3年(1783)に浅間山が噴火し、その噴出物が利根川水系の河床を上昇させたため洪水を招くようになった。この噴火により関東一体に火山灰が降り、山麓では山津波がおこり多くの人家が押し流された。多数の犠牲者の遺体が利根川や江戸川を流れ下ったそうである。地元の下小岩村の人々は、遺体を収容し、手あつく寺内の無縁墓地に埋葬した。現在、区内の善養寺には、この供養碑が残っている(江戸川区教育委員会『天明三年浅間山噴火横死者供養碑』善養寺)。
明治時代になっても、河床上昇による洪水の被害は頻繁に発生した。明治43年(1910)、利根川水系に大きな洪水を機に、江戸川への水の流量増大を目的とする江戸川改修工事が大正3年(1914)に着工された。また、大正 5年(1916)に着工した 行徳村をつらぬく新たな開削は大正 9年(1920)に竣工した。これを「江戸川放水路」とよび、篠崎から下流の旧流路を「旧江戸川」とよぶようになったのである。
(この項「江戸川区の歴史と風景写真江戸川フォトライブラリーhttps://edogawa-photo.net/」HPより)



 1880年代のようす。
1880年代のようす。



 2010年代のようす。「行徳橋」も新しくなった。
2010年代のようす。「行徳橋」も新しくなった。


旧橋梁の老朽化などから架け替えが行われ、現在の橋梁は2020年(令和2年)に開通。
旧行徳橋。撤去作業が始まっている。
上流を望む。


























