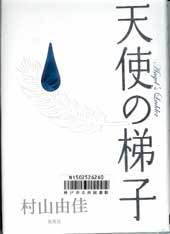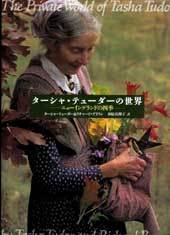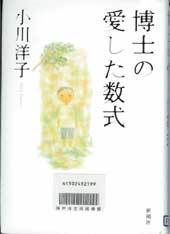村山由佳
「天使の梯子」というのは、雲間からさす光のこと。
それは、まるで天から地上に天使が降りてくるための
梯子のよう見える・・
この本のテーマは、愛する人の死をどう受け入れるかということだ。
そして残された者は、それを乗り越え、現実をどう生きるかということだ。
愛する人に、不本意ながら傷つける言葉を浴びせ、
それを詫びる間もなく、この世を去ってしまった死者に対して
どう償っていけばよいのか・・
夏姫もこの本の主人公である、「俺」、古幡慎一も同じ経験をしている。
お互いに惹かれ合い、相手を想いながらも、同じテーマで苦しんでいる。
そして、人を愛することによって、相手も自分も癒されていく。
最後にはとても救われた気持ちになる。
この本のストーリー全体を繋げるモチーフとなっているサクラ・・
サクラの舞い散るこの季節、この本に出逢えて良かった。
サクラはそれを眺める人に、いろいろな思いを抱かせる。
それは、喜びであったり、苦い思い出であったり、
二度と会えぬあの人への思いであったり・・
いろいろではあるけれど、このサクラ咲く、瞬く間の季節に
この本の中に自分を置き、夏姫や慎一、そして歩太の思いと共に
ひとときを過ごせたことは、自分にとって大切な時だったと思う。
巡り会えたこの本に感謝!
とても表現が美しく、言葉がはなかく、趣がある。
「天使の卵」の続編らしい。
村山由佳のワールドが繰り広げられているお勧めの作品。
「天使の梯子」というのは、雲間からさす光のこと。
それは、まるで天から地上に天使が降りてくるための
梯子のよう見える・・
この本のテーマは、愛する人の死をどう受け入れるかということだ。
そして残された者は、それを乗り越え、現実をどう生きるかということだ。
愛する人に、不本意ながら傷つける言葉を浴びせ、
それを詫びる間もなく、この世を去ってしまった死者に対して
どう償っていけばよいのか・・
夏姫もこの本の主人公である、「俺」、古幡慎一も同じ経験をしている。
お互いに惹かれ合い、相手を想いながらも、同じテーマで苦しんでいる。
そして、人を愛することによって、相手も自分も癒されていく。
最後にはとても救われた気持ちになる。
この本のストーリー全体を繋げるモチーフとなっているサクラ・・
サクラの舞い散るこの季節、この本に出逢えて良かった。
サクラはそれを眺める人に、いろいろな思いを抱かせる。
それは、喜びであったり、苦い思い出であったり、
二度と会えぬあの人への思いであったり・・
いろいろではあるけれど、このサクラ咲く、瞬く間の季節に
この本の中に自分を置き、夏姫や慎一、そして歩太の思いと共に
ひとときを過ごせたことは、自分にとって大切な時だったと思う。
巡り会えたこの本に感謝!
とても表現が美しく、言葉がはなかく、趣がある。
「天使の卵」の続編らしい。
村山由佳のワールドが繰り広げられているお勧めの作品。