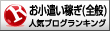カラフト・ヤマト軍は敵よりも兵力が優勢だったので、緒戦からロマンス国内に攻め入りました。ほとんどの戦線でロマンス・シベリア軍を圧倒したのです。ここで戦争の話はさて置き、シベリアへ帰ったスターリン総司令官の話題に移りましょう。
彼が帰国して間もなく、危篤状態だったイワン・レーニン皇帝が亡くなりました。多くの重臣や将軍らが見守る中、彼は静かに息を引き取ったのです。前にも言いましたが、シベリア帝国の皇帝は各部族長の投票、つまり選挙で選ばれます。したがって、各部族長はイワン・レーニンの葬儀に参列した後 次期皇帝を選ぶわけですが、大方の意見が一致していれば、投票なしに新皇帝を決めることもあります。その辺は融通無碍ですが、ここで重要なポイントになるのが、前皇帝が“遺書”を残しているかどうかということです。
イワン・レーニンは遺書を残していました。皇后であるクルプスカヤがそれを重臣らに示したのです。前皇帝の遺言というのは重い意味を持っています。その内容が明らかになれば、次期皇帝を選ぶ大きな基準になるからです。
遺書の内容は、トロツキー(西部軍総司令官)とスターリン(極東軍総司令官)を比較した文言が多くあり、おおむねトロツキーを高く評価したものでした。また、その他の重臣らを批評した文もありましたが、前皇帝が後継者にトロツキーを推していることが読み取れたのです。
これによって、トロツキー次期皇帝が有力になったのですが、同じく皇帝を目指していたスターリンは面白くありません。 実はトロツキーという男は非常に優秀で戦功も数多くあったのですが、自信過剰というか、他人を軽視するところがあって、他の実力者から敬遠されたり嫌われていた面があったのです。スターリンはそれに目を付け、同僚のジノヴィエフ、カーメネフ、ブハーリンといった実力者に“工作”を始めることになりました。
それは、前皇帝の遺書は重臣らの間だけに止め、各部族長には公表しないというものです。ジノヴィエフらも遺書の中で辛い評価を受けていたので、すぐそれに賛成しました。トロツキーはもちろん不服でしたが、重臣らの多数決で遺書は公表されないことになったのです。 この遺書をめぐる争いが、やがてスターリン対トロツキーの「内戦」に発展していこうとは、まだほとんどの人が予見していなかったでしょう。

サハリンのレーニン像
さて、話をカラフト国内に戻しますが、戦争が再び勃発したので、前線にいたスパシーバ王子は首都に帰れなくなりました。それで困ったのは妹のナターシャ姫です。彼女はスサノオノミコトとの結婚について兄の了承を得ようとしていましたが、それが叶いません。父王夫妻に直接伝えるのは危険すぎます。父や母が何と言うか分かりません。相手がヤマト帝国という「異民族」の人だからです。この当時、異民族間の結婚というのはほとんど考えられないことでした。まして、王室の一員がそうするとなると、どんな反発が起きるかしれません。
ナターシャにとって、頼りになる唯一の相談相手は兄しかいません。そのスパシーバが戻ってこれなければ、この話は暫く沙汰やみになってしまいます。困ったナターシャはいろいろ考えた末、思い切って兄に手紙を書くことにしました。その手紙をスサノオノミコトに託し、兄に手渡してもらおうということです。 スサノオノミコトは自身の大切な話だけに、もちろん引き受けました。ナターシャが心を込めて書いた手紙を、彼は懐にしまうと急いで戦場へ向かったのです。
その頃、スパシーバ王子は一軍を率いて、ロマンス国のティモフスクという拠点に迫っていました。ティモフスクは内陸部の要衝で、ここを落とせば首都・ノグリキまであとわずかです。スパシーバはすでに一軍を率いる立場にいましたが、この辺の敵の司令官はあのチェーホフ将軍でした。チェーホフはシベリア軍のほとんどの部隊を引き連れて、ティモフスクの防衛に当たっていたのです。彼はこの一帯の地形などに詳しく、ロマンス軍からも信頼されていました。
スパシーバが援軍を待っていると、そこにスサノオノミコトの一軍が到着しました。彼は大将軍のタケルノミコトに願い出てティモフスクに来たのですが、個人的には、ナターシャの手紙を早くスパシーバに届けようという思いがあったのです。でも、これは決して利己的な理由からだけではありません。ティモフスク戦線は戦局の鍵を握る重要なポイントでした。スサノオノミコトの名誉のためにも、それは言っておきましょう(笑)。
カラフト・ヤマト連合軍は敵の陣営を包囲し、いよいよ攻撃に出ようとしていました。スサノオノミコトがスパシーバの所を訪れると、彼はちょうどくつろいだ時間を過ごしていましたが、首都にいるリューバ姫と娘のマトリョーシカを思い出していたのです。マトリョーシカはもうよく歩き回るようになり、とても元気の良い子でした。娘のことを思い出しているのが、最もやすらぎを覚える一時ですね。
スサノオノミコトがナターシャの手紙を渡すと、スパシーバはそれを丹念に読みました。文面には妹の真心があふれていたのです。彼は読み終えるとこう言いました。
「副将軍、妹の気持がよく分かりました。私はナターシャを異国の地に嫁がせる気はなかったのですが、これを読んで心を打たれました。カラフト王国を滅亡から救ったのは、ヤマト帝国です。その恩義は決して忘れないでしょう。ナターシャが副将軍に嫁ぐとなれば、両国の絆はいっそう深まります。貴殿が一途で立派な方であることはよく知っています。あなたは妹を守り、きっと幸せにしてくれるでしょう。私も父や母にこのことを伝え、2人の結婚が実現するよう力を尽くします」
スサノオノミコトは震える思いでスパシーバの言葉を聞いていました。「殿下、ありがとうございます。身に沁みるお言葉でした。私はナターシャ姫を必ず幸せにするよう全力を尽くします。万一、それが不可能になるようなら、容赦なく私を斬り捨ててください」 彼は武人らしい言葉で感謝の気持を表しました。
スパシーバ王子はスサノオノミコトの両手を強く握り締めると、にっこりと微笑みました。2人は義兄弟の“契り”を結んだのです。スパシーバは同じ民族とはいえ、異国のリューバ姫を妻とした過去があります。彼はスサノオノミコトの気持がよく分かる思いでした。とは言っても、今は戦争中です。戦争が終って一段落したら、首都に戻って父王夫妻にこのことを伝えようと、スパシーバは心に決めました。
さて、ティモフスクの戦いですが、ヤマト帝国はあの空気球に加えて、新たに“熱気球”を開発し敵の頭上から攻撃を加えました。これも相当な威力なのですが、ロマンス・シベリア軍も「強弓」を用意してそれに対抗しました。強弓の必要性を説いたのはあのスターリン総司令官でしたが、チェーホフ将軍らはそれを十分に準備していたのです。
このため、カラフト・ヤマト軍が気球から矢を射かけても、すぐに強弓で“火矢”を放ち、幾つもの気球が炎上して落下しました。これにはカラフト・ヤマト側も苦戦し、なかなか思うようにいきません。前に大成功を収めた「火牛」の戦術も、ロマンス・シベリア側がすでに周辺の牛をほとんど収容していたので、使いようがありません。逆に、火牛の戦術を仕掛けられる危険性が出てきました。それどころか、チェーホフ将軍は例の“騎兵部隊”を巧みに使って攻撃をかけてくる始末です。カラフト・ヤマト軍は予想外の苦戦を強いられ、戦線は膠着状態に陥りました。
これを見て、タケルノミコト大将軍は決心します。やはりヤマト帝国自慢の海軍を使うしかありません。彼はマミヤリンゾウ司令官を呼び、ティモフスクの西方にあるオッチシ(シベリア語でアレクサンドロフスク)への上陸作戦を命じました。オッチシはサハリン島の西海岸にある要衝で、ティモフスクからは馬で1日ほどの所にあります。マミヤ司令官は先のシスカ上陸作戦でも戦功がありますが、約3千人の兵士を引き連れさっそく出発しました。マミヤ軍がオッチシに上陸すれば、ティモフスクの敵陣を完全に包囲することができます。それまでは、持久戦もやむを得ないとタケルノミコトは考えていました。
ここでもう一度、シベリア帝国の話に戻りましょう。次期皇帝の座をめぐって、スターリン総司令官は必死でした。サハリン情勢が多少は気になっていましたが、今はそれどころではありません。強敵であるトロツキー総司令官との戦いが始まろうとしていました。イワン・レーニン皇帝の“遺書”をめぐってトロツキーと対立し、これは公表しないことで収めましたが、トロツキーは黙っていません。彼は遺書の内容から見て、自分の方が前皇帝の後継者にふさわしいと宣伝し始めました。
こうなると、各部族長は当然 遺書を見たくなるもので、重臣会議で非公表を決めたことに異議を唱え出したのです。あわてたスターリンは、同僚のジノヴィエフやカーメネフ、ブハーリンらと対策を協議しました。その結果、トロツキーの態度は重臣会議の決定に背くものだと判断し、彼を当分の間「謹慎処分」にすることを決めたのです。
ところが、トロツキーとその一派はこの処分に強く反発し、トロツキー自身は任地である西部軍の司令部へ帰ってしまいました。その後、スターリンらは彼を首都・ヤクーツクへ呼び戻そうとしましたが、トロツキーは言うことを聞きません。しかし、これはスターリンにとってかえって好都合だったでしょう。当面の敵であるトロツキーに対して、ジノヴィエフらとの“同盟”を強化することができるからです。今やトロツキーは、彼ら共通の敵になってきたのです。
しかし、トロツキーには自信がありました。彼は他の誰よりも数多くの戦功があり、それは衆目の一致するところでした。だから、いざとなれば戦いに立ち上がり、スターリンらを排除すれば良いのです。トロツキーは首都への召還指令を無視したまま平然としていました。これに対して、スターリンらは決断を下さざるをえません。双方とも覚悟が出来てきたのです。そして、重臣会議はついにトロツキーとその一派を“反逆者”と決めつけ、彼らを「国外追放処分」にしました。当然、トロツキーは戦いに立ち上がりました。彼は西部軍の全将兵を引き連れ、まずジノヴィエフ将軍の中部軍陣地へと進撃を開始しました。こうして、シベリア帝国は「内戦」に突入したのです。
シベリアの情勢を知ってか知らずか、チェーホフ将軍は反撃の機会を窺がっていました。ロマンス軍側からジェルジンスキー将軍、それにあのラスプーチン宰相の息子・プーシキンも合流していたので、なかなか強力な軍勢になりました。プーシキンはもう軍の司令官として活躍しており、カラフト側も一目置く存在になっていたのです。
ある日、スパシーバ王子が一隊を率いて敵陣近くに偵察に来ると、偶然とはいえプーシキンの一隊を目にかけました。しかし、双方とも戦闘行動には出ません。持久戦になっているので、むやみに戦闘を仕掛けないのです。いずれも“決戦”に備えて力を温存しているのでしょうか。ただ、スパシーバもプーシキンもすぐ相手に気づき、緊迫した空気に包まれました。プーシキンが叫びます。「スパシーバ! 今日はお前とは戦わないが、こんど会う時は必ず決着をつけるぞ!」
「おう、そうしよう! それまで、お前も命を大切にしておけ!」 スパシーバも負けじと言い返しました。互いに10数人の部下を引き連れているので、無益な戦闘行動は控えています。もちろん、両者とも総司令官から勝手な行動は慎むようにと釘を刺されていました。しかし、もし2人だけで遭遇していたら、気持よく“一騎打ち”をしたでしょう。宿敵とはそういうものです。やがて、2人はその場を離れました。
さて、チェーホフ将軍は頃合を見て打って出る作戦を立てていました。まず俊足の騎兵部隊で敵の両翼を攻撃し、以前 苦杯をなめた「火牛」の戦術を逆に仕掛けるというものです。その後、中央から重装備の歩兵が突撃していけば、敵は必ず総崩れになると確信していました。ただし、敵は兵力で上回るので、乾坤一擲の勝負に出るしかありません。それまでは慎重にならざるをえないのです。
一方、カラフト・ヤマト軍は、マミヤリンゾウ軍のオッチシ上陸を心待ちにしていました。この上陸作戦は、敵にまだ気づかれていません。もし、マミヤ軍の上陸作戦が事前に分かっていたら、チェーホフ将軍の反撃はもっと早まったはずです。その辺の微妙な時間差が、勝敗に決定的な影響を与えるのでしょう。
そして、マミヤリンゾウ軍がついにオッチシ海岸に到着しました。上陸軍はすぐに10数発の狼煙(のろし)を打ち上げます。これを確認すると、カラフト・ヤマト軍は総攻撃の準備を始めました。しかし、ロマンス・シベリア軍も狼煙に気がつき、敵が背後からも攻めてくると直感したのです。チェーホフ将軍はただちに騎兵部隊の攻撃を命じました。
ロマンス・シベリア軍の騎兵部隊は敵の両翼に襲いかかります。チェーホフが満を持して取った攻撃なので、カラフト・ヤマト軍側の陣営はあっという間に乱れました。しかし、兵力では優勢だったので何とか持ちこたえようとします。乱戦になりました。
チェーホフはさらに、100頭余りの「火牛」を敵陣の中央に放ちます。尻に火がついた牛は猛然と突進していきました。 普通ならこれで敵は大混乱に陥るところですが、ミヤザワケンジ司令官はこの戦術を予想していたので、あちこちに深くて長い溝を掘っていました。このため、多くの牛が溝にはまり込んで身動きが取れなくなったのです。牛たちの悲痛なうめき声が周囲に響き渡りました。
それでも、少数の牛は溝から脱出して敵陣に暴れ込みます。敵はかなり混乱し守勢に回りました。チェーホフはさらに、重装備の歩兵の一隊を進撃させました。中央突破を狙ったのです。 しかし、カラフト・ヤマト軍も善戦しました。上陸したマミヤリンゾウ軍がもうすぐ応援に駆けつけてくれる、それまで何としても頑張ろうという気持になっていたのです。
やがて彼方から、6個、7個と気球が飛んできました。明らかにマミヤ軍の気球です。それらはロマンス・シベリア軍の上空に達すると、雨あられと矢を射かけてきました。カラフト・ヤマト軍から歓声が起きました。地上部隊ももうすぐ到着するでしょう。とたんにカラフト・ヤマト軍の士気が上がったのです。
地上では大混戦が続いていましたが、マミヤ軍の先鋒隊がついに姿を見せました。彼らはロマンス・シベリア軍の背後から、まず矢を射かけます。そして、後続部隊が次々に現われると、敵を包囲する形で陣形を狭めてきました。防戦一方だったカラフト・ヤマト軍は、ここでようやく攻勢への転機をつかんだのです。
戦争の話を長々とするのは止めましょう(笑)。 この後は、タケルノミコト軍とマミヤ軍が敵を挟み撃ちにして猛攻を加え、ロマンス・シベリア軍は敗走を余儀なくされました。彼らの行く先は首都・ノグリキしかありません。こうして、次の舞台は“首都決戦”へと移っていったのです。
ティモフスクを陥落させたカラフト・ヤマト軍は、ノグリキへ向けて順調に進撃しました。敵の主力はいち速く首都に退却したのです。ノグリキに近づくと、スパシーバ王子は、かつて商人に変装し王宮に入り込んだことなどを思い返していました。あの頃はリューバ姫に会いたい一心で、ずいぶん大胆なことをしたものです。
そのリューバ姫を娶り、彼女は今や一子の母親にもなりました。(これからの記述は「リューバ妃」としましょう。その方が正確だからです。) カラフト・ヤマト軍がノグリキへ進撃していた頃、リューバ妃は父王夫妻のことを心配していました。いったん和平の機運が盛り上がった時は、自分もいずれ“里帰り”ができるのではと期待していましたが、戦争状態になった今はとても無理です。それでも、ツルハゲ王とカチューシャ王妃の身をいつも案じていました。出来れば一日も早く、娘のマトリョーシカを両親に会わせようと思っていましたが、再び戦争が起こり、それははかない望みのままとなったのです。 スパシーバもリューバ妃の想いを深く感じていましたが、今はどうしようもありません。とにかく、首都・ノグリキを一刻も速く陥落させるしかないのです。
カラフト・ヤマト軍がノグリキに到達しました。ロマンス・シベリア軍は厳重な防衛線を敷いて、首都に立てこもっています。まるで“籠城戦”といった形ですね。
その頃、チェーホフ将軍はシベリアからの援軍を期待していましたが、それは全く無理だと分かりました。 前にも言いましたが、シベリア帝国では次期皇帝の座をめぐって「内戦」が勃発し、トロツキー軍とスターリンらの連合軍が死力を尽くした戦闘に突入していたのです。
極東軍総司令官のスターリンには、中部軍のジノヴィエフ将軍や北部軍のカーメネフ将軍らが味方し、兵力ではトロツキー総司令官の西部軍を上回っていましたが、統制が取りにくく司令がなかなか行き届きません。 これに対して、トロツキー軍は一枚岩の団結を誇っており、さらに配下には勇猛なコサック軍団が入っていました。このコサック軍団は騎兵戦を得意としており、昔から広大なユーラシア大陸を駆け巡ってきたのです。シベリアその他の辺境地域を征服する上でも、コサック兵は大いに活躍してきました。 つまり、トロツキー軍は数の上では劣勢でも、少数精鋭と言うか一騎当千の兵達がそろっていたのです。このため、緒戦ではトロツキー軍が連合軍を圧倒し、スターリンらは苦しい立場に追い込まれました。スターリンは、サハリンに援軍を派遣する余裕は全くなかったのです。