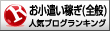マトリョーシカが20歳になったことで、ツルハゲ王はにわかに譲位の気持が高まってきました。王はこのところ体調が優れず、公務も休みがちになっていたのです。彼女が20歳になったら・・・と考えていたので、それも仕方がないでしょう。
ある日、ツルハゲ王はマトリョーシカを呼びこう告げました。
「夏にはお前に国王の位を譲りたい。私は足腰が弱ってきたし、体調も良くない。前にも言ったが、その点は分かっているね」
「はい、覚悟しております」 マトリョーシカは素直に答えました。すると、王の傍らにいたカチューシャ王妃が嬉しそうに言葉をかけてきました。
「マトリョーシカ、どうもありがとう。あなたにそう言ってもらうと、私たちは本当に安心です。ソーニャ王太后もきっと喜んでくれるでしょう。また、スパシーバ王子もリューバ姫も草葉の陰で満足していると思います。あなたが生まれてから20年、長かったような短かったような・・・」 カチューシャ王妃は思わず涙ぐみました。
亡き父母の名前を出されて、マトリョーシカも神妙な気持になりました。父母の面影が脳裏をかすめます。
「お爺様、お婆様。長い間、本当にありがとうございました。私をここまで育ててくれたのはお爺様、お婆様のお陰です」 マトリョーシカは感謝の気持で一杯になりました。
この席ではマトリョーシカの結婚話は出ませんでしたが、彼女はふと、近くサハリンにやって来る叔母のナターシャを思い出しました。以前 ヤマト帝国を訪れた時、ナターシャはこう言ったのです。
「あなたが本当にその人(アレクサンドル)を愛するのなら、自分の気持を大切にしなさい。私も異国のスサノオノミコトを愛したのですよ。周りの人は何と言うか知りませんが、誠を尽くすことが人の道だと思います」
マトリョーシカはこの言葉を聞いて、叔母から励まされたことを思い出したのです。ナターシャはほぼ年に一度“里帰り”をするので、その時、彼女に応援してもらおうと心に決めたのです。ナターシャは母のソーニャ王太后にはもちろん何でも話せるので、叔母と王太后の力を借りて、ツルハゲ王夫妻を説得しようという“作戦”を練ったのでした。いざという時、最も頼りになるのは叔母のナターシャですね。
ゲルマン帝国と不可侵条約を結んだスターリン皇帝は余裕しゃくしゃくという感じでした。次はどこを攻略しようかと想を練っていましたが、極東のサハリン王国に対しては“懐柔策”が一番だと考えたのです。
ツルハゲ王とは旧ロマンス国時代から盟友関係でしたし、間もなく女王になるマトリョーシカに次男のピョートルを婿入りさせれば、サハリン国はシベリア帝国の勢力圏に入るでしょう。そして、ピョートルとマトリョーシカが「共同統治王」として君臨すれば、これほど都合の良いことはありません。サハリン国は事実上 シベリアの属国になり、もうヤマト帝国は手の出しようがないと判断したのです。
スターリンはマトリョーシカに好意を持っていました。だから、この前 彼女がシベリアに来た時には大いに歓待し、ピョートルを引き合わせたりしたのです。帰りには立派な土産物も贈りました。そこで、スターリンはツルハゲ王宛てに親書を送ることになりました。 内容は先のマトリョーシカ王女訪問の答礼として、息子のピョートルをサハリン国に遣わせる、両国の絆をいっそう深めるためにも、王女とピョートルの婚姻を希望するなどというものです。
この親書がツルハゲ王の手元に届くと、王は非常に喜びました。今や世界的な大国になったシベリア帝国と絆を深めれば、サハリン王国の繁栄と安泰は間違いありません。 そこで、ツルハゲ王はマトリョーシカを呼び、ピョートルのサハリン訪問と将来の結婚について聞きました。
「はい、私のシベリア訪問の答礼ですから、来られることは外交上 何の問題もないと思います。ただ、結婚については私は何も考えていません」
「マトリョーシカ、そなたはピョートルとの結婚が嫌だと言うのか。こんなに良い話はないと思うが・・・」
「お爺様、近いうちに私の考えを述べたいと思います。もう少し待っていただけますか」
「ふむ、お前は何を考えているのやら。女王になれば気持も変わると思うが・・・まあ いい。時間はそうないぞ。しかと考えておけ」
ツルハゲ王は不機嫌そうにこう言うと、マトリョーシカを退席させました。マトリョーシカは、いよいよ自分の決心を実行に移す時が迫ってきたと痛感したのです。
やがて、ヤマト帝国からナターシャが“里帰り”してきました。マトリョーシカにとっては待ちに待った叔母の帰還です。ナターシャは今度は3人の子供を連れてきたので、ソーニャ王太后は孫に会えて大喜びです。マトリョーシカも久しぶりに子供たちと再会しましたが、3人とも大きくなっていました。再会を楽しんだ後、彼女はナターシャにお願いをしたのです。
「叔母様、私のアレクサンドルを紹介したいのですが、ぜひ会っていただけませんか」
「ええ、結構ですよ。いつでもどうぞ」
この後、マトリョーシカは叔母に、アレクサンドルとの交際や結婚の予定についてくわしく説明しました。すると、ナターシャは自分にできることは何でも協力するとマトリョーシカに約束したのです。
こうして何日かたった後、マトリョーシカはアレクサンドルを王宮に案内してきました。妹のベラも同行しています。ナターシャは彼と会うなり、なんと凜々しく立派な青年かと思いました。背が高くて逞しく、いかにも聡明な感じがしたのです。彼女もアレクサンドルがすっかり気に入りました。話をしても知的でしっかりとしています。彼はやや緊張気味でしたが、言葉のはしばしに“覚悟”の気持がにじみ出ていました。
ナターシャはすぐにアレクサンドルらを連れ、母のソーニャ王太后を訪れました。事前に彼のことを話していたので、王太后には少しの驚きもありません。彼女もナターシャと同じような印象を受けました。アレクサンドルと会っていると、まるで亡きスパシーバ王子を見るような思いになったのです。亡き息子も凜々しく立派な青年でした。王太后もすっかりアレクサンドルが気に入り、これこそマトリョーシカにふさわしい“伴侶”だと思ったのです。
こうして、マトリョーシカが策した紹介作戦は成功し、あとはツルハゲ王夫妻をいかに説得するかにかかってきました。しかし、ソーニャ王太后もナターシャもアレクサンドルが気に入ったので、先行きは明るい見通しになりましたね。王太后とナターシャが事前に王夫妻に話をしてくれることになったのです。 そして、マトリョーシカとアレクサンドルが連れ立って、王夫妻に謁見する日がやってきました。
謁見には2人の他に、ソーニャ王太后とナターシャも同席しました。マトリョーシカは決意を固め、しっかりした口調でこう述べたのです。
「王様、王妃様。すでにお聞きと思いますが、こちらが私の決めたアレクサンドルです。彼も私との婚姻に何の異存もありません。どうぞ私たちの気持を察していただいて、2人の婚姻をお認め願いたいと思います」
ツルハゲ王は暫く黙っていましたが、やっと重い口を開きました。
「マトリョーシカ、この件は王太后からもお話を伺っている。私も王妃も異存はない。ただ・・・いや、これ以上言うのは止めよう。まずはおめでとう」
ツルハゲ王は2人の結婚をしぶしぶ認めたという感じでした。彼も初対面のアレクサンドルには好感を持ちましたが、内心、困ったことになったと思ったのです。実はこの時、王は言いそびれたのですが、彼はスターリン皇帝に対し、マトリョーシカの婿君としてピョートルを歓迎する旨の『親書』を出していたのでした。ツルハゲ王は少し早まった感じがしますね。 ただ、王も可愛い孫娘の切なる願いを斥けるわけにはいきません。彼は近いうちに、スターリンに陳謝しようと考えたのでした。
ところが、この“行き違い”が、やがてサハリン・シベリア両国にとって重大な事態に発展しようとは、まだ誰も予測できないことでした。それはそうでしょう。親書の内容については、ツルハゲ王とカチューシャ王妃、それにスターリンしか知らなかったのですから。
ツルハゲ王からの親書を受け取ったスターリンは大いに満足し、さっそく息子のピョートルを呼びました。
「お前はあのマトリョーシカをどう思っている? いい娘だろう。素晴らしい美人だし、もちろん教養も高いし言うことはない。ツルハゲ王が、マトリョーシカの婿にお前を迎えたいと言ってきたのだ。こんな良い話はないだろう。私は大賛成だ」
父の話にピョートルは少し顔を赤らめましたが、内心は満更でもなかったのです。
「ちょうど良い。お前は間もなくサハリンを訪問するから、ツルハゲ王とマトリョーシカに会って話を決めることだな。ウワッハッハッハッハ」 スターリンは上機嫌で笑いました。
そのピョートルがサハリンの首都・ノグリキにやって来ました。彼はツルハゲ王宛のスターリンの返書を持参していたのです。王宮に着くと、ピョートルはすぐにその返書をツルハゲ王に奉呈しました。ところが、この後の歓迎晩餐会に王の姿が見えません。ピョートルがいぶかしく思っていると、マトリョーシカが「後ほど、お話したいことがあります」と丁重に言葉をかけたのです。
実はピョートル来訪の前に、ツルハゲ王とマトリョーシカの間で一悶着があったのです。王はスターリン宛に親書を送っていたことを明かしました。その内容も打ち明けたので、マトリョーシカは茫然自失の状態になったのです。彼女はピョートルと結婚する気持は全くないので、彼が来訪した際にどのように説明するかで、王と議論になったのでした。
結局、その対応はマトリョーシカに任されました。彼女自身がピョートルに説明することになったのです。ツルハゲ王は自分が早まったことをしたので、ピョートルに合わす顔がないと思ったのでした。それに、マトリョーシカは率直な性格なので、自らピョートルに説明すると言ったのです。
2人きりになると、マトリョーシカは事実関係を包み隠さず述べました。ピョートルは黙って聞いていましたが、マトリョーシカとアレクサンドルの関係が非常に深いことを知ったのです。彼は失望したとか、不満に思うような表情はいっさい見せませんでした。むしろ、マトリョーシカの気持を忖度(そんたく)するような男らしい態度を示したのです。これには、彼女も助かりました。祖父や親の勝手な思い込みで、2人は政略結婚の道にはまり込もうとしていましたが、これで事態はすっきりしたのです。
ピョートルは1週間ほどノグリキに滞在しましたが、この間、マトリョーシカはマリアと共に彼をあちこちに案内したり、自らいろいろと世話をしたのです。2人は親しい友だちといった感じになりましたね。
ピョートルは帰国に際し、ツルハゲ王からスターリン宛の新たな親書を預かりました。その内容は、2人の婚姻が不調に終わったことを陳謝するものでした。帰国すると、ピョートルはそれをスターリンに手渡しましたが、親書を読むなり彼は見る見るうちに険しい表情になったのです。そうです。スターリンは明らかに怒ったのでした。
「こんな人を馬鹿にした話があるか! わしもお前もツルハゲ王に騙されたんだぞ。2人の結婚を歓迎すると言ってきたから、どうぞ宜しくと返事を書いてやったんだ。お前は悔しいとは思わないのか!」
怒ったスターリンはその親書をびりびりに破り捨てました。しかし、ピョートルの方は意外に冷静で、マトリョーシカと会った話などを淡々と父に報告したのです。
「ふむ、マトリョーシカはそういうことだったのか。生意気な娘だ。ツルハゲ王もさぞ困っただろうな」
スターリンもようやく冷静になって息子の話を聞いたのです。「よし、分かった。後はわしがいろいろ考える。ご苦労だった」 そう言って、彼はピョートルを退席させました。
一人きりになると、スターリンの心にマトリョーシカへの憎しみが湧いてきました。生意気な女だ、あの小娘が! 今まで気に入っていた王女だけに、逆に可愛さ余って憎さが百倍といったところでしょうか。スターリンはマトリョーシカを懲らしめたいと思ったのです。
そう考えると、彼の野心がにわかに膨らんできました。サハリン王国を討とうか・・・ かつて、スターリンはシベリア帝国の極東軍総司令官としてあの地で陣頭指揮を執っていたのです。あの頃の思い出が蘇ってきました。旧ロマンス国を支援し、あともう少しでサハリンを制圧するところまでいったのです。
あの頃は自分も若くて元気が良かったな・・・ いや、自分はいまシベリア帝国の皇帝だぞ。世界最大の帝国の皇帝が、あんな“小娘”に舐められてたまるか! よし、今こそサハリンを討ってやろう! 征服者・独裁者の胸に野望が一気に広がりました。
こうして、スターリンは「サハリン討伐」の決意を固めたのですが、暫くは重臣たちに何も明かしませんでした。まず内外の情勢を分析しますが、サハリン討伐に全力を挙げても何の支障もないようです。特に、最強のライバルであるゲルマン帝国とは不可侵条約を結んでいます。あのヒトラー皇帝はいま西ヨーロッパの征服に血道をあげており、後顧の憂いは全くありません。
暫く検討を重ねた結果、スターリン皇帝はついにサハリン討伐を決断しました。彼は重臣らを呼び寄せ、その決定を通告したのです。独裁者の言うことには誰も反対しません。それどころか、かつてスターリンの指揮下でサハリンで戦ったチェーホフ、ガガーリンらの将軍たちは感涙にむせぶ有様でした。彼らも年を取りましたが、あのサハリン戦争のことは少しも忘れていません。老将軍たちは、これが最後の“ご奉公”だと張り切ったのです。
こうして、シベリア帝国は打って一丸となり、サハリン征服に乗り出すことになりました。