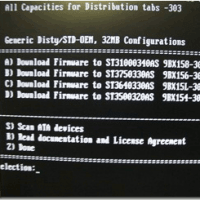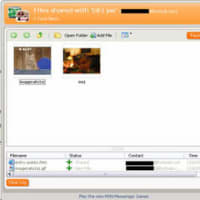最近,RAIDに関する話題を,あちこちで聞くようになった.RAIDは,複数のHDDを束ねることにより,アクセス速度を向上させたり,ディスク障害に対する耐性を持たせる仕組みだ.詳しくは,以前の記事「格安RAID5カード 玄人志向 SATARAID5-LPPCI 登場」などを参考にして欲しい.
これは,おそらく,マザーボード上のチップセットが,RAIDをサポートするのが当たり前になって来たためだろう.先日,修理交換のために購入した,マイクロATXのマザーボードECSの
PM800-M2 (v1.0)は,ドスパラ静岡店で,¥5,980という安値で購入したのだが,このチップセットVIA VT8237ですら,RAID Level 0/1/0+1およびJBODをサポートしていたのには驚いた.
もちろん,チップセットのRAIDサポートの他にも,HDDの大容量化にともない,HDDの故障によるデータの損失量が大きくなり,またシステムのダウンタイム(休止時間)の短縮が,小規模なシステムにおいても求められるようになってきたためだろう.
現在のところ,チップセットのサポートするRAID Level は,主に0・1・0+1だが,最新のチップセット(例:nForece4 SLI,ICH7R)では,RAID5もサポートするようになった.RAID5は,最低3台のHDDで構成されるが,このうち1本が故障しても,その1本を交換すれば,内部のファイルを失うことなく,元通りに復元できるというしくみだ.RAID5は,HDDへの書き込み速度や,パリティ計算に伴うCPU負荷に問題があるものの,冗長性のための「使用可能空き容量」の損失を,RAID1(ミラーリング)に比べて,かなり少なくすることができる.
ところがこのRAID5にも,弱点があるようだ.時々,2chの自作PC板「IDE/SATA RAID カードあれこれ RAID」でも激論となるのだが,「RAID5において,1台のHDDのみが障害を起こした場合でも,ディスクアレイ(RAIDのこと)が崩れる場合があるらしい」ということだ.この話の真偽は明かではないし,その原因も特定されていないようだが,機械である以上,何らかの不具合があってもおかしくはない.ただその確率は,かなり低いものと思われる.
RAID5において最もハラハラドキドキする場面は,ディスクを交換した後のRAID再構築(リビルト)の時だろう.リビルトは,生き残ったHDD(データが存在する)と,新規に組み込まれたHDD(空のディスク)で,もう一度RAIDを再構築する作業で,10時間以上かかる場合もあるらしい.当然の事ながらリビルトは,HDDに長時間の連続的な負荷をかけることとなる.生き残ったHDDの機種・ロットが,壊れたHDDと同じであった場合,その寿命についてもほぼ同様である可能性が高い.そのためリビルトによって,生き残ったHDDの息の根を止めてしまうことがあり得るわけだ.
今回紹介する記事は,このようなRAID5の弱点を克服したとされるRAID6に関する記事だ.
ImpressのEnterprise Watchの記事「安価&大容量ディスクサブシステムに欠かせないデータ保護技術「RAID 6」」には,RAID5のリビルト失敗の確率について,いくつかの興味深い試算がなされている.その中で特にPC自作派が注目すべきは,ATA HDD5台によるRAID5アレイのリビルト中に起こる,データ損失の確率だ.この計算によると,なんと!リビルト10回中1回の割合でデータ損失が起こるのだという.ただし,リビルトによるデータ損失が発生する時間間隔MTTDL(Mean Time To Data Loss)は,81年ということで,自作派にはほとんど問題ないだろうこともわかった.
ただし,安心してばかりもいられない.上記の計算は,あくまでもスペック上・理論上の計算であり,実際稼働しているHDDに関する様々なファクタが省かれている.同じ機種のHDDでも,そのアクセス頻度や設置環境などにより,当然のことながら寿命は異なるからだ.特にRAIDを組んだ場合,HDDを密集させて設置する場合が多いため,適切なHDD冷却が行われていない場合は,スペックよりも寿命が短くなる場合がある.もちろん,HDDの機種・ロット・設置環境・アクセス状況まで同じであれば,先ほど述べたように寿命もほぼ同程度と考えられるため,1台が壊れれば,他のHDDもほぼ同時に,あるいはリビルト時に壊れる可能性は十分考えられるだろう.
RAID6は,2台のHDDが同時に壊れても,障害から復旧可能なRAIDの一種だ.構成するHDDの最低台数は4台で,内HDD2台分にパリティが格納される.RAID5の場合,パリティは1つだけ計算され,HDD1台分の容量がそのパリティ格納のために,空き容量から差し引かれるが,RAID6では,パリティは2つ計算・格納されるため,HDD2台分の容量が,全体の容量から差し引かれることになる(くわしくはこちら).また上記記事にも書かれているとおり,RAID6のパリティ計算は複雑らしく,専用のプロセッサが必要になる場合もあるようだ.
このように考えてみると,比較的使用するHDD台数の少ないPCにおけるRAIDとしては,RAID6よりも,RAID1(ミラーリング)の方が,アクセス速度・コスト・フォールトトレランスと言った面において,メリットが大きいかもしれない.ただし,フルタワーケースにHDDをフル装填して,自宅ファイルサーバを構築している強者の場合,すでにRAID6対応のRAIDカード(注:PCI-X用)も発売されているため,RAID6によるディスクアレイ構築も一考には値するだろう.
これは,おそらく,マザーボード上のチップセットが,RAIDをサポートするのが当たり前になって来たためだろう.先日,修理交換のために購入した,マイクロATXのマザーボードECSの
PM800-M2 (v1.0)は,ドスパラ静岡店で,¥5,980という安値で購入したのだが,このチップセットVIA VT8237ですら,RAID Level 0/1/0+1およびJBODをサポートしていたのには驚いた.
もちろん,チップセットのRAIDサポートの他にも,HDDの大容量化にともない,HDDの故障によるデータの損失量が大きくなり,またシステムのダウンタイム(休止時間)の短縮が,小規模なシステムにおいても求められるようになってきたためだろう.
現在のところ,チップセットのサポートするRAID Level は,主に0・1・0+1だが,最新のチップセット(例:nForece4 SLI,ICH7R)では,RAID5もサポートするようになった.RAID5は,最低3台のHDDで構成されるが,このうち1本が故障しても,その1本を交換すれば,内部のファイルを失うことなく,元通りに復元できるというしくみだ.RAID5は,HDDへの書き込み速度や,パリティ計算に伴うCPU負荷に問題があるものの,冗長性のための「使用可能空き容量」の損失を,RAID1(ミラーリング)に比べて,かなり少なくすることができる.
ところがこのRAID5にも,弱点があるようだ.時々,2chの自作PC板「IDE/SATA RAID カードあれこれ RAID」でも激論となるのだが,「RAID5において,1台のHDDのみが障害を起こした場合でも,ディスクアレイ(RAIDのこと)が崩れる場合があるらしい」ということだ.この話の真偽は明かではないし,その原因も特定されていないようだが,機械である以上,何らかの不具合があってもおかしくはない.ただその確率は,かなり低いものと思われる.
RAID5において最もハラハラドキドキする場面は,ディスクを交換した後のRAID再構築(リビルト)の時だろう.リビルトは,生き残ったHDD(データが存在する)と,新規に組み込まれたHDD(空のディスク)で,もう一度RAIDを再構築する作業で,10時間以上かかる場合もあるらしい.当然の事ながらリビルトは,HDDに長時間の連続的な負荷をかけることとなる.生き残ったHDDの機種・ロットが,壊れたHDDと同じであった場合,その寿命についてもほぼ同様である可能性が高い.そのためリビルトによって,生き残ったHDDの息の根を止めてしまうことがあり得るわけだ.
今回紹介する記事は,このようなRAID5の弱点を克服したとされるRAID6に関する記事だ.
ImpressのEnterprise Watchの記事「安価&大容量ディスクサブシステムに欠かせないデータ保護技術「RAID 6」」には,RAID5のリビルト失敗の確率について,いくつかの興味深い試算がなされている.その中で特にPC自作派が注目すべきは,ATA HDD5台によるRAID5アレイのリビルト中に起こる,データ損失の確率だ.この計算によると,なんと!リビルト10回中1回の割合でデータ損失が起こるのだという.ただし,リビルトによるデータ損失が発生する時間間隔MTTDL(Mean Time To Data Loss)は,81年ということで,自作派にはほとんど問題ないだろうこともわかった.
ただし,安心してばかりもいられない.上記の計算は,あくまでもスペック上・理論上の計算であり,実際稼働しているHDDに関する様々なファクタが省かれている.同じ機種のHDDでも,そのアクセス頻度や設置環境などにより,当然のことながら寿命は異なるからだ.特にRAIDを組んだ場合,HDDを密集させて設置する場合が多いため,適切なHDD冷却が行われていない場合は,スペックよりも寿命が短くなる場合がある.もちろん,HDDの機種・ロット・設置環境・アクセス状況まで同じであれば,先ほど述べたように寿命もほぼ同程度と考えられるため,1台が壊れれば,他のHDDもほぼ同時に,あるいはリビルト時に壊れる可能性は十分考えられるだろう.
RAID6は,2台のHDDが同時に壊れても,障害から復旧可能なRAIDの一種だ.構成するHDDの最低台数は4台で,内HDD2台分にパリティが格納される.RAID5の場合,パリティは1つだけ計算され,HDD1台分の容量がそのパリティ格納のために,空き容量から差し引かれるが,RAID6では,パリティは2つ計算・格納されるため,HDD2台分の容量が,全体の容量から差し引かれることになる(くわしくはこちら).また上記記事にも書かれているとおり,RAID6のパリティ計算は複雑らしく,専用のプロセッサが必要になる場合もあるようだ.
このように考えてみると,比較的使用するHDD台数の少ないPCにおけるRAIDとしては,RAID6よりも,RAID1(ミラーリング)の方が,アクセス速度・コスト・フォールトトレランスと言った面において,メリットが大きいかもしれない.ただし,フルタワーケースにHDDをフル装填して,自宅ファイルサーバを構築している強者の場合,すでにRAID6対応のRAIDカード(注:PCI-X用)も発売されているため,RAID6によるディスクアレイ構築も一考には値するだろう.