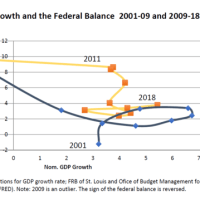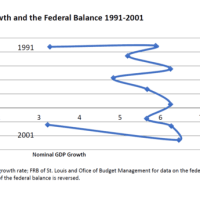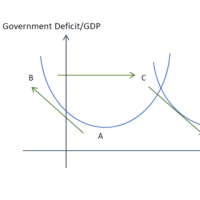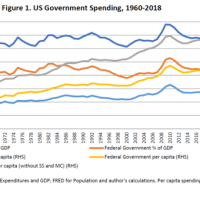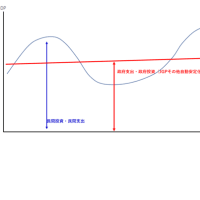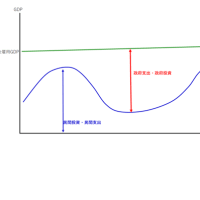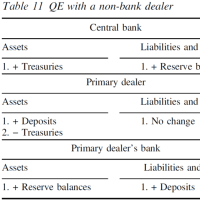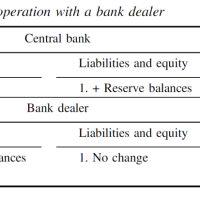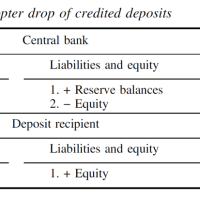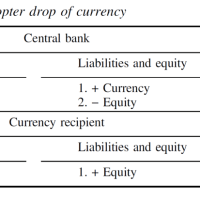MMTが日本で認知されるようになってきたのはいいが、
どうもあんまり思わしくない方向に進んでいるような気がしてしょうがない。
本当なら、レイの後期ラーナー批判とかグリーンニューディールについての
ワーキング・ペーパーを先にやった方が時宜を得ているのかもしれないが、
まあ、とりあえず、これまでの流れもあるので、世界金融危機の続きをやる。同名の書物がティモワーニュとの共著で
出版されているが、焦点にはややずれがある。
本稿(Cambridge Journal of Economics 2009, 33, 807–828)で、レイは
世界金融危機後の展望をかなり楽観的に描いていた。ただし、「楽観的」といっても、それは経済成長率がすぐに元に戻るとかいうような
意味でではなく、むしろ、この混乱の後、政治が、かつて大恐慌の後に合衆国政府が悪質な金融業界のビジネスに
メスを入れたことが資本制のその後の発展モデルの変化に大きく影響を与えたのと同じように、
今度もまた、様々な社会的圧力によってウォールストリートの動きに歯止めをかけられ、資本制経済が
より安定した軌道に乗るようになるであろうと(ただし、そのためにはもう一度ぐらいは金融危機の顕在化
――危機自体はまだ継続しているのだが、目には見えづらくなっている――が必要だが)、展望したのである。
今となっては、この希望的観測はあまりにも楽観的過ぎたと言えよう。後知恵でいうのではないが、
やはりレイという人の政治オンチっぷりはちょっとしたもので、まあ、こうなればこそ
「トランプ政権は戦後もっとも左翼的になるかもしれない」なんぞという頓珍漢な発言も出たのであろう。
以前に訳出したものからもうかがえる通り、レイのこの見通しが甘すぎたのは確かではあるが、
しかしオバマ政権の手ぬるさが多くの人々にとって意外であったというのも事実であろう。
ウォールストリートの利害はちょっとやすっとの世界金融危機ぐらいでは揺るがなかった。
その結果の一つが、トランプ政権の誕生だったわけで、そう考えると、
政治(人権や民主主義の状況を含めた広い意味で)と経済の結びつき方というものには、いわゆる「政治経済」と呼ばれているのとは
また別の角度から議論を深めていく必要があるような気もしているが、
それはまた機会を改めて(といって、すぐ忘れる。。。)。
なお、今回の疎訳は個人の学習用に作成したメモを、志を同じくする人の学習の便のために
一つの参考として公開するものですので、あくまでも個人の学習用にのみ参照ください。全部で
三回か四回ぐらいになると思います。
The rise and fall of money manager capitalism: a Minskian approach
マネー・マネジャー資本制経済の勃興と凋落:ミンスキーアプローチ
L. ランドール・レイ
要旨
われわれは深刻で、おそらく長引く景気後退を伴う世界的な金融危機の真っ只中にいる。確かに、
一部のアナリストは、これを第二次世界大戦後の最初の恐慌とも呼んでいる。この論文では、
筆者はこれがシステム的危機――ハイマン・ミンスキーがマネー・マネージャー資本制経済と呼んだものの危機――であると
論じる。これを、初期のヒルファーディング及びヴェブレンの分析とリンクさせ、そして事実上、
今回の危機がこの種の資本制経済の失敗としては2度目であることを示す。初期金融資本制経済の基本的特徴とは、
相対的に小さな政府、投資資金として外部資金の利用、「トラスト」――あるいは、今日であれば「工業」
「金融」「保険」にまたがる多様な利害関係と提携による巨大企業とでも呼ばれるであろうもの――への
経済力の集中である。最初の段階とは異なり、第二段階の金融資本制経済は巨大な政府と
ネオコンサーバーティズムのモデルという文脈の中で登場した。ミンスキーの分析によって、どのようにして
ニューディールと巨大な政府が第二次世界大戦後に家父長型資本制経済(a paternalistic capitalism)を
生出すことになったのか、それがどのような意味で高い消費水準、雇用水準、格差縮小、金融安定性にとって
好ましかったのかを理解しやすくなる。とはいえ、こうした安定性とはそれ自体、不安定化なのである。というのは
これこそマネージド・マネー(managed money)の登場を可能にしたものであるからだ。時が経つにつれ、
イノベーションと規制緩和によって脆弱性が高まった。これはますます金融危機の頻度と深刻さを高めていった。以前の危機は
「it(次の債務デフレーション)」が再び起こることを防ぐのに十分な速さで解決されていたが、今回の危機は深刻で、
マネー・マネージャー資本制そのものの生き残り自体に疑問が付けられるほどだ。[※"it"とはミンスキーの主著'のタイトルから
とったもので、2019年危機と同様の深刻な経済危機を指す。]今回の論文では現在今次危機に貢献している諸要素を
検討する。例えば不動産ブームと破裂、証券化債務やクレジット・デフォルト・スワップのような危険な
金融商品の登場、コモディティ市場バブル、そして緊縮財政などである。この記事は、この形態の金融資本制の破綻について、
どのような結果になり得るか幾つか可能性を示唆することで締めくくられる。
1. イントロダクション
現在、1930年代以降最悪の経済危機に直面しているということはほとんど疑いようない。数は少ないが、
エコノミストや政策立案家達の中には不況の可能性について話を始めたものもいる。ケインズ経済学への参照は
常識となり、政府の介入に反対するのは献身的な自由市場主義者だけになった。ウォールストリートの魔法使い達まで
金融市場の再規制に賛成し始めた。合衆国政府のコミットメントは2009年2月半ばまでにほぼ9兆ドルに達したが、
それで十分だとする論者はあまりいない。最近の国内総生産(GDP)の修正値はレーガン不況以来の急激な落ち込みを
示している。オバマ政権は今年の連邦予算赤字を1.75兆ドル(GDPの12%)、2010年には1.17兆ドルになると
予想している――しかし一部の民間予測では2009年には1.9兆ドル、GDPの13.5%、これは翌年度も減りそうにない(1)。
それどころか外国の先行きの見通しはもっとひどい。Fedは世界的な最後の貸し手となり、
外国の中央銀行に6000万ドルの準備預金融資を提供した。さらに、これはよく知られていることであるが、
合衆国の金融機関に対してベイル・アウト[※パラシュートによる緊急脱出]を提供し(もっとも知られているのは
AIGに対するもの)、それによって外国の金融機関も守られたのである(AIGはヨーロッパの銀行によって保有されていた
債務のクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)「保険」の最大の供給者である)。いまだに相対的に安全とされた
合衆国財務省証券への買いが殺到し為替レートが脅かされ、世界中でリスクスプレッドが拡がっている。社会的・政治的に
不穏な雰囲気が周辺国中で広まっている。多くの国の経済は合衆国経済が立ち直るまで回復しないだろう。筆者は
合衆国は今次危機回復のためにまだ打てる政策手段を持っていると信じてはいるが、他の多くの国にはそれがない。しかし
その点は本稿の射程を超えている(2)。
危機の原因についてはあらゆる説明が示された。手ぬるい規制と監督、格差が広まったことで家計が支出のための借入を
増やしたこと、強欲で不合理な熱狂、世界的に過剰な流動性――合衆国の安易な貨幣政策と合衆国の経常赤字によって
拍車をかけられ世界中に大量のドルが氾濫したことなども挙げられた。ハイマン・ミンスキーの業績は
かつてないほどの関心を惹きつけ、多くの人がこれを「ミンスキー・モメント」(3)と呼んだ。筆者は
本稿でこの2年間に繰り広げられた今回の出来事について細かく語るつもりはない。それはすでに2本の長い刊行物にて
行った(4)。本危機に対する政策立案者たちがこれまで行ってきたことについて詳細な批判をするつもりもない(5)。最後に
ここで本危機を解決するために特定の政策を提案するつもりもない(6)。今回筆者が提示したいのはそうしたことではなく、
世界経済の一時代を支配したある形態の資本制の発生と崩壊に関するより概括的な分析である。我々はこれを近年の発展として
跡付けることのできる「モメント」と見なすべきではない。むしろ、ミンスキーが50年近く掛けて論じたように、我々は
金融システムが脆弱な物へ向かってゆっくりと変化してゆくその渦中におかれている。この脆弱性が、最後にはシステム的な
世界危機を生み出すのである。1996年に死去するまでの最後の数年間、ミンスキーはこの進化に対する「段階」アプローチを展開し、
現在の局面を「マネー・マネージャー・キャピタリズム」と同定した――危機を引き起こしやすく、セーフティー・ネットが脆弱で、
それゆえひとたび金融崩壊が起これば経済的な災禍が引き起こされる、そんな資本制経済である。実際、我々は
数多くの危機を繰り返し体験しており、そして危機はより頻繁に、より深刻なものになる傾向がある(7)。これは不動産市場、
証券化商品市場、コモディティ市場における過熱と破裂の繰り返しの中で累積してゆき、最終的に
クレジット・デフォルト・スワップおよびその他デリバティヴの大発生へと行き着く。
要するに筆者としては、ハイマン・ミンスキーに倣ってマネー・マネージャー・キャピタリズムを批判したい――システム的に
リスクが低評価される環境の中で高レバレッジを掛けられたファンドが総収入(所得フローにキャピタルゲインを
加算したもの)を最大化しようとする行動によって特徴づけられる資本制経済である。金融機関に対する規制や
監督がほとんどないなかで、マネー・マネージャーはますます密教的な商品を創りだしていった。マネー・マネージャーの報酬は
ほとんどがキャピタルゲインであり、背後にある所得フローではない。キャピタルゲインは、背後にある資産が
曖昧であれば、比較的容易に紡ぎ出すことができる――ウォーレン・バフェットが「金融大量破壊兵器」と呼んだものだ。
そしてこれらはレバレッジを掛けられ予想報酬を得る権利の購入に使われた。なんでもこれは、また別の資産クラスを
支えており、その資産クラスの価値たるや、マネージド・マネーによる入札で上昇し得るというのである。破裂は
次々と起こるが、それでマネージド・マネーの一部が消え去ってからも、新しいブームは必然的に、まるで
灰の中から飛びたつ火の鳥のように、蘇生する。しかし今次危機は相当深刻なもので、マネージド・マネーのかなりの部分を
破壊したし、マネー・マネージャーたちの信用を完全に失墜させたし、金融部門を思いっきり縮小する――言い換えれば、
これによってマネー・マネージャー資本制経済が終焉するかもしれないのである。
筆者はまずは歴史的な文脈を分析するつもりだ。幾つかの重要な面で、資本制経済のマネー・マネージャー形態は
「金融資本制」が支配的なポジションへ立ち戻ったことを表している――それは1930年代の
巨大不況に対するニュー・ディール政策によって失われたポジションである。ミンスキーによるなら、
1930年代以前の小さな政府、レッセ・フェール経済は失敗であった。それにとってかわったのが、巨大政府資本制経済であり、
これは大きな成功をおさめた。政府が経済において巨大な領域を支配するようになったばかりでなく、
ビジネスの行動の規制と監督に巨大な役割を果たすことになり、そして無数のセーフティーネットと保証を提供し、
それによって同時に格差を縮め所得の成長とを促した。以下で要約して説明する理由により、こうした要因全てが
経済安定化へ貢献した。しかしながら時が経つとともに、安定した経済がかなり脆弱な金融構造を深化させ、それが
金融危機を引き起こした――ミンスキーが常に論していた通り、安定とは不安定化なのだ――というのは、
マネー・マネージャーたちと政府内のその代弁者たちはニューディールの足枷を切り刻み、別の目標に置き換えた。
筆者はソースタイン・ヴェブレンによる20世紀初頭の分析を手短に要約することから始める。というのは、
筆者の信じるところ、これは現代資本制経済に光を当てているからである。次いで、ミンスキーによる研究に
立ち戻る。この研究は戦後の資本制経済をマネー・マネージャーが支配力を再獲得する過程として、
その進化について研究したものである。筆者はごく簡単にこの過程において国家が果たした役割を瞥見する。
ここで国家は「自由市場」と「オーナーシップソサエティ」を推し進めた――この変容は、もっと厳しい言い方をするなら、
「ネオコン」による国家装置の略奪と見做すことができる。「ネオコン」こそミンスキーの言う「家父長型」国家を、
ジェームス・ガルブレイスが「プレディター(捕捉者)国家」として描き出したものに置き換えたのである。規則、
規制、監視機関、セーフティー・ネットを解体することにより プレディター国家はマネー・マネジャーの台頭を
助けた。最後に、本稿では金融実務あるいは金融商品のうち3つ(証券化、CDS、コモディティー先物契約)が
果たした役割に立ちもどる。これらは、フィッシャー―ミンスキーの債務デフレプロセスが可能になる条件を創りだすのに
貢献した。また消費者に過大な負担を負わせることになる3つの「引き金」(金利と石油価格の上昇、そして
税収の増加)の役割も検討する。これは債務不履行、デフォルト率の上昇へとつながり、それが安易な信用供給を断ち、
他方で失業の恐怖と住宅価格急落が支出を引き下げた。流動性への殺到が生じたため、金融機関は短期債務を使って
資産ポジションの資金を支えようにも、資産の毒性がますます強まるなかでは、それができなくなった。市場性のない資産が
価値を持つという偽装は放棄されなくてはならない、ということは、つまり金融機関は大きな債務超過に陥っていることを
はっきりさせなければならない。穴は大きすぎて、何兆ドルものベール・アウトでも埋めきらない。ラリー・サマーズと
ティミー・ガイトナーがマネー・マネジャーの資本制経済を救おうとしても、有権者と市場は彼らの努力を拒絶している
(ただし、 理由はさまざまである)。
この危機の結果、資本制経済がもっと堅牢な物へと変容する可能性もある。それは大恐慌の後、様々な機関や規制、
政策がとられそれによって安定性が増したのと同じである。しかしそうなるためには政策立案者たちが今回の
世界金融システムの危機の範囲を認識していなければならない――これはマネー・マネージャー資本制の決定的な
破綻を表しているのである。丁度大恐慌がレッセ・フェール資本制の崩壊として記憶されるべきであるのと同じことである。
マネー・マネージャー資本制に代わるものが何か、今はまだわからない。
2.金融資本制経済:マネー・マネージャー資本制経済の先行形態
前世紀の初頭、ヒルファーディングは資本制経済の新しい段階を、複雑な金融関係と、
金融による産業支配として特徴づけた(Hilferding, 1981)(8)。彼の議論では、金融資本制のもっとも顕著な
特徴は集中の昂進である。これは一方では、カルテルとトラストの形成により「自由競争」を排除し、同時に、
銀行資本と産業資本とをかつてないほど強固に結びつけた(Hilferding, 1981, pp. 21-2)。ヴェブレン、ケインズ、
シュンペーターと、後に、ミンスキーはまた、資本主義の新たな段階を認識した。:ケインズにとっては、
それが表わしているのは事業に対する投機の支配であり、シュンペーターにとっては金融にアクセスできる
イノベーターによる資源の支配であったが、他方でヴェブレンは産業業務 industrial pursuits と
貨幣業務 pecuniary pursuits とを区別していた(9)。
ミンスキーは金融資本制には「商業資本制経済」が先行すると主張した。これは企業が
商業銀行を運転資本供給(生産活動の資金繰り)のために用いる段階である。しかし、
工場と設備が高価になったため、投資には外部金融が必要となった。あらためて考えてみると、外部金融とは
将来の利益をあらかじめ約束することである。ここから債務不履行と破産の可能性が生み出される
――これがミンスキーの論点であるが――一方で、同時に所有と支配の分離のドアを開くことにもなった。ここから
ケインズは、『一般理論』第12章で取り組んだ(平均的意見を基に企業を評価することに起因する)「楽観主義と
悲観主義の旋風」を引き出した。他方でヴェブレンの分析で指摘されているのは、経営者による事業資本の
価値操作である。この点は以下で論じられる。シュンペーターの立場は明らかにもっと甘かった。というのは
彼の市場に対する「ヴィジョン」はもっとオーソドックスな物であったからだが、しかし、それでも、彼は金融の中核的
重要性を認識していた。金融によって「循環フロー」――それは、所定の規模の生産と流通を容易にするだけである
――が始まり、イノベーションへの融資を通じて循環フローの成長が可能になるのである。ミンスキーのいう
商業資本段階では外部金融は短期であり、シュンペーターの循環フローにおいて貨幣が果たしているのと
同じ役割を果たしている。つまり資産ポジションの大部分は内部資金でファイナンスされていたのである。しかし
金融資本制の台頭に伴い、資産ポジションを形成するため外部金融へのアクセスが必要になった(10)。これにより
資本制の性格は根底的に変わってしまい、経済ははるかに不安定になった。
ヴェブレンは20世紀初頭の資本制ヴァージョンを「信用経済」と呼んでいたが、そこで支配的なのは財市場ではなく、
「資本市場こそ第一義になる。。。。資本市場は現代経済の特徴であり、そうしたものとしてより大きな
「信用経済」を生み出し明確にする」(Vebren, 1958, p.75)。「資本(総資産)」という言葉でヴェブレンが意味していたのは
「資本化された想像上の収益能力 capitalized presumptive earning capacity 」である。これは「あらゆる
与信の用益権によって構成される。こうした用益権を支えているのが、その信用によって獲得された
その事業体の生産設備や暖簾である。」(Veblen, 1958, p.65)。これと対照的なのが「実効工業資本」であり、
これは工業生産に投入される素材項目の集計である。のれんは担保になり得るし、そうなれば工業資本と事業資本の間の価値の
乖離を広げることになり得る(Veblen, 1958, p.70)(11)。予想収益力 presumptive earning capacityが上昇すると
これが信用・株式市場で資本化されることとなり、信用へのアクセスが資本価値をますます引き上げ、
それがさらに信用を過熱させ、工業資本価値と事業資本価値の乖離が大きくなり、大変結構な好循環へと続く。
「推定収益力 putative earning-capacity 」が不安定で操作されやすいのは、それが「数多くの、
将来の収益その他もろもろに関する推測の結果であるからであり、そして、、、不完全で大部分憶測に基づいた現時点の
収益力に関する知識および、さらに不完全にしかわからない商品市場や企業方針の行く末についての知識に基づいて
進められるからである」(Veblen, 1958, p.77)。
事業資本の価値の上昇の方が収益見通しより早く上昇する傾向があるが、それは、後者が最終的には
最終売上に依存しており、その大部分は消費者への売上から成るものだからである(Veblen, 1958, p.56)。最終的には
過剰評価が認識され、融資は更新されず、貸付けは取立てられ、資産が売却される。「上昇局面buoyancy」の時期には
期待に基づいて膨らんだ工業設備が資本化されるのみならず、契約締結において、証券のマージンに注意を払われることが
少なくなるためでもある」(Veblen, 1958, p.97)。全般的流動性危機がそれに続く――そのために必要なのは、
ただ一人の大きな与信者が、債務者の何人かの収益力がその資本化の際に必要とされるものほど大きくないことに
気が付くことだけである。 好循環が悪循環になる。信用が打ち切られ、債務者が契約をデフォルトせざるを得なくなり、
他から債権を回収せざるを得なくなり、そして資産の投げ売りとなる。
事業資本と工業資本の乖離の拡大こそが、マネージャーの「事業利害」を突き動かす主要動機である――
「生産活動上の機能ではなく、製品の販売上の機能ですらなく」、重要なのはむしろ「事業資本の販売上の機能」なので
ある(Veblen, 1958, p.79)。彼らは「、、、その目的のために、よく知られ、大いに広まっている手法によって、、、、
乖離を引き起こすことができる。決定的な岐路で、部分的な情報、誤った情報を、ずるがしこいやり方で
配信すれば充分であろう、、、彼らは、誰しもそうである通り、抜け目のないビジネスマンなのである」(Veblen, 1958, p.77-8)。
ケインズの有名な警句を思い出そう。「深刻なのは、企業の方が投機の泡の渦にのみこまれてしまった時である。一国の
資本の発展がカジノ活動の副産物になってしまえば、仕事は悪影響を受けるだろう(Keynes, 1964, p.159)。
ヴェブレンは不確実性と投機がかかわっている点は同意するが、金銭的目論見が成功しそうであることが株価操作において
重要であることを強調し、「事業関係者」たちが大きな不確実性に直面していることを否定さえした。「収益の確実性
(その相対的大きさとまでは言えないが)を保証するには、製品販売に基づいてマネジメントするよりは、資本の市場価格を
大規模に操作する方がより簡単である。」(Veblen, 1958, p.82)。市場操作とはリスクを伴うものであるものだが、
「操作をする人にとってこのことは、企業にとって、、、、あるいは、この不正操作に直接関与していないビジネスマンにとってと
比べて、、、大した問題ではない」(Veblen, 1958, p.82-3)(12)。
この説明が大部分、現代にもあてはまり得ることについては後で考えよう。実際、間奏期間、つまり
ニューディールから1970年代までは、逸脱期間と考えるべきである。資本制経済はこの局面で例外的な
静止状態にあった――ジョン・ケネス・ガルブレイスが「新しい産業国家」と呼んだ時代である(ミンスキーは
家父長制資本制経済段階と呼んだ)。この時期にはマネージャーたちの関心はその前後に比べ公共利益と
整合的であった。不幸にして、安定性は、市場過程は本来的に安定的であるとするオーソドキシーの信念を
裏付けていると解釈された――結果として、制約が緩められればさらに安定性は増すであろう、ということになる(13)。
(広い意味での)ニューディール制度が緩められるとともに、新しい形態の金融資本制が合衆国そして世界経済において
支配的になるに至った。これがミンスキーの言うマネー・マネージャー資本制経済である。
(以下、次回)
(1) こうした数値は過去の赤字の額と厳密に比較可能ではない。というのは新大統領[※オバマ氏]は
すべての支出を予算に含めるように命じたからである――その前の政権がやっていたような、たとえば対イラク戦争の
戦費を隠すようなことはしなかった。
(2) ユーロ圏の展望についてはKelton and Wray (2009)参照のこと
(3) Cassidy (2008), Chancellor (2007), McCulley (2007) and Whalen (2007) 参照。アナリストたちは
ますます景気上昇期における投機的金融・ポンツイ金融の利用、さらにはミンスキー-フィッシャーの
債務デフレーションの危険性にも言及するようになっている。ミンスキーに関しては Kregel (2007), Lahart (2007),
Magnus (2007)を参照。金融資本制に対するミンスキーのアプローチの要約はPapadimitriou and Wray (1998)参照。
(4) Wray (2008A, 2008B)を参照。
(5) Papadimitriou and Wray(2008)を参照のこと。
(6) Wray(2009)参照。
(7) この例には、1970年代初期のREIT;1980年代初頭のLDC債務;1980年代合衆国における商業不動産、ジャンクボンド、
貸付組合危機(他の多くの国では銀行危機を伴った):1987年の株式市場崩壊と2000年のドットコムバブル崩壊;
1980[※90?]年代初頭からの日本のメルトダウン、1990年代後半のロシアのデフォルト、アメリカの債務危機、が含まれる。
(8) ヒルファーディングの分析が直接適用できるのはヨーロッパ諸国(銀行に依存していた)だけで合衆国
(こちらの方がより「市場志向的」であった)、と論じる人もいる。筆者はこの論争には立ち入るつもりはない。というのは
筆者の議論にとってはあまり重要ではないからだ。初期の金融資本制の基本的特徴は次のようなものである。相対的に
小さな政府、外部金融の利用、経済的力の「トラスト」――あるいは今日のわれわれの言葉で言うなら
「製造業」「金融」「保険業」にまたがる多様な利益と関連会社を持つメガコーポレーション――への集中。
(9) Veblenの理論でも集中が役割を果たしている。彼は、現代の危機は「工業の指揮官たち
the 'captains of industry'」たちによる「生産のサポタージュ 'sabotage of production' 」(または
「良心的効率性引下げ conscientious withdrawal of efficiency 」に帰すことができると論じている。
(10) Youngman(1906)は、コマーシャル・ペーパー(企業への短期貸付に使用される金融商品)の相対的な減少と、
金融機関による株式や債券の直接投資の増加について、興味深い説明を提供している。彼女によると、「銀行は、
独立して行動しているのではなくより大きな産業・金融全体の一部として操業しており、国内の主要銀行、信託・保険会社の
結びつきは、、、単にこのより包括的な連合の発展傾向が反映されているだけだ。実際にはそれは、集団支配の集中と同時に
投資利害関係者の拡張ヘと向かう一般的傾向の一側面に過ぎない。それは巨大投資グループを通じて巨大鉄道・工業企業を
効果的に運営しようとすることの必然的結果であると同時に、不可欠の条件でもある。それぞれのグループは、
あらゆる事業に対して支援を行う独自の金融的後支えを持っており、そしていくつかのグループが結合するときには、
彼らの金融的関係者もまた連合する」(Youngman, 1906, pp. 438-9)。彼女はつづけて、どのようにして、証券や
株式発行を引き受けする投資銀行が自分たちの資産にポジションを蓄積する――しばしば価格が上昇し続ける――に至ったかを
説明する。従って合衆国がより「市場ベース」であったという議論はおそらく過大評価である。というのは銀行が大量の
「市場性」金融商品を抱えていたのだから。
(11) さらに「寡婦の壺」がある。のれん「とは、霊的性質であり、霊的身体に特有の偏在性のおかげで、その全体は、
それを構成する多様な構造のそれぞれの部分に分割されることなく内在している」――それは決して消え去ることはなく、
むしろ「それを取得した企業結合体の中で」資本制的な価値を拡大するかもしれない(Veblen, 1958, p.85)。昔の景気過熱は
エキゾチックな商品で生じたが、それと同じことである。これら新しい資産は実現されるあてのない将来のキャピタルゲインと
所得フローを担保としている――「霊感」とはトレーダーのウインクと会釈以外には何の根拠もない。何千という毒入りローンから
一つのパッケージを担保とすることで、いくつもの様々な商品の組合せ――CDOに、またそのCDOから作られるスクエアドCDOへ、
そしてそれから創り出されるキューブドCDO――にトリプルAが与えられた。決して実行されることのなかった決済は、
創りだされた「さまざまな仕組債のそれぞれの部分に」「分割されることなく」内在していたのである。今次危機の間、
銀行その他企業は、ブームの間は支えられていた何憶ドルというのれん代の減損を強いられた。2008年には銀行は250憶ドル以上の
のれん代を減損し、そしてその年度末にはさらに2910憶ドルの簿価の切り下げを行った。多くの場合、のれん代は毒入り資産を
保有しており問題を抱えていた金融機関の購入によって創りだされていた(Healy, 2009)。同じような話は、1980年代の
貸付組合危機にあいだにもみられた。二つの明瞭な債務超過機関が買収され、そして結合された機関を健全に見せかけるため、
十分なのれん代が計上されたが、それは単に市場価値をはるかに超えた価格が支払われたというだけのことであった
(Wray, 1994)。注目すべき声明の中で、ユナイテッド・コミュニティ・バンク(四半期で7千万ドルののれん代の
評価損を出した)のCFOは、これは大した話ではない、というのは「バランスシート上、紙に記帳されただけのもの」だから、
と論じたのである(Healy, 2009)。ただしこの「紙上の記帳」は購入価格にレバレッジされ銀行の総資産に加算されたのである。
(12) ヴェブレンは「投機化」よりも「総資産化」に基づく説明を好んだが、それはミルキケン事件[※「ジャンクボンドの帝王」と
呼ばれた。MMFにジャンク(毒入り)債券を忍び込ませる手口を開発したとされる]、エンロン事件、
マドフ事件には、ケインズの「ばば抜き」のたとえ話よりそちらの方が当てはまりがいいように見える。
(13) 当時想定された新しい安定した環境をもっとも明瞭に歌い上げたのはベン・バーナンキ(2004)の
「グレート・モデレーション」テーゼであり、これは市場関係者たちから大真面目に受け止められ、リスクを割り引くために用いられた。
どうもあんまり思わしくない方向に進んでいるような気がしてしょうがない。
本当なら、レイの後期ラーナー批判とかグリーンニューディールについての
ワーキング・ペーパーを先にやった方が時宜を得ているのかもしれないが、
まあ、とりあえず、これまでの流れもあるので、世界金融危機の続きをやる。同名の書物がティモワーニュとの共著で
出版されているが、焦点にはややずれがある。
本稿(Cambridge Journal of Economics 2009, 33, 807–828)で、レイは
世界金融危機後の展望をかなり楽観的に描いていた。ただし、「楽観的」といっても、それは経済成長率がすぐに元に戻るとかいうような
意味でではなく、むしろ、この混乱の後、政治が、かつて大恐慌の後に合衆国政府が悪質な金融業界のビジネスに
メスを入れたことが資本制のその後の発展モデルの変化に大きく影響を与えたのと同じように、
今度もまた、様々な社会的圧力によってウォールストリートの動きに歯止めをかけられ、資本制経済が
より安定した軌道に乗るようになるであろうと(ただし、そのためにはもう一度ぐらいは金融危機の顕在化
――危機自体はまだ継続しているのだが、目には見えづらくなっている――が必要だが)、展望したのである。
今となっては、この希望的観測はあまりにも楽観的過ぎたと言えよう。後知恵でいうのではないが、
やはりレイという人の政治オンチっぷりはちょっとしたもので、まあ、こうなればこそ
「トランプ政権は戦後もっとも左翼的になるかもしれない」なんぞという頓珍漢な発言も出たのであろう。
以前に訳出したものからもうかがえる通り、レイのこの見通しが甘すぎたのは確かではあるが、
しかしオバマ政権の手ぬるさが多くの人々にとって意外であったというのも事実であろう。
ウォールストリートの利害はちょっとやすっとの世界金融危機ぐらいでは揺るがなかった。
その結果の一つが、トランプ政権の誕生だったわけで、そう考えると、
政治(人権や民主主義の状況を含めた広い意味で)と経済の結びつき方というものには、いわゆる「政治経済」と呼ばれているのとは
また別の角度から議論を深めていく必要があるような気もしているが、
それはまた機会を改めて(といって、すぐ忘れる。。。)。
なお、今回の疎訳は個人の学習用に作成したメモを、志を同じくする人の学習の便のために
一つの参考として公開するものですので、あくまでも個人の学習用にのみ参照ください。全部で
三回か四回ぐらいになると思います。
The rise and fall of money manager capitalism: a Minskian approach
マネー・マネジャー資本制経済の勃興と凋落:ミンスキーアプローチ
L. ランドール・レイ
要旨
われわれは深刻で、おそらく長引く景気後退を伴う世界的な金融危機の真っ只中にいる。確かに、
一部のアナリストは、これを第二次世界大戦後の最初の恐慌とも呼んでいる。この論文では、
筆者はこれがシステム的危機――ハイマン・ミンスキーがマネー・マネージャー資本制経済と呼んだものの危機――であると
論じる。これを、初期のヒルファーディング及びヴェブレンの分析とリンクさせ、そして事実上、
今回の危機がこの種の資本制経済の失敗としては2度目であることを示す。初期金融資本制経済の基本的特徴とは、
相対的に小さな政府、投資資金として外部資金の利用、「トラスト」――あるいは、今日であれば「工業」
「金融」「保険」にまたがる多様な利害関係と提携による巨大企業とでも呼ばれるであろうもの――への
経済力の集中である。最初の段階とは異なり、第二段階の金融資本制経済は巨大な政府と
ネオコンサーバーティズムのモデルという文脈の中で登場した。ミンスキーの分析によって、どのようにして
ニューディールと巨大な政府が第二次世界大戦後に家父長型資本制経済(a paternalistic capitalism)を
生出すことになったのか、それがどのような意味で高い消費水準、雇用水準、格差縮小、金融安定性にとって
好ましかったのかを理解しやすくなる。とはいえ、こうした安定性とはそれ自体、不安定化なのである。というのは
これこそマネージド・マネー(managed money)の登場を可能にしたものであるからだ。時が経つにつれ、
イノベーションと規制緩和によって脆弱性が高まった。これはますます金融危機の頻度と深刻さを高めていった。以前の危機は
「it(次の債務デフレーション)」が再び起こることを防ぐのに十分な速さで解決されていたが、今回の危機は深刻で、
マネー・マネージャー資本制そのものの生き残り自体に疑問が付けられるほどだ。[※"it"とはミンスキーの主著'のタイトルから
とったもので、2019年危機と同様の深刻な経済危機を指す。]今回の論文では現在今次危機に貢献している諸要素を
検討する。例えば不動産ブームと破裂、証券化債務やクレジット・デフォルト・スワップのような危険な
金融商品の登場、コモディティ市場バブル、そして緊縮財政などである。この記事は、この形態の金融資本制の破綻について、
どのような結果になり得るか幾つか可能性を示唆することで締めくくられる。
1. イントロダクション
現在、1930年代以降最悪の経済危機に直面しているということはほとんど疑いようない。数は少ないが、
エコノミストや政策立案家達の中には不況の可能性について話を始めたものもいる。ケインズ経済学への参照は
常識となり、政府の介入に反対するのは献身的な自由市場主義者だけになった。ウォールストリートの魔法使い達まで
金融市場の再規制に賛成し始めた。合衆国政府のコミットメントは2009年2月半ばまでにほぼ9兆ドルに達したが、
それで十分だとする論者はあまりいない。最近の国内総生産(GDP)の修正値はレーガン不況以来の急激な落ち込みを
示している。オバマ政権は今年の連邦予算赤字を1.75兆ドル(GDPの12%)、2010年には1.17兆ドルになると
予想している――しかし一部の民間予測では2009年には1.9兆ドル、GDPの13.5%、これは翌年度も減りそうにない(1)。
それどころか外国の先行きの見通しはもっとひどい。Fedは世界的な最後の貸し手となり、
外国の中央銀行に6000万ドルの準備預金融資を提供した。さらに、これはよく知られていることであるが、
合衆国の金融機関に対してベイル・アウト[※パラシュートによる緊急脱出]を提供し(もっとも知られているのは
AIGに対するもの)、それによって外国の金融機関も守られたのである(AIGはヨーロッパの銀行によって保有されていた
債務のクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)「保険」の最大の供給者である)。いまだに相対的に安全とされた
合衆国財務省証券への買いが殺到し為替レートが脅かされ、世界中でリスクスプレッドが拡がっている。社会的・政治的に
不穏な雰囲気が周辺国中で広まっている。多くの国の経済は合衆国経済が立ち直るまで回復しないだろう。筆者は
合衆国は今次危機回復のためにまだ打てる政策手段を持っていると信じてはいるが、他の多くの国にはそれがない。しかし
その点は本稿の射程を超えている(2)。
危機の原因についてはあらゆる説明が示された。手ぬるい規制と監督、格差が広まったことで家計が支出のための借入を
増やしたこと、強欲で不合理な熱狂、世界的に過剰な流動性――合衆国の安易な貨幣政策と合衆国の経常赤字によって
拍車をかけられ世界中に大量のドルが氾濫したことなども挙げられた。ハイマン・ミンスキーの業績は
かつてないほどの関心を惹きつけ、多くの人がこれを「ミンスキー・モメント」(3)と呼んだ。筆者は
本稿でこの2年間に繰り広げられた今回の出来事について細かく語るつもりはない。それはすでに2本の長い刊行物にて
行った(4)。本危機に対する政策立案者たちがこれまで行ってきたことについて詳細な批判をするつもりもない(5)。最後に
ここで本危機を解決するために特定の政策を提案するつもりもない(6)。今回筆者が提示したいのはそうしたことではなく、
世界経済の一時代を支配したある形態の資本制の発生と崩壊に関するより概括的な分析である。我々はこれを近年の発展として
跡付けることのできる「モメント」と見なすべきではない。むしろ、ミンスキーが50年近く掛けて論じたように、我々は
金融システムが脆弱な物へ向かってゆっくりと変化してゆくその渦中におかれている。この脆弱性が、最後にはシステム的な
世界危機を生み出すのである。1996年に死去するまでの最後の数年間、ミンスキーはこの進化に対する「段階」アプローチを展開し、
現在の局面を「マネー・マネージャー・キャピタリズム」と同定した――危機を引き起こしやすく、セーフティー・ネットが脆弱で、
それゆえひとたび金融崩壊が起これば経済的な災禍が引き起こされる、そんな資本制経済である。実際、我々は
数多くの危機を繰り返し体験しており、そして危機はより頻繁に、より深刻なものになる傾向がある(7)。これは不動産市場、
証券化商品市場、コモディティ市場における過熱と破裂の繰り返しの中で累積してゆき、最終的に
クレジット・デフォルト・スワップおよびその他デリバティヴの大発生へと行き着く。
要するに筆者としては、ハイマン・ミンスキーに倣ってマネー・マネージャー・キャピタリズムを批判したい――システム的に
リスクが低評価される環境の中で高レバレッジを掛けられたファンドが総収入(所得フローにキャピタルゲインを
加算したもの)を最大化しようとする行動によって特徴づけられる資本制経済である。金融機関に対する規制や
監督がほとんどないなかで、マネー・マネージャーはますます密教的な商品を創りだしていった。マネー・マネージャーの報酬は
ほとんどがキャピタルゲインであり、背後にある所得フローではない。キャピタルゲインは、背後にある資産が
曖昧であれば、比較的容易に紡ぎ出すことができる――ウォーレン・バフェットが「金融大量破壊兵器」と呼んだものだ。
そしてこれらはレバレッジを掛けられ予想報酬を得る権利の購入に使われた。なんでもこれは、また別の資産クラスを
支えており、その資産クラスの価値たるや、マネージド・マネーによる入札で上昇し得るというのである。破裂は
次々と起こるが、それでマネージド・マネーの一部が消え去ってからも、新しいブームは必然的に、まるで
灰の中から飛びたつ火の鳥のように、蘇生する。しかし今次危機は相当深刻なもので、マネージド・マネーのかなりの部分を
破壊したし、マネー・マネージャーたちの信用を完全に失墜させたし、金融部門を思いっきり縮小する――言い換えれば、
これによってマネー・マネージャー資本制経済が終焉するかもしれないのである。
筆者はまずは歴史的な文脈を分析するつもりだ。幾つかの重要な面で、資本制経済のマネー・マネージャー形態は
「金融資本制」が支配的なポジションへ立ち戻ったことを表している――それは1930年代の
巨大不況に対するニュー・ディール政策によって失われたポジションである。ミンスキーによるなら、
1930年代以前の小さな政府、レッセ・フェール経済は失敗であった。それにとってかわったのが、巨大政府資本制経済であり、
これは大きな成功をおさめた。政府が経済において巨大な領域を支配するようになったばかりでなく、
ビジネスの行動の規制と監督に巨大な役割を果たすことになり、そして無数のセーフティーネットと保証を提供し、
それによって同時に格差を縮め所得の成長とを促した。以下で要約して説明する理由により、こうした要因全てが
経済安定化へ貢献した。しかしながら時が経つとともに、安定した経済がかなり脆弱な金融構造を深化させ、それが
金融危機を引き起こした――ミンスキーが常に論していた通り、安定とは不安定化なのだ――というのは、
マネー・マネージャーたちと政府内のその代弁者たちはニューディールの足枷を切り刻み、別の目標に置き換えた。
筆者はソースタイン・ヴェブレンによる20世紀初頭の分析を手短に要約することから始める。というのは、
筆者の信じるところ、これは現代資本制経済に光を当てているからである。次いで、ミンスキーによる研究に
立ち戻る。この研究は戦後の資本制経済をマネー・マネージャーが支配力を再獲得する過程として、
その進化について研究したものである。筆者はごく簡単にこの過程において国家が果たした役割を瞥見する。
ここで国家は「自由市場」と「オーナーシップソサエティ」を推し進めた――この変容は、もっと厳しい言い方をするなら、
「ネオコン」による国家装置の略奪と見做すことができる。「ネオコン」こそミンスキーの言う「家父長型」国家を、
ジェームス・ガルブレイスが「プレディター(捕捉者)国家」として描き出したものに置き換えたのである。規則、
規制、監視機関、セーフティー・ネットを解体することにより プレディター国家はマネー・マネジャーの台頭を
助けた。最後に、本稿では金融実務あるいは金融商品のうち3つ(証券化、CDS、コモディティー先物契約)が
果たした役割に立ちもどる。これらは、フィッシャー―ミンスキーの債務デフレプロセスが可能になる条件を創りだすのに
貢献した。また消費者に過大な負担を負わせることになる3つの「引き金」(金利と石油価格の上昇、そして
税収の増加)の役割も検討する。これは債務不履行、デフォルト率の上昇へとつながり、それが安易な信用供給を断ち、
他方で失業の恐怖と住宅価格急落が支出を引き下げた。流動性への殺到が生じたため、金融機関は短期債務を使って
資産ポジションの資金を支えようにも、資産の毒性がますます強まるなかでは、それができなくなった。市場性のない資産が
価値を持つという偽装は放棄されなくてはならない、ということは、つまり金融機関は大きな債務超過に陥っていることを
はっきりさせなければならない。穴は大きすぎて、何兆ドルものベール・アウトでも埋めきらない。ラリー・サマーズと
ティミー・ガイトナーがマネー・マネジャーの資本制経済を救おうとしても、有権者と市場は彼らの努力を拒絶している
(ただし、 理由はさまざまである)。
この危機の結果、資本制経済がもっと堅牢な物へと変容する可能性もある。それは大恐慌の後、様々な機関や規制、
政策がとられそれによって安定性が増したのと同じである。しかしそうなるためには政策立案者たちが今回の
世界金融システムの危機の範囲を認識していなければならない――これはマネー・マネージャー資本制の決定的な
破綻を表しているのである。丁度大恐慌がレッセ・フェール資本制の崩壊として記憶されるべきであるのと同じことである。
マネー・マネージャー資本制に代わるものが何か、今はまだわからない。
2.金融資本制経済:マネー・マネージャー資本制経済の先行形態
前世紀の初頭、ヒルファーディングは資本制経済の新しい段階を、複雑な金融関係と、
金融による産業支配として特徴づけた(Hilferding, 1981)(8)。彼の議論では、金融資本制のもっとも顕著な
特徴は集中の昂進である。これは一方では、カルテルとトラストの形成により「自由競争」を排除し、同時に、
銀行資本と産業資本とをかつてないほど強固に結びつけた(Hilferding, 1981, pp. 21-2)。ヴェブレン、ケインズ、
シュンペーターと、後に、ミンスキーはまた、資本主義の新たな段階を認識した。:ケインズにとっては、
それが表わしているのは事業に対する投機の支配であり、シュンペーターにとっては金融にアクセスできる
イノベーターによる資源の支配であったが、他方でヴェブレンは産業業務 industrial pursuits と
貨幣業務 pecuniary pursuits とを区別していた(9)。
ミンスキーは金融資本制には「商業資本制経済」が先行すると主張した。これは企業が
商業銀行を運転資本供給(生産活動の資金繰り)のために用いる段階である。しかし、
工場と設備が高価になったため、投資には外部金融が必要となった。あらためて考えてみると、外部金融とは
将来の利益をあらかじめ約束することである。ここから債務不履行と破産の可能性が生み出される
――これがミンスキーの論点であるが――一方で、同時に所有と支配の分離のドアを開くことにもなった。ここから
ケインズは、『一般理論』第12章で取り組んだ(平均的意見を基に企業を評価することに起因する)「楽観主義と
悲観主義の旋風」を引き出した。他方でヴェブレンの分析で指摘されているのは、経営者による事業資本の
価値操作である。この点は以下で論じられる。シュンペーターの立場は明らかにもっと甘かった。というのは
彼の市場に対する「ヴィジョン」はもっとオーソドックスな物であったからだが、しかし、それでも、彼は金融の中核的
重要性を認識していた。金融によって「循環フロー」――それは、所定の規模の生産と流通を容易にするだけである
――が始まり、イノベーションへの融資を通じて循環フローの成長が可能になるのである。ミンスキーのいう
商業資本段階では外部金融は短期であり、シュンペーターの循環フローにおいて貨幣が果たしているのと
同じ役割を果たしている。つまり資産ポジションの大部分は内部資金でファイナンスされていたのである。しかし
金融資本制の台頭に伴い、資産ポジションを形成するため外部金融へのアクセスが必要になった(10)。これにより
資本制の性格は根底的に変わってしまい、経済ははるかに不安定になった。
ヴェブレンは20世紀初頭の資本制ヴァージョンを「信用経済」と呼んでいたが、そこで支配的なのは財市場ではなく、
「資本市場こそ第一義になる。。。。資本市場は現代経済の特徴であり、そうしたものとしてより大きな
「信用経済」を生み出し明確にする」(Vebren, 1958, p.75)。「資本(総資産)」という言葉でヴェブレンが意味していたのは
「資本化された想像上の収益能力 capitalized presumptive earning capacity 」である。これは「あらゆる
与信の用益権によって構成される。こうした用益権を支えているのが、その信用によって獲得された
その事業体の生産設備や暖簾である。」(Veblen, 1958, p.65)。これと対照的なのが「実効工業資本」であり、
これは工業生産に投入される素材項目の集計である。のれんは担保になり得るし、そうなれば工業資本と事業資本の間の価値の
乖離を広げることになり得る(Veblen, 1958, p.70)(11)。予想収益力 presumptive earning capacityが上昇すると
これが信用・株式市場で資本化されることとなり、信用へのアクセスが資本価値をますます引き上げ、
それがさらに信用を過熱させ、工業資本価値と事業資本価値の乖離が大きくなり、大変結構な好循環へと続く。
「推定収益力 putative earning-capacity 」が不安定で操作されやすいのは、それが「数多くの、
将来の収益その他もろもろに関する推測の結果であるからであり、そして、、、不完全で大部分憶測に基づいた現時点の
収益力に関する知識および、さらに不完全にしかわからない商品市場や企業方針の行く末についての知識に基づいて
進められるからである」(Veblen, 1958, p.77)。
事業資本の価値の上昇の方が収益見通しより早く上昇する傾向があるが、それは、後者が最終的には
最終売上に依存しており、その大部分は消費者への売上から成るものだからである(Veblen, 1958, p.56)。最終的には
過剰評価が認識され、融資は更新されず、貸付けは取立てられ、資産が売却される。「上昇局面buoyancy」の時期には
期待に基づいて膨らんだ工業設備が資本化されるのみならず、契約締結において、証券のマージンに注意を払われることが
少なくなるためでもある」(Veblen, 1958, p.97)。全般的流動性危機がそれに続く――そのために必要なのは、
ただ一人の大きな与信者が、債務者の何人かの収益力がその資本化の際に必要とされるものほど大きくないことに
気が付くことだけである。 好循環が悪循環になる。信用が打ち切られ、債務者が契約をデフォルトせざるを得なくなり、
他から債権を回収せざるを得なくなり、そして資産の投げ売りとなる。
事業資本と工業資本の乖離の拡大こそが、マネージャーの「事業利害」を突き動かす主要動機である――
「生産活動上の機能ではなく、製品の販売上の機能ですらなく」、重要なのはむしろ「事業資本の販売上の機能」なので
ある(Veblen, 1958, p.79)。彼らは「、、、その目的のために、よく知られ、大いに広まっている手法によって、、、、
乖離を引き起こすことができる。決定的な岐路で、部分的な情報、誤った情報を、ずるがしこいやり方で
配信すれば充分であろう、、、彼らは、誰しもそうである通り、抜け目のないビジネスマンなのである」(Veblen, 1958, p.77-8)。
ケインズの有名な警句を思い出そう。「深刻なのは、企業の方が投機の泡の渦にのみこまれてしまった時である。一国の
資本の発展がカジノ活動の副産物になってしまえば、仕事は悪影響を受けるだろう(Keynes, 1964, p.159)。
ヴェブレンは不確実性と投機がかかわっている点は同意するが、金銭的目論見が成功しそうであることが株価操作において
重要であることを強調し、「事業関係者」たちが大きな不確実性に直面していることを否定さえした。「収益の確実性
(その相対的大きさとまでは言えないが)を保証するには、製品販売に基づいてマネジメントするよりは、資本の市場価格を
大規模に操作する方がより簡単である。」(Veblen, 1958, p.82)。市場操作とはリスクを伴うものであるものだが、
「操作をする人にとってこのことは、企業にとって、、、、あるいは、この不正操作に直接関与していないビジネスマンにとってと
比べて、、、大した問題ではない」(Veblen, 1958, p.82-3)(12)。
この説明が大部分、現代にもあてはまり得ることについては後で考えよう。実際、間奏期間、つまり
ニューディールから1970年代までは、逸脱期間と考えるべきである。資本制経済はこの局面で例外的な
静止状態にあった――ジョン・ケネス・ガルブレイスが「新しい産業国家」と呼んだ時代である(ミンスキーは
家父長制資本制経済段階と呼んだ)。この時期にはマネージャーたちの関心はその前後に比べ公共利益と
整合的であった。不幸にして、安定性は、市場過程は本来的に安定的であるとするオーソドキシーの信念を
裏付けていると解釈された――結果として、制約が緩められればさらに安定性は増すであろう、ということになる(13)。
(広い意味での)ニューディール制度が緩められるとともに、新しい形態の金融資本制が合衆国そして世界経済において
支配的になるに至った。これがミンスキーの言うマネー・マネージャー資本制経済である。
(以下、次回)
(1) こうした数値は過去の赤字の額と厳密に比較可能ではない。というのは新大統領[※オバマ氏]は
すべての支出を予算に含めるように命じたからである――その前の政権がやっていたような、たとえば対イラク戦争の
戦費を隠すようなことはしなかった。
(2) ユーロ圏の展望についてはKelton and Wray (2009)参照のこと
(3) Cassidy (2008), Chancellor (2007), McCulley (2007) and Whalen (2007) 参照。アナリストたちは
ますます景気上昇期における投機的金融・ポンツイ金融の利用、さらにはミンスキー-フィッシャーの
債務デフレーションの危険性にも言及するようになっている。ミンスキーに関しては Kregel (2007), Lahart (2007),
Magnus (2007)を参照。金融資本制に対するミンスキーのアプローチの要約はPapadimitriou and Wray (1998)参照。
(4) Wray (2008A, 2008B)を参照。
(5) Papadimitriou and Wray(2008)を参照のこと。
(6) Wray(2009)参照。
(7) この例には、1970年代初期のREIT;1980年代初頭のLDC債務;1980年代合衆国における商業不動産、ジャンクボンド、
貸付組合危機(他の多くの国では銀行危機を伴った):1987年の株式市場崩壊と2000年のドットコムバブル崩壊;
1980[※90?]年代初頭からの日本のメルトダウン、1990年代後半のロシアのデフォルト、アメリカの債務危機、が含まれる。
(8) ヒルファーディングの分析が直接適用できるのはヨーロッパ諸国(銀行に依存していた)だけで合衆国
(こちらの方がより「市場志向的」であった)、と論じる人もいる。筆者はこの論争には立ち入るつもりはない。というのは
筆者の議論にとってはあまり重要ではないからだ。初期の金融資本制の基本的特徴は次のようなものである。相対的に
小さな政府、外部金融の利用、経済的力の「トラスト」――あるいは今日のわれわれの言葉で言うなら
「製造業」「金融」「保険業」にまたがる多様な利益と関連会社を持つメガコーポレーション――への集中。
(9) Veblenの理論でも集中が役割を果たしている。彼は、現代の危機は「工業の指揮官たち
the 'captains of industry'」たちによる「生産のサポタージュ 'sabotage of production' 」(または
「良心的効率性引下げ conscientious withdrawal of efficiency 」に帰すことができると論じている。
(10) Youngman(1906)は、コマーシャル・ペーパー(企業への短期貸付に使用される金融商品)の相対的な減少と、
金融機関による株式や債券の直接投資の増加について、興味深い説明を提供している。彼女によると、「銀行は、
独立して行動しているのではなくより大きな産業・金融全体の一部として操業しており、国内の主要銀行、信託・保険会社の
結びつきは、、、単にこのより包括的な連合の発展傾向が反映されているだけだ。実際にはそれは、集団支配の集中と同時に
投資利害関係者の拡張ヘと向かう一般的傾向の一側面に過ぎない。それは巨大投資グループを通じて巨大鉄道・工業企業を
効果的に運営しようとすることの必然的結果であると同時に、不可欠の条件でもある。それぞれのグループは、
あらゆる事業に対して支援を行う独自の金融的後支えを持っており、そしていくつかのグループが結合するときには、
彼らの金融的関係者もまた連合する」(Youngman, 1906, pp. 438-9)。彼女はつづけて、どのようにして、証券や
株式発行を引き受けする投資銀行が自分たちの資産にポジションを蓄積する――しばしば価格が上昇し続ける――に至ったかを
説明する。従って合衆国がより「市場ベース」であったという議論はおそらく過大評価である。というのは銀行が大量の
「市場性」金融商品を抱えていたのだから。
(11) さらに「寡婦の壺」がある。のれん「とは、霊的性質であり、霊的身体に特有の偏在性のおかげで、その全体は、
それを構成する多様な構造のそれぞれの部分に分割されることなく内在している」――それは決して消え去ることはなく、
むしろ「それを取得した企業結合体の中で」資本制的な価値を拡大するかもしれない(Veblen, 1958, p.85)。昔の景気過熱は
エキゾチックな商品で生じたが、それと同じことである。これら新しい資産は実現されるあてのない将来のキャピタルゲインと
所得フローを担保としている――「霊感」とはトレーダーのウインクと会釈以外には何の根拠もない。何千という毒入りローンから
一つのパッケージを担保とすることで、いくつもの様々な商品の組合せ――CDOに、またそのCDOから作られるスクエアドCDOへ、
そしてそれから創り出されるキューブドCDO――にトリプルAが与えられた。決して実行されることのなかった決済は、
創りだされた「さまざまな仕組債のそれぞれの部分に」「分割されることなく」内在していたのである。今次危機の間、
銀行その他企業は、ブームの間は支えられていた何憶ドルというのれん代の減損を強いられた。2008年には銀行は250憶ドル以上の
のれん代を減損し、そしてその年度末にはさらに2910憶ドルの簿価の切り下げを行った。多くの場合、のれん代は毒入り資産を
保有しており問題を抱えていた金融機関の購入によって創りだされていた(Healy, 2009)。同じような話は、1980年代の
貸付組合危機にあいだにもみられた。二つの明瞭な債務超過機関が買収され、そして結合された機関を健全に見せかけるため、
十分なのれん代が計上されたが、それは単に市場価値をはるかに超えた価格が支払われたというだけのことであった
(Wray, 1994)。注目すべき声明の中で、ユナイテッド・コミュニティ・バンク(四半期で7千万ドルののれん代の
評価損を出した)のCFOは、これは大した話ではない、というのは「バランスシート上、紙に記帳されただけのもの」だから、
と論じたのである(Healy, 2009)。ただしこの「紙上の記帳」は購入価格にレバレッジされ銀行の総資産に加算されたのである。
(12) ヴェブレンは「投機化」よりも「総資産化」に基づく説明を好んだが、それはミルキケン事件[※「ジャンクボンドの帝王」と
呼ばれた。MMFにジャンク(毒入り)債券を忍び込ませる手口を開発したとされる]、エンロン事件、
マドフ事件には、ケインズの「ばば抜き」のたとえ話よりそちらの方が当てはまりがいいように見える。
(13) 当時想定された新しい安定した環境をもっとも明瞭に歌い上げたのはベン・バーナンキ(2004)の
「グレート・モデレーション」テーゼであり、これは市場関係者たちから大真面目に受け止められ、リスクを割り引くために用いられた。