
一条真也さんの「和を求めて」三五館 (2015/10/22)を読みました。
この本は「和」をテーマに一条さんの文章をつづったもの。
一条さんのブログは毎日読んでいます。
◆佐久間庸和の天下布礼日記
◆一条真也オフィシャルサイト
◆一条真也の新ハートフル・ブログ
こうして「和」をテーマに編まれた本を読むと、一条さんの根底には常に「和」の精神が一貫して流れていることを感じました。
本文にもありますが、「和」は「平和」へつながる大切な心情なのです。
個々の「和」の調和の意識が波紋のように伝わることで、「平和」はおのずから生まれるのでしょう。
そして、「笑い」とは「和来」であり、「和」を呼び込むこと。
この本では、花にまつわること。月にまつわること。和歌にまつわること。・・・
日本の伝統に根ざした色々なことがあり、とても勉強になりました。
一条さんの広く深い教養に感動します。
自分は医学や生物学からのアプローチで、内臓としての植物世界の重要性に行きつき、
心身への深い理解へ至るためのアプローチとして、能楽などの伝統芸能に行きつきました。
自分の今の心情にピタリとくる内容で、シンクロニシティーを感じました。
===============
<内容紹介>
「和」は大和の「和」であり、平和の「和」です。(「はじめに」より)
聖徳太子が定めた憲法十七条にみられる、儒教・仏教・神道という三つの宗教が平和に融合した姿――それこそが「和」の精神であり、
日本人の心である。
冠婚葬祭業大手サンレーの社長である著者が、時に『古事記』や歌舞伎、相撲などの伝統文化に心ゆたかな生き方へのヒントを求め、
時に終活、無縁社会などに揺れる現代に問題提起を行なう。
戦後70年という節目に、日本文化の素晴らしさと平和の尊さを伝える論考集。
『礼を求めて』『慈を求めて』に続く、待望のシリーズ第3弾!
===============
この本から学んだ色々なことを。
■聖徳太子と「和」
偉大な編集者としての聖徳太子。
儒教で社会制度の調停を図り、仏教で人心の内的不安を解消し、神道が自然と人間の循環調停を担う。
それは、鎌倉時代の武士道、江戸時代の商人思想である石門心学、日本人の生活習慣に根付いた冠婚葬祭になった。
聖徳太子は、まさに色々なものをつなぎ合わせる「和」の象徴でもあるのです。
憲法十七条での「和」のコンセプト(和を以って貴しとなし)は、横の和だけではなく縦の和も含んでいます。
上下左右全部の和というコンセプトが素晴らしい。
十七条憲法
一に曰く、和(やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。
人皆党(たむら)有り、また達(さと)れる者は少なし。
或いは君父(くんぷ)に順(したがわ)ず、乍(また)隣里(りんり)に違う。
然れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。
孟子も「和」を重要視しています。
『孟子』「天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず」

ただ、聖徳太子の「和を持って貴しと為し」で使われている「和」は太子オリジナルではなく、『論語』に由来しているとのことなのです。
『論語(学而篇)』
「有子が日わく、礼の用は和を貴しと為す。
先王の道も斯れを美と為す。
小大これに由るも行なわれざる所あり。
和を知りて和すれども、礼を以ってこれを節せざれば、亦た行なわれず。」
(みんなが調和しているのがいちばん良いことだ。
過去の偉い王様も、それを心がけて国を治めていた。
しかし、ただ仲が良いだけでは、うまくいくとはかぎらない。
ときには、たがいの関係にきちんとけじめをつける必要もある。
そのうえでの調和だ。)
という意味から来ているようです。
→一条真也さんのブログから。一条真也の「論語塾」『リビング北九州』連載 第4回「和とは何か」にも書いてあります。

天風会の中村天風(1876-1968年)も、和の気持ちこそ平和を具体化する唯一の根本要素であると語りました。
相互に「和の気持ち」があれば、「思いやり」という高いレベルの心情が発露し、レベルの低い心情は自然と中和される。
もし、現実に「和の気持ち」を持てないときは、「何よりも、第一に個々の家庭生活の日々の暮らしの中に、真実の平和を築くことだ」と言っています。
夫婦和合。
陰と陽で太一となります。
夫婦和合は、能楽でもテーマにされることです。
実際、世阿弥作の『高砂』も、夫婦の和合と長寿、和歌の徳、国の平安を祝福するものですから。
○仕舞「高砂」 観世流 シテ・観世清和
「和」は「平和」につながる!
という一条さんの記述は素晴らしいです。
まさに、平和への道は、個々が自分自身と和する状態から、波紋のように伝わっていくのだと思います。
■歌舞伎・能楽と花のメタファー
本書では、歌舞伎や能楽に出てくる「花」という言葉に関して、色々な紹介があり、とても勉強になりました。
歌舞伎には「花形」「花道」という花にまつわる言葉がある。
相撲や芝居で「花形」に与えるお金も「花」。
心付けを「花」と呼ぶのは、見物の時に造花を送り、翌日お金を届ける習慣から。
「花形役者」は、お客さんから花を与えられるほどの才能の持ち主であるということ。
芸者や遊女と遊んだ料金を「花代」と言う。
伝統芸能には、「花」にちなんだ言葉が多いことに驚きます。
どの言葉も、遊芸者と客のあいだの「花のやりとり」に起源があるようです。
それは、もともと花が「御幣(ごへい)」として、「神々を呼ぶ力」を持っていたことにも関係があるとのこと。
遊芸者とは神々の代理人という役割があったのです。
○遊ぶ(2015-10-31)
という記事に書きましたが、
「遊」と言う漢字は、人が旗を持って外に出歩くという形から出来ているようなのですが(By.白川静先生)、それは<遊行する神の姿>のことらしいのです。
白川静『回思九十年』より
「遊という字の本来の意味は、遊行する神の姿をいうのです。
神を迎えるのが祭りである。だから遊は人間が遊ぶのではなくて、神が遊ぶ。
神は人間の愛情の対象として求めることはできない。
また神を迎えて神と共に遊ぶのが遊の本来の姿です。」
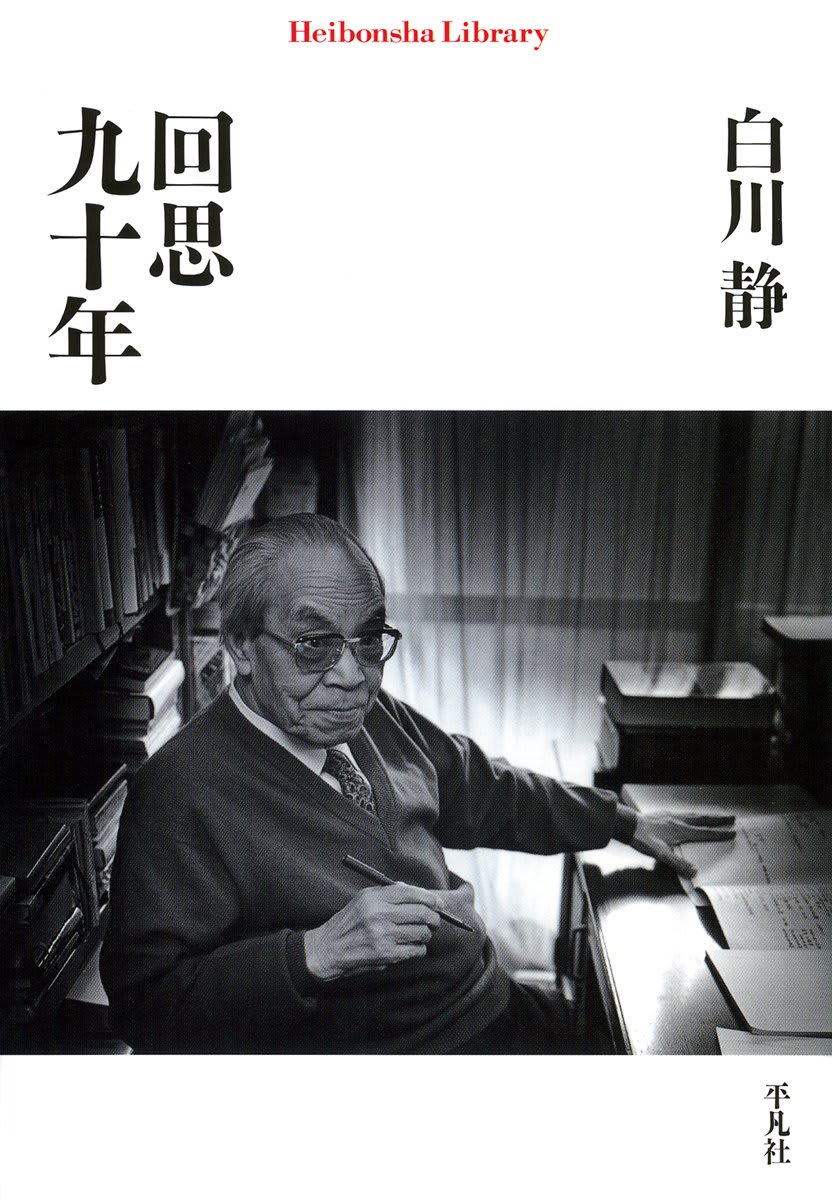
まさに、遊ぶ境地は、かみさまと深い関連があるのです。
●
次に『風姿花伝』より。
自分もこの本は何度と読みました。未だに分かるようで分からないところが多々ある、謎多き本です。
元々は秘伝の書ですから、ある領域にいる限られた能楽師だけが分かる秘密の言語で語られているのでしょうから、芸能初心者である自分がそう容易く分かるはずはないとも思います。ただ、その記述の一端からも達人の深さを感じることができます。
世阿弥の『風姿花伝』は『花伝書』と呼ばれるように「花」を論じた書物でもあります。
『風姿花伝』にある「花」の記述は、
「時分の花」「第一の花」「当座の花」「誠の花」「身の花」「外目の花」「老骨の残りし花」「時の花」「声の花」「幽玄の花」「わざよりいでくる花」「年年去来の花」「秘する花」「因果の花」「無上の花」「一且の心の珍しき花」「誠に得たりし花」、「花なくば」「花失(う)せて」「狂ふ所を花に当てん」「面白き所を花に当てん」「この道はただ花が能の命なるを」など・・・
『風姿花伝』は、「花」という植物メタファーで、人の成長を論じているわけです。
以前、「時分の花」と「まことの花」というテーマでブログに書きました。
「時分の花」とは、若い生命が持つ鮮やかで魅力的な花のことです。これは誰もが成長の過程で必ず通過します。
「まことの花」とは、自分という木の全体が枯れいくとしても、そこでひそやかに咲き続けている花のことです。自分だけが持つ本質的な花のこと。
世阿弥は、そういう自分の中に置く潜む種子が、適切な土壌と光によって花開くことを、芸道と重ね合わせていたようなのです。
○『「時分の花」と「まことの花」』(2014-02-21)
==========
世阿弥『風姿花伝』
「されば、時分の花をまことの花と知る心が、真実の花になお遠ざかる心なり。
ただ、人ごとに、この時分の花に迷いて、やがて花の失するをも知らず。
初心と申すはこのころの事なり」
==========

一条さんの本に戻ります。
世阿弥は「花と、面白きと、珍しき」の3つは同じ心であると述べています。
「花は、見る人の心に珍しきが花なり」として、人に感銘を与えるものを花としてみています。
物まね・幽玄の風姿がどうしたら人に感銘を与えうるか、その根本を世阿弥は花と見たのです。
新しい「花」との深い心の語らいのなかから、詩や歌や絵が生まれ、さまざまな舞台芸術も創造されました。
世阿弥は、舞台で生きた人間の「いのち」と共感しあう花を咲かせた人。
西行や芭蕉は花と心の会話を交わし、そのつぶやきを歌や句として残した人。
利休の演じた朝顔の花一輪も、花を究めた花への執念。
宗達も光琳も、良寛も一茶も、花の「いのち」に語りかけた人。
日本の着物には花を染めたものが多いですが、まさに日本人が「花」という姿に色々なポエジーを感じたからでしょう。
そうして、古代の人たちは「花」という存在や現象から、そこに自然の無限の相を見ていたのでしょう。
動物世界だけではなく、植物世界から学ぶことは多いものです。
ちなみに、生命が植物世界と動物世界とに分かれたのは2000000000(20億)年前とされています。
細胞にミトコンドリアという菌が共生しましたが、そのときに光合成細菌もついでに飛び込んで共生したのが植物になり、独立栄養(光エネルギーから自作で栄養を作れる)をできるようになったのです。ミトコンドリアというエネルギー工場だけが入り込んだ細胞が、後に動物へと進化していくのです。
菌とのちょっとした共生の違いで、こんなにも違う世界が展開して行くとは、まさに自然は神秘の宝庫。
■
西洋の自然観のように、自然から距離を置いて、自然との関係性を切断した上で、観察して解析しようとすると「自然科学」が生まれます。
それに対して、東洋の自然観のように、自然と一体となって自然の中から自然を体感しようとすると、東洋の哲学や詩や芸能が生まれます。
松尾芭蕉は、自然を「造化」と呼びました。
「造」はつくりだすこと、「化」は形を変えること。
「雪月花」がそのシンボルです。
ネイチュア(Nature:「自然」「造化」)とは、物ではなく運動のこと。
「雪」は、季節の移り変わり、時間の流れ。
「月」は、宇宙、空間の広がり。
「花」は、時空にしたがって表われる、さまざまな現象そのもののシンボル。
この一条さんのまとめは、簡潔で素晴らしく分かりやすい。
そういう観点で、芭蕉『笈の小文』を読み返してみると、そういう芭蕉の思いがよく分かります。
==========
芭蕉『笈の小文』
「西行の和歌における、宗祗の連歌における、雪舟の絵における、利休の茶における、其貫通する物は一なり、しかも風雅におけるもの、造化にしたがいて四時を友とす、見る所花にあらずといふ事なし、思う所月にあらずといふ事なし、心、花にあらざる時は、鳥獣に類す、鳥獣を離れて造化にしたがい造化にかへれ」
→(個人訳)
西行、宗祗、雪舟、利休でつながっているものは一つです。それは道です。
風雅つまり俳諧の道は造化(自然)にしたがって、四時(春夏秋冬)を友だちとすることなんです。
ものを見ればそこに花を見て、ものを思えばそこに月を見ることなんです。
心に花という造化(自然)をいだかなったら、それだと鳥や獣になっちゃいますからね。
造化(自然)の原理に従いながら、造化(自然)という故郷に戻りましょうね。
==========

他にも、
太陰暦、日本人の月好きの話。桜を愛する日本人の話。(平安時代より以前は、日本で単に「花」といえば、梅をさした。平安以後は桜)
咲く花は神意、つまり神々の「こころ」のあらわれだった、ということ。
なども、話題が豊富! 一条さんの引き出しの多さと深さを堪能して下さい。
つい先日自分も万葉集の輪読会をやったばかり。
○「万葉集」を詠む(2015-11-18)
本書でも万葉集が紹介されています。
『万葉集』は恋の歌集といってよいほどに恋歌が多いことで知られるものです。彼らは恋を花々によって歌いました。
からあい、なでしこ、おみなえし。
すべて女性にたとえられた花。
大伴家持『万葉集』
「わが屋戸に
まきし撫子(なでしこ)
いつしかも
花に咲きなむ
そへつつ見む」
→庭にまいたなでしこは、いつになったら咲くんだろう?
なでしこが咲いたら、あなただと思って見よう。
(坂上大嬢(さかのうえおおおとめ)さんのこと)
「なでしこ」の名前の由来は「我が子を撫(な)でるようにかわいい花」なので撫子(なでしこ)とか。秋の七草のひとつでもあります。
「なでしこ」を詠んだ歌は、古典をひも解くとたくさんあります。
『枕草子』清少納言
「草の花は、なでしこ。
唐のはさらなり、大和のもいとめでたし」
『万葉集』(読み人知らず)
「野辺(のへ)見れば
撫子の花
咲きにけり
わが待つ秋は
近づくらしも」
『万葉集』大伴池主
「うら恋し
わが背の君は
撫子が
花にもがもな
朝な朝(さ)な見む」
『万葉集』大伴家持
「久方の
雨は降りしく
撫子が
いや初花に
恋しきわが背」
松尾芭蕉
「なでしこの 暑さわするる 野菊かな」
松尾芭蕉
「酔ふて寝む なでしこ咲ける 石の上」
『万葉集』以後も、『古今和歌集』『新古今和歌集』をはじめ、多くの歌集で日本人は自らの心を花に託して歌を詠んできたのです。
なぜなら、花は「いのち」のシンボルだったからです。
日本は農業国です。
「葦(あし)の国」と呼ばれたように、植物とは深く関わってきました。
本書から少し脱線しますが、日本神話である古事記に関しての記述をご紹介。
古事記での天孫降臨神話では、ホノニニギノミコトが高千穂に天下ります。
ホノニニギノミコトは、「ホ」(稲穂(いなほ))が「にぎやか」に実る神さま。
高千穂という地名も、天皇の斎田の稲穂が千々に豊かに実っている様子。
記紀の日本神話に登場する祖先神は、『農耕・農業・稲穂(米作)・生産の神』としての特徴を持ちます。
「吾が高天原きこしめす斎庭(ゆには)の稲を以てまた吾が児(みこ)に御(まか)せまつる」
アマテラスは、高天原で作られた稲をニニギノミコトに与え米を作るように命じたのです。
アマテラスの孫がニニギノミコト、ニニギノミコトの曾孫が神武天皇(初代天皇)へと続きます。
ニニギノミコトは、アマテラスから稲穂の稔る日本を授かりました。
代々の天皇陛下は、自ら稲を栽培され、収穫が終わると新嘗祭、神嘗祭で、今年の収穫のご報告をされます。
新嘗は、新しくできた米を嘗(な)めるお祭。
神嘗は、神々が新穀を嘗(な)めるお祭りです。
天皇陛下が即位後初めて行う新嘗祭だけは、「大嘗祭(だいじょうさい)」と呼び、その儀式は遠く神代の昔から毎年続いています。
(ちなみに、伊勢神宮の20年に1度の式年遷宮は、20年に一度の周期で行う大神嘗(かんなめ)祭でもあるのです。)
日本と言う国は『農耕・農業・稲穂(米作)』を神話の核心に持っている文化だと言えます。
ここからは再度、本書からご紹介。
冬に枯死していた大地を復活させるのは、桜の花をはじめとした春の花々。
古代の日本人は、花の活霊が大地の復活をうながすと信じたのです。
この農業国を支配する王は、花の活霊を妻とし、大地の復活を祝福し、秋の実りを祈願する祭礼の司祭となったようです。
この国の王は、花祭という「まつりごと」を司ることに任務があった。
政治を「まつりごと」というのは、そのためだとのこと。
花は活霊、「いのち」そのもの。
「産霊(むすび)」は、二つの「いのち」が合体を果して新しい「いのち」を生み出すこと、つまり結婚を示す。
結婚する新郎新婦が「花婿」「花嫁」と呼ばれ、「花」に見立てられるのも、これから子どもという新しい「いのち」を授かるから。
まさに、花は「いのち」のシンボルとして愛されていて、それは無意識に使う日本語の中にも密やかに表現されているようです。
・・・・・・
本書は情報量も多く、示唆に富む表現も多く、日本の「和」の分化を紐解く素晴らしい本です。
日本文化の神髄を、色々な角度から表現していますが、様々な角度から論じられていて、多様性と調和を感じます。
多様性はそのままではバラバラですが、そこをつなげていくのが「和」という言葉。
それぞれのコンテンツも日本文化は魅力的なのですが、やはりそこをつなげて統合させる「和」というものこそが、最も大切なのではないかと思いますね。
大和も、大きい和なのですから、古代の大和人の祈りが込められているとも言えます。
日本の「和」の思想をもっと深めて、世界中に輸出できればこんなに素晴らしい事はないと思います。
ぜひ、本書をご一読ください!!!
最後に、自分が論語の中で一番好きな言葉を。これも「和」に関する言葉です。
孔子『論語・子路』
「君子は和すれども同ぜず。小人は同ずれども和せず」
→訳
(君子は、誰とも同じになりませんが、誰とでも協力します。
小人は、誰とでも同じになりますが、誰とも協力しません。)

P.S.
11月22日(日)14:00~17:00に、東京自由大学にて
一条真也「唯葬論~なぜ人間は死者を想うのか」
(鎌田東二氏とのトークセッションあり)
という素晴らしいイベントがあります。
自分は行く予定ですが、まだ空きがあるとのことですので、お時間ある方は是非ご参加を!
○東京自由大学のHP
○Fbのページ
主催ゼミ 一条真也「唯葬論~なぜ人間は死者を想うのか」
日時: 11月22日(日)14:00~17:00
講師: 一条真也(作家、株式会社サンレー代表取締役社長 佐久間庸和)
場所: 東京自由大学(東京都千代田区神田紺屋町5 T.M ビル2階)
受講料: 一般 1500円、会員 1200円、学生 1000円
予約:以下のメールアドレス(東京自由大学事務局)に、①受講日 ②カリキュラム名 ③氏名 ④一般・学生・会員の別、さらに会員以外の方は⑤電話・FAX番号をお知らせください。
問い合せ先:jiyudaigaku@nifty.com

参考
○一条真也「唯葬論」(前編)(2015-08-07)
○一条真也「唯葬論」(後編)(2015-08-14)
○一条真也「永遠葬」(2015-08-19)
この本は「和」をテーマに一条さんの文章をつづったもの。
一条さんのブログは毎日読んでいます。
◆佐久間庸和の天下布礼日記
◆一条真也オフィシャルサイト
◆一条真也の新ハートフル・ブログ
こうして「和」をテーマに編まれた本を読むと、一条さんの根底には常に「和」の精神が一貫して流れていることを感じました。
本文にもありますが、「和」は「平和」へつながる大切な心情なのです。
個々の「和」の調和の意識が波紋のように伝わることで、「平和」はおのずから生まれるのでしょう。
そして、「笑い」とは「和来」であり、「和」を呼び込むこと。
この本では、花にまつわること。月にまつわること。和歌にまつわること。・・・
日本の伝統に根ざした色々なことがあり、とても勉強になりました。
一条さんの広く深い教養に感動します。
自分は医学や生物学からのアプローチで、内臓としての植物世界の重要性に行きつき、
心身への深い理解へ至るためのアプローチとして、能楽などの伝統芸能に行きつきました。
自分の今の心情にピタリとくる内容で、シンクロニシティーを感じました。
===============
<内容紹介>
「和」は大和の「和」であり、平和の「和」です。(「はじめに」より)
聖徳太子が定めた憲法十七条にみられる、儒教・仏教・神道という三つの宗教が平和に融合した姿――それこそが「和」の精神であり、
日本人の心である。
冠婚葬祭業大手サンレーの社長である著者が、時に『古事記』や歌舞伎、相撲などの伝統文化に心ゆたかな生き方へのヒントを求め、
時に終活、無縁社会などに揺れる現代に問題提起を行なう。
戦後70年という節目に、日本文化の素晴らしさと平和の尊さを伝える論考集。
『礼を求めて』『慈を求めて』に続く、待望のシリーズ第3弾!
===============
この本から学んだ色々なことを。
■聖徳太子と「和」
偉大な編集者としての聖徳太子。
儒教で社会制度の調停を図り、仏教で人心の内的不安を解消し、神道が自然と人間の循環調停を担う。
それは、鎌倉時代の武士道、江戸時代の商人思想である石門心学、日本人の生活習慣に根付いた冠婚葬祭になった。
聖徳太子は、まさに色々なものをつなぎ合わせる「和」の象徴でもあるのです。
憲法十七条での「和」のコンセプト(和を以って貴しとなし)は、横の和だけではなく縦の和も含んでいます。
上下左右全部の和というコンセプトが素晴らしい。
十七条憲法
一に曰く、和(やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。
人皆党(たむら)有り、また達(さと)れる者は少なし。
或いは君父(くんぷ)に順(したがわ)ず、乍(また)隣里(りんり)に違う。
然れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。
孟子も「和」を重要視しています。
『孟子』「天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず」

ただ、聖徳太子の「和を持って貴しと為し」で使われている「和」は太子オリジナルではなく、『論語』に由来しているとのことなのです。
『論語(学而篇)』
「有子が日わく、礼の用は和を貴しと為す。
先王の道も斯れを美と為す。
小大これに由るも行なわれざる所あり。
和を知りて和すれども、礼を以ってこれを節せざれば、亦た行なわれず。」
(みんなが調和しているのがいちばん良いことだ。
過去の偉い王様も、それを心がけて国を治めていた。
しかし、ただ仲が良いだけでは、うまくいくとはかぎらない。
ときには、たがいの関係にきちんとけじめをつける必要もある。
そのうえでの調和だ。)
という意味から来ているようです。
→一条真也さんのブログから。一条真也の「論語塾」『リビング北九州』連載 第4回「和とは何か」にも書いてあります。

天風会の中村天風(1876-1968年)も、和の気持ちこそ平和を具体化する唯一の根本要素であると語りました。
相互に「和の気持ち」があれば、「思いやり」という高いレベルの心情が発露し、レベルの低い心情は自然と中和される。
もし、現実に「和の気持ち」を持てないときは、「何よりも、第一に個々の家庭生活の日々の暮らしの中に、真実の平和を築くことだ」と言っています。
夫婦和合。
陰と陽で太一となります。
夫婦和合は、能楽でもテーマにされることです。
実際、世阿弥作の『高砂』も、夫婦の和合と長寿、和歌の徳、国の平安を祝福するものですから。
○仕舞「高砂」 観世流 シテ・観世清和
「和」は「平和」につながる!
という一条さんの記述は素晴らしいです。
まさに、平和への道は、個々が自分自身と和する状態から、波紋のように伝わっていくのだと思います。
■歌舞伎・能楽と花のメタファー
本書では、歌舞伎や能楽に出てくる「花」という言葉に関して、色々な紹介があり、とても勉強になりました。
歌舞伎には「花形」「花道」という花にまつわる言葉がある。
相撲や芝居で「花形」に与えるお金も「花」。
心付けを「花」と呼ぶのは、見物の時に造花を送り、翌日お金を届ける習慣から。
「花形役者」は、お客さんから花を与えられるほどの才能の持ち主であるということ。
芸者や遊女と遊んだ料金を「花代」と言う。
伝統芸能には、「花」にちなんだ言葉が多いことに驚きます。
どの言葉も、遊芸者と客のあいだの「花のやりとり」に起源があるようです。
それは、もともと花が「御幣(ごへい)」として、「神々を呼ぶ力」を持っていたことにも関係があるとのこと。
遊芸者とは神々の代理人という役割があったのです。
○遊ぶ(2015-10-31)
という記事に書きましたが、
「遊」と言う漢字は、人が旗を持って外に出歩くという形から出来ているようなのですが(By.白川静先生)、それは<遊行する神の姿>のことらしいのです。
白川静『回思九十年』より
「遊という字の本来の意味は、遊行する神の姿をいうのです。
神を迎えるのが祭りである。だから遊は人間が遊ぶのではなくて、神が遊ぶ。
神は人間の愛情の対象として求めることはできない。
また神を迎えて神と共に遊ぶのが遊の本来の姿です。」
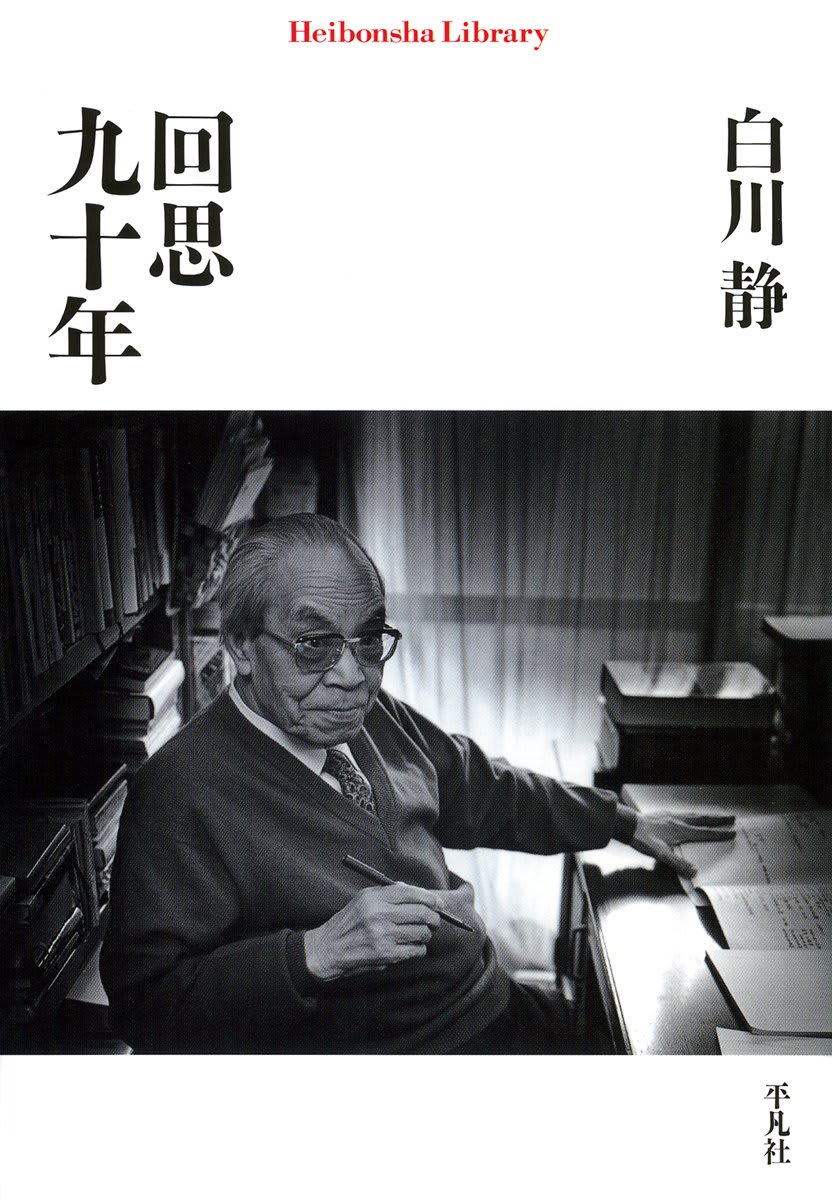
まさに、遊ぶ境地は、かみさまと深い関連があるのです。
●
次に『風姿花伝』より。
自分もこの本は何度と読みました。未だに分かるようで分からないところが多々ある、謎多き本です。
元々は秘伝の書ですから、ある領域にいる限られた能楽師だけが分かる秘密の言語で語られているのでしょうから、芸能初心者である自分がそう容易く分かるはずはないとも思います。ただ、その記述の一端からも達人の深さを感じることができます。
世阿弥の『風姿花伝』は『花伝書』と呼ばれるように「花」を論じた書物でもあります。
『風姿花伝』にある「花」の記述は、
「時分の花」「第一の花」「当座の花」「誠の花」「身の花」「外目の花」「老骨の残りし花」「時の花」「声の花」「幽玄の花」「わざよりいでくる花」「年年去来の花」「秘する花」「因果の花」「無上の花」「一且の心の珍しき花」「誠に得たりし花」、「花なくば」「花失(う)せて」「狂ふ所を花に当てん」「面白き所を花に当てん」「この道はただ花が能の命なるを」など・・・
『風姿花伝』は、「花」という植物メタファーで、人の成長を論じているわけです。
以前、「時分の花」と「まことの花」というテーマでブログに書きました。
「時分の花」とは、若い生命が持つ鮮やかで魅力的な花のことです。これは誰もが成長の過程で必ず通過します。
「まことの花」とは、自分という木の全体が枯れいくとしても、そこでひそやかに咲き続けている花のことです。自分だけが持つ本質的な花のこと。
世阿弥は、そういう自分の中に置く潜む種子が、適切な土壌と光によって花開くことを、芸道と重ね合わせていたようなのです。
○『「時分の花」と「まことの花」』(2014-02-21)
==========
世阿弥『風姿花伝』
「されば、時分の花をまことの花と知る心が、真実の花になお遠ざかる心なり。
ただ、人ごとに、この時分の花に迷いて、やがて花の失するをも知らず。
初心と申すはこのころの事なり」
==========

一条さんの本に戻ります。
世阿弥は「花と、面白きと、珍しき」の3つは同じ心であると述べています。
「花は、見る人の心に珍しきが花なり」として、人に感銘を与えるものを花としてみています。
物まね・幽玄の風姿がどうしたら人に感銘を与えうるか、その根本を世阿弥は花と見たのです。
新しい「花」との深い心の語らいのなかから、詩や歌や絵が生まれ、さまざまな舞台芸術も創造されました。
世阿弥は、舞台で生きた人間の「いのち」と共感しあう花を咲かせた人。
西行や芭蕉は花と心の会話を交わし、そのつぶやきを歌や句として残した人。
利休の演じた朝顔の花一輪も、花を究めた花への執念。
宗達も光琳も、良寛も一茶も、花の「いのち」に語りかけた人。
日本の着物には花を染めたものが多いですが、まさに日本人が「花」という姿に色々なポエジーを感じたからでしょう。
そうして、古代の人たちは「花」という存在や現象から、そこに自然の無限の相を見ていたのでしょう。
動物世界だけではなく、植物世界から学ぶことは多いものです。
ちなみに、生命が植物世界と動物世界とに分かれたのは2000000000(20億)年前とされています。
細胞にミトコンドリアという菌が共生しましたが、そのときに光合成細菌もついでに飛び込んで共生したのが植物になり、独立栄養(光エネルギーから自作で栄養を作れる)をできるようになったのです。ミトコンドリアというエネルギー工場だけが入り込んだ細胞が、後に動物へと進化していくのです。
菌とのちょっとした共生の違いで、こんなにも違う世界が展開して行くとは、まさに自然は神秘の宝庫。
■
西洋の自然観のように、自然から距離を置いて、自然との関係性を切断した上で、観察して解析しようとすると「自然科学」が生まれます。
それに対して、東洋の自然観のように、自然と一体となって自然の中から自然を体感しようとすると、東洋の哲学や詩や芸能が生まれます。
松尾芭蕉は、自然を「造化」と呼びました。
「造」はつくりだすこと、「化」は形を変えること。
「雪月花」がそのシンボルです。
ネイチュア(Nature:「自然」「造化」)とは、物ではなく運動のこと。
「雪」は、季節の移り変わり、時間の流れ。
「月」は、宇宙、空間の広がり。
「花」は、時空にしたがって表われる、さまざまな現象そのもののシンボル。
この一条さんのまとめは、簡潔で素晴らしく分かりやすい。
そういう観点で、芭蕉『笈の小文』を読み返してみると、そういう芭蕉の思いがよく分かります。
==========
芭蕉『笈の小文』
「西行の和歌における、宗祗の連歌における、雪舟の絵における、利休の茶における、其貫通する物は一なり、しかも風雅におけるもの、造化にしたがいて四時を友とす、見る所花にあらずといふ事なし、思う所月にあらずといふ事なし、心、花にあらざる時は、鳥獣に類す、鳥獣を離れて造化にしたがい造化にかへれ」
→(個人訳)
西行、宗祗、雪舟、利休でつながっているものは一つです。それは道です。
風雅つまり俳諧の道は造化(自然)にしたがって、四時(春夏秋冬)を友だちとすることなんです。
ものを見ればそこに花を見て、ものを思えばそこに月を見ることなんです。
心に花という造化(自然)をいだかなったら、それだと鳥や獣になっちゃいますからね。
造化(自然)の原理に従いながら、造化(自然)という故郷に戻りましょうね。
==========

他にも、
太陰暦、日本人の月好きの話。桜を愛する日本人の話。(平安時代より以前は、日本で単に「花」といえば、梅をさした。平安以後は桜)
咲く花は神意、つまり神々の「こころ」のあらわれだった、ということ。
なども、話題が豊富! 一条さんの引き出しの多さと深さを堪能して下さい。
つい先日自分も万葉集の輪読会をやったばかり。
○「万葉集」を詠む(2015-11-18)
本書でも万葉集が紹介されています。
『万葉集』は恋の歌集といってよいほどに恋歌が多いことで知られるものです。彼らは恋を花々によって歌いました。
からあい、なでしこ、おみなえし。
すべて女性にたとえられた花。
大伴家持『万葉集』
「わが屋戸に
まきし撫子(なでしこ)
いつしかも
花に咲きなむ
そへつつ見む」
→庭にまいたなでしこは、いつになったら咲くんだろう?
なでしこが咲いたら、あなただと思って見よう。
(坂上大嬢(さかのうえおおおとめ)さんのこと)
「なでしこ」の名前の由来は「我が子を撫(な)でるようにかわいい花」なので撫子(なでしこ)とか。秋の七草のひとつでもあります。
「なでしこ」を詠んだ歌は、古典をひも解くとたくさんあります。
『枕草子』清少納言
「草の花は、なでしこ。
唐のはさらなり、大和のもいとめでたし」
『万葉集』(読み人知らず)
「野辺(のへ)見れば
撫子の花
咲きにけり
わが待つ秋は
近づくらしも」
『万葉集』大伴池主
「うら恋し
わが背の君は
撫子が
花にもがもな
朝な朝(さ)な見む」
『万葉集』大伴家持
「久方の
雨は降りしく
撫子が
いや初花に
恋しきわが背」
松尾芭蕉
「なでしこの 暑さわするる 野菊かな」
松尾芭蕉
「酔ふて寝む なでしこ咲ける 石の上」
『万葉集』以後も、『古今和歌集』『新古今和歌集』をはじめ、多くの歌集で日本人は自らの心を花に託して歌を詠んできたのです。
なぜなら、花は「いのち」のシンボルだったからです。
日本は農業国です。
「葦(あし)の国」と呼ばれたように、植物とは深く関わってきました。
本書から少し脱線しますが、日本神話である古事記に関しての記述をご紹介。
古事記での天孫降臨神話では、ホノニニギノミコトが高千穂に天下ります。
ホノニニギノミコトは、「ホ」(稲穂(いなほ))が「にぎやか」に実る神さま。
高千穂という地名も、天皇の斎田の稲穂が千々に豊かに実っている様子。
記紀の日本神話に登場する祖先神は、『農耕・農業・稲穂(米作)・生産の神』としての特徴を持ちます。
「吾が高天原きこしめす斎庭(ゆには)の稲を以てまた吾が児(みこ)に御(まか)せまつる」
アマテラスは、高天原で作られた稲をニニギノミコトに与え米を作るように命じたのです。
アマテラスの孫がニニギノミコト、ニニギノミコトの曾孫が神武天皇(初代天皇)へと続きます。
ニニギノミコトは、アマテラスから稲穂の稔る日本を授かりました。
代々の天皇陛下は、自ら稲を栽培され、収穫が終わると新嘗祭、神嘗祭で、今年の収穫のご報告をされます。
新嘗は、新しくできた米を嘗(な)めるお祭。
神嘗は、神々が新穀を嘗(な)めるお祭りです。
天皇陛下が即位後初めて行う新嘗祭だけは、「大嘗祭(だいじょうさい)」と呼び、その儀式は遠く神代の昔から毎年続いています。
(ちなみに、伊勢神宮の20年に1度の式年遷宮は、20年に一度の周期で行う大神嘗(かんなめ)祭でもあるのです。)
日本と言う国は『農耕・農業・稲穂(米作)』を神話の核心に持っている文化だと言えます。
ここからは再度、本書からご紹介。
冬に枯死していた大地を復活させるのは、桜の花をはじめとした春の花々。
古代の日本人は、花の活霊が大地の復活をうながすと信じたのです。
この農業国を支配する王は、花の活霊を妻とし、大地の復活を祝福し、秋の実りを祈願する祭礼の司祭となったようです。
この国の王は、花祭という「まつりごと」を司ることに任務があった。
政治を「まつりごと」というのは、そのためだとのこと。
花は活霊、「いのち」そのもの。
「産霊(むすび)」は、二つの「いのち」が合体を果して新しい「いのち」を生み出すこと、つまり結婚を示す。
結婚する新郎新婦が「花婿」「花嫁」と呼ばれ、「花」に見立てられるのも、これから子どもという新しい「いのち」を授かるから。
まさに、花は「いのち」のシンボルとして愛されていて、それは無意識に使う日本語の中にも密やかに表現されているようです。
・・・・・・
本書は情報量も多く、示唆に富む表現も多く、日本の「和」の分化を紐解く素晴らしい本です。
日本文化の神髄を、色々な角度から表現していますが、様々な角度から論じられていて、多様性と調和を感じます。
多様性はそのままではバラバラですが、そこをつなげていくのが「和」という言葉。
それぞれのコンテンツも日本文化は魅力的なのですが、やはりそこをつなげて統合させる「和」というものこそが、最も大切なのではないかと思いますね。
大和も、大きい和なのですから、古代の大和人の祈りが込められているとも言えます。
日本の「和」の思想をもっと深めて、世界中に輸出できればこんなに素晴らしい事はないと思います。
ぜひ、本書をご一読ください!!!
最後に、自分が論語の中で一番好きな言葉を。これも「和」に関する言葉です。
孔子『論語・子路』
「君子は和すれども同ぜず。小人は同ずれども和せず」
→訳
(君子は、誰とも同じになりませんが、誰とでも協力します。
小人は、誰とでも同じになりますが、誰とも協力しません。)

P.S.
11月22日(日)14:00~17:00に、東京自由大学にて
一条真也「唯葬論~なぜ人間は死者を想うのか」
(鎌田東二氏とのトークセッションあり)
という素晴らしいイベントがあります。
自分は行く予定ですが、まだ空きがあるとのことですので、お時間ある方は是非ご参加を!
○東京自由大学のHP
○Fbのページ
主催ゼミ 一条真也「唯葬論~なぜ人間は死者を想うのか」
日時: 11月22日(日)14:00~17:00
講師: 一条真也(作家、株式会社サンレー代表取締役社長 佐久間庸和)
場所: 東京自由大学(東京都千代田区神田紺屋町5 T.M ビル2階)
受講料: 一般 1500円、会員 1200円、学生 1000円
予約:以下のメールアドレス(東京自由大学事務局)に、①受講日 ②カリキュラム名 ③氏名 ④一般・学生・会員の別、さらに会員以外の方は⑤電話・FAX番号をお知らせください。
問い合せ先:jiyudaigaku@nifty.com

参考
○一条真也「唯葬論」(前編)(2015-08-07)
○一条真也「唯葬論」(後編)(2015-08-14)
○一条真也「永遠葬」(2015-08-19)










ご本人様からこういうお返事頂けて、恐縮かつ感動です。うれしいです。ありがとうございます。
最近仕事忙しくて、本はすぐ読ませていただいているのですが、活字で感想書くのに時間が遅れてしまいました。。。
自分のいまの興味関心にぴたりとあっていて、すごく面白く読みました。 引き出しの多さに本を読むたびに常に発見があります。東京自由大学(と言ってもビルの一室?)でお会い出来るのを楽しみにしております!(^^