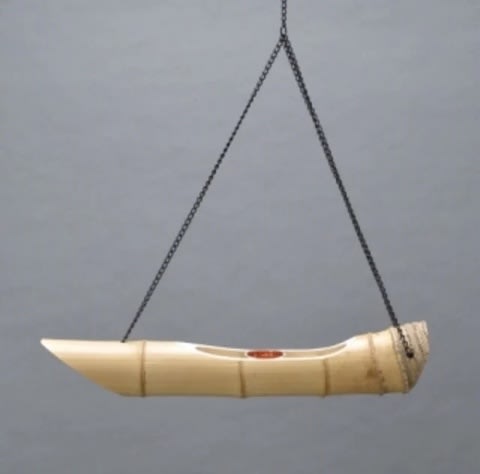発達した低気圧の影響で、気温がぐっと下がった朝。














火曜日は森カフェの日ですが雨も降っているので、電車とバスを乗り継いで神代植物公園の温室へ。

天国でした!!!



沖縄へ行きたくなりますね。
でも本日の目的はこれら南国の花ではなく、こちら!!!

熱帯ハスの花じゃないですよ
↓↓↓

開花直前のショクダイオオコンニャクの蕾です!!!

まだ開花していないので、スイレン室は貸し切り状態。雨の朝いちばんもいうのも味方したのか…
というわけで
あらゆる方向から観察というか、鑑賞





こんな写真まで(笑)

大きさこそ前回2019年に開花した249cmの半分ほどですが、なんと、葉と花が同時に出現。世界2例目だそうです。
まもなく開花ということで、植物園の皆様も今か今かと熱が入っているもよう。

9:30の開園時、入り口には当日朝8時の写真が!!!
Twitterでも随時情報が流れているようです。興味のある方はこちらで確認するのが良さそうです。
開花はわずか2日間。
開花当日は8:30からの繰り上げ開演とのこと
見たい〜!!!