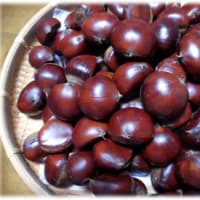少しひんやりで気持ちいいのですが、蒸し暑くなりそうな梅雨の朝、曇り、最高気温30℃(+2)、洗濯指数60乾きは遅いけどじっくり干そう、との予報。
時々薄日は指すもののほとんどどんよりした曇り空、蒸し暑くなるかと思ったのですが、それほど湿気のない風が強く、気温もあまり上がっていないように感じる一日となった北摂。


朝食のベーグルの「角煮バーガー」美味しかったし、家族にも喜んでもらい、大満足、疲れも吹っ飛んでいきそうだけど、天候の関係かやっぱり気怠い感じ、朝一、整骨院で少しスッキリさせたけど…、相変わらずPCに向かったりするけど、だらだらゴロゴロの怠惰な生活…。
今日の1枚の写真は、高槻 まちかど遺産(平成30年度)7 高槻市大蔵司2丁目2番にあるまちかど遺産「神明池跡」です。
まちかど遺産説明板を紹介します。
ここは芥川の扇状地で、地下には北摂山地から伏流水が流れています。
江戸時代、下手に位置する真上村は、農業用水として服部村大蔵寺(司)に井堰と3つの戸手(湧水池)がありました。
戸手の一つ神明池は、大蔵寺の鎮守・神明神社(神服神社に合祀、遥拝所が残る)境内にありました。
真上村は神明池を利用するため大蔵寺に真上村「城屋敷」の「堀跡」の田地を渡すなどしており、重要な水源でした。
水量の減少によって1980年代に役目を終え、境内の一部は児童遊園になっています。
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
明日7月6日(甲辰 きのえたつ 先負)
●「ゼロ戦の日」
零式艦上戦闘機、いわゆるゼロ戦の試作器による試験飛行が始まったのが1939(昭和14)年のこの日です。
零戦は「小回りが利き、飛行距離の長い戦闘機を」という海軍の要求で、堀越二郎が設計した日本最後の艦上戦闘機で、時速533キロ、航続距離3500キロ。1年後の中国戦線から実戦に投入され、第2次大戦中に1万機以上が生産されました。
●「サラダ記念日」
1987(昭和62)年に歌人の俵万智さんが出した歌集『サラダ記念日』(河出書房新社)の中の一首「この味がいいねと君が言ったから 7月6日はサラダ記念日」から生まれた記念日。
この歌集がきっかけで短歌ブームがおき、また、「記念日」という言葉を一般に定着させました。
スーパーやドレッシングのメーカー等が、商品の売り上げを伸ばそうとPRを行っています。
またダイエット関連業種も、「サラダ=ヘルシー=ダイエット」でイベント化しています。「サラダ記念日」は記念日という言葉を広く一般に定着させた意義も大きいです。
●「記念日の日」
日本記念日学会が1998(平成10)年に、毎日のようにある記念日にもっと関心を持ってもらおうと制定しました。
「記念日」という言葉を一般に定着させた「サラダ記念日」に因みます。
当初は、「祝日法」が公布施行された7月20日でしたが、2000(平成12)年から7月6日に変更されました。
●「公認会計士の日」
1948年(昭和23年)7月6日に第2次世界大戦後、アメリカの制度にならって公認会計士法が制定されたことを記念して、日本公認会計士協会(JICPA)が1991年(平成3年)に制定しました。
この日を中心として全国で広報活動や記念講演会などが行われます。
公認会計士法は監査と会計の複雑化・多様化・国際化への対応、我が国の会計監査に対する国際的な信任確保のために、2004年4月に37年ぶりに改正されました。
公認会計士は、財産目録・貸借対照表・損益計算書書その他財務書類の監査・証明をしています。
●「ピアノの日」
1823(文政6)年、シーボルトが初めて日本にピアノを持ち込んだことに因みます。
●「ワクチンの日」
1885年のこの日、フランスの細菌学者のルイ・パスツールが開発した狂犬病ワクチンが少年に接種されたことにちなみ、医療技術の世界的企業BectonDickinson社(アメリカ)の日本法人である日本ベクトン・ディッキンソン株式会社が制定しました。
ワクチンの大切さを多くの人に知ってもらうのが目的です。
●毎月6日は、「電話放送の日」「手巻きロールケーキの日」です。
●東京の下町に真夏の到来を告げる風物詩「入谷朝顔市」が開催
朝顔まつりは、東京都台東区の入谷鬼子母神(真源寺)を中心に毎年7月の6・7・8日の3日間に開かれ、境内と寺院前の言問通りに120軒の朝顔業者と100軒の露店(縁日)が並び、約2万鉢の朝顔が売られます。土日に重なると人出も増え、行き来が出来ないほど賑わうそうです。
昭和23年,下谷観光連盟並びに地元有志の方々の努力はもとより,台東区の後援を得て,入谷に再び朝顔の市が立つようになって,早晩より深夜に至るまでの終日,往時を凌ぐ盛況を極めていることは又宜なるかなということが出きるのであります。
明治から続く夏の風物詩で、俳人正岡子規が「入谷から出る朝顔の車哉」と詠んでいます。
![]() 「にほんブログ村」ランキング参加中です。
「にほんブログ村」ランキング参加中です。
今回は4616話 よかった!と思われたらポチっとお願いします。