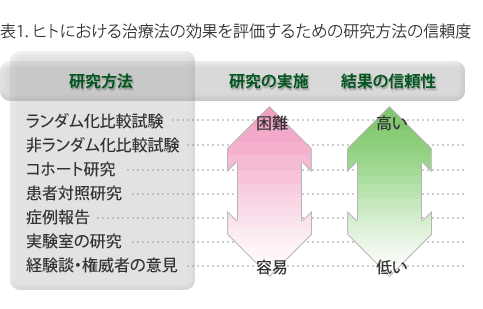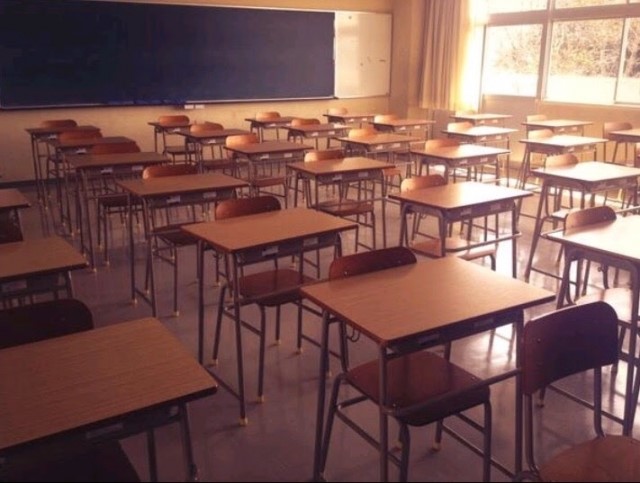就職氷河期とは、バブル崩壊後の、新卒採用が特に厳しかった1993年〜2005年頃のことで、当時大学などを卒業した世代を就職氷河期世代と呼びます。本記事では、就職氷河期世代の年齢や特徴、リーマンショック世代との違いを解説します。「就職氷河期世代支援プロジェクト」についてもお伝えしますので、参考にしてください。
社員の入退社・異動・休職・復職・介護休業にともない必ず発生する業務に社会保険・労働保険の手続きがあります。ミスをしてしまうと従業員が不利益を受ける可能性もあり注意が必要です。
就職氷河期(しゅうしょくひょうがき)は、日本において1990年(平成2年)のバブル崩壊の影響による経済的な不景気以降に就職難となった時期のことである。就職氷河期による影響を受けた世代は、2019年の内閣府による定義では「1993年(平成5年)から2005年(平成17年)に大学や高校等を卒業し就職活動を行った世代」が該当するとされる。これは大卒であった場合には「1970年(昭和45年)4月2日から1983年(昭和58年)4月1日まで」に生まれた世代、高卒であった場合には「1974年(昭和49年)4月2日から1987年(昭和62年)4月1日まで」に生まれた世代に相当する。
2025年現在、30代後半から50代前半となり、1700万人以上いるとされる。
日本における新卒に対する有効求人倍率の低水準時期とは、主に、戦後の日本で1991年(平成3年)のバブル崩壊の影響が実際に出始めたことと、冷戦終結によるグローバル化で発展途上国との低価格競争の本格開始・IT技術革新による分業化が重なったことが、国内製造業を中心に人件費削減圧力となり、1993年(平成5年)以降の不景気(不況)で就職難となっていた時期のことである。
後述のように日本の雇用制度は、非不況時に若年失業率を圧倒的に低くしているメリットがある。逆に欠点として「不景気時期に新卒となった世代」に雇用調整の負担が集中する。そのため、就職氷河期は若年失業率が10%前後と日本的にはかなり高くなる期間である(OECD各国における15-24歳の失業率)。比較参考としては2022年(令和4年)の日本における若年失業率は4.6%(大卒と院卒。15-24歳)、15-24歳を含む全年齢全学歴における国内失業率は僅か2.7%である。
1994年の第11回新語・流行語大賞では審査員特選造語賞を受賞した。
概要
就職氷河期世代は、1993年から2005年に学業卒業で社会に出た世代(高卒者ならば1974年度から1986年度、大卒者ならば1970年度から1983年度に生まれた人たち)のこと。
現役入学の高卒者の場合は、2025年(令和7年)時点で38歳(1986年度生まれの2005年卒)、大卒者の場合は、2025年(令和7年)時点で55歳(1970年度生まれの1993年卒)の人までが該当する。
ただし、1992年(平成4年)・1993年(平成5年)はまだ就職率70%台後半を維持しており、そこまで酷くはなかった。1995年(平成7年)に初の60%台に下落し、過去最低は2003年(55.1%)。以降から徐々に上昇傾向を示し、2006年に1999年以来の60%越え(63.7%)を記録した。そして、2006年以降から2008年途中にリーマンショックが起こるまでは回復していったため、第二新卒で救われた人とそうでなかった人に別れた。
グローバル化と労働構造変化の影響
リクルート社の就職雑誌『就職ジャーナル(1992年11月号)』で提唱された造語であり、バブル景気の新卒採用における売り手市場から一転して急落した就職難の厳しさを氷河期に例えたものである。このような雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代を就職氷河期世代と呼ぶ。のちに略して「氷河期世代」と呼ばれるようになった。
1989年(平成元年)12月の冷戦終結で世界でグローバル化が進展したことによる賃金が圧倒的に安い発展途上国労働者との低価格競争開始と激化・技術革新による世界的な労働構造変化が同時期に起こった。それにより、日本型雇用システムにおける新卒一括採用・終身雇用という普段は若年失業率を他の先進国よりも圧倒的に低くしているプラス面があるが、不景気時に特定世代(不景気時期に新卒となった世代)が雇用調整の負担を一手に負わされるマイナス面が出た。就職氷河期の事象に関しては様々な見解があるが、高度経済成長期の日本における判例によって形成された終身雇用を当然とする厳しい解雇規制によって、当時の不況期でも正社員を事実上解雇不可状態であった状況から、最も容易な倒産回避手段として、新卒採用減が行われた影響と指摘されている。1993年10月には有効求人倍率は0.67倍と、円高不況の影響があった1987年7月(0.68倍)以来の水準に低下し、完全失業率も2.7%と高水準となった(5年8カ月ぶりの水準)。
学卒無業率・不本意非正規雇用率・失業率の推移
ジョブ型雇用社会とは異なり、日本のようなメンバーシップ型雇用社会の国では、不景気時の新卒世代(就職氷河期世代)では採用減の影響で普段よりも、同レベルの高学歴の者でも大企業や中小企業に正社員で就職できた人・不本意非正規雇用を経てから中小企業などへ就職できた人の割合が減り、不本意非正規雇用の人・非正規雇用にも採用されず不本意無職の人の割合が増えた。具体的には就職率全体における記録開始後の過去最低(超氷河期)は2003年の55.1%だが、大卒者における「超氷河期」は2000年であり、同年の有効求人倍率は0.59%、大卒の就職率は55.8%となっている。同年の大卒は、22.5%も卒業時点でも就職先が決まっていない「学卒無業者」であった。特に男性は経済力が対異性関係には重要であり、結婚の可否に与える影響が大きかった。2013年以降の売り手市場への回復によって、日本国の非正規雇用全体に占める不本意非正規雇用の割合だけでなく、不本意非正規雇用労働者数自体も減少傾向が続いている。不景気時に不本意非正規雇用の割合が増えることは就職氷河期だけに限った一時的な問題にはとどまらず、グローバル化による発展途上国労働者との低価格競争のための人件費削減圧力・技術革新による分業や機械化の中で生じつつある長期的かつ構造的な問題である。
日本の失業率は2012年の4.3%から2019年には2.4%に低下し、有効求人倍率は2012年の0.8倍(12年)から2019年には1.6倍(19年)へと倍増した。これは「2013年以後に卒業した学生」の学力や「仕事をする能力」が、「就職氷河期の学生」のよりも改善したからではなく、アベノミクスで2012年以前よりも単に日本の景気が改善したからである。
「バブル崩壊から金融危機」(「1993-2000年」卒)
バブル崩壊後から金融危機後の就職が困難であった時期(1993年から2005年卒までが該当すると考える専門家もいる)を指す語。失われた世代(うしなわれたせだい)、ロストジェネレーションと呼ばれることもある。